2009年以前の記事はこちら。
本字と省字――和同開珎のことなど
漢字の中には同じ語を表すのに種々の形態を持つものがある。例えば、「佛」に対する「仏」はもともと俗字あるいは略字と呼ばれる字形である。「體、軆、躰、体」の場合は、順々に少しずつ構成要素が入れ替わっていて、「體」と「体」にはもはや全く共通要素がない。ひと口に異体字と言っても、様々な関係がある。
ここで話題にしたいのは、「缶(罐)」「医(醫)」のように、構成要素の一部分を取り出して、本来の字の代用にするタイプである。それを省字と称することにする。「罐、醫」が本字、「缶、医」が省字である。
日本における最初期の公式貨幣として「和同開珎」という銘を持つ貨幣が知られている。高校の教科書では「わどうかいちん」という読みがまかり通っている。和銅年間(708-715)に鋳造されたこの貨幣を「わどうかいほう」と読むべきだという論はすでに江戸時代からあった(狩谷棭斎、中川積古斎など)。「珎」を「寶」の省字と見る常識的な説である。しかるに、「珎」を「珍」の異体字と見るべきという、全く馬鹿げた論が今なお教科書にも採用されているのである。正式な貨幣には押しなべて「寶」の字があることは周知の事実であり、貨幣の通例に従えば、「珎」を「寶」の省字とする以外の解釈は成り立たない。「寶」の代わりに「珍」の字が記された貨幣が存在しない以上、「珎」を「珍」の異体字と解釈するのは非常識なことである。和同開珎から始まる皇朝十二銭も全て「〜寶」という銘を持っている。

*画像は「国立文化財機構所蔵品統合検索システム
(https://colbase.nich.go.jp/)」の「和同開珎」による
「わどうかいちん」という珍妙な読みが蔓延ってしまった理由は、貨幣史の観点から考えるという当たり前のことが軽視されたからである。なぜ日本でこの時期に公式貨幣が大量に発行されたのか。それは7世紀前半に中国で「開元通寶」という画期的な貨幣が発行され、それが中国のみならず、東は日本から西はブハラ(現ウズベキスタン)まで、基準通貨として認知されていたからである。

*画像は「国立文化財機構所蔵品統合検索システム
(https://colbase.nich.go.jp/)」の「開元通寶」による
漢字4字の銘が記された方孔円銭という形式は開元通宝に始まり、周辺諸国でも模倣された。したがって、日本における和同開珎の発行もその文脈の中で捉えなければならない。「和同開珎」は中国の「開元通寶」を模範にして、和銅年間(708-715)に発行されたのである。ソグディアナのブハラで発行されたものは銘文も「開元通宝」のままであったが、日本においては独自のアレンジを加え、'和銅版の開元通寶'の意をもって「和同開珎(=和銅開寶)」とした。同は銅の省字、珎は寶の省字である。

ブハラ発行の「開元通寶」(7-8世紀、古代文字資料館蔵)
貨幣史の観点から見れば、「和同開珎」を「和銅開寶」と読む以外の解釈があり得るとは思えない。国家の事業として大量の貨幣を鋳造するに際して、技術が十分に発達していなかったために、「銅」と「寶」という画数の多い字を記す煩を避けたことが、省字を用いた大きな理由と考えられる。
話は少しずれるが、唐の武徳4年(621)に発行された「開元通寶」は当初「開通元寶」と読まれていたらしい。つまり、上部からの時計回りである。後に作られた「順天元寶」(759)や「大暦元寶」(769)が「〜元寶」となっているのはそのためである。しかし、元号として「開元(713-741)」が採用された後は、次第に「開元通寶」の読みが広まり、「建中通寳」(780)のように「〜通寶」を用いるものが現れる。「和同開珎」が上・右・下・左の順になっているのも、「開元通寶」ではなく「開通元寶」に倣ったものと考えると合点がいく。なお、和同開珎の「開」の字形は、中が「井」になっているが、これも唐の「開通元寶(開元通寶)」と同じである。
日本で省字を用いる習慣は古い。その習慣の上に、「ア(阿)、イ(伊)」のような片仮名が発達したのである。沖森卓也(2017)『日本語全史』(ちくま新書)34頁に最古の訓読として紹介された「各田阝(ヌカタベ)」は6世紀の「岡田山一号墳鉄刀銘」に記されたもので、姓の額田部を表記したものである。つまり、各は額の省字、阝は部の省字である。これらは文字単独では理解しにくいが、「各田阝」という塊として見れば、さほど理解から遠いものではない。
省字を用いる習慣はもちろん中国にもあった。いわゆる金印として知られる「漢委奴國王」印の委も倭の省字である。後漢書東夷伝に'倭奴國'とあるものに相当し、委で倭を表していることに疑義はない。金印偽作説に対する反論の一つも、偽作ならば'倭'とあるはずだというものであった。つまり、古代中国でも省字は(公式の印においても)用いられていたことになる。
時代を下って明初になると、漢語とモンゴル語の対訳語彙集である『華夷訳語』(いわゆる甲種)に、一種の発音記号として用いられた字の中に省字が確認できる。華夷訳語はモンゴル語を(万葉仮名のように)漢字で表記したものであるが、モンゴル語にあって中国語にない音を表すために、種々の工夫が見られる。その一つに、音節末の[-l]を表す際に、漢字の左に「丁」を記す方法がある。
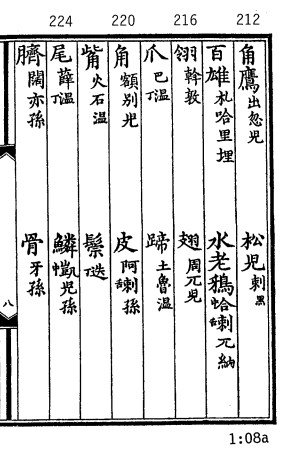
栗林均(2003)『華夷訳語』(甲種本)モンゴル語全単語
・語尾索引(東北アジア研究センター叢書10)より
「爪」を表すba'ulという語を「巴温」と表記し、さらに「温」の左に「丁」の字を添えている。これによって、ba'unではなくba'ulと読むべきことを指示しているのである。この「丁」は華夷訳語凡例に「頂舌音也」と記されている。'舌を持ち上げる音'すなわち[l]のことである。つまり「頂」の省字としての「丁」を用いて音節末の[-l]を表す記号としたのである。
以上のような省字の利用を念頭に置きながら、種々の言語資料を眺めていると、時に気になる字が出てくる。例えば、万葉集で「キ」を表す仮名として用いられる「支」である。普通には「シ」としか読めないこの字をなぜ「キ」に用いるのか。もしかして「伎」か「岐」の省字ではないか、そう考えれば納得がいく。「支」自身も上古音まで遡れば[k-]の声母を持っていたと思われるのであるが、8世紀の万葉集の仮名に上古音を持ち出すのは大仰であろうし、なにより「キ」の[-i]は中古音的である。
有名な稲荷山古墳鉄剣(471年頃、『日本語全史』26頁参照)の銘文に見られる「獲加多支鹵(ワカタケル=雄略天皇)」の「支(ケ)」については、あるいは2〜3世紀の上古音的な音形が朝鮮半島経由で伝わった可能性があるものの、これも省字である可能性を完全には否定できない。少なくとも万葉集の「支(キ)」の方は中古音の枠組みで捉えるのが自然であり、省字と判断せざるを得ないだろう。
さらに言えば、時代劇でもおなじみの田沼意次(たぬまおきつぐ)の「意(おき)」も気になる。江戸時代の人名に上古音を持ち出すのはもはや荒唐無稽であろうから、やはりこれも「憶」の省字が定着したものと考えたい。
要するに、我々の気づかないうちに、省字が一般化して使用されている例があちらこちらにあるのではないかということである。漢字を見掛けの形だけで判断しても、正確な音も意味も理解できないということを肝に銘じておくべきである。
[2026.1.31 中村雅之]
コロンス島再訪
2025年はものすごい頻度で中国に行っていた年で、列挙してみると次のようになる。
6月末〜7月初:南京で学会の後、厦門に移動して集中講義と講座
8月下旬:ソウルで学会
9月下旬:太原で学会
10月中旬:北京で講座の後、遼寧省阜新で遺跡等の視察、杭州に移動して学会と講座
11月初旬:北京で学会と講座
こうして見ると、年の後半はほぼ毎月海外に行っていたことになる。新型コロナを経て、オンラインで瞬時に世界中の人と繋がることができることを知ったばかりだというのに、我ながら呆れるような話だ。なんでそんなに行くのかと言われたら、それは呼ばれたからだが、今や向こうの経済力は相当のもので、飛行機代も宿泊費も謝礼も出すと言われると行こうかなという気になる。そして、せっかく来たんだからついでに講座を一席、という声がかかると、ええそりゃもう、こんなオレのヨタ話でよければ…などとつい嬉しくなって引き受けてしまうのだ。
その中でも一番長い滞在となったのが、7月初に厦門大学で行った集中講義だった。そもそもオファーがあった時に、集中講義をできるような長尺のネタはないので断ろうとしたのだが、断りのメールを書きかけて、そういえばないこともない、と思い直した。実はこの年、これまで中国語で書いた論文をまとめた本が中国で出版されることになっていて、前の年からずっと嫌になりながら内容の修正や校正の作業をしていたのだが(自分が過去に書いた論文なんて読み返したくもない)、その内容を順に紹介していけば一連の講義として成立するじゃないかと思ったのだ。
学期中に2週間連続で休講にはできないということで、土曜、日曜と南京で学会に参加した後、月曜日に厦門に移動、火曜から金曜の4日間に講義、木曜日の夕方に講座を詰め込み、土曜日には帰国するという強行軍になった。講義は1コマ45分の18コマ、講座は質疑応答含めて2時間である。引き受けてしまってから激しく後悔するのは僕のいつものパターンで、5月の後半からほぼ約1ヵ月、半ベソをかきながらパワーポイントの講義資料を作り続けることになった。

厦門大学構内の魯迅像
当たり前の話だが、7月初の厦門は暑かった。期間中は毎日ヘトヘトになって宿舎に帰り着き、酒を飲む気力もなく眠るという日々だったので、観光などをしている余裕は全くなかったのだが、1日だけ厦門の西に浮かぶ小さな島であるコロンス島(鼓浪嶼)に連れていってもらった。北京に留学していた1991年に訪れたことのある思い出の島だ。
僕が学部4年の時に留学していたのは中央戯劇学院という演劇系の単科大学で、もともと元曲を専門にしようと思っていたので、ここで中国演劇史を学ぶつもりだった。公費留学で行ったのだが、当時の僕の中国語能力はかなり怪しいもので、天安門事件の直後で倍率が極端に低かった年だったから、何とか合格できたのだと思っている。
中央戯劇学院の本科留学生には研修旅行のようなプログラムがあって、春節の休みを使って1ヵ月ほど出かけることになっていた。前の年は山西省で元代の舞台遺跡を訪ねたとかで、僕としてはそちらの方が興味深かったのだが、この年は福建省の泉州で「目連戯」(目連救母伝説を演じる祭祀演劇)の国際学会が開かれるのに合わせて、福建省の各地をめぐることになった。参加したのは引率の先生と僕のほかにドイツ人が3人。ベルリンの壁崩壊に始まる東西ドイツ統一の直後の時期で、1人は西ドイツ出身でゲッティンゲン大学の大学院生、あとの2人は東ドイツ出身の女子学生だった。ちなみにゲッティンゲンの院生は当時僕のルームメイトでもあり、現在はフィンランドのヘルシンキで教員をしている。
北京から寝台列車で2泊3日かけて福州に来て、それから莆田、泉州、厦門、漳州とバスで移動し、また福州に戻るという長い旅だった。活動は主に各地の伝統地方劇の鑑賞と文化交流で、何せ青い目の3人がいるので先方は張り切って上演とレクチャーをしてくれるのだが、こちらはろくな知識もないのに交流しろと言われても…と戸惑うばかりだった。旅も後半になると、正直身も心も疲れ果てていたのだが、厦門ではコロンス島に滞在し、夢のように穏やかな時間を過ごした。
車も自転車もなく、徒歩で1時間もあれば一周できるコロンス島は、かつて租界があった所だけあって異国情緒にあふれ、民族衣装を着た人たちの姿も目立った。たしか我々は島内にある音楽学校の宿舎に泊まらせてもらったはずだ。厦門市内からはフェリーで行き来することになるのだが、2元ぐらいの料金は行きの時だけ払えばよいシステムだった。沢木耕太郎の『深夜特急』で、香港でアイスクリームを舐めながら乗るスターフェリーのことを「60セントの豪華な航海」と名付けていたが、漁船よりは少しマシな程度のフェリーでコロンス島まで15分ほど揺られていく風景も、なかなかのものだった。
コロンス島へはその後長い間訪れる機会がなく、2015年に学会で厦門に来た時には、週末は観光客が多すぎてとても入れない、ということで断念したのだが、今回を逃すともう死ぬまで来ることはないだろうからと、水曜日の午後の授業が終わってから、2人の大学院生に連れて行ってもらった。

ずいぶん立派なフェリーターミナルができていた
留学中に来た時はフェリーの発着場が一つしかなかったはずだが、今回はその記憶とは違うターミナルに着いた。35年ぶりとなるコロンス島は、2017年に世界文化遺産に登録されたとかで、確かにだいぶ観光地化された面はあるのだろうが、素朴さとエキゾチックな雰囲気が奇妙に同居している感じが当時のままだった。暑さが少し和らいだ夕方の時間、院生とともに島内をぶらぶら歩きながら留学時の記憶をたどり、心地良い時間を過ごすことができた。
意外だったのは、ここが文字改革運動の先駆者である盧戇章(1854-1928)にゆかりのある島だったということだ。19世紀末から20世紀初頭にかけて、中国では漢字を廃止して新しい表音文字を作り出そうという運動が起こるが、彼が1892年『一目了然初階』という書の中で提案した「切音新字」は、新しい文字の構想を示した史上初めての試みと言える。彼については数年前に高校生向けのミニ講義の中で取り上げたことがあり、厦門で英語教師をしていたことは知っていたが、なるほど租界があったのだからコロンス島に居を構えていても不思議はない。新たな観光資源として光が当たったということなのだろうが、島内には「ピンインロード」と称して、一文字ずつ切音新字を埋め込んだ小道もあった。

盧戇章像

ピンイン・ロード
最後は小ぎれいなビーチに出た。夕闇迫る中、対岸の市街地を眺めながら、浜辺で幸せそうにはしゃぐ人々の声を聞くのも悪くなかった。たった2時間程度の小旅行だったけれど、今回コロンス島に来れて本当に良かった。かつての思い出をたどる感傷旅行は何回も行くものではないから、おそらくもうここに来ることもないだろう。

最後に出た海水浴場
ちなみに、コロンス島に滞在した35年前、その後厦門から漳州を経て福州に戻った後、ドイツ人の3人は、帰りまで寝台に乗るのは嫌だ、飛行機で帰ると言い出して引率の先生とケンカになり、実際自分たちでチケットを取って空路で帰ってしまった。僕はと言えば、どっちつかずの協調主義、というか日本人性を発揮して、結局は先生と2人で寝台に乗り帰ることになった。北京に着いて留学生宿舎に帰ってきたら、同じ階にいる友人から、よう竹越、帰ったの?と声をかけられて、あっ、日本語を聞いたのは1ヵ月ぶりだ、と思ったのが記憶に残っている。
もうあれから35年にもなるのか。歳を取ったものだ。まあでも、ただでコロンス島に連れてきてもらえたし、講義と講座の報酬も出るそうだから、歳を取るのも悪くない。
[2025.12.31 竹越孝]
1988年度のNHKラジオ語学講座
部屋の片づけをしていたら、古いカセットテープが出て来た。1988年度後期のNHKラジオ講座を録音したものである。以下のものが含まれていた。
1.フランス語講座入門編(柏岡珠子、1988.10-1989.3)
2.フランス語講座応用編(恒川邦夫、1988.10-1989.3)
3.中国語講座応用編(黎波、1988.10-1988.12)
4.中国語講座応用編(宮田一郎、1989.1-1989.3)
いずれも懐かしい顔ぶれだ。とっくに処分したと思っていた37年前の録音テープが残っていたのは嬉しかった。
1の柏岡珠子氏は1994年から中井姓に変わる。Wikipediaの「中井珠子」の項には「1996年から1998年にかけてNHKラジオ、NHKテレビのフランス語講座を担当。」とあるが、これは中井珠子名義でのことで、柏岡珠子時代の情報が抜けている。長い間フランス語講座の人気講師だった林田遼右氏の後を継いで、柏岡氏がこの1988年度後期から担当するようになったのではなかったかと記憶する。彼女のフランス語講座は非常に楽しかった。毎回の臨場感あふれる会話音声もよかったが、何よりも彼女の声がきれいで、それを聴くだけでも勉強意欲が湧いたものだ。
2の恒川邦夫氏の講座では、19世紀の作家アルフォンス・ドーデ(Alphonse Daudet)の短編小説「アルルの女」を半年かけて読んだ。これも効果音の入った素晴らしい朗読と恒川氏の丁寧な解説で耳に心地よかった。この時期のフランス語講座応用編は前期を福井芳男氏、後期を恒川邦夫氏が担当することが多く、二人とも、スタンダールやドーデなど19世紀の小説をよく題材にしていた。
3の黎波氏の講座では、巴金の『随想録』の中から数篇の文章を読んだ。巴金の文章と黎波氏の解説を通して、文化大革命の悲惨さを実感した記憶がある。黎波氏は、北京語辞典たる倉石武四郎編『岩波中国語辞典』のインフォーマントだった方で、1980年代にはしばしば中国語講座応用編を担当されていた。
4の宮田一郎氏の講座は、なんと上海語講座だった。上海語の講座がNHKで開かれたのは、後にも先にもこの時だけだろう。この講座が始まる少し前の1988年9月に、宮田氏は光生館から『上海語常用同音字典』を上梓していた。
上海語にはもちろん正書法はないが、マイケル・シェラード(1981)「上海語表記法の実用化について」(『中国語学』228号)によって、比較的合理的な表記案が提案されたことがある。1983に東京都立大学で古屋昭弘氏を講師とする勉強会が開かれた時にも、シェラード方式が採用された。しかし、宮田氏の用いた表記は独自の方式だった。
私が印象に残っている上海語と言えば、都立大の旧目黒校舎の学生室での勉強会で古屋氏が聞かせてくれた「独脚戯」という漫才のラジオの録音音声だ。次々と繰り出される上海語のセリフを古屋氏が何とも楽しそうに解説するのを聞きながら、世の中にはこのような趣味を持った人がいるものかと、やや呆気にとられたものだった。やがて1987年10月には都立大院生の同人誌であった『語学漫歩』に吉池孝一氏の「当代上海語会話テキスト」の連載が始まり、さらに同じ頃に榎本英雄・范暁(1987)『エクスプレス上海語』(白水社)も出たりして、俄かに上海語ブーム(?)が到来した。宮田氏の上海語講座が始まったのはそういう時期だったのだ。
私はNHKラジオの語学講座を聞くのが好きで、学生時代から気に入った放送を録音していた。媒体は、カセットテープからMD(ミニディスク)を経て、今ではソニーのラジオレコーダーによる自動予約のデジタル録音へと移り変わったが、語学講座への愛着は消えない。今では録音するだけでほとんど聞かないものも多いが、それでも時々昔の放送を聞き返すのは至福のひと時である。
[2025.10.1 中村雅之]
18世紀の英語の合字(ligature)
古代文字資料館には、18世紀前半に発行されていた英国の夕刊紙『The Evening Post』の1748号(1720年)と1974号(1722年)がある。そこに見られる綴りはほぼ現在のものと変わらないと言ってよい。どうあるべきか様々な論争のあった英語の綴りは、一般に、Samuel Johnson の辞書(A Dictionary of the English Language,1755)をもって固定化したとされるが、18世紀前半においてすでに現在と変わらぬ綴りが使用されていたことが当時の新聞から分かるのである。

現在の我々が18世紀の新聞を見た時に戸惑うのは、その綴りではなく、字形および二つの字の合成形である。字形では何と言っても「s」の字形に特徴がある。語末のsは通常の字形であるが、語頭と語中の小文字は長いs(long s)になる。下に示したのは「possible」であるが、「f」に酷似しているため、慣れないと「poffible」のように見える。
possible

大文字では長いsは用いられない。小文字にのみ語頭・語中形と語末形の区別があるのは、ギリシア文字のΣに対する小文字のσとςの用法に類似している。なお、語末形のs(つまり通常のs)は厳密に言えば、語中におけるアポストロフィーの前にも用いられる。
dispos'd

過去分詞の「-ed」は時に「-'d」と記される。同じ語でも両様に綴られ、区別はないようである。アポストロフィーの前では(直後に文字がないことから)語末に準ずるものとして通常の(短い)sが用いられるのであろう。なお、この語は他の箇所では「disposed」とも記されているが、その際には2か所のsはどちらも長いsになっている。
disposed

厄介なことに、この長いsはしばしば合字を形成する。つまり、st/sl/shなどにおいて、一字のようなかたまりになる。
Post

stood

slight

short

このような合字を英語では「ligature」と称する。合字の歴史はかなり古く、古代文字資料館が所蔵する前2世紀のローマの貨幣にも「NT」の合字が確認される。『The Evening Post』に見られる合字で珍しいのは、「ct」の合字で、次のような形になる。
October

actual

長いsの使用は中世以来の歴史を持つものであったが、印刷では18世紀末まで、手書きでは1850年代までで役目を終えたらしい。(cf.堀田隆一氏のブログ「hellog〜英語史ブログ」#584. long s と graphemics[2010-12-02])それに伴って長いsを利用した合字も姿を消すことになった。
なお、斜体(イタリック体)の長いsは下に長く伸びており、IPAのシュー音を表す記号[ʃ]はその形によっている。
Brussels

[2025.1.1 中村雅之]
フランスっぽい日々(9)〜帰国まで〜
若干の感傷を交えつつ、意気揚々とカタール航空のチェックインカウンターに行ったのはよかったが、自分の順番が来ると係の女性から何事か早口でまくし立てられ、は?みたいな顔をしていると、はい次、という感じであっという間に列からはじかれてしまった。列が途絶えるのを待って再度トライしてみると、また同じようにはじかれそうになったが、かろうじてインシューランスという言葉が聞き取れた。あっ、「保険」か!ということで海外旅行保険の証書をカバンから取り出した。もう使うこともないだろうとアパートを出る時に捨てようとしたのだが、いざという時のために取っておいて本当によかった。
ところが、それを見せても係の人は日付を指して首を振るだけだ。聞いたところでは、タイという国はたとえトランジットであっても旅行保険に入っていない乗客を受け入れることはできず、僕の保険は25日で期限が切れるから乗せられないというのだ。もともと25日に直行便で帰る予定だったので、出国前に加入した旅行保険はその日までしか契約しておらず、このままではバンコクに着く26日の分がカバーされないことになる。そ、そんな。
じゃあどうすれば?と聞くと、さあね、クレジットカードの会社にでも電話したら?とにべもない返事。海外だと、クレジットカードの会社が保険もカバーしているのは常識なのだろうが、自分のカードが保険をやっているかなんてこれまで意識したこともない。第一、電話しようにもいま日本は真夜中だ。そこでなぜか猛烈に怒りがこみ上げ、そもそも25日に直行便で帰れるはずだったのに、26日にタイを経由することになったのはロシアのウクライナ侵攻のためじゃないか、オレのせいじゃない、It's not my fault! などと叫んでみるのだが、全く埒があかない。
かわいそうに思ったのか、スタッフの一人が、わかった、自分が知っている保険会社を紹介してやるからアクセスしてみい、ということで教えてくれるのだが、中身は全部フランス語。チェックインカウンターの閉鎖時間はどんどん迫ってくるし、間の悪いことに、スマホの充電も20%を切って、じりじりと焦りだけがつのる。これはもう何日かパリに留まるしかないかも…。
その時、あっとひらめいたのが、手元にある保険会社のサイトにアクセスして、1日だけ新たな海外旅行保険の契約を結ぶことだった。フランスではできるんだし、空港にはよく数日だけ旅行保険に加入するための機械が置いてあるじゃないか。調べてみると、確かに1日3000円くらいで加入できるプランがあり、よしこれだ!ということで手続きを進める。いよいよ充電が10%を切ったところで、何とか保険証書がメールで届き、カウンターで画面を見せるとチェックインできた。よしやった、僕もやればできるではないか!
同じ目に遭って困っていた日本の若者(確か法政大学の学生だと言っていた)にアクセスの方法などを教えてあげた後、二人で走って手荷物検査場に行き、搭乗が始まる直前になんとか出発ゲートまでたどり着いた。タクシーに乗ったおかげで出発の4時間前には空港に着いていたのに、お土産を買う時間も、ビールを飲む暇もなく、ギリギリでの搭乗となった。
その後、パリを発って早朝のドーハに着き、数時間待ってバンコク行きに乗る。バンコクには夕方に着いて、深夜に羽田行きに乗りこんだ。羽田にたどり着いた時はもうフラフラで、入国審査の前に抗原検査を受けなければならなかったのだが、その長い列を目にして気絶しそうだった。
さて、滞在記の最後となるこの文章を書いている現在は2024年の12月で、僕がフランスから帰ってもう3年が経とうとしている。その後、新型コロナウィルス感染症は何とか終息を迎え、滞在中は修復中だったノートルダム大聖堂(Cathédrale Notre-Dame)もつい先日一般公開が再開された。ある程度時間が経ったところで、改めて考えてみる。この旅で自分は何か変わったのだろうか?

滞在中にセーヌ川から見たノートルダム大聖堂
結論から言うと、行く前と何も変わらなかった。フランス語の勉強は結局放棄してしまったし、英語で論文を書けるようにもなっていないし、渡航が比較的自由になっても中国にしか行っていないし、日常的に付き合いがあるのも中国の研究者ばかりだ。要するに、東洋と西洋のバランスが取れた、真に国際的な視野を持った研究者にはなれなかったし、今後それを目指すこともないということだ。
おそらく、海外の長期滞在で何かを得るには、歳を取り過ぎていたのだろう。自分の人生なり学問なりがある程度固まってしまっていて、新しいものを受け入れるだけの素地が充分には残されていなかったのだ。最初に書いたように、若い頃から遠藤光暁先生の「北京からパリへ―ヨーロッパ中国語学の旅」(1995)のような旅がしたいとずっと思ってはいたけれど、いざそれができる環境になったら、経験を吸収するためのスポンジが硬くなりすぎていた。それに比べると、二十歳そこそこで北京に留学したことで、僕の人生は決まったようなものだから、やはり旅には適齢期があるのだ。とりわけ人生を変えるような旅には。
もちろん、だからといって後悔はしない。半年にわたるフランス滞在は僕の人生に彩りを添えてくれた。今度科研が取れたら、またパリに行こう。
[2024.12.30 竹越孝]
フランスっぽい日々(8)〜帰国準備の3月〜
2022年の2月末に始まったロシアのウクライナ侵攻は、日に日に大きく報道されるようになっていった。何せ地続きなわけだから、ヨーロッパの人々の受け止めは日本とは比較にならないほど深刻なものだっただろう。パリの街でもそこかしこでデモや集会を目にするようになった。

サン・ミシェル広場(Place Saint-Michel)でのウクライナ支援集会
このことで直接的な影響が出たのが帰国便の問題だった。僕が取っていたチケットは3月25日午後発、全日空のパリ〜羽田直行便だったが、3月に入るとすぐに全日空から、この便はロシア上空を通るため、キャンセルとなる可能性が高い、ついては再検討してほしいという連絡が入った。希望すれば代替便を手配するが、いつになるかはわからないという話だった。アパートの退去日程は決まっているから、これはキャンセルして別の便を取り直すしかない。
そこで、ネットであれこれ調べて、同日発のカタール航空便に変更することにした。パリ〜ドーハ〜バンコク〜羽田という南回りの経路で、金曜日の夜にパリを出て、土曜日は一日中移動、日曜日の朝に東京につくという、いかにも疲れそうな便である。開高健の短編『玉、砕ける』(1978)だったか、途中で香港に立ち寄りたいから、ヨーロッパからの帰国便は必ず南回りに乗ることにしているという一節があって、若い頃はそういう旅にあこがれていたのだが、こちとら4月1日から業務に完全復帰しなければならない身だから、トランジットで数日滞在なんてできるはずもない。
さて、12月から1ヶ月に1回は小旅行に出ることに決めていたので、最後となる3月はラマール先生から勧められていたボルドー(Bordeaux)に行くことにした。北東のストラスブール、北西のモン・サン・ミッシェル、南東のリヨンと来て、最後に南西のボルドーに行けば、コロナで移動もままならない中ではあっても、まあフランス全土を制覇したことになるだろう。
モンパルナス駅からTGVに乗ると2時間余りでつく「月の港」ボルドーも、落ち着いた美しい街だったが、観光名所の大劇場(Grand Théâtre)にも連帯を示すウクライナの国旗が掲げられていて、侵攻の影響はそこかしこにあった。ボルドーと言えば一般のイメージはワインで、実際ワイナリー巡りのようなツアーもあったのだが、中心部を流れるガロンヌ川(Garonne)のほとりに建つワイン博物館(Cité du Vin)を訪れ、2杯ほど試飲するともうこれで充分という気分になった。美しい景色とワインを堪能する一方、自分はおそらく死ぬまでこの土地を再訪することはないだろうなという確信が芽生えて、かすかに悲哀を感じる。

ボルドーの大劇場

ワイン博物館にて
ボルドーから帰ると、いよいよ本格的に帰国準備を始める時期になった。久々に学生気分で質の高い講義を満喫したヒラリー・チャペル先生の授業ともお別れである。毎回聞いているばかりだと申し訳ない気がして、温度表現(temperature terms)の類型論的考察がテーマになった回では、日本語の温度形容詞について、国広哲弥氏の研究などを参考に、英語で簡単な発表をさせてもらった。チャペル先生は中国語もよくできて、受講者はほぼ全員中国からの留学生なのだが、授業の中では学生が中国語で発言することを許さなかった。学生に迎合して、大学院では下手な中国語で授業している僕とは矜持が違うのだろう。

チャペル先生の授業が行われていた教室
満洲語講読の最後の授業の翌日、クラスメートたちがレストランで送別会を開いてくれた。カトリーヌ・ジャミ先生はコロナの濃厚接触者になったとかで来られなかったが、その代わりに遼金元史が専門のピエール・マルソン(Pierre Marsone,馬頌仁)先生が来られた。満洲語の授業を実質的に主宰している院生、アリスさんの指導教員なのだそうで、話が合うだろうとわざわざ呼んでくれたのだ。この人は旧知の孫伯君さん(中国社会科学院民族学与人類学研究所)から、フランスに行ったらぜひ会うといいと勧められていたのだが、何もつてがないので無理だろうと諦めていたら、思いがけず最後に会うことができて嬉しかった。当然ながらこの方の中国語も完璧である。この席では、生まれて初めて本場のエスカルゴというものを食べた。

マルソン先生と
今回のフランス滞在における最後の行事は研究会である。到着直後にラマール先生とジャムリ先生から、僕の滞在中に中国の研究者ともオンラインで結んで研究会をやるので出るようにと言われていて、それから長いこと何の連絡もなかったのだが、日程が決まったというので通知を見たら、帰国の前日と当日だった。帰国便が全日空のままだったら、2日目は出れなかったことになる。
研究会は“中国北方語言接触与漢語歴史演変”研討会(Symposium on "Language Contact in Northern China and the Historical Evolution of Chinese")といい、コンドルセ・キャンパスで3月24日と25日に開かれた。ジャムリ先生とラマール先生が取っているフランス版科研のプロジェクトで、楊永龍先生、祖生利さん、陳丹丹さんなど、中国社会科学院の面々もオンラインで参加していた。この研究会は帰国後の2023年7月と12月に第2回と第3回が開催され、2025年に『歴史語言学研究』の専刊として論文集が出ることになっている。
帰国直前の慌ただしさの中で研究会の準備をこなすのはなかなか大変だった。日本人医師から証明を出してもらえるというので、研究会前日の23日午前にアメリカン病院(American Hospital of Paris)までPCR検査を受けに行き、24日は自分の発表を済ませてからPCR検査の結果を受け取りに行った。25日は朝一番にアパートの退去手続きを済ませてから研究会に参加し、研究会が終わったらそのまま空港に向かうという強行軍だった。
2日目の研究会は午後の早い時間に終わり、夜まで時間もあるから電車を乗り継いで行こうと思っていたのだが、トランクも大きいしタクシーの方がよいと勧められた。ラマール先生のもとで博士を取った宋娜(Song Na)さんがタクシーを手配してくれて、コンドルセから直接シャルル・ド・ゴール空港へ向かった。
やれやれ、最後は慌ただしかったけど、7ヶ月に及んだフランス滞在もついに終わったなあ。長かったような、短かったような…。空港でチェックインが始まるまでしばし感慨にふけり、後は帰国便に乗るだけだと思っていたのだが、最後に一波乱が待っていた。
[2024.12.20 竹越孝]
AIと語学
ここ数年間、AIは急速に進化したが、とりわけ言語学習への応用には目を見張るものがある。小型の自動翻訳機が簡単に利用できるようになったし、音声での自由な会話が可能なアプリも多く出ている。その中でもOpenAI社の「ChatGPT4o」(〜フォー・オムニと読む)に2024年9月末に正式リリースされた「Advanced Voice Mode」(高機能音声モード)が音声対話アプリとしては最高級レベルにある。
ChatGPT自体はテキスト、画像、音声を扱えるソフトだが、旧版の音声機能は反応速度や声質、感情表現などに不満の声が多かった。「Advanced Voice Mode」では9種の声を選ぶことができ、反応速度・感情表現・多言語対応など、ほぼストレスを感じないレベルになった。日本語の質問に英語や中国語で答えてもらうことも可能だし、今の言葉をフランス語で話してとか、ロシア語で話してと命令することもできる。分からない部分はもっとゆっくりとか、明るい声でとか、英国式発音でなどと注文を付けることも可能だ。さらに自分の英語が不自然なら訂正してくれと言えば、どこを直すべきか丁寧に教えてくれる。基礎的な外国語学習はスマホとアプリだけで出来てしまうので、中級程度までは人間の講師は不要になる。
音声とはいえ、基本的にはデータの塊なので、何か質問をするとすぐに答えてくれる。「パキスタンではどのような言語が話されているか」とか「ヒンディー語とウルドゥー語は互いに通じるか」という質問を投げかけると適切な答えが返ってくる。あるいは「音韻学とは何か、中国語で説明して」と言えば、流暢な中国語で説明してくれる。ちょっとした百科事典として、非常に使い勝手がよい。
対応言語は25種とも50種とも言われているが、おそらく徐々に増えていくのだろう。今の所、広東語は話すが、上海語は話せない。主要言語はいずれも非常に流暢だ。語学学校に通うには50〜70万円程度、オンライン学習なら月2〜3万円程度が必要だ。そして今やChatGPTなら毎月2860円(2024年12月現在)で好きなだけ学習ができるのだから、これからは語学学校も淘汰されていくのではなかろうか。
なお、PCでChatGPTを利用すると、テキストでより詳しいことが訊ける。例えば、「奥の方に詰めてください」を中国語でどう言うかを質問してみたら、次のような答えだった。
ChatGPT:
「奥の方に詰めてください」は中国語で次のように表現できます:
丁寧な表現:
請往里面挪一挪,可以嗎?
(Qǐng wǎng lǐmiàn nuó yī nuó, kěyǐ ma?)
→ 奥の方に少し詰めていただけますか?
麻煩您往里面靠一点,可以嗎?
(Máfan nín wǎng lǐmiàn kào yīdiǎn, kěyǐ ma?)
→ 奥の方に寄っていただけませんか?
カジュアルな表現:
往里辺挪一点!
(Wǎng lǐbian nuó yīdiǎn!)
→ 奥の方に詰めて!
請靠里面一点!
(Qǐng kào lǐmiàn yīdiǎn!)
→ 奥の方に寄ってください!
「往里面 (奥の方へ)」や「靠里面 (奥の方に寄る)」を使うことで、奥に移動するニュアンスを自然に伝えられます。
以上がChatGPの説明である。ネイティヴに質問するよりも早く適切な回答が得られる。YouTubeでは語学学習へのAI活用の有効性を説く動画が無数にあるにも関わらず、まだ十分に浸透していない。紙の辞書や参考書ではAIの情報量に太刀打ちできないのである。
検定試験である英検も読む・聴く・書く・話すの4技能を全てPC相手に行う時代である。AIと言語学習の親和性が高いことは疑いない所だ。中学や高校の英語学習は数年以内に一変するだろう。数年前からすでに英語教師受難の時代が始まっていたが、それに拍車がかかること間違いなし。中学の英語教師のほとんどが英検準1級に受からず、TOEIC平均点が600点前後という冗談のような時代は続くはずがない。デジタルネイティブの中学生がAIを活用すれば、あっという間に教師よりも英語ができるようになる可能性がある。そのような時代はすぐ近くにある。
[2024.12.18 中村雅之]
ジパングのラテン語表記
今年(2024年)の1月に発売されて以来ベストセラーになっている『世界はラテン語でできている』(SB新書)を読んだ。非常に面白い。著者は「ラテン語さん」というペンネームで旧ツイッターやウェブマガジンなどでラテン語に関する文章を執筆している人だ。
この本にはあらゆる話題が盛り込まれていて飽きない。カエサルが暗殺される際に発したという「Et tu, Brute?(ブルータス、お前もか?)」というラテン語が、実は歴史書には記載がなく、シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』から来ているらしいとか、有名なフェルマーの最終定理はラテン語で書かれていたなど、一般にあまり知られていないネタが満載である。
対音資料という面で興味を引かれたのが、かのマルコ・ポーロの書、一般には『東方見聞録』という名で知られている書の日本と中国に関する記述である。マルコ・ポーロの口述をルスティケッロという人物が記述したものとされる。13世紀末の原典はおそらく存在しないが、それに非常に近いと目されるものがパリの国立図書館にあり、ほかに翻訳本を含めた各種伝本(14〜16世紀)が140種以上知られている。原典に近いとされるパリの写本(F写本という)はフランス語とイタリア語の混淆語のような言語で記されているが、後に伝わったものの中で最も利用されたのは15世紀に印刷されたラテン語訳だったらしい。
ラテン語訳はもともと14世紀前半にドミニコ会士のフランチェスコ・ピピノが訳出したもので、15世紀後半には最初期の印刷物となり流布した。この印刷本はコロンブスも大陸横断の際に参考にしたもので、東京の東洋文庫ミュージアムにも所蔵されており、2016年には東洋文庫善本叢書の一冊として刊行されている。東洋文庫にあるのはモリソンの旧蔵書で、このラテン語版以外にも80余種の伝本を(主に写真版で)所蔵している。
『東方見聞録』にはいわゆる「ジパング」に関する記述があり、『世界はラテン語でできている』の175頁に引用されたものによると、「ジパング」が「Cyampagu」、中国南方は「Mangy」と記されている。「Cyampagu」は当時の発音をそのまま当てはめれば、「チャンパグ」ということになるが、おそらくは「Cypangu」からの伝写の転であろう。前述のとおり、膨大な種類の写本があり、表記は多種にわたる。最も古いF写本では「Zipangu」と書かれ、一般にはこの表記がよく引用される。ほかに「Sypangu」などの表記もある。
中国南方を意味する「マンジ(Mangy)」は他の伝本に「Mangi」「Manzi」などの表記がある。漢語の「蛮子」に由来する。『世界はラテン語でできている』の引用部分には出て来ないが、中国北方は「Catay」(ほかに「Cathai」「Cataio」など)である。モンゴル語の「Kitad」に相当するが、直接にモンゴル語からの借用とは思えない。ウイグル語などのチュルク語かアラビア語などからの借用ではなかろうか。
「Cyampagu」「Mangy」の「cy-/gy-」は古典ラテン語であれば、おそらく[ky][gy]と発音されたであろうが(ギリシア語からの借用語に用いた)、中世では「y」と「i」の発音上の区別はなく、さらに[i]の前で[k][g]は舌面音化していたから、結局「cy-/gy-」は[tʃi][dʒi]と発音されていたことになる。
今から十年以上前のことになるが、2013年7月に、愛知県立大学図書館で「モンゴル帝国―パスパ文字と『東方見聞録』―」という展示が行われたことがあった。(「いろいろな話[2013.7.30]」に紹介がある)そこにも、5か国語の『東方見聞録』が展示されており、私も直接手に取って、スペイン語版やイタリア語版などをめくって見た記憶がある。ただし、それが古い写本の翻刻なのか、現代の出版物なのか、当時は気にも留めなかった。いま図書館のウェブサイトで書誌情報を確認する限り、ほとんどが現代語訳のようであるが、直接確認しないと分からない。
今ではF写本系統の古いテキストをバーデル(Pierre-Yves Badel)が校訂して現代フランス語との対訳にした本が<Livre de Poche>版(岩波文庫のようなもの)で安価に入手できる。10歳若ければ買っていたかも知れないが、13世紀末〜14世紀の伊仏混淆語に取り組む元気はもはやない。
[2024.10.8 中村雅之]
神田川を表わす新漢字
この文章は僻字・新字を含むため、以下のPDFファイルをご覧ください。
神田川を表わす新漢字(日本語版)
表示神田河的新漢字(中国語版)
[2024.5.1 和平](2024.5.5 中国語版追加)
フランスっぽい日々(7)〜文献調査の2月〜
フランスに来た目的の一つは、フランス国立図書館のリシュリュー館(BnF-Site Richelieu)をはじめとするいくつかの所蔵機関で満洲語関係の書籍を調べることだった。手引きとなるのはJ.-M. Puyraimond他編『Catalogue du fonds mandchou』(Bibliothèque nationale,1979)と、Tatjana Pang編『A catalogue of Manchu materials in Paris』(Harrassowitz,1998)の2冊で、このために日本からわざわざ持ってきていた。
フランス国立図書館には、新館にあたるフランソワ・ミッテラン館と旧館にあたるリシュリュー館があり、リシュリュー館の方には版画・写本・貨幣などのセクションと、国立美術史研究所及び古文書学校の附属図書館が入っている。ここには2013年の夏に一度来たことがあり、その時は改修中とのことでプレハブの建物だらけだったが、驚いたことに、ほぼ10年ぶりに訪れた今回もまだ改修中だった(全面再開は2022年9月)。

入口にあるプレート。

中庭の様子。
前回は2日ほどの限られた時間でとりあえず見られるものを見るという感じだったが、その後世界中の図書館で所蔵資料の画像公開が進み、居ながらにして各地のコレクションをダウンロードできるようになったのと、僕自身もいろいろな所で調査をして、すでに満洲語資料の全体像については概ね把握している状態にあったので、滞在中の文献調査は1ヵ月もあれば充分と考えていた。そこで、9月から続けてきた満漢合璧会話書の文法・語彙項目を記述する作業がほぼ終わりに差し掛かった2月に、まとめて文献調査を行うことにした。
2013年に訪れた時は、事前にメールで問い合わせをし、文献指定、日時指定で予約することが必須だったが、すでに利用登録している今は、ウェブサイト上でログインした後、見たい文献を指定するだけでよいので、手続きはごく簡単に済む。ただ、貴重書はいつでも見られるわけではなく、やはり日時を予約する必要がある。
漢籍等を扱う写本部は3階にある。有名な楕円形閲覧室(Salle Ovale)よりはだいぶこじんまりとしているが、写本部の閲覧室も伝統的な佇まいがなんとも美しい。閲覧予約した書物は取り置いてくれるので、その日に全部終わらなくても翌日続けて見ることができる。前回来た時は写真撮影はもとより、ボールペンの使用もNGだったはずだが、今は皆がパソコンを持ち込んでいて、撮影も自由である。

写本部の入口

閲覧室の様子。
今回の調査で最大の収獲は出版書肆不明の『兼漢清文指要』で、2013年にこの本を手に取った時は、単なる『清文指要』の一バージョンだろうと思っていたが、その後自分で校注本や対照本を作っていく中で、ただならぬ重要性を持っていることがわかってきた。ほぼ10年ぶりの対面となった今回は、一方で使用語彙をまとめる作業を行っていたおかげで、書物の成立過程をめぐる点と点がつながり、これまでおぼろげだったものが、はっきりと像を結ぶ感覚があった。日々手を動かしてはいたけれど、それぞれがいつ形になるかはわからないので、今回のフランス滞在の成果はとりあえずこれ!と胸を張って言えそうなのはやはり嬉しい。これについては帰国後に論文をまとめ、近年には珍しい自信作となっている。
写本部には在華宣教師やヨーロッパの東洋学者が著した満洲語関係の資料もたくさんあったが、僕程度の能力ではそもそも手書きの文字がうまく判読できないので、全部を調べるのは途中で諦めてしまった。ロシア語で書かれた文献も数多く残されていて、あまり手掛けられていない分野だけに、その重要性はわかるのだが、自分がこれからロシア語を一からやり直して取り組もうという気にはちょっとならない。まあ、人が一生をかけても全部をやり尽くすことはできないのだから、自分が最も貢献できる分野に注力すればよいのだ、と思うことにする。
さて、滞在も残り2ヵ月となると、どこにも行かないで終わってしまうのが急に惜しくなってきて、1月のモン・サン=ミシェルに続いて、2月はリヨンに行ってみることにした。やはり週末を使った一泊旅行である。
リヨンにはパリのリヨン駅(Gare de Lyon)からTGVに乗って約2時間で行ける。リヨンと言えば美食の都、文学だったらサン=テグジュペリ(Antoine de Saint-Exupéry,1900-1944)、日本人なら遠藤周作(1923-1996)といったところだろうが、あいにくグルメには全く興味がなく、『星の王子様』は読んだことがなく、そういえば中学生のころ狐狸庵先生の『ぐうたら生活入門』が好きだったなあという程度。むしろ、目的は1245年に行われた「第一リヨン公会議」の雰囲気を感じたいということだった。
ローマ教皇インノケンティウス4世が召集した第一リヨン公会議の主目的はフリードリヒ2世の弾劾だったが、もう一つの議題はモンゴルの侵入で、そこで決まった対応策の一つが、修道士プラノ・カルピニ(Iohannes de Plano Carpini,1182-1252)のモンゴル帝国派遣だった。カルピニはカラコルムで第三代グユク・ハン(在位1246-1248)の即位式に列席し、帰国後に『モンゴル人の歴史』(Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus)を著した。言ってみれば、リヨンはヨーロッパが最初に東方世界を意識した舞台だったわけで、東洋学を専攻する者として、一度は訪れてみたかったのだ。
リヨンは美しい街だった。市街地を望む小高い丘の上にあるフルヴィエール大聖堂(Basilique Notre-Dame de Fourvière)は、もちろん公会議の行われた場所ではないものの、内部は息を呑むような壮麗さで、フランス滞在中に見たカテドラルの中でも出色だった。落ち着いた佇まいの旧市街をあてもなく散策するのも楽しい。古くから水運で栄えた都市ということで、ホテルは市南部のローヌ川とソーヌ川が合流するあたりに取り、翌朝は川沿いをジョギングして、中世ヨーロッパの雰囲気を存分に味わうことができた。

フルヴィエール大聖堂。

リヨン旧市街の様子。
リヨンから帰って、そろそろ帰国の準備に取りかかりはじめた2月末、気になる動きが出てきた。ロシアのウクライナ侵攻である。これが帰国に影響を及ぼすことになるとは、まだ予想していなかった。
[2024.3.30 竹越孝]
フランスっぽい日々(6)〜もう一つの授業開始の1月〜
2022年最初の日となる1月1日は、昼から出かけてエッフェル塔に上った。30年ほど前に北京に留学していた時には、初日の出を見ようと友人とともに故宮の裏にある景山に登ったものだが(あいにく曇っていて見えなかった)、今回は初日の出ならぬ初日の入りということになる。それにしても、海外だと節目節目で何かしたくなるのは、僕が生来のおのぼりさん気質だということなのだろう。

エッフェル塔から。遠くにモンマルトルのサクレ・クール寺院(Basilique du Sacré-Cœur)が見える。
1月から変わったのは、ヒラリー・チャペル(Hirary Chappell)先生の授業が始まったことだった。チャペル先生といえば、東アジアの言語を主なフィールドとする世界で最も有名なタイポロジストの一人である。実は、神戸で2019年に開催した国際学会(IACL-27)の時に招待講演で呼ぼうという計画もあったのだ。今回の講義タイトルは「通時的意味変化における通言語的な規則性:アジアにおける類型と接触(Régularité translinguistique dans le changement sémantique diachronique: Typologie et contact en Asie)」というもので、授業は英語で行われるため、ラマール先生が受講を勧めてくれたのだ。
教室はコンドルセ・キャンパスではなくパリ中心部に位置するInalcoの研究館(La Maison de la recherche)を使い、6月までの半年間、毎週金曜日の午前中に行われる。研究館はセーヌ川沿いのカルチェ・ラタン(Quartier latin)にあり、ソルボンヌやコレージュ・ド・フランスにも近く、僕が住んでいるモンパルナスのアパートからは歩いて20分ほどで行ける。授業はハイブリッド形式で、対面での参加者は毎回10名ほど、オンラインでは中国に一時帰国した後、コロナでフランスに帰って来れなくなった留学生たちが多く参加しているようだった。

Inalco研究館の中庭にあるド・サシ(Antoine-Isaac Silvestre de Sacy)の像。

コレージュ・ド・フランスにある歴代教授のプレート。アベル=レミュザ(Jean-Pierre Abel-Rémusat)、シャンポリオン(Jean-François Champollion)、スタニスラス・ジュリアン(Aignan-Stanislas Julien)などの名前が見える。
自分の理解度は甚だ心もとないものの、講義は全くもって素晴らしいの一言だった。僕が出ていた3ヵ月の間に取り上げられたテーマとしては、所有表現、温度形容詞、親属名称、使役表現などがあったが、アフリカの言語の例がポンポン出てくるような視野の広さと、シナ・チベット諸語に対する分析の深さ・鋭さには何度も圧倒される思いだった。毎週木曜日の夜に先生からメールで翌日用のレジュメが送られてくるのだが、毎回ほぼ独立した論文と言ってよいほどの質と量があった。フランスの正教授は日本に比べて圧倒的に担当コマ数が少ないので、確かに時間はあるのだろうが、毎週学会発表をするようなペースでアイディアを生み出し続けられる研究者は世界にどれほどいるだろうか。
一度は親属名称に関する講義の予告で、来週はプロフェッサー・イワタの論文を検討しますと言われ、おお、岩田礼先生!と驚喜した。ヨーロッパにおける東洋学の中心地パリで、誰もが認める世界的な研究者が日本人の研究成果を取り上げるなんて、何だかそれだけで誇らしい気持ちになる。つい嬉しくなって、実は院生の時に岩田先生の授業に出たことがあるんです、つい最近も岩田先生の記念論集に論文を書いたんです、などとまくしたてたら、師弟関係だとでも思われたのか、授業で論文の概要が紹介されてから、ではここでプロフェッサー・タケコシからコメントをいただきましょう、と促されて真っ青になった。
受講生のほとんどは中国語圏からの留学生だったが、交換留学で来ている学生もちらほらいた。初回たまたま隣に座った男子学生に、ここってWi-Fi使えますかね?と英語で聞いてみたら、満面の笑みで、竹越先生ですよね!と中国語で返されて驚いた。彼は浙江大学から1年の予定で交換留学に来ている叶雁鵬(Ye Yanpeng)君で、指導教員は汪維輝先生だという。汪先生は僕の最も親しい中国人研究者の一人で、遠藤光暁先生、朴在淵先生とともに『朝鮮時代漢語教科書叢刊続編』(2011年、中華書局)を編んだ仲。ううむ、世間というのは本当に狭い。
たとえ1年の間でも、全く違う文化圏に身を置いて、第一級の教授陣から自分の母語に対する理論的な分析手法を学べるのだから、ここで勉強できる学生たちは本当に幸せである。中国学を専攻する日本人の院生がヨーロッパやアメリカに留学するというのはまず考えにくいことで、そもそも交換留学の枠がない。こうした環境で切磋琢磨している中国語圏の学生とは差がついて当然である。
満洲語の読解クラスは相変わらずオンライン授業が続いていたので、対面の形で定期的に留学生たちと接することができたのはありがたかった。コロナのワクチンは日本で2度接種してから来たのだが、フランス政府が年末になって衛生パス(Pass sanitaire)更新の根拠となるワクチンの有効期間を5ヵ月から3ヵ月に短縮したため、1月中に3回目の接種を受けないとパスの期限が切れることになった。一人でフランスに暮らす身としては心細いことこの上なかったが、留学生たちに助けてもらってスマホで接種の予約をし、近くの保健所で無事3回目を済ますことができたのは幸いだった。
前に懇親会の席で僕の名前を知っているといっていた黎浩(Li Hao)さんも授業に出ていたが、彼女はもう7年もパリにいて、指導教員は徐丹先生、バオアン(保安)語の文法を書いて博士号を取る準備をしているとのことだった。フランスでの学位は、そのまま出版できる程度の質と量が求められるそうで、昨今の日本でよくあるように、博士課程在学中に発表した論文を繋げて一丁上がりというスタイルとは明らかに違う。そのせいか、交換留学などでいずれ帰ることが決まっている留学生とは違って、彼らは一様に暗い表情をしている印象を受けた。
1月17日には満洲語読解のクラスで発表をした。これもオンラインだったが、今回は全編英語なので、中国語の場合とはだいぶ勝手が違って緊張した。当然ながら、フランスでも英語はよく通じるので、正直言ってこの頃になると、何とかフランス語でコミュニケーションを取ろうというモチベーションはほとんどなくなり、下手な英語で押し通すことが多くなったが、滞在中に英語が上達したという感覚は最後まで全くなかった。帰国してからも野蛮なジャパニーズ・イングリッシュのままである。
発表を終えた週末は、ご褒美と称してモン・サン=ミシェル(Mont Saint-Michel)に一泊旅行をした。『地球の歩き方』を手にレンヌ(Rennes)までTGVに乗った後、バスに1時間ほど揺られて行ったのだが、空はどんよりと曇り、雰囲気は完全にシーズンオフである。バス停から長いこと歩いて、ようやく予約したホテルにたどり着くと、入口には、向かい側にあるホテルのフロントまで部屋の鍵を取りに来られたし、という貼り紙があった。また、ケチってホテルの夕食を予約しなかったのは完全に失敗で、とにかく店という店が全部閉まっているので、仕方なく1キロほど戻って小さなお土産屋を見つけ、夕飯はそこで買ったシードルとビスケットで済ませるしかなかった。パリでよく見ていたNetfrixのドラマ『エミリー、パリへ行く』(Emily in Paris)の中で、やり手の女性社長が、ブルターニュ地方のことを「あんなシードルしかないような所!」と吐き捨てる場面があるのだが、パリに暮らして日々ワインを楽しんでいる人たちからすれば、この辺りは確かに文化果つる地というイメージになるのかもしれない。

モン・サン=ミシェル。
さて、滞在もあと2ヵ月、そろそろ文献調査の方を本格化させなければならない。
[2024.3.23 竹越孝]
くずし字学習の楽しみ
私の伯父は生前中学の国語教師をしていた人だったが、隠居してから時折、自作の俳句を認めた葉書を父のもとに書き送っていた。当時大学生だった私は、帰省した際にその葉書を父から見せてもらったが、情けないことに所々読めない文字があった。俳句ということもあってか、いくらか崩して書かれていたのだ。当時はフランス語やラテン語を必死に勉強していたのだが、伯父の葉書も満足に読めない自分に愕然としたのを覚えている。
伯父の晩年の趣味は親族名簿を作ることであった。自分の父(私の祖父)から始まって、その子、孫、ひ孫まで、総勢50人ほどの詳細な名簿を作っていた。私の所にもその名簿が送られて来たが、付録として祖父の自筆の文書のコピーが添えられていた。
祖父は明治半ばの生まれで、大正15年(1926)から昭和17年(1942)まで、岩手県沿岸の中野村という小さな村の村長をしていたらしい。最初の大きな仕事が鉄道の敷設であったという。現在のJR八戸線であるが、1924年以降徐々に延伸工事をして、1930年に中野村を経由して終点の久慈まで開通した。その当時の業務にかかわる内容の文書が親族名簿に添えられていたわけである。なかなかの達筆で、伯父の解説がなければ、私には全く読めないものであった。大正生まれの伯父の文章は所々読めず、明治生まれの祖父の文章はほとんど読めない。これは内容云々の問題ではなく、くずしてある字が何の字なのか認識できないのである。
今から18年前のこと、古代文字資料館では江戸時代の土地売買契約書を入手し、その画像だけをウェブサイトの表紙画像として紹介したことがあった。できることなら、活字に文字起こしをした上で、正式に資料として紹介したかったが、いかんせん読めなかった。付け焼刃的に古文書の入門書を何冊か買って解読を試みたが、くずし字に慣れていなかったため、手も足も出なかった。自分の伯父の字も読めない者が、江戸時代の文章を読めないのは当然のことである。
最近「初心者のためのくずし字解読講座」というYouTubeで、くずし字の勉強を始めた。この講座は歴史資料としての古文書ではなく、歌留多や歌仙絵などの和歌を読むことを目的としているようである。資料としての古文書とは、書き手や日付などが記された公文書や私文書のことで、そのような文書は大学の日本史学科の古文書演習などで読む訓練を積むべきものである。
「初心者のためのくずし字解読講座」はいわゆる変体仮名を覚えることが主な目標である。変体仮名は50音に対して約300種あり、常用のものだけでも150種ほどある。この講座では「百人一首」を題材として、毎回一首ずつ字形を確認していくのだが、一首だけなのでコンパクトで取り組みやすい。とはいえ、一つの変体仮名だけでも無数の(?)くずし方があり、一朝一夕で習得できるものではない。
講師いわく、一文字だけを単独で見てもどの字か決定できないことがあるので、前後の字を見て、文脈を考えながら判断しましょう、とのこと。複数の字が同形になる例はかなり多い。以前にくずし字を覚えようとした時には、そのことが苦痛で長続きしなかった。今回は割と楽しみながら続いている。一種の複雑な神経衰弱(ゲーム)なのだ。加えて、百人一首が材料になっているので、内容を味わえるのもいい。
百人一首は江戸歌留多や歌仙絵が豊富にあるので、それらを眺めながら勉強するのはなかなか楽しい。今はネットで各機関の収蔵する種々の資料を手軽に見られるようになったし、紙の書籍や電子書籍では、資料のきれいな写真とともに簡単な解説が添えられている。資料ごとに使われている変体仮名が異なっていたり、同じ仮名でも字形に差があったりするので、複数の素材にアクセスする楽しみもある。
『石原正明著・享和四年成立 百人一首抄−翻刻・影印−』というキンドル本がある。わずか300円の電子書籍だが、19世紀前半の版本の影印とその翻刻からなる。石原正明は本居宣長門下にあった人だが、それぞれの歌の語句や表現について実に分かりやすい注釈が付けられている。例えば、小野小町の有名な「花の色は うつりにけりな いたずらに 我が身世にふる ながめせしまに」では、「うつりにけりな」の「な」について、詠嘆の詞とした後に、「今も「うれしいなア」「かなしいなア」などいふ「な」は、これと一ツ物なり」と解説されていて、思わず膝を打った。流麗な書体とあわせてなかなか魅力的な本である。ほかにも、百人一首関連の資料がいくつか電子書籍として廉価で提供されている。
18年前には一旦諦めたくずし字学習であるが、ここ数年の電子書籍とYouTubeの盛況によって、何とか続いている。
[2024.2.27 中村雅之]
フランスっぽい日々(5)〜悪夢の12月〜
12月に入るとパリの街はクリスマスムード一色である。街の中心部には所々にクリスマスマーケットが立ち、生花店の軒先には家庭用のクリスマスツリーが積まれるようになった。観光ガイドによれば、オペラ座の近くにある老舗高級デパート、ギャルリー・ラファイエット(Galeries La fayette)のツリーはヨーロッパ随一の規模だそうで、デパートやブランドに何の関心もない僕にも、確かに一見の価値はあった。

サン・ジェルマン・デ・プレ(Saint-Germain-des-Prés)のクリスマスマーケット

ギャルリー・ラファイエットのクリスマスツリー
華やかな街の雰囲気とは対照的に、フランス滞在の折り返しとなるこの12月は、僕にとってかなり気が滅入る期間だった。一つには日が短くなったのがある。冬至が近づくと、朝は8時ぐらいまで明るくならないし、夕方は4時には暗くなってしまう。ヨーロッパの冬は昼が極端に短いので、ずっと夜が続いているような感覚になるのだ。また、コロナの感染状況がかなり厳しくなり、出ていた授業がオンラインに切り替わったこともあって、Inalcoの図書館やコンドルセ・キャンパスに行くのも億劫になってきて、毎朝ジョギングに出る以外は、アパートにこもって作業をする日が多くなった。加えて、日本から所属している学会の選挙で会長に選ばれたというメールが来て更にぐったりする。やれやれ、学校の方からようやく解放されたと思ったら今度は学会か、勘弁してくれよ…。
変化のない生活を続けていると内向的になる。アパートの部屋にテレビはないし、ラジオはフランス語の放送だけで、僕程度のリスニング力では聞いても分からない。夜は床に就くのが早くなり、勢い朝は異常に早い時間に目が覚めてしまう。もう一度寝ようとすると、眠りが浅いため、よく夢を見るようになった。見る夢といえばほとんどが悪夢である。いくつかパターンがあるが、自分が学生で、これから試験なのに全く準備をしていないとか、自分が教師で、これから授業なのに全く準備をしていないとかいったものがほとんどだった。よほどこういうシチュエーションを恐れているということなのだろう。大抵はハッと目を覚まして、ここどこだっけ?となり、現状を認識して安心する、というのがお決まりだった。
夢見が良くないのは確かに嫌なものだが、だからといって二度寝しないで起きてしまうと翌日に差し支える。もちろん、眠るために酒を飲むようになるとアルコール依存症へまっしぐらだから、これだけは避けなければならない。つまり、この状況では悪夢と共存するしかないのだ。そこで、少し発想を変えてみることにした。しょせんは夢なのだから、現実に起こったことではないし、悪夢の場合は目が覚めると絶対に安心できる。つまり悪夢は決して不都合なことではなく、むしろ精神を安定させるためのよい材料なのだ、と。この発想の転換は存外うまくいった。
12月15日にはペローブ、ジャムリ、ボテロ三先生の合同授業にゲストとして呼ばれて発表をした。これもオンラインである。その夜は、ジャムリ先生の自宅に呼ばれてペローブ、ラマール両先生とともに夕食を取り、久々に対面でコミュニケーションを取ることができた。その帰り道、ラマール先生は僕の鬱屈した雰囲気を感じ取ったのか、せっかくフランスにいるんだから小旅行でも行ったらどうですか、と言ってくれて、翌日には、行くなら北東のストラスブール(Strasbourg)か南西のボルドー(Bordeaux)がお勧めですという連絡をくれた。
滞在中に文献収集以外の目的で旅行するというつもりは全くなかったのだが、この時は素直に行ってみようかなという気になり、ドイツとの国境に近いアルザス地方のストラスブールに行くことに決めた。このあたりは、むかし国語の授業で読んだドーデ「最後の授業」(La Dernière Classe)の舞台で、そもそも田舎の小学生にはあまりに想像しづらい世界だったこともあり、その時は何も感じなかったのだが、大学生になって田中克彦『ことばと国家』(岩波新書)などを読んで、物語の政治性を意識させられたという縁がある。
後で気づいたのだが、数年前に取り組んだ『古新聖経』の著者である在華宣教師ポワロ(Louis Antoine de Poirot, 1735-1813)が、アルザスに近いロレーヌ地方の出身だったらしく、彼の故郷を訪ねるということであれば、この小旅行にも別の意味が見つかったのかもしれないが、フランス語も大してできない僕の調査能力などたかが知れているので、無謀な挑戦になったことだろう。
フランス版の新幹線(というと失礼かも知れないが)といった趣のTGV(Train à Grande Vitesse)と現地の安いホテルをネットで予約し、暮れも押し迫った12月27日から1泊2日で出かけた。パリ東駅から出発して大体2時間ぐらいの行程で、乗り心地は頗る快適。フランスという国は、都市と都市の間はひたすら農地が続いているという印象である。

パリ東駅(Gare de l'Est)から乗ったTGV
ストラスブールはクリスマスマーケットで有名な観光地で、すでにその時期は過ぎていたものの、大変な人手だった。こぢんまりとした街は全体がドイツ風で、いかにもヨーロッパらしい、おとぎ話のような世界である。大聖堂を始め、主要な観光スポットは半日もあれば見て回れる。一人旅の夕食はいつものように、スーパーで買ってきた総菜をワインとともにホテルの部屋でもそもそ食べる。印刷術の発明で有名なグーテンベルクが若い時に過ごした街らしく、その名を冠した広場に彼の像が立っていた。フィロロジスト(文献学者)を自認する僕だから、ここでグーテンベルクに出逢ったのも何かの縁だろう。

ストラスブールのクレベール広場(Place Kléber)にあるツリー

グーテンベルク広場(Place de Gutenberg)の像
ストラスブールへの小旅行から戻り、2021年最後の日となる12月31日の夜も早々にベッドに入る。近くにレストランやパブもあるので、アパートの外からは夜通し騒ぐ音が聞こえてくる。もちろん起きて一人で店に入っていくだけの勇気はないから、今夜も眠るだけだ。わがフランス滞在もようやく折り返しとなる。明日の早朝にはまた悪夢を見ることだろう。でもいいや。悪夢もまた楽し。
[2024.1.10 竹越孝]
電子書籍出版
この度、アマゾンから電子書籍(いわゆるkindle本)を出版した。『言葉のはなし』というもので、2018年〜2022年に「いろいろな話」やその他の場所に書いた小文をまとめたものである。将来的に古代文字資料館では、個々の文字資料の写真に詳しい解説を記した書籍を公刊したいという希望があり、紙やCD書籍より今の時代には電子書籍の方が手軽に作成および入手ができるだろうということになった。
なにぶん、古代文字資料館の運営は年寄りたちが担っているので、電子書籍の作成方法など分かるはずもない。そこで、まずは試しにテキストベースの本を作ってみようということで、私の小文集を電子書籍化してみた。はじめはファイルを「epub」という形式に変換して、アップすればよいのだろうと思っていたが、少し複雑な手続きが必要で、YouTubeなどで調べながら、作成に2日、アマゾンの認証に3日ほどかかった。来年は本格的な文字資料解説本が出せればよいのだけれど。よかったら、次の本をアマゾンでチェックしてみて下さい。

(画像をクリックすればアマゾンに飛びます)
[2023.12.21 中村雅之]
前5世紀のギリシア文字(2)
前回は境界石を見たので、今回は引き続き陶片(オストラコン)のギリシア文字について解説したい。前5世紀のアテネでは、僭主になるおそれのある人物を市民が投票によって10年間の国外追放に処する制度があった。その投票に用いられたのが陶器の破片で、その陶片をオストラコン(ostrakon〜ostracon)、その制度を陶片追放(ostracism)という。寺澤さんの写真の中にアゴラ内の柱廊に展示されたオストラコンを写したものがある。

中央のオストラコンには「ΜΗΕΛΑΚレΕΣ」と記されているが、「Λ」はガンマで、「レ」がラムダなので、我々の知っている字形に直すと「ΜΗΕΓΑΚΛΕΣ(mhegakles)」となる。「メガクレース」は前486年に追放された人物の名である。イオニア式の標準的な綴り(=我々が学習する古典ギリシア語の語形)では「ΜΕΓΑΚΛΗΣ(megaklēs)」と記されるのが普通なので、2番目の文字「Η(h)」は衍字のように見えるが、私がネット上で捜索した結果、メガクレースの陶片でこの「Η」が記されたものが13個中3例見つかった。つまり、標準的ではないが、全くの誤りという訳ではないらしい。
続く「ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ(hippokratos)」は字形の面では特に問題はない。強いて言えば、「Π」の右の縦線が短くなっているが、これがこの時代の通常の字形である。この語は文法的には主格「ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΕΣ」の属格形で、通常は「ヒッポクラテースの息子(son of Hippocrates)」という訳が与えられることが多い。イオニア式の標準的な綴りでは主格が「ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ(hippokratēs)」で、属格が「ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ(hippokratous)」となる([h]は表記されない)。つまり、もともと短い[o]と長い[o:]は同じく「Ο」で表記されたが、後に標準的な表記として長い[o:]を「ΟΥ」と表記して区別することになった。さらにその後、[o:]が[u:]に変化したため、現在我々が古典ギリシア語を学習する際には、「ΟΥ」を[u:]と読む習慣になっている。この音変化は前4世紀から前3世紀頃に起こったと思われるが、正確には分からない。いずれにしても、写真に見える「ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ」の語尾「ΟΣ」は実際には長母音[o:s]であり、イオニア式の表記ではそれを「ΟΥΣ」と表記したということである。
ところで、「ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ」(=ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ/hippokratous)という属格形を「ヒッポクラテースの息子(son of Hippocrates)」と訳すのは、解釈を加えた意訳である。直訳すれば「ヒッポクラテースのもの」となる。ここでの属格は「ヒッポクラテース家のもの」を意味しているので、意訳として「ヒッポクラテースの息子」と理解されているのである。全体は「メガクレース、ヒッポクラテース家のもの」あるいは「ヒッポクラテース家のメガクレース」となるが、この形式がアテネのオストラコン銘文の一般的なものである。名前の後に出身地を記すものもある。
写真の下の部分のオストラコンには「ΚΙΜΟΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟ(kimon miltiado)」とあり、イオニア式の標準的な綴りに書き換えると「ΚΙΜΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ(kimōn miltiadou)」となる。「キモーン、ミルティアデース家のもの」あるいは「ミルティアデース家のキモーン」の意である。「キモーン」は前461年に追放されている。字形で興味深いのは、ラムダがイオニア式の「Λ」となっていることである。伝統的な「レ」の字形は前5世紀後半まで使われたが、前461年にはすでに「Λ」も用いられていたことが分かる。前416年頃のオストラコンに記された「ΑΛΚΙΒΙΑΔΕΣ(アルキビアデース)」や「ΥΠΕΡΒΟΛΟΣ(ヒュペルボロス)」においてもラムダが「Λ」で記されている。(ちなみに後者では語頭の[h]も表記されない)
「ΚΙΜΟΝ」の「Ο」と、「ΜΙΛΤΙΑΔΟ」の「Ο」がそれぞれ標準形の「Ω」と「ΟΥ」に対応しているが、これは伝統的な「Ο」がもともと3つの音を表しており、それがイオニア式で区別されたことによる。長母音は狭い[o:]と広い[ɔ:]の2種があった。
[o]→「Ο」
[o:]→「ΟΥ」
[ɔ:]→「Ω」
したがって、[kimɔ:n miltiado:]は標準表記で「ΚΙΜΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ(kimōn miltiadou)」と表記されることになる。なお、比較的まとまった量のオストラコンは、ウィキペディア・コモンズの古代アゴラ博物館のページなどで見ることができる。
以上、前6世紀末〜前5世紀のギリシア語資料である境界石(ホロス)と陶片(オストラコン)について、文字表記の解説を試みた。古典ギリシア語の学習をしただけでは前5世紀の資料を簡単には読むことができないという、当たり前のことを確認した訳である。
なお、余談ながら、ギリシア文字の「Υ(ユプシロン)」をここではラテン文字「u」で翻字した。ほかには「y」で翻字する流儀もある。何故このような不統一があるかというと、文字の系統関係から見ると、ギリシア文字の「Υ」はフェニキア文字(北西セム文字)の6番目の文字「Υ(ワウ)」に由来し、ラテン文字の「Y」「U」「V」「F」はすべてそのワウに源を発するからである。詳細は省くが、ユプシロンの本来の大文字はラテン文字「Y」と同形であり、中世に広まった小文字の「υ」はラテン文字の「u」とほぼ同じである。私はかつて「y」と翻字したこともあるが、最近は「u」にしている。若いころに勉強したフランス語では、単独の「u」が[y]、「ou」が[u]と発音されるが、それが前4世紀ごろ(?)のギリシア語の状況によく似ているので、綴りから音声を連想しやすいというのが理由である。もっともIPAの[y]がまさに古代ギリシア語の「Υ(ユプシロン)」の音価に由来するのだから、「y」で翻字する方がよいという意見にも一理あるので、この先のことは分からないが、当面は「u」と翻字する方針で行こうと思う。
[2023.11.5 中村雅之]
前5世紀のギリシア文字(1)
以前、寺澤知美さんが「いろいろな話」にギリシア旅行の写真を載せてくれたことがあった。「ギリシア旅行(その1)」と題したもので、2007年4月7日の投稿であるから、もう16年前のことになる。それらの写真の中には、アテネにある古代アゴラの遺跡の写真が多数あるが、特に興味を引くのは、境界石(ホロス)と陶片(オストラコン)に刻まれたギリシア語である。16年前には上手く読めなかったが、最近古代ギリシア語の表記について少し調べているので、改めて寺澤さんの写真の解説をしてみようと思う。今回は境界石について。

これは神聖な場所であるアゴラ(広場)の境界を示すための標識である。日本西洋古典学会のホームページの解説によると、アテネの古代アゴラの遺跡からは、3個の境界石が発見されているらしい。その内の2個がアゴラ内の柱廊に展示されており、上の写真はその一つである。刻まれた文は左上から始まって右下で終わり、「我はアゴラの境界石なり」と記されている。古代ギリシアでは、器物の銘文はその器物自身を一人称とした語りの形式で記されるものが多い。文字の解説に入る前に、寺澤さんの別の写真を見てみよう。アゴラ内の出土地に置かれたこの碑石のレプリカとその案内板である。


上の写真で左下に横たわった石が案内板で、右が境界石のレプリカ。下の写真は境界石だけを写したもの。案内板には銘文を現代風に(あるいは古典期の標準的な表記風に?)転写して、「ΗΟΡΟΣ ΕΙΜΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ」と記し、その下に「I AM THE BOUNDARY OF THE AGORA」という英訳を添えている。「ΗΟΡΟΣ(horos)」は境界石、「ΕΙΜΙ(eimi)」はコピュラ動詞(=英語のbe動詞)の一人称単数、「ΤΗΣ(tēs)」は定冠詞の属格(=所有格)、「ΑΓΟΡΑΣ(agoras)」は「ΑΓΟΡΑ」(アゴラ)の属格。古代ギリシア語は語順が比較的自由である。
アゴラの境界石は前6世紀末、つまり大雑把に言えば前500年頃に建てられたと言われている。一方、我々が古典ギリシア語を学ぶ時、それは前5世紀から前4世紀のアテネを中心としたアッティカ地方のギリシア語であると教えられる。つまり、アテネで前500年頃に建てられた境界石の碑文は、我々が授業で習う古典ギリシア語とほぼ同一の言語と言えるだろう。にもかかわらず、古典ギリシア語の学習者はこの碑文を読めない。それは字形をも含めた綴字法が異なるからである。中級の文法書を読むと、アテネでは前403年(ないし402年)に公式にイオニア式の綴字法を採用したとある。その綴りが、現在我々が古典ギリシア語として習っているものだと言ってよい。
文字の解説に移る。写真でははっきり見えない部分があるので、「ASCSA Digital Collections」というサイトに公開されている模写を参照しよう。(前述の日本西洋古典学会のホームページからたどることが可能)

まず最初の「Η」はこの時代には[h]を表す子音である(つまりラテン文字と同じ)。しかし、アッティカ方言以外の多くの方言ではすでに[h]は消滅しており、この文字を広い長母音[ɛ:]を表すために用いた。イオニア式綴字法を採用したアテネでも、公式には前403年以降はこの文字を[ɛ:]という母音として用いることになる。その結果、[h]を表す文字はなくなった。したがって、古典ギリシア語の標準形としては、境界石を表す語は「ΟΡΟΣ」と綴られる。寺澤さんの別の写真に、アゴラの北西に位置するケラメイコスという地区の境界石がある。

首を右に傾ければ、「ΟΡΟΣΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ」(oros kerameikou=ケラメイコスの境界石)という銘文が読める。この境界石がいつのものかは分からない。やたらと綺麗なので、あるいは新しい物かも知れないが、綴りがアゴラの境界石と違っているのを確認するには丁度よい。
アゴラの境界石の「ΗΟΡΟΣ(horos)」では、「P」と「Σ」がラテン文字の「R」や「S」に近い形になっているので、古典ギリシア語の知識を持たない方が「horos」と正しく読めるかも知れない。続く「ΕΙΜΙ(eimi)」は標準形と同じである。右側に縦書きになっている部分は、うっかりすると「ΤΕΣΑΛΟΡΑΣ(tesaloras?)」と読んでしまうかも知れない。「ΤΕΣ」の「Ε」は長母音の[ɛ:]だが、この時代にはまだ文字の上では短母音[e]と長母音[ɛ:]の区別はない。後に標準形では長母音は「Η」で表されるので、「ΤΕΣ」の標準形は案内板に記されたように「ΤΗΣ(tēs)」となる。そして最大の問題は[g]を表すガンマがこの時代にはあたかもラムダのように「Λ」と記されることである。「ΑΛΟΡΑΣ」のように見える部分は標準形では「ΑΓΟΡΑΣ(agoras)」となる。
以上をまとめると、イオニア式の綴字法が採用される以前には、アテネでは[h]を「H」で記し、長母音[ɛ:]を短母音と同じく「Ε」と記し、そしてガンマを「Γ」ではなく「Λ」と記したのである。このような知識を基に案内版に転写された文字を見ると、おおむねイオニア式(あるいは現代風?)でありながら、文頭に「H」を置いている点が擬古的な綴りになっていることが分かる。
[2023.10.31 中村雅之]
フランスっぽい日々(4)〜授業開始の11月〜
11月から大学院の授業が始まった。
中国語史関係のペローブ、ジャムリ、ボテロの三先生は博士課程の授業を合同でやっているそうで、前期は講義、後期は受講生の発表という構成だと聞いた。講義はフランス語で行われるというので、うーん、聞いてわかるかなあ……とためらっているうちに、申し込む機会を逸してしまった。一方、前回コンドルセ・キャンパスに来た時に知り合った高君から、満洲語の読解をやっている授業があると聞いたので、出席させてもらうことにした。
コンドルセ・キャンパス
授業では何を読んでいるの?と聞くと、トゥリシェンだという。トゥリシェン?と聞き返したら、『異域録』のことですと言い直してくれた。『異域録』は、康熙帝の命を受けたトゥリシェン(図理琛)率いる使節団が、1712(康煕51)年に北京を出発し、モンゴル、シベリアを経由して、カスピ海の北に住むトルグート族の長アユキ・ハンのもとを訪れ、3年後に帰着するまでの壮大な記録で、露清関係史の第一級資料にして、中国史上最大規模の旅行記とも言われている。同書には満洲語のオリジナルとその漢訳本があり、ここ何年か、授業で満文本の方を講読しているのだという。中国語畑ではあまり馴染みがないが、ヨーロッパでは訳書が何種類もある有名な本だ。
担当はカトリーヌ・ジャミ(Cathérine Jami)先生で、「テキスト読解による満州語入門:トゥリシェンの旅行記」(Introduction à la langue mandchoue par la lecture des textes: le récit de voyage de Tulišen)というタイトルが付いていた。ジャミ先生はかつて関西大学に1年滞在したことがあるとかで、片言の日本語で挨拶してくれた。面白いのは、ジャミ先生自身は中国科学史の専門家であり、満洲語に関してはほぼ門外漢だと公言されていて、実質的に授業を運営しているのは、高君と清朝史専攻のアリスさん(Alice Crowther)という二人の大学院生だということだ。言ってみれば、院生の読書会のために授業という母屋を貸しているようなもので、へぇー、こんなやり方もありなのかと思った。
授業は2週間に1回、12時半から14時半までの2時間で、当面は対面とオンラインのハイブリッドで行うそうだ。ジャミ先生も含む4〜5人で分担して、各自がテキストのローマナイズと翻訳を前日までにネットの掲示板にアップし、授業の中でそれを検討するという形式。初回の授業は高君とアリスさんによる『異域録』の沿革や参考文献などに関するレクチャーだったが、満洲語の単語はまず“Tohoku”で検索すべし、とのことでデモを見せてくれた。何かと思ったら、栗林均先生が作られた東北大学・東北アジア研究センターの「言語資料検索システム」のことで、日本の研究成果がこんなところで役立っているのかと誇らしい気持ちになった。次回からの分担を決める段になり、僕はお客さんだから聞いているだけでよいのだろうと思っていたが、人手が足りないのでぜひ分担に加わってほしいと言われ、それならと引き受けることにした。その代わりと言っては何だが、授業は通常フランス語のところを英語でやってくれることになった。
アパートに帰ってから早速少し取り組んでみたが、満洲文字だけのテキストをローマナイズして、それを英語に訳していくのは相当に骨が折れる作業だということがわかった。何せ、転写を1文字間違ったら延々と辞書を引き続ける羽目になるし、普段のように中国語にも頼れない。日本にいれば、すぐさま図書館に行って今西春秋氏の訳注(『校注異域録』天理大学おやさと研究所1964、また『異域録:清朝使節のロシア旅行報告』平凡社東洋文庫1985)を借りてきて、座右に置きたいところだが、フランスでおいそれと見つかる書物ではないし、ネットで探しても電子版は手に入らない。まるで、満洲語を学びたての頃に戻ったようだ。
2週間後にあった講読初回のための準備にはかなり苦戦したが、細かい語釈や疑問点を付けたレジュメを作ったので、こちらとしても勉強になったし、授業での討論も弾んで、それなりに刺激を与えることができたようだ。読んでみて分かったのだが、ロシア語の固有名詞に対する満洲文字の転写と漢字音による表記では、それぞれに微妙なずれがあり、これは面白い研究テーマになるかもしれない。それは良かったのだが、その後回を重ねるごとに、担当の分量が僕のところだけ格段に多くなっていくのには閉口した。割り当てる側も現金なものだ。
11月23日には、徐丹先生の主宰する研究プロジェクトにゲストとして呼ばれて発表した。本来はハイブリッド形式の予定で、当日はセーヌ川沿いのリール通りにあるInalcoの研究館(Maison de la recherche)に来るようにと言われていたのだが、その前の週あたりからコロナの感染状況がかなり厳しくなってきたため、直前になって完全オンライン形式に変更された。知り合いの中国人研究者に発表のことを伝えたら、WeChatで広めてくれたらしく、当日は中国から参加した人もかなりいたのだが、発表言語は中国語で、しかも自分のアパートからアクセスしているので、あまり海外で発表しているという実感がわかない。
Inalcoの研究館
とはいえ、授業に追われるだけの日々も嫌だし、全く外部との接点がないものも嫌だから、こういうペースで仕事ができるのは楽しい。秋の深まりとともに、どんどん日が短くなっていくパリ市街を眺めながら、このコロナの波が収まったら、旅行にでも行ってみようかと思うようになった。
晩秋の雰囲気ただようセーヌ川
フランスっぽい日々(3)〜再出発の10月〜
手を動かすというのはつまりこういうことだ。
ここ10年ほど継続してきた僕のメインの仕事は、清代の満漢対訳会話書類について校注本を作ることだった。そのほとんどは『KOTONOHA』の連載である。最も時間のかかった『満漢成語対待』が終わり、あとは『庸言知旨』を残すだけとなった2021年の春から、サバティカルとコロナのため家に籠ることになったので、とにかく海外に行く前にこれを終わらせなければとシャカリキになって進めた。その結果、出発前になんとか最後までたどり着き、不在中の連載のストックもできたので、とてもすっきりはしたのだが、その分パリ到着後は一種のバーンアウトのような状態だったかもしれない。
ギメ美術館でぼんやり仏像を眺めているうちに浮かんできた考えというのは、これで一つのステージが終わったのだから、次のステージに進もう、ということだった。次のステージというのは、これまで作った校本に基づいて、それぞれの文献の語彙と文法を記述していくことである。言ってみれば、各文献の「方言志」を作るようなもので、その枠組には太田辰夫『中国語歴史文法』(1958年)をアレンジして使えばよい。もちろん、採録した語彙には対応する満洲語の情報もつけなければならないから、かなりの時間がかかるだろう。だが、今回のフランス滞在こそが、その作業をするのに最適な時間ではないかと気づいたのだ。アウトプットはしばらくやめにして、今はインプットに専念しよう。そうだ、やっぱりこれだよな、うん。
というわけで、ギメに行った翌日からは、これまでに自分が作った校本を検索し、名詞、代名詞、数詞、量詞……といったカテゴリーごとに、主な中国語の機能語とその全用例、そして満洲語の対応語彙を記述したファイルを作っていくことにした。平日は、朝にジョギングする以外はアパートにいるか図書館に行くかして、とにかくひたすら手を動かす。一人でカフェに行ったりレストランに入ったりする勇気はないから、食事のための外出はしない。ある意味とても単調で内向的な日々だが、生活に一定のリズムができてくると、精神も不思議と安定するものだ。せっかくフランスにいるのだから何かフランスっぽいことをしなければ、という妙なプレッシャーも消え、毎日の作業の合間に行く散歩や週末の街歩きを楽しむ余裕が出てきた。
アパートの近くにあるモンパルナス墓地
9月末に、ラマール先生に誘われてパリの北部郊外にあるコンドルセ・キャンパス(Campus Codorcet)を訪れることになった。ここは、パリ市内にあるいくつかの大学や大学院大学が共同で運営する新しいキャンパスで、社会科学高等研究院(EHESS: École des hautes études en sciences sociales)の研究室も一部入っている。パリ市内の大学は伝統的に土地不足で、ほとんどの教員に個室の研究室がないというのは有名な話だが、ここでは個室が与えられるというので喜んで移った人もいれば、郊外にあるのを嫌って移らなかった人もいるという。
コンドルセ・キャンパス
モンパルナスから乗り換えなしで行ける地下鉄12号線の終点、「人民戦線」という意味のフロン・ポピュレール(Front Populaire)駅にあるキャンパスに行ってみると、確かに一般的なパリの大学のイメージとはかけ離れた広大な敷地に、近代的なビルがいくつも建っている。9月中旬にあったヨーロッパ文化遺産の日(Les Journées Européennes du Patrimoine)の一般公開で見学したソルボンヌ大学などとは全く違った雰囲気である。
ソルボンヌ大学の構内
訪問の主な目的は、EHESSを構成する組織の一つ、東アジア言語研究センター(CRLAO: Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale)の主任であるフランソワーズ・ボテロ(Françoise Bottéro)先生に会い、施設利用関係の書類にサインをもらうというものだったが、行ってみるとルドゥアン・ジャムリ(Redouane Djamouri)先生が待っていて、昼時ということもあり皆で食事をすることになった。漢字研究のボテロ先生は京都大学に滞在経験があるとのことで、日本語がとても流暢だった。ジャムリ先生は遠藤先生の『ヨーロッパ中国語学の旅』にも出てきた方で、甲骨文の文法研究で学位を取り、近年は中国語西北方言の研究で名高い人である。その時は、近いうちに1回授業の中で講演してほしいという話と、来春までの間に中国の研究者も交えて言語接触関係のシンポジウムをやりたいという話が出て、もちろんこちらに異存のあろうはずもない。
驚いたことに、院生研究室の一角にビジティング・スカラー用のデスクが用意されているという。そこはヒラリー・チャペル(Hilary Chappell)先生のもとで学ぶ院生用の部屋だったが、全員留学生で、コロナのため誰もパリに戻って来られないので、当面の間は一人で自由に使ってよいとのことだった。Inalco、BnFに続く第三の居場所ができて、しかもほぼ個室だというのだから、これは嬉しい。入退館用のカードキーについては、しばらくこれを使うようにと中国人留学生の名前が入ったものを渡され、結局最後までこれを使うことになった。たまたま隣の院生室には、アレクサンダー・ボビン(Alexander Vovin)先生の学生で満洲語をやっているという高君(Kao Hsiang-Tai)という人がいて、同好の士なのでいろいろと情報を教えてもらえることになり、とりあえず週に一度はここで仕事をすることに決めた。10月はいろいろと運が向いてきそうだ。
用意されていたデスク
大学院の授業は11月から始まるそうで、10月下旬にCRLAOの総会と顔合わせを兼ねた立食パーティがコンドルセで行われると誘われたので赴いた。パーティでは琉球語のトマ・ペラール(Thomas Pellard)、シナ・チベット諸語のジャック・ギョーム(Jacques Guillaume)といった新進気鋭の研究者達を紹介されたが、みんなこんなに若いのかよ……という印象で、さすがは天才肌の人を多く輩出しているフランス東洋学である。徐丹先生のもとでバオアン(保安)語に関する博士論文を書いているという院生にも会い、先生のこと知ってますと言われたので、ワインの酔いも手伝って、それは嬉しいねえと調子に乗っていろいろ話していたら、帰宅直後に徐丹先生からメールが来て、11月に研究会をやるので講演をよろしくとあって青ざめる。
でもなんだか、ようやく在外研究らしくなってきた。
[2022.11.8 竹越孝]
フランスっぽい日々(2)〜悩み多き9月〜
そうなのだ。実はそれが大問題だったのである。
もともと、海外に長期滞在できるなら、勝手知ったる(というほど知ってはいないが)中国語文化圏よりは、断然欧米に行きたいと思っていた。それは、若い頃に読んだ遠藤光暁先生の「北京からパリへ――ヨーロッパ中国語学の旅」(もと『中国図書』1995.4-1996.3、『漢語方言論稿』好文出版2000所収)に影響されて、いつか自分もこういう旅をしてみたいと憧れていたからである。サバティカルを取る段階になってもその気持ちは変わらなかったが、いつの間にか、海外に長期で出ること、欧米に行くこと、フランスに来ることが自己目的化してしまって、本当のところ自分がそこで何をしたいのかは曖昧なままだったのだ。
文献調査? もちろんそれが目的の一つではあった。だが、フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France)に所蔵される主要な満漢対訳資料のテキストは、前回来た2013年の夏にあらかた見て、その結果はもう論文や著書の形にしてしまっているので、いま一つテンションが上がらない。この機会に、フランスあるいはヨーロッパにある満洲語文献を一つ残らず調査する、という計画も考えないではなかったが、基本的に関心があるのは言語関係の資料だけだから、満洲語文献の大多数を占める歴史資料をひたすら見続けていくのも気が進まない。やっぱりそれはその分野を専門にしている人がやればよいと思うのだ。
研究交流? もちろん旧知のアラン・ペローブ(Alain Peyraube)先生や徐丹先生など、フランスでお目にかかりたい研究者はいたが、自分よりはだいぶ上の世代の偉い人ばかりだし、日々接する中で切磋琢磨したい、ぜひとも共同研究をしたい、というようなお目当ての研究者はいなかった。ラマール先生に受け入れ教員をお願いしたのも、専門分野の近さというよりは、先生が元同僚のパートナーなので頼みやすかったという理由からである。滞在中に講演や発表を頼まれたら積極的に引き受けるつもりだったし、主だった大学院の授業にも出させてもらうつもりだったが、それは決してメインの活動とは言えない。
観光? もちろんそんなことは口が裂けても言えないし、そもそも全くその気はなかった。実際のところ、これまでさんざん学校のために働いたんだから、半年間の骨休めのつもりでフランスの生活を楽しめばいいじゃないの、とアドバイスしてくれる人(妻です)もいたのだが、何せ目的のない旅が苦手な僕のこと、浮世のことは何もかも忘れて楽しむなんて、1週間どころか3日が限界である。つくづく損な性格なのだ。
悶々とする思いを抱えながらも、とにかくまずは環境を整えなければならない。パリに到着してから1週間ほどたったころ、かたじけなくもラマール先生がアパートの近くまで迎えに来て下さり、一緒に13区にあるInalcoのキャンパスに行って、併設されているBULAC(大学間共同利用言語・文化図書館:Bibliothèque universitaire des langues et civilisations)の利用登録をした。ここはパリ市内の複数の大学と研究機関による共同利用図書館で、東洋学関係の蔵書や情報の一大拠点になっている。ラマール先生がInalcoの副学長だった時代に体制を整えたのだそうだ。登録すると自宅のパソコンからもログインすることが可能になり、代表的な中国関係の論文データベースであるCNKI(中国知網:China National Knowledge Infrastructure)もダウンロードし放題である。開架閲覧室では、朝から晩まで大勢の学生が勉強しているとのことで、いい仕事場所になりそうだ。

13区にあるInalcoのキャンパス

文字部分の拡大
翌日にはInalcoの近くにあるフランス国立図書館のフランソワ・ミッテラン館(新館)に行き、こちらの利用登録もした。新規登録のカウンターで、もちろんフランス語では無理だから、怪しげな英語を駆使しつつ申し込むと、2013年にリシュリュー館(旧館)で登録した時の記録が残っていたらしく、新規ではなく更新になるので以前のカードはそのまま使えるとのこと。とっくに失効していると思って、日本から持ってこなかったことを後悔した。地下にある研究者用のスペースも利用できる1年有効のカードを改めて発行してもらい、その料金は50ユーロだった。フランスに来る前に、身につまされつつ読んだバンド・デシネ(漫画)、ティファンヌ・リヴィエールの『博論日記』(原題:Carnets de thèse、中條千晴訳、花伝社2020)は、この地下空間が一つの舞台である。

フランス国立図書館のフランソワ・ミッテラン館
とりあえず研究の基盤らしきものは整ったが、まだ滞在中にこれをやるという方針が決まっていないため、新しい一歩を踏み出せないようなもどかしい感覚で、せっかく花の都パリにいるというのに、なかなか明るい気分で過ごすことができない。どこに出かけるでもなくアパートの部屋にいて、日本から来たメールに返信したり、残務処理のような書類を作るだけで一日が過ぎていく。あーあ、フランスまで来て毎日何をやっているんだか。
そんな中、2013年には訪れる機会がなかったギメ東洋美術館(Musée national des Arts asiatiques-Guimet)に行ってみようかという気になった。ここは、太田辰夫先生が『中国語学新辞典』(光生舘1969)の「孝経直解」の項目で、パスパ文字版の同書が所蔵されているらしいと記した美術館兼図書館である。僕にとっては、いつかそのパスパ文字版とやらを自ら探し出したいと思っていたロマンチックな場所だったが、どうもそれは誤解らしいことが近年では定説となっていて、前回来た時にはスキップしていたのだ。図書館部門は申請なしでは訪問できないから、とりあえず今回は美術館の参観だけにする。入国から2週間以上たってやっと発行されたワクチン接種証明である衛生パス(Pass sanitaire)を提示して中に入る。もちろん帝国主義・植民地政策の産物なのだろうが、ヨーロッパの中心にあるパリで、これだけの量の東洋美術品に出逢えるというのは、一つの奇跡のように感じる。日本、朝鮮半島、中国、東南アジア、中央アジア、インド、アフガニスタン…と東から西に移っていくにつれて、顔立ちがどんどん西洋風になっていく数々の仏像は、その一つ一つが胸に沁み入ってくるようだった。

ギメ美術館の展示室
そうして仏像を眺めているうちに、ぼんやりとある課題が浮かんできた。悩んだ時には手を動かす、というのが僕のモットーである。とりあえず手を動かしてみようか。
[2022.9.3 竹越孝]
フランスっぽい日々(1)〜パリ到着まで〜
2021年の9月から2022年の3月まで、7ヵ月ほどフランスのパリで生活をしたので、その記録を残しておくことにしたい。タイトルは、フランス語をやり始めてから愛読している『フランス語っぽい日々』(じゃんぽ〜る西・カリン西村著、白水社、2020)をまねたもの。
今や多くの大学でサバティカル(研究休暇)の制度がある。昔は「在外研究」と「内地研修」に分かれていたが、現在では国外・国内の縛りはなく、どこでも好きな所にいられるので、だいぶ融通が利くようになった。ここ数年、大学でも学会でも、忙しくてストレスのたまる役職をやらされ、そろそろ限界に達しそうな感じがしていたので、両方の任期が切れる2021年度にサバティカルが取れるよう、2019年の夏に申請し、それがうまい具合に通った。これで役職の任期延長を打診されることもないし、ゼミの募集もしなくてよい。4月からの半年をフランスのパリで、一旦帰国して9月からの半年をアメリカのハーバードで、という壮大な計画を立て、英会話とフランス語の教室に意気揚々と通い始めた。
ところが、好事魔多し。2020年の初頭から本格的に始まった新型コロナウィルス感染症の世界的流行で、早々とこのプランはあきらめざるを得なくなった。サバティカルを1年延期するという選択肢もあり、実際そうしている同僚もいたのだが、マジック365から数え始めて、やっと行かなくて済むことになった学校に、やっぱり行くなんて絶対に嫌である。それに実際のところ、もとの計画にも無理があったというか、この歳になると全く馴染みのない文化圏で1年にわたる生活を送るというのも相当しんどいので、たとえ数か月でもどちらかに行ければ御の字と、コロナの情勢が変わるのを待つことにした。
年度が改まり、2021年の4月からは家に籠って『KOTONOHA』の連載の貯金を作る一方、週に2度、英会話とフランス語のオンラインレッスンを受けるだけの日々となった。初級中国語の授業という、ここ25年あまり続けてきたルーティンがなくなるというのは、さすがに少し奇妙な感覚である。メールのついでに、こんな感じで毎日単調な生活をしていると書くと、複数の知り合いから、酒の飲みすぎにはくれぐれも注意するようにと釘を刺される。うーむ、そんなに心配されそうな状態なのだろうか。とはいえ、この蟄居生活の中でも何とか心身のバランスを保って過ごせたのは、やはり家族と毎朝のジョギングのおかげなのだろう。
潮目が変わってきたのは6月中旬のことで、EUがこの夏からワクチン接種を条件にビジネス・留学関係の渡航者を受け入れ始めることになったというニュースが入った。ハーバードは9月からの新学期も全面オンラインに決めたとかで、ほぼ受け入れてもらえる見込みはなさそうだ。そこでフランス一本に絞り、受け入れ教員となっていただく国立東洋言語文化学院(Institut national des langues et civilisations orientales, 通称Inalco)のクリスティーン・ラマール(Chrisine Lamarre)先生に連絡を取った。ラマール先生には半年ほど前に、4月から8月までということで受け入れ承諾書(コンバンション・ダキュイ:convention d'accueil)の発行をお願いしたのだが、結果的にそれは無駄になってしまったので、9月から3月までの予定で再度取り直せるだろうかという打診である。受け入れ自体は機関として決定しているのだから問題ないと思う、手配しておきますとの返事で、それならとアメリカの方には断りのメールを入れた。
そうと決まれば準備を急がなければならない。ワクチン接種については、まだまだ自分の年齢に接種券が回ってくるまで時間がかかりそうだったが、基礎疾患ありだと予約が申請できて、自慢ではないが僕は喘息持ちなのである。そのおかげもあって、首尾よく7月末と8月中旬の予定で2回分の接種が決まった。そして、都内にあるフランス留学のあっせん業者をネットで探して、ビザ申請のための書類確認や向こうでのアパート探しなどを依頼するとともに、9月初出発、翌年3月末帰国の航空券を予約した。
6月末にラマール先生の仲介で改めてInalcoにコンバンションを発行してもらったところ、古い書式だったらしく、ビザ申請の際に突き返される恐れがあるというので出し直してもらう。全部紙でやり取りしなければならないから、こういうのが本当に面倒である。ところが、その後再度発送されたはずの書類が待てど暮らせど来ない。ラマール先生に確認してもらったところ、すでに前の日から全学が夏季休暇に入っており、今後1ヵ月は連絡がつかないかもしれないという。まったく何だよ、もう航空券も手配したのに……と頭を抱えていたら、翌日ひょっこり航空便が届いた。後で聞いた話では、空港職員のストで国際郵便にも遅配が起きたらしく、フランスではよくあることらしい。
8月の初めに麻布のフランス大使館に行って研究者ビザを申請、約1週間後に無事発給された。その後はたまっている原稿を片付けることに専念して、年内締め切りの論文2本も何とか仕上げた。最後の2週間は国際学会での発表が連続したが、今は全部オンラインなので気楽といえば気楽である。英会話とフランス語の学習も一旦区切りをつけて、9月1日の深夜、パラリンピックの関係者が目立つ羽田を飛び立った。約12時間のフライトで早朝のフランクフルトに着く。入国審査ではワクチンの接種証明をかなり念入りに調べられると聞いていたのだが、ほとんどフリーパスだった。3時間ほど待ってから乗り換え、1時間ほどでパリのシャルル・ド・ゴール空港に到着。まだ9月2日の朝である。

フランクフルトの空港で
空港には留学業者の人に迎えに来てもらった。貧乏旅行しか選択肢のなかった学生時代でもないので、少々のお金で済むなら、しなくてよい苦労はしない主義である。車に乗って1時間ほどでパリ14区、モンパルナスのアパートに着く。そこではもう一人が待っていて、不動産屋とのやり取りを代行してくれるとともに、居住にあたっての説明を受ける。最後に大ぶりな部屋の鍵を渡され、とにかく鍵は絶対持って出るように、と何度も念を押された。こちらの建物の多くはオートロックだから、確かに鍵を中に忘れて出てしまったら大変なことになる。1年足らず、不真面目に学んだ程度のフランス語で、管理人に状況を説明できるとも思えない。

暮らすことになったアパートの部屋
アパートの部屋は家具付きだがテレビはない。少し寂しい気もするが、たった半年の滞在のためにテレビを買う余裕もないから、近いうちにラジオでも買いに行くことにしよう。一番心配していたWiFi環境は特に問題なく、スマートフォンもパソコンも無事つながったので一安心である。近くにフランスを代表するスーパーチェーンのカルフールがあるとのことで、とりあえず生活に支障はなさそうだ。
業者の人が帰ってから、とりあえず一眠りしようと思ったが、身体の奥の方が妙に興奮している感じで、ソファーに横になってもなかなか寝付けない。それどころか、全く意識していなかった疑問が急に浮かんできて、なかなか頭の中から消えてくれない。……自分はフランスに何をしに来たんだっけ。
[2022.8.6 竹越孝]
あおい春のうた(4)―詩と擬似歌
いまから50年ほどまえ、数年のあいだ、うた(詩や童話や短編の物語)を書く日々をすごしました。 「あおい春のうた」はそのころ(18歳から20歳)のものの一部です。ほぼ半世紀のあいだ書架などの片隅にねむっていました。 いま読みかえすと青春の熱と陰りをみとめることができます。このような熱と陰りやモチーフは、いまの私にはみとめがたく、すでに他人のものと言ってよいかもしれません。 手書きの原稿の誤字をただし、やや表現を整え、「こういち」という名で形にしました。
初回の「あおい春のうた(1)」では詩2題と童話1題をだしました。 これ以後は、童話詩3題、童話2題、擬似歌6首、詩(その1)9題、詩(その2)11題、の5つに分けてだします。 詩と童話ですが、当時の私は両者を区別せずに書いていたと思います。ここでは長短により分けました。 童話詩と詩は内容によります。詩の方には総じて陰りのようなものがみとめられます。 詩(その1)の詩は表現が抽象的で、詩(その2)の詩は写実的です。 擬似歌は和歌のリズムがある詩ですが、和歌の作法にはしたがっていません。
擬似歌6首
詩(その1)9題
詩(その2)11題
[2022.7.2 こういち]
あおい春のうた(3)―童話2題
いまから50年ほどまえ、数年のあいだ、うた(詩や童話など)を書く日々をすごしました。「あおい春のうた」はそのころ(18歳から20歳)のものの一部です。ほぼ半世紀のあいだ書架などの片隅にねむっていました。いま読みかえすと青春の熱と陰りをみとめることができます。このような熱と陰りやモチーフは、いまの私にはみとめがたく、すでに他人のものと言ってよいかもしれません。手書きの原稿の誤字をただし、やや表現を整え、「こういち」という名で形にしました。
初回の「あおい春のうた(1)」では詩2題と童話1題をだしました。これ以後は、童話詩3題、童話2題、詩(その1)9題、詩(その2)11題、擬似歌6首、の5つに分けて順にだします。詩と童話ですが、当時の私は両者を区別せずに書いていたと思います。ここでは長短により分けました。童話詩と詩は内容によります。詩の方には総じて陰りのようなものがみとめられます。詩(その1)の詩は表現が抽象的で、詩(その2)の詩は写実的です。擬似歌は和歌のリズムがある詩ですが、和歌の作法にはしたがっていません。
童話「雨ふり」
童話「母さんのおはなし」
[2022.5.19.こういち]
あおい春のうた(2)―童話詩3題
今から50年ほど前、数年の間、うた(詩と童話)を書く日々をすごしました。「あおい春のうた」はそのころ(18歳から20歳)のものです。ほぼ半世紀のあいだ、書架などの片隅にねむっていました。いま読みかえすと、青春の熱と陰りをみとめることができます。このようなものは、いまの私の中にはみとめがたく、すでに他人のものと言ってよいかもしれません。手書きの原稿の誤字をただし、やや表現を整え、「こういち」という名で形にしました。
初回の「あおい春のうた(1)」では詩2題と童話1題をだしました。これ以後は、童話詩3題、童話2題、詩(その1)10題、詩(その2)12題、擬似歌4首、の5つに分けて順にだします。詩と童話ですが、当時の私は両者を区別せずややながい詩が童話であるというつもりで書いていたと思います。ここでは長短により分けました。童話詩と詩は内容によります。詩の方には総じて陰りのようなものがみとめられます。詩(その1)の詩は表現が抽象的で、詩(その2)の詩は写実的です。擬似歌は和歌のリズムがある詩ですが、和歌の作法にはしたがっていません。
童話詩3題
[2022.4.23.こういち]
あおい春のうた(1)―詩二題「シャボン玉」「北山の赤犬と女」と童話「ジークの白いカバン」
今から50年ほど前、数年の間、うた(詩と童話)を書きためる日々を過ごしました。ここにあげる「あおい春のうた」はそのころ(十八歳から二十歳)のものです。私にとって、詩と童話は区別がなく、ややながい詩が童話、というつもりで書いていたと思います。ほぼ半世紀のあいだ、あるときは段ボールのなかに、あるときは書架にねむっていたものです。いま読みかえすと、青春の熱と陰りをみとめることができます。このようなものは、いまの私の中にはみとめがたく、すでに他人のもの、と言ってよいかもしれません。さまざまな紙に書き付け、メモのようなものとして残っていたわけですが、その誤字をただし、やや表現を整え、「こういち」という名で形にしました。
詩 「シャボン玉」「北山の赤犬と女」
童話「ジークの白いカバン」
[2022.3.26 こういち]
遥かなるケンブリッジ
このタイトルは、後に『国家の品格』で大ブレークを遂げる藤原正彦氏の初期エッセイ集で、氏が1987年から約一年間、イギリスのケンブリッジで在外研究生活を送った時の記録である。『若き数学者のアメリカ』とともに、研究者なるものの生活に淡い憧れを抱いていた学生時代の僕が、最も好んで読んだ本の一つだ。
在外研究ではなかったけれど、そのケンブリッジに行く機会が訪れたのは2019年冬のことである。その年度に科研が取れなくていささか意気消沈していたところ、別の大型科研に関わっていた同僚の一人が勧めてくれたもので、やはり持つべきものはよき同僚と科研である。

正面から見たケンブリッジ大学図書館
一般には理系に強い大学と認識されているケンブリッジ大学だが、その中国学講座初代教授は「ウェード式」で名高いトマス・ウェード(Thomas F. Wade, 1818-1895)で、図書館には彼の旧蔵書が収められている。その蔵書目録(A catalogue of the Wade collection of Chinese and Manchu books in the library of the University of Cambridge, 1898)は、彼の後任だったハーバート・ジャイルズ(Herbert A. Giles, 1845-1935)の編。そして、ウェードの作った近代的中国語教科書の嚆矢である『語言自邇集』(1867初版)は、清代の満洲語文献と浅からぬ縁があるのだ。
『語言自邇集』の会話編をなす「談論編百章」(及びその前段階の著作である1860年の『問答編』)について、多くの先行研究は満漢合璧会話書『清文指要』(1789)の中国語部分を改訂したものとしているが、僕は『清文指要』ではなく、その蒙漢合璧版である『初学指南』(1794)が底本ではないかと睨んでいて、ウェードの旧蔵書の中にその証拠がありはしないかとかねがね思っていたのだ。これまで旧蔵書の中から『語言自邇集』の底本らしきものが見つかったという話は聞いていないのだが、満洲語とモンゴル語は文字がよく似ているから、探し方次第では自分がその発見者になれるのではないかという期待を膨らませていた。
こちらの学校が冬休みに入り、向こうではクリスマス休暇の直前にあたる12月中旬、全部で6日間の行程を組んでイギリスに行くことにした。今回はヒースロー空港に着くのが午後の遅い時間で、いつもだとまずロンドンまで地下鉄で行くのだが、ロンドン経由でケンブリッジに行くとすると、着くのが深夜になるので、本数は少ないがケンブリッジまで直接行けるリムジンバスに乗った。それでもターミナルに着いたのは午後7時ぐらい。滞在先は通常のホテルではなく、ケンブリッジ大学を構成するカレッジの一つ、ニューナム・カレッジ(Newnham College)の宿泊施設で、雨のそぼ降る中、真っ暗な細い通りをグーグルマップ頼りに歩いて行くのは、心細いことこの上なかった。何とか到着し、無事チェックインを済ませると、残してあった機内食のパンをかじってすぐ寝てしまった。

宿泊したニューナム・カレッジの建物
翌日、朝食を済ませてから、雨の中を歩いてケンブリッジ大学図書館へ。受付に行くと、前もって記入してきた閲覧申請書に英語の身分証、パスポートといったところを出し、その場で顔写真を撮られて閲覧カードが発行される。イギリスの図書館は大体どこも同じ手順のようだ。中国・朝鮮・日本関係書のセクションは広い図書館の一角にある「青井パビリオン」にある。一部ずつ申請カードを書いて書庫から出してもらい、閲覧が終わったら一部ずつ返すというシステムで、複数のテキストを比較対照するにはちょっとしんどいシステムである。

中国・朝鮮・日本関係のコレクションを扱う「青井パビリオン」

青井パビリオンの閲覧室
それからの三日間、昼食を図書館内の食堂で取る以外は、青井パビリオンの開室から閉室まで粘り、ひたすら文献の閲覧に挑んだ。あらかじめ目録で目星をつけていたものを最初に見て、それが終わるとコンピューターのキーワード検索や分類カードで当たりをつけたものを出してもらった。時間がないのでできる限り多くの文献を見たいし、一目見て外れだとわかるものも多いのだが、すぐに返すと怪訝な顔をされるので、一応全体を見てノートを取ったりするのがまどろっこしい。結局、残念ながら『初学指南』に関係がありそうな文献は発見できなかった。
とは言え、全く別のことで嬉しい収獲もあった。コレージュ・ド・フランス中国学講座の二代目教授スタニスラス・ジュリアン(Stanislas Julien, 1797-1873)がパリの東洋語学校(Langues O')で教えていた時に作った中国語教材『日常口頭話 Dialogues chinois』(1863)は『満漢字清文啓蒙』(1730)の会話編「兼漢満洲套話」の中国語部分をそのまま引き写したものだが、今回目にした『Dialoghi Cinesi』(1866)というフィレンツェで出た本が、そのイタリア語による注釈編であることがわかった。イタリア語ができるようになったら取り組む価値のある文献だ。
文献調査の方は苦あれば楽ありのとても充実した時間だったが、今回は天気の悪さに参ってしまった。とにかく毎日朝から晩まで、ずっと細かい雨が降り続いているのだ。それに、朝は8時ぐらいにならないと明るくならないし、夕方は4時には暗くなってしまうので、昼が極端に短い。このところ海外出張といえばジョギングが定番で、今回もシューズとウェア持参で行ったのだが、まともに走れたのは一日だけだった。宿舎の部屋にはテレビがないため、図書館から帰っても日本のネットニュースぐらいしか見るものがない。おまけに時差の影響で夜中の変な時間に目が覚めてしまうので、眠るためにスーパーで買った安物のワインをひっかけるという具合で、このままだと確実にアルコール依存になりそうな状態だった。ケンブリッジの気候については『遥かなるケンブリッジ』にもさんざん描写があったのに、すっかり忘れていた。藤原氏は、気候の陰鬱さが世界に冠たる科学大国の源泉ではないかという趣旨のことを書いていたが、全くもってむべなるかなである。
かくして、ほうほうの体で日本に戻ったが、年が明けた2020年からは新型コロナウィルスの世界的流行が始まり、とても海外に行ける状態でなくなったのは周知の通りである。気が滅入って仕方がなかったケンブリッジの陰鬱な天気も、今となってはとても懐かしい。
[2021.9.14 竹越孝]
洋楽と語学
子供の頃、外国語というものを耳にする機会はテレビか映画、あるいは洋楽レコードぐらいしかなかった。私が初めて外国語を外国語として意識して聞いたのは、小学校の3年生か4年生の時に街の映画館で見た『アルプスの若大将』の中のセリフだった。加山雄三と星由里子がスイスで初めて出会うシーンで、互いに日本人だと分からず、英語で会話を始めるというものだ。そのシーンはYouTubeで簡単に見ることができるが、今聞いてもなかなかしっかりとした発音である。
小学生の頃は、外国語はすべて「外国語」であって、英語かフランス語か、あるいはその他の言語かということは意識しなかった。英語を英語として聞くようになったのは、中学に入って英語の勉強を始めてからだ。NHKラジオの『基礎英語』なども聞こうとはしてみたが、何しろ住んでいたのが片田舎で、電波状態が悪く、継続して聞くことはできなかった。それでも「Yes, it is.」の発音が「イエス、イリューズ」としか聞こえなかったのを覚えている。
中学の頃、AMラジオは相変わらず雑音だらけだったが、近隣にFMの中継局ができて、FM放送がクリアに聞こえるようになり、外国語の歌が頻繁に耳に入ってくるようになった。英語ではビートルズ(Beatles)、カーペンターズ(Carpenters)、サイモンとガーファンクル(Simon&Garfunkel)などの歌が英語の発音の手本(というよりサンプル?)になった。ビートルズの「Let it be」はやはり「レルッピー」としか聞こえず、どうやら「t」がラ行に聞こえるのは『基礎英語』だけではないらしいと納得した。一方で、ビートルズの「Yesterday」にしても、高校に入学した年に流行ったカーペンターズの「Yesterday once more」にしても、「イエスタデイ」としか聞こえず、「t」がどういう場合に「ラ行」に聞こえるかに興味を持ったりした。
今は外国語のヒット曲はほとんどが英語で、たまに韓国語が流れるくらいだが、私の中学高校時代にはヨーロッパの曲がちまたに溢れていた。中学に入る頃にヒットしていたのはジリオラ・チンクェッティ(Gigliola Cinquetti)の『雨(La pioggia)』で、そのイタリア語を意味も分からずに口ずさんだものだ。そのサビの部分で「La pioggia」と歌い上げるのだが、私は「ラピオッチャ」と歌っていた。かなり後になって、イタリア語の綴りを見た時に、「チャ」だと思っていたのが「ggia」だと知って驚いたのだが、今聞いてみると、確かに「ラピオッジャ」と聞こえる。今ではイタリア語にどのような音声があり得るかを知っているからだろう。当時の中村少年には「ggia」の部分が濁音には聞こえなかった。それも当然で、日本語には促音(小さい「ツ」)の後には清音しか来ないので、脳の中で「ggia」を清音に変換してしまったのだ。ちょうど、「Let it be」の「be」を清音として「レルッピー」と聞いたのと同じである。
イタリア語の歌といえば、シルヴィ・ヴァルタン(Sylvie Vartan)の『哀しみのシンフォニー(Caro Mozart)』もかなり流行った。これはモーツァルトの「交響曲第40番 第1楽章」にイタリア語の歌詞を付けて歌ったもので、中学の音楽の授業でも先生がレコードをかけてくれた。大学生になってから、横浜の朝日カルチャーセンターまでイタリア語を習いに行ったのも、この曲の歌詞が知りたいからだった。今ではネットで簡単に調べられるのだが。
フランス語の歌もよくラジオから聞こえていた。ヴィッキー・レアンドロス(Vicky Leandros)の『恋はみずいろ(L'amour est bleu)』は私が小学生の時の曲だが、ポール・モーリア楽団のinstrumental盤とともに、中学時代にもよく流れていた。そして『シェリーに口づけ(Tout, tout pour ma chérie)』をはじめ多くのヒット曲を出したミッシェル・ポルナレフ(Michel Polnareff)も強く印象に残っている。イタリア語が底抜けに明るい響きを持っているのに対して、フランス語には一種の“気難しさ”を感じたものだった。それはミッシェル・ポルナレフが与えた印象もあったかも知れないが、日本語やイタリア語にない音声を多く含んでいることも理由だったと思う。有名な鼻母音だけでなく、口蓋垂の「r」があり、さらに円唇の前舌母音が3種類もあったことが、少し取っ付きにくい雰囲気を醸し出していたのだろう。
スペイン語の曲としては、高校に入った年にドラマの主題歌として、グラシエラ・スサーナ(Graciela Susana)がカヴァーした『アドロ(Adoro)』が流行った。日本で活躍した彼女は、この歌をまず日本語で歌いはじめ、途中から原曲通りのスペイン語に切り替えた。彼女の歌唱力もあって、哀切ただよう情熱的なスペイン語の響きに魅了された。その影響で、テレビのスペイン語講座でスペイン語の勉強を始めたほどだ。大学も外国語学部のスペイン語科を受験したが、不合格だった。それでも大学時代、2年間スペイン語の授業を受けた。2年目は受講生が私一人だけになり、ガルシア・マルケスの小説を読んだ。ちょうどその頃、フリオ・イグレシアス(Julio Iglesias)の『ビギン・ザ・ビギン(Begin the Beguine)』や『黒い瞳のナタリー(Nathalie)』が日本でも大ヒットしていた。スペイン語で歌う彼のレコードが全世界で3億枚売れたというのだから、今考えてもすごい。イタリア語とスペイン語はよく似た言語だが、与える印象は全く異なる。イタリア語は軽薄なほど明るく、スペイン語は切なくも厳粛である。イタリア語で女性と語り、スペイン語で神と語ると言われる所以だ。
外国人が日本語で歌うのを聞くのも楽しかった。1960年代に、サルヴァトール・アダモ(Salvatore Adamo)がフランス語で歌う『サン・トワ・マミー(Sans toi ma mie)』『雪が降る(Tombe la Neige)』は世界中でヒットしたが、日本では特に彼自身による日本語版『雪が降る』がヒットした。その日本語はフランス語の癖が少し残っていて、なかなか魅力的だった。特にウ段の母音を明瞭な円唇母音[u]で発音するのが際立った特徴だった。1960年代から1970年代にテレビで活躍したフランソワーズ・モレシャン(Françoise Moréchand)の日本語も全く同じ特徴があって、私はフランス語そのものよりもフランス語訛りの日本語の方が好きになったほどだ。それで(というわけでもないが)大学ではフランス文学を専攻して、毎日フランス語の文章を音読することを楽しみにしていた。フランス語の発音モデルはアダモの『雪が降る(Tombe la Neige)』やエディット・ピアフ(Edith Piaf)の『愛の讃歌(Hymne à l'amour)』だった。
フランス語の[u]にこだわったのは、中学時代以来の宿題(?)とも関連する。当時の中村少年がなぜ「Yes, it is.」を「イエス、イリューズ」と聞き、「Let it be」を「レルッピー」と聞いたのかということである。今思うに、これには二つの要因がある。一つは英語の「it」や「is」の母音が日本語の「イ」よりもかなり舌の位置の低い母音であること。もう一つは、私の「ウ」が完全に非円唇中舌母音であったことである。まず、前者についてだが、当時中学生の私が使っていた英和辞書では「it」と「eat」の発音はそれぞれ[it][i:t]と表記されていた。私はそれを鵜呑みにして長短の違いだと思っていた。しかし、これは日本人による解釈であって、英語ネイティヴの音韻観念から見れば、それらの示差的特徴は舌の位置が低いか高いかにある。今では多くの辞書が[ɪt][it]として区別しているはずである。後者については、日本語の「ウ」の円唇性が地方によって異なることが問題としてある。関西ではフランス語ほどではないが、比較的円唇性が保たれている。関東ではその円唇性がだいぶ緩い。そして、私の故郷である岩手では、さらに緩いのである。半世紀前には、「ち」と「つ」の区別ができない老人が多くいたものだ。そんな地方で英語の「it」「is」を聞くと、その母音が当時の中学生の耳には「イ」よりは「ウ」に近く聞こえたということなのであろう。
今では英語以外の洋楽を聞く機会はほとんどないので、音楽を通じて外国語に接することもあまりない。もっとも、興味さえあれば、ネット上で様々なアクセスが可能なので、洋楽に限らず、YouTubeの動画などで種々の言語に接することはできる。しかし、選択肢が多すぎるというのも、かえって不便なものだ。音楽やドラマを受動的に聞いたり見たりする機会はどんどん減り、よほど自ら能動的に関わらなければ、英語以外の外国語に触れることはないのが実情であろう。自らの中学高校時代を振り返る時、選択肢が少なかったが故に、かえって多くの言語に接することができたのは幸せであったと思うのだ。
[2021.5.28 中村雅之]
「墓と本」
このところ、在華宣教師ポワロ(Louis Antoine de Poirot,1735-1813)の手になる満漢合璧版『古新聖経』に関する研究書を作ることに注力している。原本はサンクトペテルブルクのロシア科学アカデミー東方文献研究所蔵の鈔本、内田慶市先生(関西大学)の研究グループが発見してきたもので、先ごろ影印も出た(内田慶市・李奭學編『古新聖經殘稿外二種:北堂本與滿漢合璧本』,関西大学出版部,2019年)。数人の院生とともに、2年ほど読書会の形で読み進めてきて、このたびその校注・索引と関連の論考を一書にまとめて出版しようという計画である。
1770年に来華した最後期のイエズス会士であるポワロは、宮廷画家として清朝廷の信任を得る一方で、新旧約聖書の単独全訳という大事業に挑んだ人物である。北京では蛍池口の北堂教会に起居し、標準ラテン語版(ウルガタ)の新旧約聖書をすべて満洲語に訳したほか、中国語では全体の三分の二に及ぶ量を訳した。『古新聖経』と称されるこの書は、世界で最初の満洲語訳であり、最初の白話体中国語訳と言える。彼は1803年にバチカンの教皇庁に訳書の刊行を願い出たが、すでに聖書をいかなる言語にも翻訳することを禁じていた教皇庁は、出版の不許可を言い渡し、彼は失意のうちに生涯を閉じる。出版されることのなかったこの書は、長らく「幻の聖書」と言われてきた。
今回サンクトペテルブルクで発見されたのは満漢対訳の合璧版だが、『古新聖経』には単独の満洲語版や中国語版の鈔本も現存する。満洲語版は東洋文庫やイギリスの聖書協会(Bible Society,英国外国聖書協会 The British and Foreign Bible Society を前身とする)等にあり、東洋文庫本は今回満漢合璧版と校合している。その解説を書くために、東洋文庫本について記した松村潤「満洲語訳の聖書について」(『東洋文庫書報』第7号,1976年)を読んでいたら、聖書協会本に触れた部分で、Swanという人物がサンクトペテルブルクで鈔写したという記述が目に入り、はたと考え込んだ。この名前はどこかで見た覚えがある。
スワン、スワン…としばらく考えたり調べたりした後に、売り払わずにまだ自宅に残っていた、クリーム色の背表紙を持つ文庫本に行き着いた。衛藤利夫(1883-1953)の『韃靼』(中公文庫,1992年)、もとは1938年に刊行された本である。衛藤は旧満州国にあって奉天図書館の館長を務めた伝説の図書館人。その巻頭にあった「墓と本」という随筆を学生時代に読んでいたのだ。
奉天から大連に向かう夜行列車の中で、大藪と名乗る紳士と知り合った衛藤は、簡単な挨拶を交わした後に、ふとあることを思い出して、だしぬけに次のような会話を始める。
「貴下は蒙古語のバイブルの訳書を御覧になったことはありませんか?」
「蒙古語のバイブル? エゝ一冊持っております」
「旧約ですか、新約ですか?」
「新約です」
「誰か、訳者を御記憶はありませんか?」
「サア、久しく見ないものですからハッキリしませんが、たしかスワンと云ったように憶えております」
「ナニ、Swanですって!?」と恐らく自分は絶叫したかも知れない。少くとも対手方は、自分の突拍子もない語調にビックリされたらしかった。同じ車室に居合わして、まだ寝つかない二、三人が顔を上げてこちらを見たような視線を自分は頬に感じて、われながらハッとした。
「や、ドウも」とテレ隠しに笑いながら、「実はそのSwanをこの二年来、親の仇でも探すように探していたものですから。…」(pp.16-17)
独特の諧謔味ある戦前の文体と、「親の仇でも探すように」という表現が強く印象に残ったことを思い出す。この文章は、19世紀初頭、ロシア統治下にあるブリヤートにやって来た二人のイギリス人宣教師、スワン(William Swan,1791-1866)とスタリーブラス(Edward Stallybrass,1794-1884)をめぐるものである。彼らは1817年、張家口、キャフタを経由してシベリアに入ると、セレギンスクという町から奥地のオナーゲン・ドーメに至り、以来25年その地で宣教活動を行うとともに、新旧約聖書のモンゴル語訳に励んだ。1840年に旧約聖書のモンゴル語訳をセレギンスクで出版した後、ロシアの官憲によって退去させられると、新約の方はロンドンで出版した。その間、スタリーブラスは二人の妻と子供を病気で失い、その墓が今もセレギンスクにほど近いセレンガ河の堤上にあるという。
ポワロが暮らした北堂教会の蔵書は、その後ロシア正教会に接収されたというから、彼の生前刊行されることのなかった『古新聖経』もその中に入っていたことは疑いない。松村氏の論文を突き合わせると、スワンはブリヤートに向かう途中、あるいはその帰路に、サンクトペテルブルクに立ち寄ってポワロの満洲語訳聖書を目にして鈔写し、イギリスに送っていたことになる。
スワンとスタリーブラスによるモンゴル語訳聖書は、夜行列車での会話が縁で、大藪氏から奉天図書館に寄贈されることになった。衛藤はこの文章を次のように結んでいる。
当年の露都セント・ペテルブルグから渡り渡って、今ここ奉天に来るまでに、何人の手沢を留めたか、背革は少し磨れて、中古のいい本にのみ見られる蒼勁の色を湛えている。自分は、永久にこの図書館に置くことを許されたその本を、飽かず愛撫しては、ヤハリ今も涯てしなき白雪に掩われているであろうところの、セレンガ河畔と、そのまた奥にある墓のことを思うのである。
「墓と本!」
左様云って見ては、云おうようなき人生の哀歌を、曠野の果てに聴くような思いをする。(pp.42-43)
この部分を読んだ時は胸が熱くなる思いで、強烈にロマンをかき立てられたことをよく覚えている。当時僕は駒込の東洋文庫でアルバイトをしており、図書館人という将来の選択肢も割と現実味のある頃だった。何せ、大学に就職が決まったと早稲田の古屋昭弘先生に報告した時に、てっきり東洋文庫に就職するものだと思っていたと言われたぐらいである。
その後、東西交渉や宣教師関連の資料とはあまり縁のない勉強を続けてきたのだが、今回全くの偶然から点と点が繋がり、こうした世界が自分の興味の範疇に入ってきたのは、正直言ってとても嬉しい。そしてまた、おそらく30年ぶりに、この本を読んだ時の自分の感情とも向き合うことになった。幸い、その時に感じた書物をめぐるロマンは、自分の中で全く衰えていない。自分はやっぱり、言語学者であるよりも文献学者でありたいなあ。まあ実態は中国語教師だから、どっちでも呼ばれないだろうけれど。
[2021.3.23 竹越孝]
字源研究
漢和字典を開くと、[字解]などと称して、それぞれの漢字について、字形の構造や成り立ちについての説明がある。しかし、字典ごとに説明はバラバラであり、どれが正しいか全く分からない。困るのは、どの字典も自説のみを述べ、読者に判断材料を与えないことである。
近年、落合淳思氏が積極的に字源研究の成果を一般向けに発表しており、この分野に興味を持つ者としてありがたくも喜ばしい。具体的には『漢字の成り立ち』(筑摩書房、2014)、『漢字の構造』(中公選書、2020)、『漢字の字形』(中公新書、2019)であるが、特に前二者はこれまでの主な解釈を示しながら自説を展開しているので、読み手が是非を判断しやすい。
落合氏の方法の特徴は、甲骨文字や金文の古い字形を丹念に集め、さらにその用例を精査して、基本的な字形と字義の最も古い形をとらえようとしていることである。本来これは基本的な作業のはずであるが、実はこれまでの研究には、『説文解字』の説明を鵜呑みにしたり、後期の字形や字義を用いて自説を都合よく組み立てることが非常に多かった。
「求」の字源について、過去のほぼ全ての研究者が毛皮の象形と見なしているが、それは『説文解字』の誤読によるものと落合氏は言う(『漢字の成り立ち』p.223)。『説文解字』の「裘」の項に「皮衣也、从衣求聲…」とあり、続けて「求」のみの字形を挙げて「古文省衣」として、秦代以前の字形では衣を省いた「求」のみで「皮衣」を表すという。この説明によって、多くの研究者は「求」を「かわごろも」の象形と誤解したのだが、落合氏の指摘のように、『説文解字』ではそのようなことは述べていない。単に古文の字形が声符の「求」のみを表記した、いわゆる仮借だと言っているだけである。つまり、「求」の字形と「かわごろも」とは何の関係もない。実際、甲骨文字では「かわごろも」の意味で「求」は用いられず、「衣」に短い線を数本加えた形で見えるという。西周の時代になってやっと「求」を声符とする字形が出て来る。
これはかなりの驚きであった。私自身も、「求」が「皮衣」の象形だという説は知っていたし、『説文解字』も見たはずだが、疑ったことはなかった。よく見てみると、「求」の字形は確かに「かわごろも」には全く似ていない。落合氏によれば、「求」の古い字形は祭祀に用いる植物の象形であるという。「奏」の甲骨文字が“求”を両手でささげる形であることなどを根拠としている。
字源研究にはそれぞれの研究者のアプローチの方法(つまり“癖”)がある。加藤常賢や藤堂明保は字音を中心に据え、白川静は主に字形を扱ったが、落合氏の評価が実に的確で面白い。いわく、「字音を重視した研究者のうち、加藤常賢は、象形文字や会意文字であっても形声文字として解釈する特徴があった。また、藤堂明保はかつての右文説に近く、形声文字の声符にも意味を認める傾向が強い。これに対し、白川は形声文字であることを否定し、会意文字として解釈することが多かった。大雑把に言って、加藤が「形声説」、藤堂が「亦声説」、そして白川が「会意説」ということになるだろう。」(『漢字の成り立ち』p.189)
言い得て妙である。いわゆる声符には、もともと象形文字や指事文字だったものに後から意符が加えられて声符になったものや、純粋に発音のみを表したものがあるが、それらの見極めにはなかなか微妙なものがあり、そこにそれぞれの癖が露出する。予想通り加藤や藤堂に対しては容赦ない批判が展開されているが、意外だったのは白川に対してもバッサリと切り捨てている部分があり、冷静な検討を加えていることである。本の奥付で落合氏の経歴を見ると、立命館大学の出身で現在は「立命館白川静記念東洋文字文化研究所客員研究員」という肩書なので、てっきり白川学説の継承者かと思っていたが、そういう訳でもないらしい。その白川評は、「特に大きな問題は、呪術儀礼を重視しすぎたことである。白川は字形からの字源分析法を確立した人物といっても過言ではないが、その白川自身が、字形からの分析よりも、呪術儀礼としての解釈を重視して字源研究を行ってしまったのである。」(『漢字の成り立ち』p.150)というものだ。
甲骨文の豊富な用例に基づいた上で、字形と字義を検討した落合氏の字源分析は信頼できるが、字音に関する部分には危うい記述も多い。例えば、もともと「鼻」の象形であった「自」について、『漢字の字形』では次のように述べる。
「しかし、これらの字形は本来の「はな」の意味ではなく、当て字で起点を表す文字として使われた(「〜より」の意)。」(p.136)
「現在の音読みでも、「自」と「鼻」は子音が異なっているが、この変化が早くに発生し、その違いを表記するため、「はな」の意味には発音記号として「@」を追加したという経緯が想定される。」(p.137)*「@」は「田+丌」
この表現から察するに、落合氏は《はな》という語の発音を借りて、《〜より》という語に当てたと考えているらしい。しかし、日本語の音読みで「ビ」と「ジ」であるように、この二者は全く異なる発音であり、それは中古音でも上古音でも同様である。上古以前に遡れば仮借できるほど近い発音だったと考えるのは、少々無理がある。事実はおそらく次のようなことではなかろうか。《はな》の象形である「自」の字形が《はな》を意味する語(「ビ」に相当する)のほかに《みずから》を意味する語(「ジ」に相当する)をも表した。多くの研究者が言うように、殷代には日本と同じように鼻を指して自分を意味したためであろう。そして、その「ジ」に相当する音が《〜より》と同音だったために、仮借して「自」を《〜より》の語に用いた。つまり《はな》と《〜より》には直接の関係はない。《はな》と《みずから》が字形によってつながり、《みずから》と 《〜より》が字音によってつながっているのである。
字音にのみ注目して、字形や字義を疎かにするのは愚かなやり方だが、字音を軽んじれば、やはり正確な字源研究はできない。漢字の研究はなかなか難しい。
[2021.2.26 中村雅之]
生殺与奪
「生殺与奪」の読みが話題になっているようだ。え?「セイサツヨダツ」だったの?「セイサイヨダツ」じゃないの?という訳だ。このテーマは数年前から何度かネット上で盛り上がったたことがある。そして今月になって再燃した。きっかけは『鬼滅の刃』(きめつのやいば)だ。2016年から連載が始まったこの漫画は大人気を博し、2019年のTVアニメ放送は、子供のみならず青少年、主婦、OL、オジサンに至るまで、一大ブームを巻き起こした。そして今月公開された『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』はわずか10日目にして史上最速で興行収入100億円を突破した。
この『鬼滅の刃』第1話に「生殺与奪の権を他人に握らせるな」というセリフがあり、そこには「せいさつよだつ」とルビが振られている。子供が「せいさつよだつ」ってどういう意味?と尋ねると、親や先生は「それはな、セイサツではなくて、セイサイヨダツと読むのだ」と得意げに言うのだが、子供に辞書を引かせると「セイサイヨダツ」という項目はなく、「セイサツ〜」しかない。最初、親の方は、最近は正しい読みを忘れて間違った読みが通用しているのか、と嘆くのだが、実はどんなに古い国語辞典を引いても「セイサツヨダツ」しかないのを知り、途方に暮れる。
昭和時代に高校を卒業した世代なら、「セイサイヨダツ」と読むことが当たり前で、その読みを疑ったことがないのではないか。たまに「セイサツ〜」と読む生徒がいると、先生が「セイサイ〜」と読むのだと教え諭す風景は全国で見られたはずだ。それなのに、その読みが辞書にないと知って、狐につままれたような気になるのだ。ネットには時々こんな書き込みがある。−−「殺」を「サイ」と読むのは「そぐ、へらす」の意味の時だ。「相殺(ソウサイ)」「減殺(ゲンサイ)」のように。「ころす」の時は「サツ」と読むべきなので、「生殺与奪」の場合は「セイサツ」が正しい、と。しかしながら、昭和世代は釈然としない。それなら、なぜ我々はわざわざ「セイサイヨダツ」という普通でない読みを覚えさせられたのか?
ありうる答えは、おそらく日本ではかなり昔から「生殺」を「セイサイ」と読み習わしていたのだが、近代になって辞書編纂の際に理屈として正しい読みを導き出した結果、「ころす」の時は「サツ」という解釈を取るようになったのではないか。それではなぜ口伝では「セイサイ」だったのかというと、「殺」には「ころす」の意味の時に「サツ」と「サイ」の両方の読みがあるからである。上に紹介したように、「ころす」は「サツ」で、「そぐ、へらす」は「サイ」と思い込んでいる人も多いが、実際には「サイ」には「そぐ」と「ころす」の両方の意味がある。
中国語音韻史の中心的な資料である『広韻』(正式には『大宋重修広韻』、1008年刊行)では、去声怪韻と入声黠韻に「殺」が見える。去声の方は「鎩(所拜切)」の小韻にあるので、日本語の「サイ」に相当する。入声の方は「所八切」で「サツ」に相当する。そして去声怪韻の「殺」を見ると、その注釈には「殺害又疾也、猛也、亦降殺周禮注云殺衰小之也。又所八切」とある。つまり、「サイ」と読む場合でも、真っ先に挙げられている意味は「殺害」であり「ころす」に他ならない。「そぐ」に相当する意味は最後の方に『周礼』の注を引用して述べられている。入声の方は「殺命。説文戮也。所八切」とあり、これも「ころす」である。要するに、「生殺与奪」を「セイサイヨダツ」と読むことには相応の理由があり、決して誤りではない。だからこそ、永い間の口伝によってその読みが続いてきたのであろう。
「サイ」と読む「殺」は、伝統的には「shài」という発音だが、今の普通話では採用されず、「shā」に統一されている。「殺」のように去声と入声の二つの発音を持つ字はいくつかある。「切(サイ、セツ)」「出(スイ、シュツ)」など、いずれも入声の読みが有力で、去声の方は限られる。念のために去声に読む例を挙げると、「一切(イッサイ)」「出師表(スイシのヒョウ)」など。「切」の去声は「すべて」の意、入声は「きる」の意で棲み分けがあるが、「出」は「スイ」でも「シュツ」でも意味は変わらない。「出師(スイシ)」は「出陣(シュツジン)」と同義である。時代が下れば、「スイ」の読みは退けられて、「シュツ」に統一されるかも知れない。その時は「出師(スイシ)」や「出納(スイトウ)」も「シュッシ」「シュットウ(シュツノウ)」になるのだろう。
言葉は時代とともに変わるものであるから、「生殺与奪」が「セイサイ」から「セイサツ」に変わろうとも本来目くじらを立てる必要はない。ないが、やはり気に入らない。語呂が悪いのだ。「セイサツヨダツ」は「ツ」が多くて言いにくい。まあ、これも慣れなのだろうが。『鬼滅の刃』は大正時代の話である。おそらく、その頃には「セイサイヨダツ」と読む人が多くいたのではないかと想像する。それならば、時代の雰囲気を出すためにも「セイサイ」でよいのでは?とウジウジとこだわってしまうのだ。「早急(サッキュウ)」も最近は「ソウキュウ」と読まれるようになった。「早」に入声の読みはないから。「早速(サッソク)」もそのうち「ソウソク」になるのだろうか。その時にも、それは語呂が悪い、と言い続ける年寄りになりそうだ。
[2020.10.31 中村雅之]
韓国語なまりの英語
今年の4月・5月はご多聞に漏れず疫病蔓延に伴う自宅待機が続いたので、朝ゆっくりテレビを見る機会が増えた。その中でたまたま見た「虹プロジェクト」がなかなか面白かった。これは韓国の大手芸能事務所「JYPエンターテイメント」と日本の「ソニーミュージック」が共同で行ったガールズグループ結成のための人材発掘プロジェクトで、約1年間にわたって選考がおこなわれた。なにしろK-POPは今や世界を席巻している。男性グループ「BTS(防弾少年団)」はアメリカのヒットチャートで何度も1位を獲得しているし、女性グループである「TWICE(トワイス)」も日本を含む世界各地でコンサート開いている。他にも多くのグループが世界中にファンを持ち、最近ではHKT48にいた宮脇咲良や矢吹奈子が所属する「IZ*ONE(アイズワン)」も大人気だ。
「虹プロジェクト」には最初1万人ほどの応募者があったらしいが、一次審査から三次審査までを経て合格した26人が東京で4泊5日の合宿トレーニングをおこない、さらにそこで選抜された13人が6か月にわたって韓国で訓練を受けた。ダンスや韓国語の授業を受けながら、毎月のようにプロデューサーであるJ. Y. Parkことパク・ジニョン氏の前で発表会(showcaseというらしい)をおこなった。初めは1人で、次には3人から4人のグループ、最後は6人のグループになって課題曲に挑んだ。最終的に9人のメンバーが選抜され、12月2日に「STEP AND A STEP」という曲でデビューすることが決定している。これに先立って結成直後の6月30日に発表したプレデビュー曲「Make You Happy」は、わずか数日で再生数1千万回を超え、累計ではすでに1億回を超えるという快挙を達成している。
私が注目するきっかけは、彼女たちの韓国語との格闘であった。東京合宿での最後のショーケース(“発表会”ですね)で、数名ずつに分けられた中のあるグループがそれまで聞いたことのない曲をやることになった。課題曲を知らされてからJ. Y. Parkの前で披露するまでに、わずか48時間で韓国語の歌とダンスの振り付けを覚えなくてはならない。かなりのムチャ振りだが、それにどう対応するかも審査項目だったのだろう。15〜18歳の少女たちが必死で韓国語を覚える姿には心を打つものがあった。小さなミスはあったものの、そこそこの発音で歌い切ったのは、若さ故の対応能力と彼女たちの必死の努力であろう。
ショーケースの課題曲になったのはK-POPのヒット曲ばかりで、取り分け事務所の先輩である「TWICE(トワイス)」の曲が多かった。私が特に興味を持ったのは、韓国合宿のMission 3で「IRIS(アイリス)」というグループ名でマヤ、ミイヒ、ユナ、アカリの4人が披露した「Feel Special」であった。これはTWICEの去年のヒット曲で、サビの部分に「You make me feel special」という歌詞がある。ミイヒが歌ったそのサビの「make me」の部分に私は少し違和感を持った。「make[meik]」の[k]が全く聞こえなかったからである。まあ、15歳のミイヒだから、英語の発音をそんなに気にしなくてもいいかと思いながらも、せっかくの機会なので、TWICEの原曲を聞いてみた。驚いた。そこでは「make me」が[meiŋ mi]と発音されていた。[m]の前の[k]が[ŋ]で発音されているのだが、鼻音の前の破裂音が鼻音に同化するのは韓国語なまりである。
2016年まで国連事務総長だった潘基文(パン・ギムン)氏が何かのインタビューで「私のニックネームは……」と英語で言ったことがあった。その時の彼の発音が[mai niŋneim]であった。その映像をテレビで見ながら、おお韓国なまり、と思ったものだった。かなり英語が達者だった潘氏だが、この訛りは抜けなかった。それほど、韓国人にとって鼻音の前の破裂音はやっかいな発音なのである。日本語で似たような例を探すとすれば、促音の後の濁音だろうか。「ベッド」「バッグ」のように小さい「ツ」の後に濁音が来ると、10人中9人はおそらく「ベット」「バック」と発音する。日本語では促音の後は清音と決まっているからである。韓国語では、鼻音の直前で破裂音の鼻音化はオートマチックに起こる。それが英語を話す時でも自然に適用されるのであろう。
TWICEの原曲で「make me」を[meiŋ mi]と発音していたと上に述べたが、実はこのサビを最初に歌うのは日本人メンバーであるSana(サナ)なのだ。その後にJihyo(ジヒョ)も同じ個所を歌うが、当然[meiŋ mi]と歌う。Sanaはコンサートや歌番組で歌う時には[meiŋ mi]と歌うこともあれば[meik mi]の時もある。Sanaはどうして[meiŋ mi]と発音するのか。これには二つの解釈があり得る。一つはこの曲を作ったJ. Y. Parkのデモ録音の発音を真似した。もう一つは韓国語に熟練した結果、韓国人と同じ癖が出た。私はその両方かもという気もしている。何しろSanaの韓国語はネイティヴ並みである。韓国人が聞いてもすぐには日本人だとバレないレベルだ。IZ*ONE(アイズワン)のメンバーとして2年前に韓国に渡った矢吹奈子もかなり流暢な韓国語を話すが、Sanaのレベルには程遠い。
ところで、「虹プロジェクト」で生まれた新しいグループの名前は「NiziU」である。「ニジュー」と読む。この名前はJ. Y. Parkによれば、「need you」に掛けたものらしいが、果たしてこの説明に納得した人はどれほどいただろうか。「need you」は日本語式には「ニージュー」であって、「ニジュー」ではない。「ニジュー」と聞いて、「need you」を連想する日本人は皆無だろう。しかし、母音の長短の対立を持たない韓国語の話者にとっては、「ニージュー」も「ニジュー」も区別がないのである。
私は韓国の歴史や文化にさほど興味はないし、ましてやK-POPには露ほどの関心もなかった。しかし、K-POPの世界に進出するために韓国に渡って、あっという間に韓国語を習得してゆく若い歌手たちを見るのはこの上なく楽しい。
[2020.10.17 中村雅之]
舞台で聞いた中国語28……依拉克特瑞!(エレクトラ!)
一昨年の春の北京にてたまたま悲劇の公演に行き当たった。古代ギリシア悲劇を基にして書かれた『晩餐』である。ギリシアの作家、ヤコボス・カンバネリス(1912-2011)の戯曲が原作である(羅錦鱗演出、北京人民芸術劇院実験劇場)。
おお、出た、王道ギリシア悲劇! などと感心している場合ではなく、基になっているという「アガメムノン」などのギリシア神話を少しでもおさらいしてから観劇に臨むべきだったが、時間と労力の関係で一切省いてひとまず劇場へ。以前の稿で、中国語発音のロシア人の名前が難解だと書いたことがあるが、ロシア人以外も同じだった、とその日にはたと気付がつく。しかも、ギリシア人の名前は日本語で聞いても煩雑で、「〜ステス」くらいしか私の耳には残らない。何やら高校の世界史の授業が思い出されるばかりで、日本語にしたところで結局心許ない。知識も中国語力も乏しい私が劇場の客席に座ったら最後、頼りにできるのは(心理的に)、日本から携えてきたビクセンの双眼鏡だけである。

北京人民芸術劇院実験劇場の入口(劇場は4階)
物語は血で血を洗う悲劇で、最後、一人を残して皆死んでしまう。「晩餐」は、毒を盛る本人も含めた全員の死を仕掛ける最後の晩餐である。なぜ殺し合うかというのは複雑だが、一つは復讐、もう一つは贖罪だ。あらすじを言うと、夫に自分たちの娘の一人を神への生贄にされた恨みから、妻が恋人を作り共謀して夫と夫の愛人もろとも殺す。妻は恋人と再婚する。夫婦の息子ともう一人の娘がそれにふつふつと怒りをたぎらせ、母親と継父を殺して実父の仇討ちを果たす。子供たちは母殺しの罪の決着を自害してつける。古代ギリシアの話として聞くと、ふーん、と思ってしまうが、現代でも、しかもご近所あたりでも起こり得そうだと考え出すと結構恐怖する。
実際には物語では子供たちだけが生きていて、すでに死んでいる親たちが亡霊となって行き来する。親殺しの罪悪感で半狂乱になった子供たちが亡霊の声を聞きつけたり、亡霊たちが自分たちの言い分を(一方的に)語りかけたりすることで、殺し合ったいきさつがわかってくる。もちろん私は人一倍亡霊の判別に忙しい。観客だけに見える人物、という演出は難易度が高くて困るのだが、とりあえず近い距離ながらもせっせと双眼鏡を覗いてみるのだった。
硬派な悲劇もたまには観ようかという試みは成功だった、と述べたのには、もう一つ、「老演員」が出演していたことがある。北京人民芸術劇院の小劇場は比較的若手の出演者が多いようだが、『晩餐』では小劇場であまり見かけないベテラン俳優も出ていた。その一人、継父アイギストス役の叢林はどんなに控えめに言っても最高だった。その張りのある伸びやかな美声は若手と比べて質、力量が断然違い、そのため明らかに俳優自身の存在感も違う。舞台と距離の近い小劇場の観客席で接すると、なおのことプロの凄さが迫る。傍で演じている若手俳優の声があまりにか細く聞こえ、「ご飯食べてますか」と聞きたくなるほどだった。まだまだ目の肥えていない私の感想とはいえ、「いやー、びっくりした」としか言いようがない。
もう一つ印象的だったのは、ときおりじっくり流れる乾いた笛と打楽器の音楽。物語の舞台はギリシアだが、とても東洋的で、中央アジアの草原や閑散とした寺院、あるいは日本の寂れた草庵といった風景を彷彿とさせるようだった。今思い返すと、最後に訪れる全員の死と、彼らの死もまた時とともに過ぎ去ってゆくのだという無常さを感じさせるようでもあった。

カーテンコール
[2020.9.5 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語27……你自己不想好起来嗎?(自分でよくなりたいと思わないのかい)
一昨年、北京、蓬蒿劇場を訪れた。この劇場は入口が表通りに面していないため、いつも入口を見過ごしてしまう。何度か行ったことがあるにもかかわらず、この日はそもそもの裏路地(胡同)から間違ってしまい、見当違いの通りを右往左往してから、3回も地区守衛の男性に道を聞いてようやく汗をかきかきたどり着いた。
それにしても、毎日この地区の守衛に当たっている人たちが、1、2本路地を隔てただけのこの劇場の存在を知らないのには少々参った(すぐ傍の南羅鼓巷という小さな通りが商業街になって賑わい出してから、こうしたガードマンが立つようになった。主には車輌進入を規制しているようだ)。劇場のオープンは10年ほど前(2008)であるし、場所も有名な演劇大学(中央戯劇学院)のお隣だから知られていそうなものだが、小さすぎて全然目に入らないらしい(私の方も最初から大学の場所を尋ねればよかったのだが)。確かに、劇場といっても家屋の建物だ。観客席は100席に満たない、大きめの部屋といった空間の小劇場である。
汗を拭きつつ、気を取り直して臨んだ上演は『アンナの心理相談』《安娜的心理咨詢》(劉紅卿脚本、趙瑞寧演出)。第9回南羅鼓巷演劇祭の演目とのこと(演劇祭は文化振興の一環で、いろいろな脚本、演出家を推奨して上演を行う主旨のようだ)。寂しく孤独に心理相談を長年やってきた男が、ある日相談にやって来た女性患者・アンナの心を開かせて巧みに誘導し、心理相談室を引き継がせ、自分は自由になるという物語である。
なるほど。若き悩めるアンナがどう問題を口に出し、解決の道を見つけるのか、という話のように見えて、実はカウンセラーの男の方が心理相談室に縛られ孤独に悩んでいたという話だった。この心理相談室はこうして交代できる者が見つかるまで離れることができないらしい。後半からの主客転倒と、なんとなく背筋がぞくっとする感じが、星新一のショートショートに似た雰囲気である。
最初、自分をさらけ出すことに抵抗のあるアンナは、話し渋り、男とまっすぐ向かい合えない。話しているうちに眠り込んでしまったりする。しかし、男は「你自己不想好起来嗎?」と押しの強い口調でアンナに迫りながら、徐々に話を引き出してゆく。アンナの身の上話が少し調子づいてくると、男はスポットライトの照明器具を抱えひたすらアンナを照らし続ける。アンナの影が背後の壁に大きく映り、アンナの存在がどんどんくっきりと、大きく変わってゆく。男がアンナの話をうまく引き出している様子がよく演出されていた。そしてこの誘導は、カウンセリングではなく、相談室交代への誘導だった。
最後、話し終えたアンナは何かに憑かれたように、この孤独で寂しい仕事はしたくないのでしょ、私が代わってあげる、と言って眠りに落ちる。目を覚ましたアンナは表情が一変して冷たい顔になり、客席をまじまじと見つめ、自分がかつて当てられたスポットライトを取り上げ、観客席を満遍なく照らした。
まともに当てられると、ライトの強烈なこと。まぶしいのを通り越して、何も見えない。ある楽器奏者が、舞台でライトを浴びるのはまるで焼肉だ(そのくらい熱い)、と言っていたのを思い出す。「こ、これは確かに焼肉だ……」と思いつつ、光の中に露わにされると思わず何か自分のことを話し出しそうな心境にもなってくる。少々不思議な体験だった。
とはいえ、全体の感想としては、やはり俳優の技量がもう少しあるとよいのに、と感じた。私でもわかる台詞の言い間違い(言い直し)が3、4回、声量の不十分さなどが少々難だった。それから終演後、観客が席を立って帰り始めるやすぐに舞台上で始まる、出演者とその身内の記念撮影もちょっと。まあいいけどね、と横目で見つつ、混雑の中、ロビー兼カフェで行われ始めた脚本家、出演者たちとの交流会もちら見だけして失敬した。
勇気を奮って、脚本家の人に星新一を読んだのか尋ねてみればよかったかな、と思ったのはすでに劇場を出てだいぶ後のこと。その前に、星新一はどの程度中国語の翻訳が出ているのだろうか。ウムム。観劇後の帰り道はいつも反省会である。

開演前の舞台

終演後の交流会
文字は悲しい
最近、阿辻哲次『日本人のための漢字入門』(講談社現代新書、2020年2月20日発行)を読んだ。いろいろな話題が詰め込まれていて楽しく読めたのだが、「言語学のなかの文字学」という一節の中の次の記述にはがっかりした。
「よく知られているように、ラテン文字もそのルーツであるフェニキア文字の段階では表意文字だったが、しかし早い時期に他の言語の表記に使われるようになって、表音文字としての道を歩みはじめた。」(127頁)
フェニキア文字はそれこそ“よく知られているように”表音文字であり、表意文字というのは誤りである。あまりにも初歩的な誤りなので、単純なミスプリかとも思ったのだが、文脈から見てそうではない。理由は分からないが、本当にそう思い込んでいるらしい。実は上に引用した文を含む一節はもと『月刊しにか』1998年5月号(大修館書店)に掲載された文章である。今回の再録に際しても訂正を要しないと判断されたのであろう。著者の阿辻氏は言わずと知れた漢字学の第一人者である。そんな学者にしても、漢字以外の文字に対してはかくもぞんざいなのかと、がっかりした次第である。
フェニキア文字がギリシア文字の元になったという話は高校の教科書にも載っていたと思うが、一般にはそれほど知られていないのであろうか。子音字のみで母音を表記しないフェニキア文字がギリシアに伝わって、ギリシア人はギリシア語の表記のために母音字を考案したのだという話を聞いてワクワクした思い出があるが、多くの人はギリシア文字にもフェニキア文字にも関心はないのかも知れない。かくも冷淡な扱いを受ける文字は悲しい。
商業の民であるフェニキア人は地中海の各地に植民地を作った。再三にわたるローマとの戦争で有名なカルタゴ(シチリア島の対岸、現チュニジア共和国)もその一つである。フェニキア人をラテン語ではポエニ(Poeni)と呼んだため、ローマとカルタゴの戦争をポエニ戦争という。歴史に「if」はないが、もしもカルタゴが勝利していたら、現在のヨーロッパではフェニキア語が広く話されていたかも知れない。
フェニキア文字のルーツがエジプトのヒエログリフ(聖刻文字)であるという説を唱えたのは名著『エジプト語文法(Egyptian Grammar)』(1927)を著したアラン・ガーディナーであった。エジプトとアラビア半島の間にあるシナイ半島で発見された碑文がヒエログリフとフェニキア文字をつなぐ文字資料と考えられた。フェニキア文字などセムのアルファベットの一番目の文字の名称「アレフ」(いまヘブライ語の読みによる)は「牡牛」を意味するが、原シナイ文字ではまさに牡牛の頭の形をした文字が「アレフ」の音価(声門閉鎖音)を表していたからである。ギリシア語には声門閉鎖音は必要なかったため、フェニキア文字の「アレフ」がギリシア語に取り入れる際には、母音の「Α」に転用されることになった。「アルパ(アルファ)」という名称はフェニキア語のギリシア語なまりということになる。
シナイ半島の碑文の文字(原シナイ文字)がアルファベットの起源であるというガーディナーの説はその後多くの議論を巻き起こした。一時は否定的な見解が優勢だったが、最近では有力な説として認める方向に傾きつつあるようだ。昨年のNHK高校講座の「世界史」で古代メソポタミアをテーマにした回では、アルファベットの起源はヒエログリフであるという説明が堂々となされていた。古代ローマ史の研究者である本村凌二氏も解説に加わっていたから、おそらく氏の意向が反映されたものであろう。阿辻氏がフェニキア文字を表意文字と思い込んだのは、その源がヒエログリフにあるという説を聞きかじって、消化せずに吸収した故であろうか。
ハングルはパスパ文字から作られたとか、ウイグル文字は初め横書きだったというのは、眉唾ではあるが検証する価値はある。しかしフェニキア文字が表意文字だというのは冗談としても全く笑えない。仮にも文字を専門としてきた人が軽々しくそんなデタラメを言うのは、漢字以外の文字はまともに研究する価値がないと思っているからだろう。見下された文字は悲しい。
[2020.4.10 中村雅之]
舞台で聞いた中国語26……竇娥冤(竇娥のぬれぎぬ)
一昨年の新春、北京にて『関漢卿』を観た(田漢作、唐鎏演出、北京人民芸術劇院首都劇場)。今季、女性演出家によって新解釈されたとのことだが、長年再演されているレパートリーということであまり目新しく映らなかったのか、私が足を運んだ日は空席が目立っていた。主役のキャスト二人、王斑と于明加という実力派がそろっているだけに残念である。それぞれ関漢卿(かんかんけい。元代の雑劇作家)役と、彼を慕う友で雑劇女優の朱簾秀役である。はじめ、言葉遣いが難しそうな歴史劇だし、大劇場だし……と少しためらいがあったが、于明加目当てでチケットを買ってみたら、予想よりも素晴らしい舞台でほくほくとした。

関漢卿役・王斑(首都劇場ロビーのパネル)
于明加はテレビのドラマやコントでよく見かける女優だ。ふだん存在感ある役柄を演じていて(あるいは彼女が演じるから存在感が出るのか)、興味をひかれていたが、舞台映えという点ではどうだろう、と実は少々疑問視していた。というのも、中国の女優(とくに若い人)はバービー人形のような華奢な体型、高い声の人が多く、于明加も例外ではないからである。

朱簾秀役・于明加(写真出所:北京人民芸術劇院公式ウェブサイト)
「テレビよりも見劣りしてがっかりするかもしれないな、でもやっぱり実物も見てみたい、うーん」と半分ミーハーな気分で劇場に行くと、いざ舞台に現れた于明加は、立ち居振る舞いは美しく、話す声は抑えたトーンで遠くまでもよく通り、劇中で歌う雑劇の歌声も素晴らしかった。登場していくらも経たないうちにその実力に圧倒され、「疑ってどうもごめんなさい」と心中素直に謝った。
関漢卿はよく知られるとおり、中国文学史に名を残している作家である。医者をしながら雑劇を書いたらしい。その生涯についてほとんど史料がなく、舞台作品としては田漢の創作とのこと。関漢卿は友の朱簾秀に励まされながら、今日にも残る『竇娥冤』(とうがえん:竇娥のぬれぎぬ)を書いて成功するが、書き換えろと言う権力者の圧力を拒み、投獄、処刑されてしまう。しかし作家の精神と名作は不朽だという話である。 処刑されるとわかっていながら、圧力を突っぱね淡々と(でもないかもしれないが)牢に入る関漢卿は、王斑自身のきりりとした顔だちも相俟って、実に男前だった。処刑の日が迫り、朱簾秀が獄中の関漢卿を見舞って別れを惜しむ場面はさめざめとしていたが、その後は「見送って来たわ」などと言って彼女の方も意外とあっさりしている。「そんなもんですか?」と思ったものの、逆境の中でも悠然とした二人のほどよい力の抜け具合が、とてもよかった気がする。幾ばくかの侘しさが残りつつも爽やかに感じた舞台だった。

カーテンコール
そう感じたのには、繰り返し流れる音楽の効果もあった。この舞台に限らず、中国ではあちこちで耳にしたことのある有名な曲である。悲しげなようでいて、途中転調して明るく流れるようになるところがとても美しい。琴のような音色で、どうやら『竇娥冤』といえばこの曲ということらしいが、残念ながら後日いろいろ検索してみても、作曲者や演奏音源の配信の有無、曲名すらわからない。以前、頭の中にある音楽(旋律)をデータベースでどう検索するか、という話を聞いたことがあったのだが、とんと忘れてしまった。情けないことである(といっても、話の内容は確か、確実な検索方法があるということではなく、いかに難しいかというものだったと思うが)。
『竇娥冤』について少々。殺人の冤罪で処刑される女性・竇娥の不遇、そして死後に父親の夢に出て自分の無実と真犯人を訴える雪辱の物語である。この竇娥、日常会話でも名前を聞くことがある。自分が不本意に悪者にされてしまったようなシチュエーションで自分の正当性や善意を主張して、「比竇娥還冤」(竇娥よりもひどいぬれぎぬだ)と言ったりする。誤解されて悔しいと嘆く愚痴の表現だが、テレビドラマで小学生も使っていた。竇娥よりひどいぬれぎぬって何なんだ、というツッコミはおいておくとして、比較の構文もマスターできることだし、一つ覚えておいて損はないかもしれない。
[2020.3.31 榊原真理子]
直訳と誤訳の間で
外国語の翻訳というのはなかなか難儀な作業である。まず考えるべきはどこにターゲットを定めるかということだろう。理解しやすくて自然な日本語を目指すのか、あるいは多少ぎこちない表現であっても原文のニュアンスをなるべく崩さないようにするのか。文学作品ならば前者を選ぶだろうし、学術的な文章ならば当然後者になる。そして、やや特殊な位置にあるのが宗教的な教義や王などの統治者の命令を記した文章である。聖なる言葉、あるいは権威のある言葉であるがゆえに、その翻訳には時として不自然なほどに直訳的な手法が用いられることがある。その場合、翻訳は完成品というより、原典の姿を知るためのよすがに過ぎない。しかしまた、あまりにも直訳になり過ぎて日本語として意味不明になると、それは誤訳のそしりを受けることになる。
<正しい教えの白蓮>
最近、植木雅俊『サンスクリット版縮訳 法華経』(角川ソフィア文庫、2018年)を購入した。仏教や梵語に漠然とした興味を持っている者が『法華経』について知るには最良の手引き書と言ってよい。平易な日本語訳に、章ごとに注釈と解説が施されている。その解説を読むだけでも『法華経』を読んだ気になる。ところで、その経典名について「はじめに」で次のように記している。
--------------------------------------------------
『法華経』の正式名称はサッダルマ・プンダリーカ・スートラである。岩本裕氏が「正しい教えの白蓮」(岩波文庫『法華経』、一九六二年)と訳したことで、この訳が長年、何の疑問も持たれずに採用されてきた。それは、サンスクリット文法、欧米語の訳し方、国文法から見てもトリプルの誤りであり、「白蓮華(プンダリーカ)のように最も勝れた正しい教え(サッダルマ)の経(スートラ)」と訳すべきである。
--------------------------------------------------
植木氏によれば、「トリプルの誤り」ということであるが、最初の「サンスクリット文法」について説明すると、梵語では名詞Aと名詞Bの複合語「AB」は時として「BのようなA」という意味になる。後に来る名詞Bが比喩として使われるということである。「人+獅子」で「獅子のような人」の意になる。したがって「正しい教え+白蓮」は「白蓮のような正しい教え」と解される訳である。実際、その後の多くの研究書や翻訳ではそのように訳されることが多い。
さて、それでは「正しい教えの白蓮」は誤訳なのか。私の個人的な感覚から言えば、「白蓮華のように最も勝れた正しい教えの経」という訳は正確ではあっても美しくない。「正しい教えの白蓮」という訳は語呂もよく、しっくりくる。私の理解では、岩本訳の「正しい教えの白蓮」は梵語の語順に則ったもので、誤訳というより一種の直訳である。我々が「法華経」と呼んでいるお経は、正式には「妙法蓮華経」という。これは西域の鳩摩羅什(くまらじゅう)による訳であるが、これも梵語の語順で「妙法(サッダルマ)蓮華(プンダリーカ)経(スートラ)」としたもので、まさに直訳である。もしも「正しい教えの白蓮」が誤訳であるならば、鳩摩羅什の訳も誤訳ということになる。研究書としては植木氏の訳を取るべきだが、経典の訳という点からは岩本訳も十分に“あり”である。原典の梵語の“匂い”を感じさせる訳だと思う。
<カーンなる我らがおおせ>
13〜14世紀のモンゴル帝国の皇帝(カーン)たちが発した命令文は碑文としてかなりの数が残っているが、その冒頭には常套句として「とこしえの天の力において、大いなる福蔭の加護において、カーンなる我らがおおせ」という語が置かれる。原文はもちろんモンゴル語で、クビライ帝以降定型化したとされる。この「カーンなる我らがおおせ」という意味不明の日本語訳については、かつて論じたことがある(中村雅之「<カアンなる我らがおおせ>について」『KOTONOHA』第93号、2010年8月)。要するにモンゴル語の直訳なのであるが、あまりにも意味不明である。誤訳と言われても弁解のしようもないが、東洋史の研究者たちは例外なくこの類の訳を用いる。
カーン・ジャルリグ・マヌ(qaγan jrlγ manu/qān jarliq manu)の「ジャルリグ」は碑文の漢訳では「聖旨」にあたり、皇帝の発した命令、お言葉のこと。「マヌ」は「我々の」で、碑文の漢訳では「俺的/俺毎底」だが省略されることもある。漢訳では全体として「皇帝聖旨/皇帝聖旨俺的/皇帝聖旨俺毎底」のようになるが、通常の漢語の語法を逸脱しており、まさに蒙文直訳体と称される文体である。もちろん、このような漢訳は当時のお役所が意を以て作ったもので、誤訳云々と言うべき筋合いのものではない。しかし、「カーンなる我らがおおせ」という日本語訳はいかがなものか。この定型句の実際の意味は「カーンである私の言葉」という意味である。「マヌ(我々の)」と複数形になっているのは稿をなした書記による一種の敬語表現と考えられる。モンゴル語学者の小澤重男氏は山西省玄中寺の皇帝聖旨碑文の研究において「可汗なる我が詔勅」と訳しており、東洋史家のように意味不明の直訳を用いていない。ここでの「マヌ」が「私の」という意味だと理解していないという点において、「カーンなる我らがおおせ」は誤訳と判断せざるを得ないだろう。もっとも、東洋史家には別の言い分があるかも知れない。直訳か誤訳か、判断は容易ではない。
[2020.3.20 中村雅之]
翻訳におけるセンスと誠実さ
4月からの一般文字学の講義の準備の一つとして、最近モーリス・ポープ著、唐須教光訳『古代文字の世界』(講談社学術文庫)を読み直している。以前にも感じたことだが、この日本語訳は本当にひどい。おそらく英語原文自体がくどい表現の羅列であることが原因ではあろうが、それをまるで高校生が英語の授業で直訳するような調子で訳してあるので読みにくいことこの上ない。分かりやすい日本語で表現できないというのは、はっきり言えばセンスの問題なので、改善は望めない。
しかし、自分の知識の及ばない部分をいい加減な推測で提示するとしたら、それは誠実さの欠如と言わざるを得ないだろう。この書の第3章はシャンポリオンのヒエログリフ解読について述べているが、その中にヒエログリフと漢字の比較について触れた個所がある。フランスにおける中国学の創始者と言えるアベル=レミュザの著書からの知見が述べられるのであるが、その中に次のような一文がある。
「それだけ文字数が豊富なのに、レミュザによると、中国語は、それでもヒン・チンhîng-chîng(「音をあらわす」)と呼ばれる一群の表音文字を必要としたのである。」(147頁)
中国語の知識をもつ者でも、この訳文を理解するのは困難であろう。訳者には中国学の知識がないばかりか、フランス語の知識もない。誠実な訳者であれば、中国語史の専門家にこの箇所の原文を読んでもらって教えを乞うはずである。さらに誠実な訳者であればレミュザのフランス語原文にも目を通すだろう。本書の訳者はhîng-chîngという未知の語を調べることなく、英語読みして「ヒン・チン」というありもしない語を創作したのである。
中国語史の知識があって、西欧人による明清代の官話資料を読みなれている者ならば、レミュザの著書にあったというhîng-chîngが「形声」という語の官話音のフランス式の綴りであることを一瞬にして見抜くことができる。仮に中国学の知識をもたなかったとしても、レミュザがフランス人であることから、hîng-chîngのchîngが「チン」でなく「シン」に近い音であることが想像できるはずであるが、chを[ʃ]と発音するというフランス語の基礎知識も訳者にはなかった。そのために「ヒン・チン」という噴飯ものの読みを与えてしまったのである。
シャンポリオンがヒエログリフの初歩的な解読を提示したことで有名な『表音聖刻文字のアルファベットに関するダシエ氏への書簡(Lettre à M. Dacier relative a l'alphabet des hiéroglyphes phonetiques)』が公表されたのは1822年であり、その2年後に総合的な解読である『古代エジプト人の聖刻文字体系概要(Précis du système hiéroglyphique des anciens Egyptiens)』が出版されている。1822年にはレミュザによるフランス中国学の記念碑的な著作『漢文啓蒙(Elémens de la grammaire chinoise)』が出版されており、上の「hîng-chîng」云々もこの書の記述を参考にしたものである。ヒエログリフの表音文字と漢字の造字法の一つである形声(部首と声符からなるもの)を比較することの妥当性についてはにわかに判断しかねるが、膨大な文字数をもつ漢字でさえも表音的な手法を必要としたということがヒエログリフの解読に際してそれなりの示唆を与えたということなのであろう。
なお、レミュザの表記では母音の上の「∧」は平声(陰陽の区別なし)を表し、「\」が上声、「/」が去声、「V」が入声である。
[2020.3.4 中村雅之]
舞台で聞いた中国語25……愛情不是用眼睛,而是用心霊看着的(恋すれば、だれも目では見ない、心で見るの)
一昨年の夏の北京滞在中、優柔不断な私にしては珍しくためらうことなく、奮発して前方の席の公演チケットを買った。かのシェイクスピア、『夏の夜の夢』《仲夏夜之夢》である(イギリスのクリス・ホワイト演出、国家大劇院小劇場)。普段シェイクスピアは敷居が高いように感じて近づき難いのだが、実はメンデルスゾーンの音楽のお陰で、「夏の夜の夢」の妖精の森のイメージだけはとりわけ気に入っている。ところが、その先入観が災いしたらしい。いざ赴いて観た舞台は少々予想と違っていた。
俳優陣はよかった。衣装や舞台装置のデザインも洗練されていて、美しかった。脇役たちが舞台横で打楽器を演奏して主役たちを引き立てる演出も、趣向が凝らされていてワクワクした。意外と原作に忠実で、奇をてらう脚色もなかった。
しかし、ときどき白けるような妙に古典的なギャグが入り、それにまたなぜか観客がウケて喝采しているのには、最後、本当に白けた。「それ、おもしろいの? そんなギャグがここで必要なの?」と、せっかく出来上がりつつあった夏の夜の微笑ましい情景が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちるのに呆気にとられながら、思わざるを得なかった。
「あなたが好き!」と腰のあたりにすがりついたら、相手(男)のズボンをずり下げてしまい、派手な柄のトランクスが丸見えになって大仰に慌てふためくとか、男が服の中の胸のところに大きな風船を二つ入れて女装し、典型的なお姉キャラになるとか、またその女性の胸に見立てた風船を誰かが鷲掴みにして割るとか、そういうギャグである。
原作自体賑やかな喜劇であるし、風船芸も最後の道化的な劇中劇としての脚色だから、意図はわからなくはない。わからなくはないのだが、しかしどうしてここで急激に路線が変わって、「ごめんやして遅れやして〜」の吉本新喜劇調なのだ。まるで統一感のない方向性もさることながら、「なんちゃって吉本」ギャグの中途半端さに言葉が出ない。吉本新喜劇の人が見たら、きっと精一杯コケてフォローしてくれるに違いない……。
そうは言っても、そこは半分観光目的で訪れる人が多い、天安門前の国家大劇院。やはりそんなわかりやすい演出も必要なのかもしれない。実際のところ、こうした沸かせるシーンがしばらくないところでは、靴音高く中座して出てゆく観客が目に付いた。
あらすじをかいつまんで。それぞれ想う相手がいる人間の男二人と女二人、妖精の男一人(王)と女一人(女王)。想う相手には想われず、想い合えば周りに阻まれる。妖精たちは夫婦喧嘩中。女王のつれない態度に腹の虫の収まらない妖精の王は、手下の妖精パックに命じて女王の目に魔法の惚れ薬をぽとり。目論見どおり、目覚めるなり薬が効いて、ロバの化け物男に血道を上げる女王の滑稽な姿を見て、王は満足げ。この一方で、妖精の森に入り込んだ件(くだん)の人間たちにパックが惚れ薬を誤って使ってしまい、こちらも見当違いな相手を追い掛け回したり女の戦いが勃発したりして、ドタバタがしばし。最後は落ち着くところに落ち着いて2組の幸せなカップルと元さや妖精夫婦が出来上がり、ロバ男も人間に戻り、結婚の祝宴での余興劇も熱演が披露され、すべてハッピーエンドである。
「恋すれば、だれも目では見ない、心で見るの。」
「なんと馬鹿者ばかりでござろうか、人間というものは!」
「理性と恋心とは、当節めったに折りあいがつかないようだがね。」
残念ながら上演で聞いた中国語で記憶しているのは一つ目だけなのだが、いずれも有名な台詞である。すべての幕引きに妖精パックが語る一節もまた。
「夜の住人、私どもの、とんだり、はねたり、もしも皆様、お気に召さぬとあらば、こう思召せ、ちょいと夏の夜のうたたねに垣間みた夢まぼろしにすぎないと。それならお腹も立ちますまい。」*
後日改めて戯曲の日本語訳を読んで、細かな台詞がようやく腹に落ちた。予習をさぼったことと、筋を追うばかりで台詞がうまく頭に入っていなかったこと、芝居の見方も狭量になっていたのは恥ずかしい限りだ。私にとっては、北京の夏の夜の夢。そう思えばあの風船芸も、鷲掴みにして割るのは結構力を使うようで、大変そうだったな、と今ではクスッと思い出し笑いしている。

妖精の王と女王

祝宴の劇を稽古する村人たち
(写真出所:国家大劇院公式ウェブサイト)
*台詞はいずれも福田恆存訳「夏の夜の夢」(『世界文学全集Ⅱ-2シェイクスピア』河出書房新社、1963)。古い版だが、言葉の流れが力強いと感じた福田恆存訳を引用した。
[2020.2.28 榊原真理子]
国際学会開催記(5)〜開催当日とその後〜
日本で最初に開催されたIACL-11のオーガナイザーである岩田礼先生(公立小松大学)いわく、国際会議は初日を迎えたらもう終わったようなものだそうだが、とてもそんな気にはなれなかった。
開催初日となる5月10日(金)は晴れ、幸い3日間とも雨が降ることはなかった。午前中のメインはYSAのファイナルセッションで、54件の応募から選ばれた3名のファイナリストがプレゼンを行い、その後審査委員会が協議して受賞者を決めるという段取りである。審査員になっているIACL事務局の人には、ホテルに迎えの学生を行かせる。基調講演者には午後の開会式に合わせる形で別の迎えを行かせた。会場では直前になって音声を流したいという発表者がいて焦ったが、機器担当の人を呼んで何とかなった。お弁当も無事届き、アルバイトの学生に引き継いだところで受付に戻る。
昼前から本格的に受付を始めたが、案の定最初は大混雑で、特に領収書関係には長い行列ができている。参加費の領収書を渡すところまではスムーズにいくのだが、年会費の領収書が見当たらないというケースが目立つ。そもそも年会費を払ったかどうか怪しい人とか、終身会員なので年単位で払う必要のない人まで何となく並んでしまうため、その確認に手間取るのだ。そうした混乱の中、IACL元会長で基調講演の司会を担当して下さる戴浩一先生(国立中正大学)に向かって「会員の方ですか?」と声をかける受付の学生がいたりして慌てる。
幸い、恐れていたほどの混雑にはならず、1時前にはホールの席もほぼ埋まったので、定刻通りに開会式を始めることにする。司会は僕で、セレモニー関係は基本的に英語で進行しなければならない。下手な英語を聞かれるのは恥ずかしいが、原稿はあらかじめ作ってあるし、そもそも聴衆のほとんどは英語のネイティブではないのだからと腹を括る。4本の招待講演は王士元・サガール両氏の後、休憩を挟んで魏培泉・大西克也の両氏となる。サガール氏の講演前、画面がうまく映らないというので機器担当の人を呼んで見てもらったら、パソコンの表示が全部フランス語なので、急遽千葉謙悟さん(中央大学)を壇上に呼んで解説してもらい、間一髪で何とかなるという一幕もあった。
この日のプログラムはここまでで、夕方からはホテルに場所を移して理事会(ExCom Meeting)となる。例年、結構なコースの食事を食べながら行うのだが、今回は松花堂弁当のようなもので、ひょっとしたらショボいと思われたかも知れない。それよりも、僕は夕食時には必ずお酒を飲むので、ただ食べながらの会議というのに何となくムズムズしてしまう。次回のIACL-28は杭州の浙江大学に決まり、昨年ウィスコンシンで僕がしたように、開催校の程工氏が翌日の総会でプレゼンをすることになった。
5月11日(土)、いよいよ分科会のスタート。この日の会場配置はやや複雑なので、予想通り朝から混乱が見られ、急遽林さんと下地さんが案内板や表示の増設に走った。セッションが始まろうとする時になって、タイムキーパーの学生から司会の先生が来ていないという連絡を受けて、慌てて代打に飛んだりする。今回多かったのが、発表者が時間になっても現れないというケースで、ああやっぱり、そういうことだったのかと思った。実は開催前日にある大学院生からメールが来て、3月中に参加登録しなかったので、特に連絡しなくても発表取り消しになるものと思っていたというのだ。キャンセルの場合は事前連絡しろと何度も通知したのに、まともに読んでいなかったらしい。日本の学会では考えられない感覚だが、特に中国の司会者たちは格別気にするでもなく次の発表を前倒しにしたりして対応している。北京でやったIACLの時もそうしたケースがかなりあったのをすっかり忘れていた。まさに日本の常識は世界の非常識だが、中国式のユルい大会運営に慣れていれば、開催側もいちいち気をもまなくて済むのかも知れない。
夕刻からは招待講演1本と総会、それを終えるとホテルに移動してバンケットである。総会の開始が遅れたため、だいぶ時間が押してしまい、すでにホテルの宴会場でスタンバイしている司会の任鷹さんからひっきりなしに電話がかかってくる。結局、もとの予定から1時間も遅れて始めることになった。バンケットの恒例行事はYSA受賞者の発表と表彰なのだが、今年は受賞者なしとなった。ここ数年、バンケットの後半は国対抗歌合戦のような雰囲気で、任さんもマイクを手にテーブルを回り、さかんに歌や余興を勧めるのだが、いつものように日本チームは逃げ回っている。1時間半ほどで終わり、やれやれと学校に帰ってきたところ、ホテルから忘れ物の連絡が入り、こちらで預かるために受け取りに行く。帰ろうと地下鉄に乗ったら、忘れ物をした本人がホテルに現れたというので慌てて引き返す。何だか漫画のようなドタバタである。
5月12日(日)、この日を乗り切ればおしまいである。受付関係はほぼ仕事がなくなり、分科会、最後の招待講演、閉会式とこなしていけば終了。昼食やティーブレイクについても今のところトラブルは聞いていない。ここまで長かったなあ…としばし感慨に耽っていたら、下地さんと任さんが何やらひそひそ話している。何人かの参加者が、昨日のバンケットで神戸牛が出なかったことに不満を漏らしているというのだ。ある日本人の参加者は、同席した中国人から、メニュー表の「神戸ポーク」を指され、「ポーク」という文字は「牛肉」の意味かと問われたという。ホテルと打ち合わせをした段階で、バンケットで神戸ビーフを出した場合は一人1万円を超えるというのであっさり諦めたのだが、張洪明氏の「来歳同嘗神戸牛」もあったことだし、神戸イコール神戸牛を刷り込まれている参加者が期待するのも無理はない。ただ、だからと言って今さらどうにかなるものでもないので、張氏がどんな詩を詠んだとしても、我々はバンケットで神戸牛を出すとは一言も言っていない、という理屈で押し切ることにする。
結局、この日も大きなトラブルなく終了。閉会式まで残っている参加者はごくわずかだったが、最後となる開催校スピーチで、Thanks to my collegues, and thanks to our students!と声を張り上げた時は、さすがに少し感極まった。

アルバイトの学生たちと
今回、いろいろな場面で林さんを始めとする同僚や知り合いの研究者からの助けを得て、何とか大過なく終了するところまで漕ぎつけたわけだが、振り返ってみると、我ながらよく体が持ったものだと思う。実は僕はこの他に学会誌の編集委員長をやっていて、3月から5月というのはちょうど査読の割り振りや集計などで最も忙しい時期だったし、大学の仕事で4月初旬には弾丸ツアーで広州の大学視察をこなしたこともあった。開催までの半年間はほとんど毎日が皿回しのような状態だったが、そんな中で精神的にも肉体的にもバランスを保って予定のスケジュールをこなせたのは幸いなことだった。
辛い時、苦しい時に支えになったものは何か? それは家族です、とか言えればカッコいいのだが(もちろん否定はしませんが)、実は毎朝のジョギングである。約1年に及んだ準備の中で、うまくいったり助けてもらったりしたことが多かった半面、頭に来たり空しくなったりしたことも多々あった。そんな中で僕はほぼ毎朝、1時間のジョギングを続けた。時には暗い気持ちで、時には悶々としながら。でも、走り終えてシャワーを浴びると妙にスッキリして、しゃあない、やるか、という気分になるのである。これは座禅とかヨガでも同じだろうが、一日のうちに「何も考えない」時間があるというのは大事なことではなかろうか。学会の翌日、空港に向かう招待講演者たちを見送り、残っていた仕事を片付けた後で僕がしたことは、帰って夕闇の迫る街をジョギングすることだったのだ。
日本で二回目となるIACLを終えて、最初に去来した感情は何か? もちろん安堵感が一番大きかった。ただ、さぞかし爽快な気分になるかと思いきや、意外にも胸の中には苦い思いが残った。このままだと日本のこの業界はかなりヤバいのではなかろうか、と。
言うまでもなく、日本の中国語学界で多数を占めるのは現代語文法の研究者だが、今回、特に中堅以上の参加者は意外なほど少なかった。この分野で日本のプレゼンスがどんどん下がっているのは否定できないところで、なぜなら日本語で書いても限定されたマーケットでしか流通しないし、中国語か英語で書いてもネイティブの水準には及ばないからである。最新理論の吸収といった面でも、日本が中国の先を行っている時代は過ぎてしまった。こうした中で、必然的に研究者も内向きにならざるを得ないのではないか。
もう一つは、日本の学界には世界の潮流を全くフォローできていない分野があることで、それは例えば生成文法だったり、実験音声学だったり、言語習得だったりする。日本で認知言語学のアプローチを取る研究者が多いのは事実だし、それなりに有効ではあるのだろうが、一方でその理由が「生成文法は難しいから」といった消極的なものだとしたら、それは問題なのではあるまいか。学会後に誰かのツイッターで、これからは日本も他の国と同じように、在留の中国人研究者がマジョリティになって学界を担っていくのだろう、と書いていて、ウームとうなってしまった。これほどの研究伝統を有する日本の学界がそんな状況ではあまりに悲しい。もちろん、何でお前が心配するんだ、というツッコミはあるでしょうが。
ともあれ、IACL-27は終わった。ヒラノ教授の本にあったように、大規模な国際会議を主催するのは一生のうち1回でいい。僕にとって、これからは「余生」みたいなものなので、研究と教育とジョギングに集中させてもらう、とここに宣言します。
[2020.2.25 竹越孝]
舞台で聞いた中国語24……你怎麼不辞而別呀?(なぜ黙って去ったのだ)
一昨年の梅雨の合間、名古屋市の日本特殊陶業市民会館(金山)で京劇を観た。中国の湖北省京劇院の日本公演(東京、名古屋、大阪)である(電光掲示板の日本語字幕付き)。
白状すると、演劇に興味がありながら、これまで京劇にはあまり食指が動かなかった。京劇は伝統劇と言われるが、京劇改革、革命現代京劇と歴史的にも大きな刷新が試されてきており、必ずしもずっと同じ伝統が継承されてきたわけではない。が、一言で言うと、やはり京劇とは古式床しい形式美の集成である。新しい京劇も伝統の枠に立脚する。ゆえに、受ける印象はどうしても似通ってくる。演目や演出がどう変わろうと、共通するその煌びやかで華々しい技と美のてんこ盛りに、「も、もうお腹いっぱいです……」という気持ちになっていまい、不遜ながら、もっと他にも味わいたいという気があまり起こらないでいた。
しかし、今回観た京劇はなぜだかすんなり心に響き、もっと観たい、もっと唱ってほしい、という名残惜しささえ感じた。一つには私自身の変化があると思う。目が肥えたなどと言えるものでは決してないが、徐々に鑑賞した舞台の数が増えるにつれ、観るときに多少気持ちの余裕ができてきたようだ。
今回の京劇も、主役級の堂々たる俳優たちに目をやるのもそこそこに(派手な色の衣装に目がチカチカするというのもあったのだが)、傍らに押し黙って仕える下級家臣をまじまじと観察したりした。12人ほどもいただろうか、ほとんど台詞もなく、一括りの家臣役で全員揃いの衣装を着た若手の俳優たちだが、立ち居振る舞いは実に美しい。
彼らが演じるのは「跑龍套」とか単に「龍套」と呼ばれる端役ではあるが、芝居全体の流れ、舞台の上における役者たちの立ち位置のバランスを左右するなど重要な働きを任されている。彼らの演技の良し悪しが、主役の演技を引き立たせもすれば、芝居を壊してしまうことすらあるほどだ。
上半身をまったく動かさず、脚だけをスッスッと運ぶ歩み、主役たちの横で長い時間微動だにしない直立不動の姿勢。簡単な基礎のようであって、相当な訓練を積まなければできないはずだ、とため息が出た。体操の床の競技でやるような宙返りを長剣を両手に持ったまま連発する妙技も、観客を驚かせていた(観客はシニア層が多かった)。
順序が逆になったが、演目は「項羽と劉邦:覇王別姫」。

軽んじられて項羽の下を去った策略参謀の韓信が、紆余曲折を経て劉邦に登用され、かつて仕えた項羽を追い詰める物語である。前半は劉邦派閥内の政治的小競り合いが続き、後半は追い詰められつつある項羽と虞姫のさめざめとしたやり取りで、さっと空気が入れ替わった。そして、虞姫は四面楚歌を悲観して自害し、孤立無援の項羽は取り囲む敵と一人対峙する……項羽の運命やいかに。ウムム。というところで幕が閉じた。 事の顛末はわかってはいるものの、気を持たせる幕引きに色香漂うようである。この余白が心打たれたもう一つの理由だろう。
途中、「你怎麼不辞而別呀?」と劉邦が韓信を追いかけるシーンは風向きが変わっておもしろかった。雇ってくれないならもういいわい、と劉邦の下からもプイと去って行った韓信を、それまで強気だった劉邦が慌てて引き留めに行く、という図である。
今の時代なら、くどくど連絡してほしくないと思いながらも、メッセージの無視やメール返信がないのには思わず気を揉むというところか。いつの世も人間関係はエネルギーを使う(韓信には、張良の推薦状という劉邦をその気にさせる小道具もあったのだが)。
さて、樋泉克夫先生(愛知県立大学名誉教授)はこの作品を次のように評した。「従来のものとは違った色合いで、天下取りに敗れた項羽の物語の中に虞姫との別れを挿入したといった趣で、全体的にスッキリ(ということは些か淡白ですが)と纏まった新解釈だったと思います。」
私には何も批評らしいことはできないが、何でも盛れるだけ盛るのというのではない、引き算したところから生まれた風通しの良さやほどよい余白は、確かに感じ取ることができた。何事も過剰な今日、やっぱり腹八分目がちょうどいいですよね、と誰に話しかけているのかよくわからない例えで恐縮しつつ、私なりの感想としたい。
この京劇公演には樋泉先生が、観に行くきっかけを作って下さった。また、未熟なこの稿の校閲にもお力添えいただいた。末筆ながら、この場を借りて深謝の意を表したい。
[2020.1.18 榊原真理子]
国際学会開催記(4)〜開催当日まで〜
4月初めにプログラムが組み上がると、いよいよ本番1ヶ月前ということで、開催の準備はソフト面からハード面へと移行する。それ以前から動いていたことも含め、開催当日までのこまごまとした準備について書いておこう。
招待講演者への対応……招待講演者については、航空費、宿泊費、国内移動費がすべて開催校持ちになる。航空費について、以前は立て替え払いが普通だったのでレート換算とかの面倒も多かったと聞くが、最近はこちらで予約して、そのEチケットを添付で送るだけでよいので簡単である。それぞれの講演者にパスポートの写しを送ってもらい、滞在予定を確認した上で、だいたい3月中旬までには予約を済ませた。問題は出迎えの態勢で、中国だとたいてい大学お抱えの車が空港まで迎えに来たりするものだが、日本だとそういう大学は少ない。かと言ってタクシーを頼むと結構な値段になるから、神戸までは空港のリムジンバスを使うことになる。最初は関西空港と三宮のバス降車場にアルバイト学生を一人ずつ配置して、ピストン輸送しようかと考えたのだが、それぞれの到着時間がバラバラなので、結局は講演者一人に学生を一人付けて、空港到着からホテルまで同道してもらうことにした。宿泊はバンケットで使うホテルに人数分予約を入れた。このホテルは神戸外大の最寄りから3駅ほどで、駅の真ん前にあるので、会場との行き来にバスやタクシーを手配する必要はない。東京から来てもらう大西克也先生にも、往復の交通費と宿泊代はこちらで持ちますと連絡したのだが、もう自分で予約済みなので勘定に入れないでくれとのメール。さすがこちらの事情を分かって下さっていて、ありがたいことである。
食事関係……開催期間中の食事に関しては主に生協と打ち合わせをする。昼食時には生協食堂を営業してもらうことになっているが、国内学会と違い最初から食事代が参加費に含まれているので、受付で2日分の食券を渡すことにした。ティーブレイクは午前と午後に1回ずつだが、午前のティーブレイクをあてにして朝食は食べてこないという参加者もいるぐらいだから、国内学会の休憩室にあるような湯沸かしポットと袋菓子程度では不満が出そうだ。そこで、ややボリュームのあるケーキやフルーツなども加えてもらうことにした。初日は正午から受付開始だが、午前にYSAのファイナルセッションが行われるので、その審査員とファイナリストには弁当を出さなければならない。中国系の人は一般に冷たいご飯を嫌がるので、ご飯だけはホカホカのものにできないかと生協に依頼する。何とかしましょうとの返事で、こういう融通が利くのも生協ならではである。
バンケット……2日目の夕方に行われるバンケットはホテルの宴会場を借り切って着席形式でやる本格的なもので、国内学会でよくある立食形式の懇親会とはだいぶ雰囲気が違う。これは事前申込制なので、参加登録の時に選択することになっている。ホテルからは連休に入る前に最終の確定人数を伝えてほしいと言われていて、Early Birdの締め切り時点で登録のあった数をもとに考えるのだが、その後どれくらい増えるかを読む必要があるし、当日の飛び込みにも備えなければならない。当日申込は断るのが原則だが、経験上なかなか断りにくいケースもあるのだ。それとともに聞かれたのはベジタリアンやハラールの対応で、その注文は連休の一週間前でなければ困るという。とにかく、10連休の間はすべての作業がストップするという前提で動かなければならないのが厄介だった。

バンケットの様子
会場関係……プログラムを組む段階で使用会場はすべて決めてあり、プレゼン用のPCも情報関係の部署から借りる手配をしている。掲示については、分科会会場の表示、各会場の入口に掲げるプログラム、「報告人」「主持人」など教卓や机に貼るもの、「剰下両分鐘」「時間到了」といったタイムキーパーが使うパネルなどを中英対訳で作る必要があり、特に今回は分科会の1日目と2日目で使用する建物が変わるので、矢印などで導線を細かく示さないと混乱を招きそうだ。こうした掲示物は下地さんが昨年の中国語学会の例を参考に作ってくれることになった。開会式・閉会式や基調講演の行われる大ホールには横断幕があるのが望ましい。中国ではごく小規模な会合でも結構立派な横断幕がかかっているものだが、日本ではそれを業者に発注するとだいぶお金を取られてしまう。幸い、校門のところに置く立看板も含めて研究支援の部署が作ってくれることになった。実はその部署のトップは僕なので事務の人に頼みやすかったのだ。 学会は金曜日から始まるが、その日は夜9時まで第二部の授業で教室を使っているので、PCを借り出すのは金曜の夜、分科会の掲示を貼り出すのは土曜の朝しかない。
マニュアル……今回は延べ30人程度のアルバイト学生に参加してもらうことになっている。大学院にいる留学生がほとんどで、あとはゼミの学部生がちらほらといった陣容。これだけの人数にきちんと動いてもらうためには運営マニュアルが必要である。一から作ろうとすると大変な作業だが、昨年の中国語学会の時に使ったものを基礎に改訂すればよいし、そもそも中国語学会の開催校用マニュアルを最初に作ったのは、5年ほど前まで大会運営委員長だった僕なのだ。それでも、受付については中国語学会とだいぶ勝手が違ってくるようで、逐一名前をチェックして事前登録の有無を確認する必要があり、参加費や年会費の領収書を出すセクションも設けなければならない。初日は12時に受付開始で、13時には開会式が始まるが、受付に参加者が長蛇の列を作り時間通りに始められないという事態だけは避けるべく、何度も頭の中でシミュレーションを繰り返してマニュアルを書き直した。 4月中旬に15ページほどの冊子が出来上がると、まずそれぞれの指導教員を通じて学生たちに説明してもらうとともに、連休前にはタイムキーパーを集めた説明会、連休明けには全体を集めた説明会を行って、学会全体の流れ、学生と教員の動きを確認するとともに、冊子版プログラムの修正、袋詰め、領収書や名札の整理などを行った。
4月に入った段階で、もともと4人だけでやっていた組織委員会に、受付で主に現金の管理を担当する責任者をプラスすべく、同僚の紺野達也さんに声をかけた。紺野さんは中国語学会の事務局をやっていた時にも会計担当として八面六臂の活躍をしてくれた人物で、本人にとってはいい迷惑だったと思うが、僕としては心強いことこの上ない存在だった。
採否通知の直後から、採択者に対しては3月末までに参加登録をして費用を振り込むこと、出席できなくなった場合は速やかに連絡すること、という二点をしつこく告知していたので、4月以降も発表キャンセルのメールが五月雨式にやってくる。その都度プログラム変更の対応はしていたが、一方で直前まで参加登録すらしていない発表者も一定数いるようなのがどうにも不安だった。ウェブサイト上のプログラムは直前まで変更可能だが、紙媒体の印刷は連休前までに発注しなければならず、それ以後の変更については出来上がってきたものに人海戦術で字消し線を引くしかない。ウェブサイトの更新、プログラムの印刷、名札の作成をお願いしていた業者からは4月中旬以降ひっきりなしに電話がかかってきて、特に連休前の数日は本当に目が回るようだった。それでも10連休に入ると、まるで台風の眼に入ったかのようにパタリと連絡が途絶え、運営の最終チェックをするとともに、本番に向けて鋭気を養うだけの時間が作れたのは幸いなことだった。
連休が明けると台風の吹き返しである。各所から最終確認の連絡が入り、共同研究室には学会で使用する資料や機材が続々と搬入されていく。5月8日には王士元先生夫妻とサガール氏が無事到着したという連絡が入り、9日にはプレ・ワークショップがスタート。最初だけ顔を出して挨拶し、あとはひたすら翌日の準備と会場設営。そして5月10日、いよいよ開催初日を迎えた。
[2019.12.31 竹越孝]
舞台で聞いた中国語23……搞不懂的五彩人生(解し難きめくるめく人生)
「解(げ)し難きめくるめく人生」(搞不懂的五彩人生)。歌詞ということで、書き言葉風に訳してみた。北京某所、脳腫瘍で余命1か月と診断された男が歌う、甘酸っぱい3拍子の歌の一節である。

開場前のロビー
話は続く。空中庭園目当てに殺人犯に成りすまそうと企む輩はほかにもまだ二人いる。一人は映画女優に恋する医師。もう一人は刑務所から出てきたろくでなしの男。二人はそれぞれ、女優に贈るために、苦労をかけた子供たちへの埋め合わせのために、我が身と引き換えに空中庭園を手に入れようと考える。
話はさらに続く。やがてこの3人と彼らを取り巻く人々は全員あるレストランに居合わせる。各々自供のための筋書き作りに余念がないが、さて空中庭園は誰の手に……? こんなストーリーと歌が舞台という器に盛られ、一つのミュージカルとなる。タイトルは『空中庭園殺人事件』《空中花園謀殺案》。私が観たのは一昨年の北京での公演である(史航・孟京輝作、孟京輝演出、蜂巣劇場)。
ミュージカル、当然ながら中国にもある。タモリが「突然歌い出すのが嫌い」と言っていた、あれである。中国語は「音楽劇」という。演出家の孟京輝は劇中で歌や生演奏を用いるのが好みのようだが、それが高じてなのかたまにこうした本格的な「音楽劇」を制作する。私はといえば、タモリと違ってミュージカル賛美派。どうとでもおもむろに歌って踊ってハモり出すのが実に楽しいと思う。
『空中庭園殺人事件』は、余命幾ばくもない男が人妻にチューしたいなどと言い出す設定からもわかるとおり、滑稽なドタバタ劇で、軽いとは思いながらも癖になる痛快さだった。殺人犯に成りすまそうとする3人と彼らを取り巻く人間模様が、入れ代わり立ち代わり歌声と個性を競い合う。観客の方は次は何が出て来るかと、目をそらす暇がない。終盤のレストランのシーンでは、満を持してバリトンの美声の「料理長」が登場する。3人の行く末の鍵を握るその怪しげな役どころも相俟って、最後の最後まで観客の目は釘づけである(耳も)。
引き込まれる仕掛けというか、孟京輝の舞台の特徴として大音量の音響もある。始まりからベースやドラムのけたたましいロック音楽が鳴り響き、劇場は音楽にすっぽり包まれた異空間となる。数々披露される歌は甘酸っぱかったり陽気だったり悲しげだったりといろいろだが、どれも若者好みで耳によく馴染む。サビのところは何度もリピートされ、自然と耳が覚えてしまう。舞台には電光掲示板があって歌に合わせて歌詞が表示されるから、歌詞も目と耳両方で追いかけて、観客はどんどん洗脳されてゆく。ほの暗い劇場、無言の熱気をたたえた満員の客席、実に怪しいひとときである。
最後は結局どんなオチなのか、後日批評を読んでみても、実はいまだによくわからない。3人はどうするのか。訳あり料理長のその後の人生は。答えが示されないまま哲学的な台詞と歌で劇は終わる。このモヤモヤはどうやら演出家からの宿題のようである。だが後味は悪くなく、俳優たちの熱唱に若者で満席の客席から惜しみない拍手が起こっていた。

カーテンコール
[2019.12.21 榊原真理子]
国際学会開催記(3)〜査読・採否通知・プログラム〜
アブストラクトの投稿を締め切った1月11日の朝にEasyChairを開けたら、うわっと頭を抱えてしまった。その数、670。昨年のウィスコンシンでは500前後の投稿があったと聞いて驚いたものだが、今回は間違いなく歴代最多である。それにしても、前の日に確認した時は300ぐらいだったから、最後の1日だけで350以上の投稿があった計算になる。アブストラクトではなく論文全体を投稿することになっているYSAの方はメールで受け付けたのだが、そちらも54本あった。
これらを査読者に割り振って結果を集計し、2月末までに投稿者に採否を通知する、その後1ヶ月かけてプログラムを組む、というのが当面のミッションである。一般発表とYSAで合計720本あまりという数を考えると、気が遠くなりそうな道のりだが、とにかく走り始めないことには開催まで漕ぎつけられない。とりあえず僕が最初に全部のアブストラクトを見て、分野を現代語文法、音声音韻、方言、歴史文法、教育…といった具合に大雑把に分けていき、その後組織委員会の4人で分担して査読者を割り当てることにした。YSAについては1本につき3人、一般については1本につき2人の査読者をつけるという方針である。同時に、規定違反のものや、どう見ても箸にも棒にも掛からないものはこの段階ではじくことにする。
学期末に入るこの時期はセンター試験などもあって大変だったが、目がショボショボになりながら1週間ほどで何とかその作業を終えると、最も数の多い現代語文法や教育に関わる分野は任さんと下地さんに任せ、僕はそれ以外の分野について査読者を考え、林さんが英語のものを中心に全体をチェックするという分担にした。この作業がだいたい10日ぐらい。YSAの方はメールで査読者とアセスメントシートのやりとりをし、一般発表の方は査読者にEasyChairにアクセスしてもらい、アブストラクトを閲覧した上で点数を入れてもらうという仕組みである。YSAファイナリストの決定はIACL事務局の管轄なので、YSAに関しては僕が責任を持ち、EasyChairでの査読管理については操作方法に明るい林さんが主となった。各査読者には1ヵ月ほどかけて見てもらうことにし、2月20日を一応の締め切りとした。
予想通り、依頼を発してからは日々査読者との対応に追われることになった。依頼の段階で断られるのはまだいいのだが、全くなしのつぶてで反応がないというのが一番困る。EasyChairの方は査読者のうち誰がアクセスしたかが分かるので、未アクセスの人にはリマインダーを出したり、それでもだめな場合は代わりの査読者を充てなければならない。かなり信頼していた人がずっと無反応なので訝しんでいたら、そもそも前回の組織委員会からもらったメールアドレスが間違いで依頼が届いていなかったということもあった。「目の病気」を理由に査読を断ってきた人が2人いたのだが、学会の後に中国で会った時にはピンピンしていて、やれやれと思ったものだ。
YSAの方は査読の集計結果をIACL事務局に送り、上位何名をファイナリストにするか学術委員会(Scientific Committee)に決めてもらう。今回は3名となった。一般発表の方は平均点の上位からずらっと並んだものがEasyChair上に表示されるので、我々の仕事は何点までを採択するかという判断である。これは分科会をいくつ立てるかという問題に直結するので慎重にならざるを得なかったが、結局例年並みとして200位ぐらいまでを採択することにする。日本中国語学会の全国大会は分科会が1日で6会場、大体50人程度の採択だったから、大体その4倍ぐらいの規模でプログラムを組むことになり、今から頭が痛い。それでも採択率は3割を切っていて、おそらくIACL史上随一の狭き門だろう。

YSAセッションの様子
通知を出した直後から色々な悲喜劇を物語るメールが来る。特に不採択だった人からのメールは、怒り散らすもの(自分はこの学会にかけていたのにどうしてくれる!)、泣き落としにかかるもの(これに通らないと博論を提出できないんです…)、めげずにお願いするもの(もしキャンセルが出たら自分のを入れてくれませんか?)と様々だが、そんなのに一々付き合っている暇はない。
参加登録を開始してからは、インビテーション(邀請函)を作って送るのが日課になった。最初は一枚ずつ打ち出したものに僕がサインして組織委員会の印鑑を押し、それをスキャンしていたのだが、林さんが僕のサインと印影を画像として貼り付けたWordファイルを作ってくれたので、以後は名前と発表のタイトルだけを入れ替えてPDFにし、それを添付で送るという具合にした。開催の直前までほぼ毎日この作業は続き、全部で180通ぐらいは作ったはずだ。
今回一番頭を悩ませたのがビザ関係の問題である。中国では日本への短期滞在ビザを申請する時に「身元保証書」「招へい理由書」「滞在予定表」という通称「日本三書」が必要になる。そのうち「身元保証書」は僕の在職証明書で代用できるのだが、この「三書」を郵送してくれというメールが3月中旬からひっきりなしに来るようになった。当初はフォームにこちらの情報を書き入れて組織委員会の印鑑を押したものをスキャンし、それを添付で送って向こうに自分の情報を書き入れてもらえばよいと考えていたのだが、原本でないため窓口で突き返されたとか、そちらで印鑑を押した原本を至急送ってくれというメールが相次いだ。
それに対応していたら郵送費がいくらかかるか分かったものではない。何か良い方法はないものかと方々に問い合わせ、挙句の果ては任さんを通じて北京の日本大使館(任さんの学生だった神戸外大のOBが勤務している)にまで聞いてもらったのだが、どうにもならないということが分かった。こちらとしては、どうしてそんな書類を一々こちらで用意しなければならないんだという気持ちだが、中国の人にとってみれば、何で日本という国はこんな面倒な手続きを踏ませるのだという思いだろうから、どっちもどっち、というか悪いのは日本のシステムである。
そうこうしているうちにもメールは増えていく。結局、諦めて要求があったものについては全部こちらで書類を作って郵送することに決め、卒業式から新学期の始まりまでの2週間ほどはほぼ毎日郵便局に通って、全部で60通近くのEMSを送った。ビザの関係では、上から目線の居丈高なメールも多くて嫌になる。海外の学会ではこういった作業はたいてい大学院生がやっているので、向こうもまさか教員が全部やっているとは思いもしないだろう。今にして思えば、早い段階からアルバイトの大学院生を一人か二人雇って手伝ってもらえばよかったのかもしれないが、とにかく予算のことが心配で、そんな余裕はなかったのだ。
今回は一般発表のほかにワークショップが全部で五つ立つことになっていて、そのうちの一つはプレ・ワークショップとして5月9日(木)に行うことが決まっている。種々考えた結果、分科会は2日間にわたり9会場を同時進行させ、うち1会場をワークショップに充てるという具合にした。分科会の中身については、まず分野ごとに発表タイトルの一覧を作り、それぞれのセッションはできるだけ中国語の発表もしくは英語の発表で一貫させるという方針でまとめていき、最後に内容に応じて司会者を割り振るという手順で作っていった。発表者として来る人には当然他のセッションで司会を担当してもらってもよいだろうが、発表予定のない日本の人には前もってお願いしておく必要がある。また、学生の健康診断がある関係で、2日目と3日目は使用する建物が違うので、会場となる教室の配置や導線にも気を配らなければならない。その他、基調講演や総会をどこに置くか、昼食休憩の時間をどれくらい取るか、ティーブレイクをどこに入れるか等々、様々な試行錯誤や紆余曲折を経て、プログラムがようやく組みあがったのは、会期のほぼ1ヵ月前となる4月8日のことだった。
[2019.10.26 竹越孝]
国際学会開催記(2)〜予算・ウェブサイト・基調講演〜
アメリカ・ウィスコンシン州マディソンで行われたIACL-26から帰ってきて、早速検討し直さなければならなかったのが日程の問題だった。そもそも、学会のために連続した三日間を確保するとなると、学期中であれば三連休しかないわけだが、実際には二日半を予定しておけばよいという話だったので、金曜日の午後からスタートして土・日をフルに使うことにした。金曜日には授業をやっているから分科会はできないが、ホールで基調講演をまとめてやってしまえばいいだろう。学校側とも相談の上、会期を5月10日(金)から12日(日)までと決めた。二日目の11日には学生の定期健康診断が入っているが、使う建物は限られるから、学会が開催できないほどではないらしい。
結果的にはこれが功を奏した。というのも、ちょうどその時期から平成天皇の退位と新天皇の即位に伴うゴールデンウィーク10連休の話が出てきたからで、もし日程がGWのままだったら、その間すべての作業がストップすることになって、かなり苦労しただろう。
開催を引き受けるにあたって一番心配していたのは予算の問題だった。これまで開催したことのある日本中国語学会のような国内学会だと、学会事務局から降りてくる予算に参加費収入をプラスして、赤字が出たら事務局が補填してくれるし、黒字が出たら事務局に返金するというシステムなので、どう転んでもトントンになり、原則としてお金のことを気にする必要はないのだが、国際学会では基本的にすべて自分たちで賄わなくてはならない。
もともと、今回の学会はなるべくシンプルに、お金をかけずにやりたいというのが希望だった。2002年に愛知県立大で開催されたIACL-11の時は、オーガナイザーの岩田礼先生が大変な苦労をされて各方面から資金を集め、至れり尽くせりの学会にして下さった。何しろ日本で初めての開催だし、学会でも大学でも、国際学会に対する支援体制が整備されていない時代だったから、その困難は想像するに余りある。僕はその時ただの一参加者に過ぎなかったわけだが、日本で初めてのIACL年次大会を何としても成功させたいという熱意は充分に感じ取ることができた。その結果、日本の中国語学界が一気に国際化することになったのだから、これはとても意味のあることだったと思う。
しかし時代は変わり、日本人研究者が海外の学会に参加したり、中国を始めとする外国の研究者と交流したりするのがごく当たり前のことになった現在にあっては、総力を挙げて海外からの賓客をもてなすとか、日本の学界の力を世界に示すというような意識を持つ必要はなくなった。勘所だけ押さえて、あとは極力シンプルにやるという欧米式にシフトしてよい時期である。ただ、もちろん全く予算のあてがない中で開催することなどできない。
IACL-11の開催を機に創設されたという中国語学会の「国際会議開催支援積立金」は、既に前の年に申し込んであって、事務局から内諾を得ていたのだが、アメリカから帰ってきた翌週に開催された理事会に出てみると、学会のお金を使うのだから会員に何らかのメリットがなければならない、とか様々な注文がついて意外と厄介だった。その他、勤務先の「国際会議・セミナー開催支援金」や神戸コンベンション協会の支援金など、およそ考え付く限りのものをリストアップして申込の書類を作る。さらに、神戸外大中国学科の同窓会組織である「同学会」にも寄付を募ることにして、会長である名誉教授の佐藤晴彦先生に協力を要請した。
8月末にはウェブサイトを立ち上げて、会員に向けてファースト・サーキュラーを出さなければならないので、夏休みに入る頃から本格的にその準備に取り掛かった。大学のサーバーを使えば自分たちで自由に更新することができて楽なのだが、その分手続きや管理に色々と面倒なことも多いので、今回は民間のレンタルサーバーを契約し、最初の設計やデザイン、そして更新を業者に頼むことにする。サーバーの契約は同僚の林範彦さんがやってくれた。
ウェブを立ち上げるためには当然ながらコンテンツを決めていかなければならないが、この時点で一番重要なのは「Call for Papers」である。IACLで受け付ける研究発表は一般発表とYSA(Young Scholar Aword:青年学者奨)に分かれるが、一般発表はかなりの数の応募が予想される。これを全部メールでやり取りするには相当の人員を割かないと難しいので、一般発表については「EasyChair」という学会開催支援のサイトを利用することにした。これはウェブ上でアブストラクトの投稿受付、査読者の割り当て、査読状況の管理から採否結果の通知までを行うことができる優れモノで、IACL-25のハンガリー大会で使われた時から注目していたのだ。
その他にも考えなければならないことは多かった。例えば参加費にしても、IACLを始めとする国際学会では、参加申込の時期に応じてEarly Bird、Regular、Late/On Siteに分け、IACLの会員・非会員、会員の場合学生・一般というように細かく示す必要がある。僕はそもそも参加費をどうやって決めるのかすら考えたことがなかったのだが、林さんに尋ねてみたところ、基調講演で6人呼ぶとして、1人につき飛行機代と宿泊費はこれぐらい、参加者は300人から400人と見て、2日分の昼食代がこれぐらい、ティーブレイクは4回でこれぐらい、プログラムの印刷費はこれぐらい、参加者に配るグッズはこれぐらい、アルバイトは20人から30人雇うとしてこれぐらい、…といった具合にサラサラと書いていき、たぶん参加費はこれぐらいで大丈夫でしょうね、と計算してくれた。うーむ、さすが経験者は違う。
現時点で決められるものは決めて、まだ決まっていないコンテンツはすべてTBA(To Be Announced)としておく。ウェブサイトは英語版と中国語版で同じ文面を用意する必要があるので、英語版は林さんに任せ、中国語版は僕が作って任鷹さんのネイティブチェックを受けるという具合にした。内容的にはまだスカスカだったが、一応8月末にはIACL-27のウェブサイトが立ち上がり、事務局から会員に向けてCall for Papersがメールで送られるとともに、「今日語言学」というWeChat(微信)のアカウントでも広めてもらうことになった。
次は基調講演の人選と依頼である。上に記した開催スケジュールの関係で、初日に4本の基調講演をまとめ、二日目と三日目に1本ずつの計6本で行うことにした。人選は国や地域のバランスなど悩ましいことも多いと聞くが、今回に関しては目玉となる講演者をわりと早くから決めていた。一人は遠藤光暁先生(青山学院大学)からサゼスチョンがあった初代IACL会長、王士元氏(William S.-Y. Wang; 現在は香港理工大学に籍がある)で、呼ぶことになったら斎藤成也先生(国立遺伝学研究所)の科研から経費が出せるという。もう一人は、シナ・チベット語関係の人を呼びたいということで、フランスのロラン・サガール氏(Laurent Sagart)に依頼してみることになった。こちらも、実現したら林さんを通じて池田巧先生(京都大学)の科研から関連経費を出してもらうという手はずである。
王氏の方は遠藤先生が内諾を得て下さっているという話だったが、むろん正式は依頼はこちらから出さなければならない。英語に不慣れな僕はメールの書き出しにいつも困るのだが、林さんが別件で同送してくれたメールを見ると「Greetings from Kobe City University of Foreign Studies!」で始まることが多く、便利なので以後はもっぱらこれを使わせてもらうことにした。それにしても、僕程度の英語力でも何とかメールでやりとりできるのは、全くもってGoogle翻訳のおかげである。
結局、交渉はごくスムーズに行き、王士元・サガール両氏に加えて、IACL現理事長の劉丹青氏(中国)、現副理事長(次期理事長)の張洪明氏(アメリカ)、前々から講演を聞いてみたかった魏培泉氏(台湾)、そして日本中国語学会現会長の大西克也氏(日本)といったところで基調講演を組むことになった。こうして見ると地域や年齢のバランスも上々ではなかろうか。
これらの作業を進めていた2018年の秋は、一方で日本中国語学会の第68回全国大会が神戸外大で開催される予定になっていたので、はからずも国内学会と国際学会の準備を同時並行で行うことになった。そもそも、どうして神戸外大で連続して大きな学会を開催しなければならないのか、不思議に思った人も多いだろうが、IACLの方が心づもりとしては先に決まっていて、中国語学会の方は急遽頼まれたからである。アルバイトの主力となる大学院生は中国からの留学生が大半だが、彼らに全国大会であらかじめ経験を積んでもらえるという期待もあった。この時期は体力的にはなかなかしんどかったが、中国語学会は2006年に一度開催したことがあるし、正直言って国際学会に比べたら国内学会の苦労なんて何ほどのこともない。

日本中国語学会全国大会の様子
2018年の暮れから、年明けに始まる査読に備えての作業へと重点が移ってくる。張洪明氏からもらったIACL-26の査読者リストをもとに、手分けして査読者の専門領域を調べたり、手薄な分野については国内外の研究者に査読への協力を依頼したりといった具合である。
そしていよいよ2019年が幕を開け、1月10日のアブストラクト締切を迎えた。
[2019.9.6 竹越孝]
国際学会開催記(1)〜開催決定まで〜
2019年の5月10日(金)から12日(日)まで、勤務先の神戸市外国語大学で国際中国語言学学会(International Association of Chinese Linguistics)の第27回年次大会(IACL-27)を開催した。1992年にシンガポールで第1回が開催されたIACL(設立時の名称はICCL:International Conference on Chinese Linguistics)は、年に一度、北米、アジア、ヨーロッパの各地で年次大会が開かれることになっている。日本で初めて開催されたのは2002年8月のIACL-11で、場所は愛知県立大学、岩田礼先生が全体のオーガナイザーを務められ、当館の吉池さんもそれをサポートされたと聞いている。僕は当時鹿児島大学に勤めていて、国際学会に参加するのも、中国語で発表するのもこれが初めての機会だった。それから17年の月日が経って、今度はその学会を主催する側に回ったわけである。僕自身は定年までもうこの手の学会を開催することはないと思うが、もしかしたら十年後ぐらいに日本の誰かが開催しなければならなくなるかもしれないので、今回経験したことを少し書き残しておこうと思った次第。
2002年に参加したIACL-11の後は、一度アブストラクトを投稿したことがあるぐらいで(落ちました)、ほとんどこの学会に関心を持つことはなかったのだが、2015年の初めにいきなり英語で略歴を送ってくれというメールがIACL事務局から来て、何かと思ったら15人ほどいるIACLの理事(Exective Committee)の一人になってほしいということだった。どうやら理事会の構成には国・地域別の割り当てというのがあって、日本枠の一人で声がかかったようだ。そういえばうちの妻も理事をやっていたことがあるから、その線で名前が出たのかもしれない。その年はソウル・漢陽大学校で韓国では初となるIACL-23が開催されることになっていて、もう発表の申込期限は過ぎていたので、理事会だけならと物見遊山気分で参加したのだが、今から思えばこれがそもそものきっかけだった。
IACL-23の理事会と総会の会務報告で、各国の会員数やこれまでの開催実績がグラフで示されたのだが、日本は会員数では3番目ぐらいの多さなのに、開催実績が1回だけというのがいかにも少なくて、これはちょっとまずいのでは…という気になった。その時のIACL理事長は旧知のラマール先生だったので、それとなく聞いてみると、確かにそろそろまた日本でやらなければならないかもね、というような話だった。翌2016年のIACL-24は北京語言大学ということだったが、次回あたりそんな声が上がりかねないな、と焦り始めた。
日本で開催するにしてもなぜお前が焦るんだというツッコミは当然あるだろうが、今や語学専攻の専任教員が3人以上いる大学は外国語大学ぐらいしかないし、しかも新たな日本枠理事の一人が同僚の任鷹さんになったと聞いて、当然神戸外大が狙われるだろうと思ったのだ。この危惧は任さんも同様だったようで、北京のIACL-24理事会では任さんと、これはちょっとまずいかもね…という話をヒソヒソやっていた。こういう空気感というのは周囲に伝わるもので、直後からそろそろ日本で、神戸外大で、という声が陰に陽に聞こえてくるようになった。
2017年のIACL-25はハンガリー・ブダペストのエトヴェシュ・ロラーンド大学で行われ、僕の理事としての任期はそこまでだったので、最後となる理事会に出席した。席上、2018年はアメリカのウィスコンシン大学マディソン校で行われることが正式発表されたのだが、その主催者でかつ学会の副理事長である張洪明氏が、長らく日本でやっていないことだし、ウィスコンシンの次は神戸にしようじゃないかと宣言してしまった。皆さん、おお、それはいい、という雰囲気。うう、ついにその時が来た。

エトヴェシュ・ロラーンド大学でのIACL-25
ただ、この時点ではある程度あきらめがついていた、というか何とかなるだろうという感触を持っていたことも事実である。これには信頼できる同僚が複数いるというのが大きい。言語学科の出身で英語に堪能な林範彦さんは「国際ヒマラヤ言語学シンポジウム」(2011年)など国際学会の開催経験があるし、中国社会科学院出身の任鷹さんはIACL事務局や中国の有力研究者と日常的にコミュニケーションが取れる。僕の大学院での後輩にあたり、いつも誠実に仕事をこなしてくれる下地早智子さんもいる。この業界では、表向きの話と裏の意図が違うことがあって何かと厄介なので、任さんからその手の情報も入りそうだというのが特に心強かった。
僕自身が引き受けてもいいかなと思ったのは、今野浩『工学部ヒラノ教授』のシリーズで目にしたさる高名な研究者の言葉、「大学人として一度は国際学会の主催者をやらなければならない、ただし二度やる必要はない」に共感するところがあったからである。この歳になると、自分の一生のうちにできること、できないことがある程度見えてくるようになって、体力、精神、経験のバランスから考えて、生涯に一度の大きなイベントを引き受けるのにはちょうどいいタイミングかもしれないと思った。それと、尊敬する金文京先生が早くから、「自分が呼ばれて国際学会に出席するのはよいが、日本で学会を開くために忙しい思いをするのは御免だという風潮」に警鐘を鳴らしていたこと(「学会、学界と個人研究」『日本中国学会便り』2005年)も消極的な動機としてあった。我々が海外の学会に行って多少とも厚遇されるのは数々の先達のおかげなのだから、こんな傲慢さだけは決して持つまいと自戒していたのだ。
2018年の5月にウィスコンシン州マディソン市で開催されたIACL-26には、任さんは招待発表、他の3人はアブストラクトが通ったので、神戸外大の教員4人で参加することになった。せっかくだから今回はみんな英語で発表しようと呼びかけ、出発の前には院生も集めて予行演習会を行った。日常的に英語で発表している林さんには何を今さらという感じだったろうが、IACLは基本英語で進行することが求められるので、英語にからきし自信のない僕にとっては大きなチャレンジとなる。

ウィスコンシン大学マディソン校でのIACL-26
ウィスコンシンには我々神戸外大チームの他にも遠藤雅裕(中央大学)、千葉謙悟(同)、伊藤さとみ(お茶の水女子大学)、中田聡美(大阪大学)、宮島和也(東京大学・院)といった面々が参加していて、口々に竹越さん勇気ありますねえ…と驚かれる。こちらはそれほど意識していなかったのだが、一回やってしまえば向こう十年は日本で開催しなくてもよいだろうから、お国のために人身御供になったと言えなくもない。
IACL-26では、自分の研究発表の他に、理事会と総会で次期開催校としてのプレゼンテーションをしなければならない。もちろん英語である。幸い、前の2回の年次大会で行われたプレゼンを見ていたので、大体の雰囲気はわかっていて、用意したスライドを映しながら途中で学校紹介のビデオを挟んだりすれば、それほどの苦労はないだろうと思っていた。実際、プレゼン自体は首尾よく終わったのだが、一つ厄介な問題が持ち上がった。
学会の開催日程は2019年5月4日から6日のゴールデンウィーク期間を予定していて、大学の事務局にも確認した上で使用施設を押さえてもらっていたのだが、理事会でそれに難色が示されたのだ。アメリカの多くの大学ではその週が最終試験期間にあたっているので、それだとアメリカの研究者のほとんどが参加できなくなるという。こちらとしては、連休中でないと3日間フルの日程は取れないし、ゴールデンウィークの翌週末には学生の健康診断が入ってくる。とりあえず持ち帰って大学側と協議することにして、総会では最終決定の日程ではないとアナウンスした。早速大きな宿題をもらった気分だ。
IACL-26の閉幕式では、肩の荷を下ろした張洪明氏が最後にこんな詩を披露していた。

張洪明氏による七句
今日はウィスコンシンの名物である牛乳を飲み、来年は共に神戸牛を味わおうという趣旨である。押韻のためとはいえ、やっぱり神戸といえば神戸牛なのだなあ。もっとも、このイメージがもとでバンケットの準備で難しい判断を迫られることになるのだが。
[2019.7.27 竹越孝]
二度目のロンドン(下)
ロンドン滞在の後半は大英図書館で、主に『問答語』を書き写すことに費やした。

大英図書館
前回と同様、まず中2階の受付で閲覧証を発行してもらうことになる。今回は新規ではなく更新だったので手続きはわりと簡単だったが、やはり英文による住所の証明が必要で、銀行の残高証明を準備していったのは正解だった。新しい閲覧証を発行してもらい、3階にあるAsian & African Studiesの閲覧室へ行く。前回はそこで閲覧したい文献を1件ずつ申請したのだが、今回は事前にメールでリストを提出してあったので、受付で取りおいてくれた。

Asian&African Studies閲覧室

大英図書館も吹き抜けの構造になっている
『問答語』(1827年)は全22葉ほどの薄い線装本だが、満漢対訳で「來了麼?―來了」「坐之―不坐」「喫了飯麼?―喫了」「喫了幾碗?―喫了三碗」「飽了麼?―飽了」という平易な問答が延々と続いていく面白い教材である。池上二良先生の『満洲語研究』(汲古書院,1999年)に掲載された書影を見て以来のファンなのだ。実物は今回が2度目の対面となる。
写真は最後に撮ればよいので、まずはひたすらこれを書き写していくことに決める。漢字の部分は書き取り、満洲文字の部分はローマ字転写である。今やほとんどの図書館でパソコンの持ち込みが許可されているので、それに直接打っていけば楽なのだが、僕はノートパソコンを持ち歩く習慣がないし、何となく文献調査には紙と鉛筆というイメージがあるので、まだ導入していない。こういうところは妙に保守的なのだ。
もちろん本に関しては別で、今回はわざわざ日本から重たい『満洲語文語辞典』(福田昆之編,FLL,1987年)を抱えて行った。ちなみにこの辞書は、僕がこれまでの人生で間違いなく一番多く引いた辞書である。「読書百遍…」ではないけれど、中国語の場合、文脈から考えることに慣れてしまって、ある時期からはかえって辞書を引かなくなったのだが、満洲語が相手だとそうはいかない。それと、僕にとって満洲語は「読めればいい」言語なので、単語を覚えようという気がまるでないことも一因である。
SOASの時と同じように、午前中は時間を測りつつじっくり作業を進めると、どうやらそのペースでも丸2日かければ1冊写し終わりそうだとわかった。そうと決まれば、あとはひたすら手を動かすのみである。そういえば学部4年で北京に留学していた時、卒論で扱うことにした永楽大典戯文『張協状元』の地方劇脚本が伝わっていると聞いて、2泊3日の列車で福建省の莆田市まで出かけて行き、文化局の人にかけあって1950年代の上演台本を借り受けると、写真撮影は不可と言われたので、2日間徹夜で全部書き写したことがあった。こういうことには妙にテンションが上がる性質なのだ。
少しだけ3日目の午前中に持ち越したが、何とか全体を写し終わり、指先のじんじんする痛みに耐えながら、1葉ずつ写真を撮ったり、他の文献を見たりした。午後の早い時間に、予定していたすべての作業が終了。ビールで祝杯でも挙げたいところだが、とてもそんな気力は残っていない。いつものようにスーパーでサラダとパンとワインを買い、いつものようにホテルの部屋でダラダラ過ごした。

『問答語』と写し終えたノート
とはいえ、ひたすらダラダラしていたわけではなく、今や僕の人生はジョギングと共にある。今回もジョギングシューズとウェア持参で行き、朝は毎日1時間ほど走ってから図書館に行っていた。ロンドンでジョギングと言えば中心部にあるハイドパークが有名で、最初の2日間はここを走ったが、3日目にちょっと気分を変えるつもりで北部のリージェンツ・パークまで行ってみたら、すばらしく気に入ったので、以後はもっぱらこちらで走った。朝靄の中、真っ直ぐな並木道がどこまでも続くボードウォークを走っている時の充実感は忘れられない。まるで自分がロンドンの風景の一部になったようだ。
最終日は夜の便で、出発までだいぶ時間があるので、列車で1時間ほどかけてケンブリッジ大学に行ってみた。ケンブリッジには「ウェード式」で名高いトマス・ウェード(Thomas F. Wade, 1818-1895)の旧蔵書が収められており、彼の作った中国語教科書『語言自邇集』(1867年初版)は清代の満洲語教材と浅からぬ縁があるので、今回時間があれば見に行くつもりだったのだが、イースターのお休みということで閲覧はかなわず、予定にも入れていなかった。ケンブリッジに着くと、定番観光スポットのキングス・カレッジ、トリニティ・カレッジなどを回ってみるが、すぐに飽きてしまい、天気も悪いので早々に引き上げた。やっぱり目的のない旅は苦手なのである。

ケンブリッジのキングス・カレッジ
今回も充実したいい旅だった。時間があれば、二度目のパリを始め、ベルリン、サンクトペテルブルクといった他の都市にも足を伸ばしたいものだが、今はとにかくまとまった時間が取れないのが悩みである。とりあえず変な役職に選ばれないように対策を考えなければ。
[2018.12.29 竹越孝]
二度目のロンドン(上)
2017年の4月からちょっとした役職についてしまったせいで、学内での会議や打ち合わせの量が飛躍的に増え、一定の期間海外に出ていることが難しくなった。6月にはハンガリー・ブダペストで国際中国語言学学会の第25回年次大会(IACL-25)、7月にはアメリカ・シアトルで第2回韓漢語言学国際会議(ISSKL-2)に参加したのだが、いずれも学会の出席だけでトンボ返りせざるを得なかった。せっかくリゲティ(1902-1987)、ポッペ(1897-1991)、ノーマン(1936-2012)といったアルタイ学の巨匠達にゆかりの深い土地を訪れたのに、じっくり街の雰囲気に触れる余裕がなかったのは残念だ。

ブダペスト市内を流れるドナウ川の夕暮れ。

ワシントン大学キャンパスから見たマウント・レーニア。
そうこうするうちにどんどん月日が経ち、科研の予算執行はどうするんですか、早く予定を決めて下さいと事務からせっつかれたので、3月末の1週間程度ならば大きな問題はないだろうと、その時期に「世界満洲語学の旅」を入れることにした。
行先は、当初アメリカ・ワシントンDCにある議会図書館(Library of Congress)を予定していて、松村潤「米国議会図書館所蔵満洲語文献目録」(『東洋学報』57/1・2,1976年)を見ながら調査すべき文献の目星をつけていたのだが、先方にメールで打診したところ、満洲語のコレクションは未整理なので閲覧は不可という返信が来た。だとすると考えられる行先は、2013年に一度訪れて、二つの文献に心を残したロンドンしかない。
一つはロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)所蔵の『満漢合璧集要』(1764)、もう一つは大英図書館所蔵の『問答語』(1827)である。前者は、前回来た時に写真を撮ったのだが、帰って見てみたら所々ピンボケしていて校本を作る気になれずにいたもの、後者は、写真撮影が不許可だったため複写を申請したつもりが、結局手元には届かなかったものである。このところ、清代の満漢合璧会話書を転写・翻刻して公刊するという仕事を続けているのだが、『清文啓蒙』(1730)、『清文指要』(1789)、『満漢成語対待』(1702?)といった大物はそろそろ終わりが見えてきて、残ったものを片付ける時期に差し掛かっているので、ちょうど良いタイミングかもしれない。
文献調査は事前準備が命で、少なからぬお金と時間を費やして海外に行っている以上は、休みで図書館に入れなかったとか、目当ての文献が見れなかったとかいうことがあってはならない。今回もしつこいぐらい先方に問い合わせて、文献の所在と閲覧の手続きについて確認した。SOASの貴重書閲覧室は水曜日が閉室で、それ以降イースターの休みに入るということだったので、月曜日からの二日をSOASで『満漢合璧集要』に費やし、水曜日からの三日を大英図書館で『問答語』に費やすという計画を立てた。
大英図書館でもすでに閲覧者自身による写真撮影が許可されているそうだが、前回のこともあり、僕の腕だと品質に不安がある。写真を撮り直すとともに、可能な限りその場で筆写やローマ字転写を済ませて校本の作成に備えたい。そして、少なくとも写真を撮ったままほったらかしにしている『満漢合璧集要』については、手持ちの画像に基づいて事前にテキストを打ち込み、ロンドンで現物を見ながら照合する方が絶対に効率が良い。3月は各種の締め切りやら共同作業やらがわんさかたまっているのだが、行くと決めたからには事前準備を優先させなければならない。各方面にすみませんすみませんと頭を下げつつ、出発の前日まで画像の判読と入力に没頭することになった。おかげで肩がバリバリに凝って、帰国までの間ずっと肩と首の痛みが消えなかった。
卒業式の翌朝、大阪・伊丹空港を出て成田で乗り換え、一路ロンドンのヒースロー空港へ。前回作ったオイスターカードがまだ使えることがわかったので、早速地下鉄に乗り換えてホテルに向かう。今回のホテルは大英博物館のすぐそばにあり、SOAS・大英図書館ともに歩いて行ける距離である。目の前がスーパーなので、食事にも不安はなさそうだ。僕は海外では外食する習慣がなく、ホテルの部屋で一人テレビを見ながらもそもそ食べるのが好きなのだが、これは中国や台湾に行っても同じだから言葉の問題ではない。
翌朝、そそくさと朝食を済ませると小雨の中を歩いてSOAS図書館へ。手続きは前回と同様で、まず閲覧証を更新してから貴重書閲覧室に行って来意を告げる。中国系と思しき女性が親切に対応してくれたのだが、次に来た人とは中国語でやりとりしていたので、僕も気取らないで最初から中国語を使えば良かった。早速『満漢合璧集要』が出てきて調査開始。

SOAS図書館の外観。相変わらず謎の像が鎮座している。

貴重書閲覧室の入口。
文献調査は常に時間との勝負だが、今回は特に調査の対象と費やす時間が決まっているので、まず期間内に最後まで見終われるかどうかを見定める必要がある。それには、どれくらいのペースで見て行けばどれくらいに終わるかを計算しなければならないので、最初は時間を測りながら最も遅いペースで見て行くことにした。この文献は、「合璧」と銘打ちながらも満洲語と中国語の並置対訳形式ではなく、「上満下漢」の形式なのでやや勝手が違う。随所に墨筆で書き加えた部分があり、これはやはり画像だけ見ていてもわからない。
結局、かなり時間をかけて見ても二日かければ充分に終わりそうだという感触が得られたので、やや安心する。例によって昼食は食べずに、手持ちの入力資料と見比べながら、修正点や注記すべき箇所を細かくメモしていく。その日は閉室時間まで粘ったが、だいたい全体の三分の二ぐらいまで進んだから、明日一日あれば何とかなりそうだ。図書館を出ると、フラフラになりながら何とかホテルに帰り着き、時差ボケもあって夕飯もそこそこに寝てしまった。
翌日もほぼ同じ時間にSOASを訪れて照合を継続し、だいたい午後3時ぐらいにすべての作業を終了した。最後に開架閲覧室の蔵書を見て歩いたのだが、その悠揚迫らぬ佇まいにはやはり伝統の重みを感じる。ふと気になって古代文字資料館の刊行物が置かれていないか調べたが、残念ながら発見できなかった。

SOAS図書館は全体が吹き抜けになっている。
50歳を目前にした今も、僕は図書館で古い文献を見ている時間が一番好きだ。他のことを何も考えずに集中できるし、大げさに言うと自分の生きる世界はここなんだという実感がある。この感覚は、留学中に卒業論文のため福建省まで地方劇の脚本を見せてもらいに行った時や、院生の時に駒込の東洋文庫でアルバイトをしていた時から変わっていない。
前回来た時も入った、大学内の生協のようなパブに入ってギネスを1パイント頼み、ちびちび飲みながらほっと一息つく。これでロンドンでやるべきことの半分は終わった。明日からは大英図書館だ。
[2018.11.25 竹越孝]
舞台で聞いた中国語22……先生、お誕生日おめでとうございます!(老師,生日快楽!)
昨年、北京にて鼓楼西劇場という小劇場を初めて訪れた。名前のとおり、観光地の鼓楼の西隣のエリアにある。鼓楼西大街というバスの走る通りから向かえばすぐだが、地下鉄の鼓楼駅の方から歩いて行くと、こんなところに劇場があるのかい、というような古い長屋の続く裏路地(胡同)を、寝間着姿で表をぶらつく地元住民とすれ違いつつ長々と進む。やがて、おお、こんなところにあったあった、と古びた公民館のような建物にふと到着する。劇団運営に携わっていた女性が2014年にオープンさせた民営の劇場とのこと。レトロな建物の中には小洒落たカフェもあったりして、胡同の一角だが、開場時間の頃になると三々五々若者たちが集まって来ていた。
この日の公演は『青春の禁じられた遊び』《青春禁忌遊戯》(彭遠江演出)。原作はロシアの作家リュドミラ・ラズモフスカヤ(柳徳米拉・拉祖莫夫斯@@)の戯曲『親愛なるエレーナ・セルゲーエフナ』、ソ連時期(1980)の作である(なおこの戯曲は長い間、中国国家話劇院で公演されていた。鼓楼西劇場のは別の団体による)。すでに回収され金庫で保管されている落第点の答案をすり替えるのに、金庫の鍵を貸してほしい、あとほんの少しの点数で将来が安泰になるのだから、と卒業を目前に教師に食い下がる生徒4人と、それを拒む数学の女教師エレーナの物語である。押し問答の末、最後には教師は生徒に金庫の鍵を渡すのだが、このテーマは観客の宿題にもなっていた。

カーテンコール
終演するとアフタートークがあり、活動紹介に続いて、もし自分が教師だったらどうするか、皆の意見を出口で投票してほしい旨が呼びかけられた。不正を黙認し生徒に鍵を渡してやる人は黒の箱、鍵は渡さない人は赤の箱に「鍵」を入れて下さいという(投票用紙代わりに、金属製のアンティークキーがたくさん用意されていた)。これまで少々変わった趣向のアフタートークを聞いたことはあったが、投票は初めてだ。中間開票結果(連日公演していた)は、反対派が優勢とのこと。私ももちろん劇前半の教師のように、「何を甘えたことを言っとるか、ズルはいかん」と心は決まっていたのだが、投票の列に並んでいる間に、「しかし待てよ、話はソ連の社会、大学に行けなかったら軍に入るしかないとか言ってたしなあ」と情にほだされそうになる。
生徒の計画は、「老師,生日快楽!」というセリフから始まる。彼らは教師の誕生祝いにかこつけてご機嫌を取り、拝み倒す計画だった。しかし、教師が生徒の目論見を知って態度を頑なにすると、生徒の方も態度が変わり、出始めたさまざまな本音が教師への恨みつらみへと変わってゆく。一枚岩だった4人にも亀裂が入り、一人は自殺し、一人は渡された鍵を使おうとし、残りの二人はそれを阻む(原作では鍵を渡した教師が自殺するようだ)。

投票箱
私の投票した箱の色は「保密」だが、自分の前後の様子を見たところでは、やはり反対票を投じている人が多いようだった。外国で投票することがあるとは、思ってもみなかった。テーマは少々重かったものの、投票は国籍、ビザ問わずで、おまけの愉快な経験だった。
反対に難儀だったことと言えば、中国語で聞くロシア人の名前。これまでにも薄々感じてはいたのだが、正直なところなかなか苦痛である。劇中、教師のフルネーム「葉蓮娜・謝爾蓋耶夫娜」(エレーナ・セルゲーエフナ)が出てくるセリフは、早口と声調に惑わされるのか、何度聞いてもどこで名字を言い終わっているのかさっぱりわからなかった。まあ日本語のカタカナ発音の違和感も似たようなものかもしれないが。ともあれ、私にはロシアの翻訳劇は要予習という宿題もしかと出たのだった。
[2018.9.19 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語21……まだ話してる途中なんだけど!(我還没説完[口+尼]!)
夫婦喧嘩は万国共通の日常茶飯事だが、中国のそれはというと、格別に迫力があると思う。北京で観たある夫婦の物語の二人芝居は、ソ連の原作ではあるが演技はど迫力だった。


作品名は中国語では《家丑外揚》(家の恥を世間にさらす)という(顧威演出、北京人民芸術劇院実験劇場)。原作はソ連生まれで後にニューヨークに移住した演出家のアレクサンドル・ゲルマン(A. 蓋利曼)による。この演出家に関する日本語の資料は、少なくともウェブ上ではほとんどないようだ。英語の記事を参照してみると、作品名はA Man with Connections(コネを持った男)となっている。ロシア語の原題は《Наедине со всеми》(みんなと一緒に)*である。
ばらばらでややこしいが、要は1980年代のソ連、人間関係の癒着で建設事業を成功させてきた男アンドレイの挫折の物語である。社会の腐敗がテーマのようだ。建設の仕事で起こった事故で息子が両手を失う大けがを負ってしまった後から、話は始まる。アンドレイは息子を仕事の研修に行かせることになった原因をめぐって、妻ナターシャと互いに出世欲や虚栄心を責め立て合い、夫婦関係がこじれにこじれてゆく。
あらすじは夫婦喧嘩の一言で括れるが、その展開はなかなか複雑だった。怒りのあまり、だんまり作戦があったり気持ちとは裏腹な言葉が出てきたりと(誰もが思い当たる節がありそうだ)、一筋縄ではいかない。 とくに、憤りの頂点から演技が始まる妻役は、その殺気立った沈黙、ぎらつく眼光、口を開けば鋭い刃物のように夫を突き刺す怒声と語気、と、観客席も凍りつく凄みと緊迫感で感嘆した。いつだったか、JRの満員電車の中で突如、それはものすごい剣幕で痴漢の犯人を怒鳴りつける女性の声が上がり、その車輌にいた誰もが度肝を抜かれた場面に遭遇したことがあったが、それに匹敵する緊迫感だった(例えになったかわからないが)。
しかし夫もさるもの。途中まではまだ、ねちねち言いながらも比較的穏やかに言い訳していた。うっかり妻の話を遮って「まだ話してる途中!」とピシャリとやられては、なよなよと「頭痛が……」と仮病を使ったりする恐妻家の体でもあった。それが、和解に近づいてきて妻の方が調子づいてくると、そもそも元はと言えばおまえが悪い、と一気にちゃぶ台(そんなものはないけれど)をひっくり返して猛反撃し、妻を家から追い出してしまう。最初穏やかだった人がだんだん激昂してくると、それはそれで余計に怖い。 何か自分に仲裁できることはないかと思わずはらはらしながらも、実際の場面でも第三者が迂闊に口を挟むとろくなことにならないと思うので、(観客だから当然だが)終始静かに見守った。
最後、妻は出て行き、家にぽつんと残った夫は、病院にいる息子からの電話を受け、無理に明るく「お母さんはもうすぐ帰ってくるよ」と答える。その背中にいくらか悲哀を感じないでもなかったが、どこでも夫婦喧嘩って……、と少々苦笑したのだった。 キャストは張万昆(夫役)と呉珊珊(妻役)。どちらも細身でいかつい印象などないところに、またプロの凄さを感じる。ああ怖かった、誰も血を流さず劇場を出られてよかった……。という演劇鑑賞らしからぬ感想が、私の最高の賛辞である。
*アルファベットも覚束ないまま検索した。誤記があればご教示下さい。
[2018.8.19 榊原真理子]
余計なお世話
言葉に関わる人たち、つまり、本の校正や辞書編纂に携わる人たちには共通した性癖がある。 それは、誤りは正すべきものという信念を持っていることだ。 単純な印刷上の誤記(=ミスプリ)はもとより、原著者のあるいは世間一般の勘違いは当然正されねばならぬというドン・キホーテ的な信念である。これが時として“余計なお世話”になる。
<Guten Morgen>
吉池孝一氏の「有坂秀世『音韻論』の増補版について 」(『KOTONOHA』59、2007)では興味深い例が紹介されている。 言語学者・有坂秀世の博士論文である『音韻論』は昭和15年の初版以来何度も版を重ねており、吉池氏の手元にあるものだけでも、以下のように7種を数える。
①『音韻論』昭和 15 年 12 月 15 日発行。印刷者:三省堂蒲田工場。
②『音韻論』昭和 17 年 1 月 15 日再版発行。印刷者:三省堂蒲田工場。
③『音韻論』昭和 18 年 12 月 10 日三版発行。印刷者:三省堂蒲田工場。
④『音韻論』昭和 22 年 9 月 30 日初版発行。印刷者:清和印刷株式会社。
⑤『音韻論 増補版』昭和 34 年 5 月 5 日初版発行。印刷者:萩原印刷所。
⑥『音韻論 増補版』昭和 44 年 9 月 20 日 4 版発行。印刷者:不記。
⑦(復刻版)『音韻論 増補版』1992 年 11 月 25 日復刊第 1 刷発行。印刷者:不記。
その166頁にドイツ語の「Guten Morgen!」の発音の崩れについて述べた個所があるが、その「Guten Morgen!」の音韻表記を増補版では 「《ɡu:tən mɔrɡən》」とする。これについて吉池氏は次のように述べる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問題となる部分はドイツ語音韻表記の《mɔrɡən》である。諸版本をみると、①②③④ 「《mɔrjən》」→⑤⑥⑦「《mɔrɡən》」とある。 Morgen の g に相当する音韻表記を前者 は接近音《j》とし、後者は破裂音《ɡ》とする。 ⑤「増補版」の編集者は意をもって破裂音《ɡ》に訂正したわけであるが、これはかえって有坂氏の意に反する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
20世紀前半のドイツでは「《ɡu:tən mɔrjən》」がごく普通の発音であったこと、 そして有坂氏が『音韻論』以前の論文においても「《ɡu:tən mɔrjən》」を用いていたことを増補版の編集者(校正者)は知らなかった。 そのために訂正を要しない《mɔrjən》を《mɔrɡən》に訂正(!)してしまった。 仮にも『音韻論』という名を冠する書の校正において、音韻表記を改竄してしまうというのは、まったく余計なお世話としか言いようがない。
<的を得る>
「的を得る」が「的を射る」あるいは「当を得る」の誤用であるという説は『三省堂国語辞典』第3版(1982年)が初出であるらしい。 その後、テレビのクイズなどではこの辞書を根拠として、「的を得る」が誤用であるという説明が繰り返されることになる。 いわく、「的(まと)」は「射(い)る」ものであって、「得(え)る」ものではない、と。 「的を得る=誤用説」は『三省堂国語辞典』を作り上げた見坊豪紀の主張によるのであろう。 彼の1960年代の語彙採集カードにも「的を得る」を誤用と記しているようであるから、一貫した信念だったと言えようか。 しかしこれも余計なお世話の類である。
6月11日放送のNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」はプロの辞書編纂者である飯間浩明氏を追っていた。 『三省堂国語辞典』に第6版から参加した飯間氏が「的を得る=誤用説」を「冤罪」と表現しているのが印象的であった。 2013年12月の『三省堂国語辞典』第7版では「的を得る」が項目として載った。 来るべき第8版の編集会議で彼が「的を得る」が「誤用ではない」と明記したいと主張しているのには溜飲が下がった。
「的を射る」を「核心を突く」の意味で用いる例は、明治大正期にはまだない-----ように思うが、 ないことを証明するのは容易ではないから、今のところ見当たらない、ということにしておく。 明治期によく使われた表現は「正鵠(せいこく)を得る」である。「正」も「鵠」も的(まと)の種類で、「正鵠」は「的(まと)」と同義。 「正鵠」は表現としていかにも硬いし、戦後の漢字改革で「鵠」が当用漢字からはじかれたこともあって、 「正鵠を得る」は戦後には「的を得る」という形で広まった、という説が「BIFFの亜空間要塞」というブログに展開されている。 もちろん「的を得る」という表現は戦前にも(というか江戸時代にも)あったのであるが、 「正鵠」という表現が敬遠される過程で存在感を増したということなのであろう。 「正鵠を得る」から「的を得る」への置き換えが起こったとすれば、 「的を得る」が「的を射る」の誤用であるという説がそもそも「正鵠を失している」(=的を得ていない)ことになる。
<…に不滅である>
2009年に吉池孝一氏、竹越孝氏、私の3人で、恩師である慶谷壽信先生の論文集『有坂秀世研究−人と学問−』を編集出版したことがある。 その時にはまだ先生もお元気だったので、本人による校正が毎週のように郵送されてきた。 その論文集には書評や雑誌への投稿なども採録したが、 その中に雑誌『中国語』第214号(1977年)に「私のこの一冊」として有坂秀世著『国語音韻史の研究(増補新版)』を紹介した文があった(論文集301頁)。 その最後の部分に、「博士の壮絶な一生は、珠玉の名篇と教訓とに不滅である。」とあって、我々3人はその日本語に違和感をもった。 「名篇と教訓とに不滅」の部分はミスプリか抜け落ちがあるのではないか。
おそるおそるこの件について問い合わせると、先生の返事は意外にも、どこがおかしいのか、という調子のものだった。 どうやら「名篇と教訓とに不滅」の「に」は「において」「によって」を意味する一種の文語表現であるらしかった。 最終的には、弟子たちが分からないなら他の人はもっと分からないだろうと思ったのか、「珠玉の名篇と教訓とによって不滅である」と直して下さったのだが、 あるいは余計なことをしたのかも知れない。しかし、生前にご本人から確認してもらったのだから、一応よしということにしておこう。 もし先生のいない今、この編集作業をやっていたら、 暴走して「博士の壮絶な一生は、珠玉の名篇とともに不滅である。」というつまらない表現に訂正(!)していたかも。 それこそ余計なお世話以外の何物でもない。
[2018.6.19 中村雅之]
それらしいこと
<ミール>
黒田龍之助『ロシア語だけの青春 ―――ミールに通った日々』(現代書館、2018年3月)は、 著者が高校時代から通ったロシア語学校「ミール・ロシア語研究所」での日々を綴った非常に面白い回想録だ。 その中に「ミール」というロシア語の意味について記述した部分がある。引用してみよう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ミールмирとはロシア語で「平和」という意味である。
実をいえば、現代ロシア語にはもうひとつ「ミール」という単語があって、そちらは「世界」を意味する。 古い時代は違っていたが、いまでは多義語となってしまい、ときにはどちらの意味なのか、判断に迷うこともある。
だがわたしたちの学校は、間違いなく「平和」だった。なにしろミールのあったビルの名称が、「平和ビル」だったのである。 さらには、ミールと同じフロアに雀荘があって、そこは「麻雀ピース」といった。これはどう考えても「平和」ではないか。 わたしは勝手にそう決めつけていた。(94頁)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ところがその後、「ミール・ロシア語研究所」はもともと別の場所にあり、「平和ビル」に引っ越したのは偶然であることがわかった。 この場合、「平和ビル」にあるから「ミール」も「平和」の意味だろうという推論は根拠としては誤りだったことになる。 しかし、平和を意味する「мир」が「平和ビル」にあるというのはいかにも“それらしい”というか、思わせぶりである。 このような、それらしい状況というのは至る所に潜んでいて、我々の判断を惑わす。
<日暮里>
東京に「日暮里(にっぽり)」という地名があり、山手線に「日暮里駅」もある。 学生の頃、駅のアナウンスで「にっぽり」を耳にするたびに、多少の違和感をいだきつつも、漢字音なのだろうと思っていた。 「日(にち)」と「里(り)」は問題ない。「暮」は何かの事情で「ぼ」が「ぽ」に転訛したのであろう、と。
しかし、ある時、佐伯泰英『居眠り磐音江戸双紙13 残花ノ庭』(双葉文庫、2005年)を読んでいて愕然とした。 そこには次のようにあった。
「日暮里(にっぽり)は新堀からの変化で、風雅にも日暮里(ひぐらしのさと)と呼ばれるようになるのは、享保期(1716-36)以降のことだという。」(16頁)
この説明によれば、「にっぽり」という発音は「新堀(にいほり)」からの転で、表記の方はその地の別称である「日暮里(ひぐらしのさと)」に由来するという。 発音と表記に直接の関係はないというのだ。 「日暮里」と「にっぽり」の間に、漢字音としても解釈できそうな“それらしさ”が存在したことから思い込みが生じたのである。
<「つ」「ツ」>
仮名の「つ」「ツ」の字源については例えば『広辞苑』に、 「平仮名「つ」は「州」の略体の草体とも、「川」「津」「鬥」の草体とも。片仮名「ツ」は「州」の略体。」とあり、 各種の概説書にも「川」や「州」が「つ」「ツ」の字源として挙げられている。どうしてこのようなデタラメがまかり通るのか不思議である。 「川」と「ツ」がともに三本線からなるという偶然が、いかにも“それらしく”見える原因なのであろう。 「ツ」が「州」の中の小さな三つの点に由来するという説に至っては、もうタチの悪い冗談としか思えない。
仮名(万葉仮名)には音仮名と訓仮名があり、広辞苑にも挙げられた「津」は訓仮名としての資格を有している。 一方、「州」「川」は音としても訓としても、「つ」には結びつかない。 「川」の現代中国語音「chuan」がそこはかとなく「つ」に近いように感じられるとしても、 「つ」がかつて[tu]と発音されていたことを知れば、「川」の中国語音と全く合わないことは明らかである。
結論としては、広辞苑にも挙げられた「鬥」(闘の原字)が候補として最適ということになろう。 漢音が「トウ」、呉音が「ツ」であるこの字は、草書体がまさに「つ」(の古体)と同じであり、片仮名「ツ」もその名残をとどめている。 14世紀に中国で出版された『書史会要』の中に平仮名のサンプル(いろは歌)が収められているが、 そこに記された「つ」の字形は「鬥」の草書体そのものと(私には)見える。 実際には、「鬪・闘」の略体として「鬥」の草書体(=門の草書体)が仮名として用いられたのであろう。
[2018.5.22 中村雅之]
細かいこと
細かいことが気になって仕様がない。 そのままスルーしても大勢に影響がない場合がほとんどだが、気になることを溜めておくのもカラダによくない。 酒席での年寄りの愚痴のように、この際吐き出してみようかと思う。
<李斯列伝?>
史記に始まる紀伝体の歴史書は皇帝の伝記である「本紀」とその他の人物の伝記である「列伝」を柱としている。 その中で、例えば始皇帝の宰相であった李斯の伝記を「李斯列伝」などと記している書物がある。 日本で出ている史記の翻訳ではほとんどがそうなっているのではないか。しかしこれは論理的におかしい。 「列伝」というのは様々な伝記を総合して言うから「列伝」なので、「李斯」のような個人の伝記は「李斯伝」でなければならない。 中国の書物では「李斯列伝」式の表現はあまり見たことがないが、あろうことか中文版のWikipediaでは「李斯列伝」となっている。やれやれ。
それではなぜこのような誤りが生じたのか。理由は明らかで、古い版本の見出しを誤読したのである。 「史記」第87巻の見出しは次のようになっている。
「李斯列伝第二十七」
これを頭から読めば「李斯列伝」となってしまうが、ここは「李斯・列伝第二十七」と読むのが正しい。 現代風に書けば、「列伝第二十七・李斯」となる。見出しの後に巻の順次を記すのが伝統的な方法である。 今から40年近く前に岩波文庫の『史記列伝』(小川環樹ほか訳)を読んだ時に、「李斯列伝」とあるのを見て、 個人の伝記に列伝はないだろうとひそかにツッコミを入れていたが、今に至るまでその誤りは正されていないようである。
<重紐の紐は声母?>
中古音の中心資料である『広韻』に、「重紐」と称される現象(というか状況)がある。 例えば、平声支韻の「奇(渠羈切)」と「祇(巨支切)」はどの方言でも同音であるため、まるで同音の音節が重複して登録されているように見える。 このようなペアが『広韻』全体では60例以上あり、今では「重紐」と呼ばれている。そこで、なぜ「重紐」と名付けられたかが問題となる。
平山久雄氏の「中古漢語の音韻」(『中国文化叢書1 言語』所収、大修館、1967年)では、 「このようなpairは、反切系聯の結果では下字が系聯してしまうことが少なくない。 その場合には、同一声母が同一韻母と重複して結合している観を呈する。声母を<紐>ともいうので、したがって<重紐>と呼ぶのである。」と説明する。 太田斎『韻書と等韻図1』(神戸市外国語大学・研究叢書52、2013年)も「この名称は声母に、「紐」という言い方があるところから来ている。」 と記す。
私にはどうしてこのような説明がなされるのか理解できない。 「紐」がかつて「声母」の意味で使われていたことがあるのは事実であるが、「重紐」の「紐」が声母を意味するとは思えない。 「重紐」の本質は『広韻』に別々の小韻として登録されているペアが一見同音に思われるものであるということ、 換言すれば、同音の小韻が重出している(かに見える)ことである。決して声母が問題の本質なのではない。
『広韻』に先立つ『切韻』系韻書の唐写本を世に知らしめたのは王国維であるが、 彼の「書巴黎国民図書館所蔵唐写本切韻後」(『観堂集林』所収)では「小韻」を「紐」と称している。 「蒙紐」(=蒙小韻)、「洪紐」(=洪小韻)のような表現があるし、また「紐末」(=小韻末)に増加字があるとか、 「紐首」に何の字を置いているというような表現があるから、「紐」が小韻の意味であることに議論の余地はない。 つまり、「紐」は小韻のことで、「重紐」は「重複した小韻」あるいは「(同音の音節が)重出している(かに見える)小韻」と解釈するのが妥当である。
<パクパ文字?>
フビライの命によってチベット僧パスパが作成し、13世紀後半に公布された文字は、日本では通常「パスパ文字」と呼ばれている。 これは直接には中国語の「八思巴字」に由来する。英語では「’Phags-pa script」が一般的だが、その「’Phags-pa」はチベット文字表記の翻字である。 「聖なる」を意味するこの語を現代チベット語(ラサ方言)では「パスパ」よりは「パクパ」に近く発音するらしい。 それで、服部四郎氏などは文字名をも「パスパ文字」でなく「パクパ文字」とする。モンゴル史の研究者にも「パクパ文字」を用いる者は多い。
チベット人の名前(というかニックネーム?)なのだからチベット語式に記すというのは、一見筋が通っているようであるが、 個人的にはどことなく違和感を覚える。 例えて言えば、唐代の詩人「李白」を、中国人であるからという理由で現代中国語風に「リーバイ」と読むようなコソバユイ感じがある。 日本語の文章においては日本の音読みで「リハク」とするのが最も落ち着くわけである。
元代に用いられた「八思巴」あるいは「抜合思巴」という漢字音写がそもそもチベット語の発音に基づいた音写なのかということに疑問を投げかけたのは 吉池孝一「パスパとパクパ」(『KOTONOHA』30、2005年5月)であった。
「’Phags-pa」のチベット語音からの音写は明代の『西蕃館訳語』に「恩怕克思罷」という形で見られる。 最初の「’」で示される鼻音要素「恩」については今は措くこととして、次の「怕」は「Pha」に相当する無声帯気音である。 しかるに元代の音写では「八」「抜」と無気音になっている。 これにより、元代の音写が直接チベット語に基づいたのではなく、モンゴル語を介してなされた可能性があると吉池氏は指摘する。 モンゴル語には有声の/b/(漢字音写では無気音に相当)はあるが、無声の/p/(漢字音写では帯気音に相当)がないからである。 つまり、漢字音写から見る限り、元代には「’Phags-pa」はチベット語風にではなく、 モンゴル語なまりで漢人に受け受け入れられていた可能性が高い。 13世紀のウイグル文字モンゴル語碑文にはこの語を「baγisba」と転写しうる形で記したものがある。 その語形に対応する漢字音写が「抜合思巴」であろう。 「八思巴」はその省略形と言えるが、この省略がモンゴル語の段階で生まれた形か、中国語に取り入れられてから生まれたものかは不明。
以上のような状況を見ると、やや大げさな言い方をすれば、日本語で「パスパ」と称するのは、元代のモンゴル人や漢人の習慣を引き継ぐ呼称なのだと言えないこともない。 少なくとも、「パクパ文字」という表記の方が言語学的に正しいとか、歴史的に正当だということにはならないのである。
[2018.3.27 中村雅之]
中国の民族文字資料(4)
「いろいろな話」では演劇にまつわる話題を書かせていただいているが、今回は突然ながらキリル文字(ロシア語)の話題を紹介したい。 というのも、実は「いろいろな話」を遡っていただくと、中国の観光地で見かけた満洲語やモンゴル語を紹介した拙文の 「中国の民族文字資料(1)〜(3)」がある。先日資料収集で北京を訪れた折に町中でロシア語表記を見かけ、好奇心でいくつか立ち寄ってみた。 「中国の民族文字資料」の続編として写真を少し紹介したいと思う。






緑の板の単語はフルークトィ(果物)


広い北京の民族文字、またぼちぼち探してみたいと思う。
[2017.10.17 榊原真理子]
ボストン滞在記(下)〜レッツゴー・レッドソックス!〜
こんな感じで滞在中は毎朝チャールズ川沿いをジョギングし、その後ハーバード燕京図書館で夕方まで過ごし、 ご飯を食べてホテルに帰るというパターンを繰り返した。気持ちの良い季節に体を動かし、思う存分勉強して、 夜ぐっすり眠るというのは何たる愉悦だろう。ああ幸せ。ある方から来たメールに、 いまボストンにいて毎日とても楽しく過ごしていると返信したら、折り返し、在外研究でまた来ればいいと言われてすっかりその気になる。 よーし、待ってろよ在外。
見たいと思っていた文献をすべて調査し終えたのが金曜日の午後4時、後は翌日の便で日本に帰るだけとなった。 ボストン最後の夜に何をすべきか。その答えは、フェンウェイ・パークでボストン・レッドソックスの試合を見ることである。 その日からカンザスシティ・ロイヤルズとの3連戦があるのだ。
チケットは日本からでもネット予約できるらしいが、さすがに行く前からそんなことはできない。 試合開始の1時間前から当日券が売り出されるので、2〜3時間並ぶ覚悟があればゲットできるかもしれないと『地球の歩き方』には書いてあった。 これからすぐに地下鉄で行けば2時間ほど待つ計算になる。まあ、仕事は終わっているわけだし、もう夕方だし、明日帰国だし、問題ないよね、 いいよね…などとなぜか言い訳口調になってしまうのが悲しい性。
地下鉄グリーンラインの「ケンモア」駅で降りると、すでに球場に向かう人の波。とりあえずそれらしき列を見つけて最後尾に並んでみる。 途中で係の人が並んでいる人数を数え始めたが、どうやら買える範囲に入っているようだ。まんじりともせずに長い間待って、ついに列が動き出す。 勢い込んで売り場の窓口から顔を突き出すと、とたんに早口で何事か尋ねられて、あわわわ…となったが、 とっさにオレ60ドル持ってる!と叫んだら、その値段で買える席を向こうが見つくろってくれた。

当日券を求めて並ぶ人々

試合開始前
買えたのはネット裏後方の席で、視界の左手に大きな鉄骨の柱が入る。その向こうに名物のグリーン・モンスター。 隣席との間隔も狭くて若干窮屈だが、そこが全米最古の球場たるゆえんである。早速ビールとホットドックを買いに行ってみる。 ボストンでビールと言えば「サミュエル・アダムズ」で、村上春樹も愛飲しているそうだが、苦みが強くてあまり好きになれず、 二杯目からは定番の「バド・ライト」にした。酒はカッコつけずに自分の好みに合うものを飲むのが一番である。

試合中の様子
試合そのものはずいぶん大味で、レッドソックスは初回にいきなり5点を奪われ、追いつけそうな雰囲気が出てくるとさらに離されるという展開だった。 途中で日本人投手・田澤純一がマウンドに立っておおっと思ったが、特大のホームランを浴びてすぐに引っ込んでしまった。 それでも誰も途中で席を立つことなく、攻撃の時には「レッツゴー・レッドソックス!」と節をつけて大きな声援を送っている。 ロイヤルズのファンは全体の1%もいない感じである。
でも、本当に勝ち負けなんかどうでもよかった。自分がいまボストンのフェンウェイ・パークで、 ビールとホットドックを手に野球を見ているなんて、何だかとても信じられない。 お約束のセブンスイニング・ストレッチ「私を野球に連れてって」はもとより、 フェンウェイ・パークでだけ8回裏の開始時に流れる「スイート・キャロライン」も、周りの雰囲気に誘われるまま大声で歌ってみる。 我ながらこのハイテンションぶりが不思議なぐらいだ。結局試合終了まで見て、酔いと充実感でフワフワした状態のままホテルに帰ると、 倒れるように眠ってしまった。
翌日は夜の便なので、午前中は時間がある。少し遅めに起きて最後のジョギングを楽しんだ後、朝食を済ませホテルをチェックアウトしてから、 地下鉄ブルーラインの終点まで行ってリビア・ビーチという所を散歩してみる。すでに泳ぐには寒すぎる季節だが、 日光浴を楽しむ人々がちらほらいる。初めて見る大西洋の青さは胸に染み入るようだった。

リビア・ビーチ
午後、ホテルに預けてあった荷物を引き取って空港へ向かう。7時頃にボストンを離陸すると、 深夜にサンフランシスコで乗り換えて翌早朝に羽田着、それから国内便で伊丹へ。羽田についた時にメールを見たら、 翌日の会議のリマインダーが来ていて現実に引き戻される。でも、今回は本当に心に残るいい旅だった。いつもの文献探索に加え、 ジョギングで直に街の雰囲気を体感できたことが大きい。
さて、夢のようなボストン滞在から半年が過ぎたこの春、待ってろよ在外、の気合もむなしく、 さる事情が発生して在外研究までには少なくともあと数年待たなければならなくなった。人生なかなか思い通りには行かないものだ。 「ふらんすへ行きたしと思へども ふらんすはあまりに遠し せめては新しき背広をきて きままなる旅にいでてみん」(萩原朔太郎『旅上』) のような心境で、僕は今日もお土産で買ったレッドソックスのTシャツを着て、近所の川沿いをジョギングしている。
[2017.4.18 竹越孝]
ボストン滞在記(中)〜ハーバード燕京図書館〜
前の日は7時ぐらいに寝てしまったはずだが、長旅の疲れで夜中に起きることもなくひたすら眠り続け、翌朝6時前に目が覚める。 天気は良さそうだ。このために日本から持って来たジョギングシューズを履いて、いざチャールズ川沿いの遊歩道へ。 昨日大まかに決めたコースは、少し下ってロングフェロー橋を渡ってから一路上流に向かい、ハーバード橋を渡って帰って来るというもの。 川にはボートのシングル・スカルがちらほら。MITの広々としたキャンパスを横目に見ながらゆっくり走っていると、 もうそれだけで幸せな気分になってくる。すれ違うランナー達と気軽にハーイなどと声を掛け合うのも楽しい。 一度、すれ違うタイミングで向こうがやおら手を挙げたので、あっ殴られる!と反射的によけたら、 ハイタッチを求めていたらしく不思議そうな顔をされ、何だか悪いことをしてしまった。
1時間ほど走ってから、帰り道のコンビニでサラダを買いホテルで食べる。日本で売っているサラダのパックに比べてかなり大ぶりで、 チキンなども入っているのでこれだけでお腹いっぱいになる。コーヒーを飲んでからいよいよ出発。 地下鉄のグリーンラインからレッドラインに乗り換え、「ハーバードスクウェア」で降りると、目の前にハーバード大学のキャンパスが広がっている。

ジョン・ハーバード像
ハーバード燕京図書館はハーバード燕京研究所(Harvard-Yenching Institute)の付属施設で1928年設立、 この研究所は過去にライシャワー(1910-1990)が所長を務めたことでも知られ、全米の東アジア研究における一大拠点である。 図書館利用の手続きについては、数年前に訪れたという氷野善寛さん(関西大学)から聞いてあって、 まずワイドナー図書館(Widener Memorial Library)のオフィスでVisiting Researcher Cardというのを作る必要があるということだった。 大学の教職員は写真入りの身分証明書を提示すると無料で発行してもらえるそうで、 これさえあればハーバード構内に30近くある図書館はどこでも利用可能だという。 早速中に入って身分証を提示すると、一瞬漢字ではわからないと突き返されそうになったが、裏の英語版を見せて納得してもらい、 その場で写真を撮られて数分後には顔写真入りのカードが発行された。これで3ヶ月間有効だそうだ。

ワイドナー図書館

ハーバード燕京図書館前の獅子像
燕京図書館はワイドナー図書館から徒歩10分ぐらいの古風な建物で、入口に獅子像があるのが目印。 木製の扉を開けて一歩入ってしまえばそこは中国語の世界で、僕などにとっては緊張しないで済む快適な空間である。 今回見たい文献についてはあらかじめ検索してリストを作ってあったので、受付に行って来意を告げると、 3階にある貴重書のオフィスに行くよう促される。貴重書はオンラインで申請して書庫から取り出してもらい、 貴重書閲覧室のようなところで見る仕組みである。

燕京研究所・図書館の入口
ここの図書館は、以前行った大英図書館やフランス国立図書館に比べるとざっくばらんで気前が良いという印象で、 一度に何冊までという制限はないし、翌日も来ると言えばブックトラックごと取り置いてくれる。 建前上はオンライン申請なのだが、先に本を取ってくるからリストを貸してくれ、昼休みにでも申請すればいいと言われたり、 隣に同じ書名の本があったから、と言って申請した以外の版本も持ってきてくれたりした。 おかげで『清文虚字指南編』(1885)と『重刻清文虚字指南編』(1894)の版面の違いを細かく比較することができて助かった。 開架図書をコピーしたい時は、受付でクリムゾンカードというのを発行してもらい、そこにお金をチャージする仕組みで、 今回は『哈佛燕京図書館満文書簡目』という簡易製本の目録をコピーできたのが収獲。 他にも、いくつかの書籍にモンゴル学者として名高いクリ―ヴス(Francis Cleaves, 1911-1995)のサインを見つけて感動したりもした。
2日目の午後、貴重書閲覧室で斜め前に座った男がいきなり満洲語の本を広げ始めたので、気になってチラチラ見ているうちに目が合い、 自己紹介することになった。プリンストン大学の鄭さんという人で清朝史専攻、東大にも半年ほど滞在経験があり、 現在は博士論文の執筆中だそうだ。満洲語はどこで習ったのかと聞くと、 ハーバードのマーク・エリオット(Mark C. Elliot)教授による夏期講座だという。その名前に聞き覚えがあったので、 もしかして子弟書の?…と言ってみたらその通りだった。 この間校注本を作ったばかりの満漢混合体子弟書『Katuri Jetere』(pang蟹段兒)の英訳として参考文献に挙げてあったのだ (The “Eeating Crabs” Youth Book, in Under Confucian Eyes: Writings on Gender in Chinese History, University of California Press, 2001)。 こんな感じで意気投合し、彼とは滞在中何度か一緒に昼食を食べに行った。
ハーバード燕京図書館には都合5日ほど通ったが、8月末というのはいちばん活気に溢れた良い季節だったと思う。 アメリカでは9月から新しい学年がスタートするので、ちょうど新入生が続々とキャンパスに集まってくる時期に当たり、 キャンパスのあちこちで引っ越しが行われたり、オリエンテーションやウェルカムパーティが開かれたりしていた。 今回の滞在はホテル代がすごく高くついて閉口したのだが、それはハーバード、MIT、ボストン大学など、 一流どころに入学する子供の入学式に付き添い、ついでにボストンを見物して帰ろうという両親がホテルを押さえているからなのだそうだ。

ウェルカム・パーティの会場
夏の終わりにハーバードのキャンパスに集ったフレッシュマンたちの顔は一様に晴れがましそうで、希望に満ちているように見える。 そりゃそうだよな、世界のハーバードに入るんだから。微笑ましさ半分、羨ましさ半分で彼らを眺めつつも、 もう自分の人生にそういう輝かしい季節が訪れることはないのだなあ、と思うとかすかに悲哀を感じる。 でも、死ぬ前にハーバードに来れて、ジョギングもできたんだから、まあ良しとしよう。
[2017.3.28 竹越孝]
ボストン滞在記(上)〜私はいかにしてジョギングを愛するようになったか〜
またしても予算がついたので、世界満洲語文献探訪の旅ということで、この夏はアメリカのボストンに一週間ほど行くことにした。 訪問先はハーバード燕京図書館(Harvard-Yenching Library)、ここは北米最大の中国書コレクションがあることで有名である。 本当は同じ東海岸にあるワシントンDCの議会図書館(Library of Congress)にも寄りたかったのだが、時間的に厳しいのでこちらは断念した。
前々から、ボストンに行ったらぜひやってみたいと思っていたのが、街を流れるチャールズ川沿いをジョギングすることだった。 こういう話をすると、なんだ、村上春樹にでも憧れてるの、と言われるのだが、その通り、実は大好きなんです。
僕は村上春樹の小説には全く不案内なのに、エッセイや紀行の類はほとんど読破しているという変な読者である。 語学屋の僕には、彼の小説世界に込められた隠喩や寓意を読み取ることが苦手だということもあるが、それよりも大きいのは、 エッセイの中に現れている彼のものの考え方がとても健全で、共感できる部分が多いからである。 「走る作家」の実生活について語った『走ることについて語るときに僕の語ること』(文春文庫)や、 アメリカでの生活を綴った『うずまき猫のみつけかた』(新潮文庫)はとりわけ好きな二篇だ。
さて、なぜ僕は走るようになったか。もともと運動は嫌いな方ではなく、小・中・高・大とずっと体育系の部活をやっていたのだが、 大学院を経て就職する頃には全く運動とは無縁になり、煙草も吸うようになった。 2006年の夏、ちょうど愛知県立大で日本中国語学会全国大会の準備をしていた頃、あまりにも頻繁にギックリ腰を繰り返すので、 医者から運動不足をとがめられて仕方なくウォーキングを始め、数年前からジョギングに切り替えて現在に至っている。
ちょっと昔語りをすると、若い頃はとにかく「才能」とか「個性」とかいうものが欲しくて仕様がなかった。 その発露として論文がある、という考えに捉われていたためか、一流の論文は締め切りぎりぎりになって徹夜のあげく、 突然閃光のようなひらめきが訪れて一気に書き上げるものだ、というようなステレオタイプな思い込みがあった。 これは僕がもともと文学専攻だったことも関係しているかもしれない。 何せ、○○先輩はたったの3日で周囲をうならせるような修論を書いたとか、 △△先生は一夜にしてあの珠玉のような論文を書き上げたとかいうような、数々の伝説に彩られた世界だったから。
ただ、歳を取るにつれて、そういったものが神話に過ぎず、徹夜は結局のところ効率が悪いし、 締め切りぎりぎりになるのはただの怠惰だということがわかってきた。 それは、自分は特に才能に恵まれていないし個性的でもないのだから、 コツコツ努力してきっちり基礎を固めてからでないとまともな論文一つ書けない、と悟った時期とも重なる。 そうした時に、学生の頃に少し小説を読んだことがあるだけの村上春樹に再び出逢い、思い切りかぶれてしまったというわけである。 かくして、僕は「走る作家」ならぬ「走る研究者」目指して再び運動を始めている。
8月下旬のある朝、大阪・伊丹空港を出て成田で国際線に乗り換え、長い長いフライトを経てニューヨーク・JFK空港着、 そこから乗り継いでボストン・ローガン空港に降り立ったのは午後の遅い時間だった。 市内の中心部、パブリック・ガーデン近くのホテルにチェックインし、夕暮れの中を散歩に出てみる。

パブリック・ガーデンのジョージ・ワシントン騎馬像。
ボストンは夏が一番いい季節だそうだが、確かにその暑さは全く不快に感じない。5分ほど歩くとすぐチャールズ川岸に出たが、 ゆったりと流れる川に浮かぶヨットやカヌー、川沿いに長く続く遊歩道、音楽を聴きながらジョギングする人々など、 何だか村上春樹の描くボストンそのままの光景である。

川辺には至るところにカナダ雁がいる。

チャールズ川の遊歩道夕景。
しばらくぼんやりした後、明日の朝走るコースをざっと決めてホテルに帰る。 ボストンでレストランと言えばこれ、という「リーガル・シーフード」とか、ファストフードと言えばこれ、 という「ダンキンドーナツ」には目もくれず(まあ入る勇気がなかったわけですが)、 コンビニでサンドイッチを買ってホテルの部屋でもそもそ食べる。旅の食事はいつもこの程度で充分である。 食べた後で酒を飲んでいなかったことに気づき、買いに出ようかな、と思わないでもなかったが、眠気が勝ってそのまま寝てしまった。
さて明日だ。
[2017.2.21 竹越孝]
舞台で聞いた中国語20……這是怎麼回事了,幹了一輩子為這所房子付款,最後這房子都帰ni了,可没人住 (考えてみるとだね、一生働きつづけてこの家の支払いをすませ、やっと自分のものになると、誰も住む者はいないんだな*)
北京人民芸術劇院で1983年に上演された『セールスマンの死』《推銷員之死》の録画を観た(ウェブ上で公開されている)。 アメリカの作家アーサー・ミラーの戯曲で、初演は1949年、ニューヨークである。北京人芸ではミラー本人を演出に招いて制作された。 話劇史に残る上演の一つとなっている。

あらすじは、セールスマンをするウィリーが仕事もうまくいかず、期待をかける息子も将来性がなく、 一旗揚げる夢を捨てきれないまま自殺してしまうというものだ。1940年代のアメリカの市場経済社会に適応しきれない人々が描かれている。 近年の中国社会に当てはまるような話で、北京人芸で2012年に再演されたのもうなずける話だと思った。
私には立派な持ち家のないかわりに住宅ローン返済のプレッシャーもないが、ウィリーの「一生働きつづけてこの家の支払いをすませ、 やっと自分のものになると、誰も住む者はいないんだな」という台詞には身につまされるものがあった。 いろいろ積み上げてきていざそれを享受しようとする段になると、もう状況が変わっているということはよくある。 たとえがずれるかもしれないが、人間、長生きになったとはいえ、やることのリストをどんどん片付けていくに越したことはない (あるいは、リストを作らないという手もある)。
話を戻すと、家(房子)はとくに中国ではのっぴきならない現実問題である。 日本では結婚するときに持ち家があるかどうかはそれほど問題にならないと思うが、中国では一番の必須条件のようである。 中国のテレビドラマを見ていると、たいていどの家庭、どのカップルも「房子」の有無や購入資金をめぐって引っ越しだの転職だの別れるだのともめて、 それでドラマが出来上がる。現実の状況はもっと厳しそうだ。その苦労して所有した「房子」もやがて子供が独立すると、 自分たちは年老いて、建物も老朽化している。このあたりは空き家の増加する日本の問題にもなるだろう。
ウィリーの隣人で会社を経営するチャーリーも、中国、アメリカに限らず身近にいそうな象徴的な成功者である。 ウィリーは個別訪問でセールスマンの名を上げる夢を捨てられない上、足りない給料を補うため毎週チャーリーのところへ週給を借りに来る。 人間関係より効率優先のビジネスマンであるチャーリーは「いつ大人になるんだ」と諭しながらも、ウィリーに情けをかけずにはいられない。 燃え尽きたりリストラされたりした会社員が自殺するのも、世界中どこにでも見られる結末かもしれない。 どことなくしんみりとわが身のことも考えてしまう舞台だった。
2012年の再演では丁志誠がウィリー役だった。私は丁志誠の隠れファンなので(別に隠れなくてもいいが)、 丁志誠出演の舞台を報道で知るばかりなのはいつももどかしい。いつか生の舞台に駆けつけたいものである。
[2017.2.21 榊原真理子]
江華島へ行く
2015年の第7回訳学書学会は8月初旬に韓国・ソウルの成均館大学校で開催され、僕も参加してきた。自分の中で、 このところ『老朴』を始めとする朝鮮訳学書の研究は一段落といった感じで、清代の満漢対訳文献の研究に注力しているのだが、 最近は韓国の清学(満洲語学)研究がとても盛んなので、そのフォローという意味合いもある。 期待にたがわず、韓国では今猛烈な勢いで満洲学が進んでいることを実感する機会となり、 その中でたまに自分の研究が引用されたりするのも嬉しいものだ。二日目の夜には比較的若手の人たちと連れだって、 久々にタッカンマリ(鶏の丸ごと一羽鍋)を食べに行った。 夏の夜、屋外でチャミスル(韓国焼酎)を片手に大汗かきつつ食べるこの鍋は本当に最高である。
帰国は翌日だったが、夜の便なので夕方まで時間がある。そこで、東京外大大学院・ソウル大大学院を経て現在は京都産大の専任となっている杉山豊氏に、 どこか半日ぐらいで観光できるところはないですかねえ…と相談してみると、江華島(カンファド)はどうでしょうか、 という話になった。それはいい、高麗王朝の高宗32年(1245)、モンゴル軍の侵攻に抵抗するため、開城から遷都された江華島は、 金文京先生主宰の『朴通事』読書会でもたびたび出てきた地名で、いつか行ってみたいと思っていたのである。
杉山さんとその話をしていた時に、私もご一緒していいでしょうか、と遠慮がちに言ってきたのが東京外大博士課程の高橋春人さん。 この人は伊藤英人先生のもと学生で、今回の学会では『老朴』の清代改訂本に墨筆で付された声点について発表されていた。 博士論文のテーマは中期朝鮮語の文法だそうだが、早大の古屋昭弘先生の授業も聴講しているらしいし、 東京外大ではサンスクリットの授業が一番楽しいという。伊藤先生はすでに東京外大を離れているが、杉山さんしかり、 どうして伊藤門下はこんなすごい人ばかり出るのだろう。
さらに杉山さんから、今回は私の友達も一緒に連れて行きたいのですが…という話。そりゃもちろん、どうぞどうぞ、 ということで翌日待ち合わせの場所に行ってみると、その友達というのは女性だった。ふーん、なるほどね。
江華島へはソウルからバスで1時間半ほど、遠浅の黄色い海が延々と続く景色を見ながら行く。 朝鮮半島の西側はずっとこうなのだそうで、「黄海」の意味を実感する。高橋さんは途中、 トイレに行きたくなったので次のバスで追いかけます、と途中下車。こういったことが可能な語学力がうらやましい。
江華島のバスターミナルに降りた後、皆でタクシーに乗り禅源寺(ソンウォンサ)址に行った。 ここは、国難の克服を願って開版され、高宗38年(1251)に完成した『高麗版大蔵経』が一時保管された場所として知られている。 版木はその後慶尚南道の海印寺に運ばれ、現在世界遺産となっているが、中国語学を専攻する者にとっては、 むしろその蔵外補版として作られた『祖堂集』の方が重要だろう。僕自身は扱ったことがないが、 文献に関する記述研究のお手本としての太田辰夫「『祖堂集』語法概説」(1988年、『中国語史通考』所収)や、 語彙語法史における『祖堂集』が音韻史における『切韻』と同等の重みを持つことを説いた 梅祖麟「唐代、宋代共同語的語法和現代方言的語法」(1994年)など、影響を受けた論文は数多い。

下から見上げた遺跡

上から見下ろした遺跡
現在の禅源寺跡は1976年に東国大学校の調査団によって発見されたものだそうだが、敷地面積は意外と小さくて、 遺跡が現在の場所なのかどうかについては文献史学の側からの異論もあるようだ。遺構の復元途中なのか、 作業員の人たちが車座になってご飯を食べていたりしたが、方々に瓦の破片が無造作に積んであって、 まるで「お土産にお一つどうぞ」と言わんばかり。えーと、これって確か800年前の遺産ですよね…。

所々に積まれた瓦
皆であれこれ確認しつつ遺跡の中を歩き回っていると、時折遠くから演歌のような音楽が聞こえてくる。 この時期はちょうど近くで「蓮の花祭り」というのをやっているのだそうだ。ちょうどいい、 じゃあそこでお昼を食べましょうということになり、歩いて行ってみると、中央に仮設のステージがあり、 周りのテントでは町内会のおばちゃんみたいな人たちが料理を作っていて、何だか日本の地域のお祭りのような雰囲気である。 蓮マッコリというので乾杯し、蓮チジミや蓮冷麺など、何だかやたらと蓮が入っている料理を買って食べる。 中央のステージでは「のど自慢大会」らしきものをやっていて、さっき流れて来た音楽もそれのだったようだが、 一曲終わるたびに司会者が大声で「クンバクス(大きな拍手を)!」と言うのも日本のそれとそっくりで面白かった。

のど自慢大会の様子
その後、高麗宮址などを見に行ってから、いい時間になったので帰りのバスに乗り、 僕だけ鉄道駅で下してもらって仁川空港に向かう。今回の小旅行も楽しかった。いつもながら、 僕は韓国に行くと強烈に郷愁をくすぐられ、ああもっと長くいたいなあ、もっと色んなところに行きたいなあと思う。 訳学書学会で発表できるネタがいつまで続くかわからないが、今後もできる限り参加して、韓国との縁は切らずにおきたいものだ。
ところで、この文を書いているのは江華島への旅から一年ほどたった2016年の8月である。 今年の訳学書学会は横浜の鶴見大学で開催され、杉山さんはすでに中堅といった雰囲気で全体の司会や通訳に大車輪の活躍だった。 それで、ご飯を食べている時に、例の「友達」とはどうなりました?とさりげなく聞いてみると、 ええ、実は今月末に結婚することになりまして…という話。それはよかった。杉山さんおめでとう。
[竹越孝 2016.9.13]
舞台で聞いた中国語19……廃話!(アホ言え!)
いつも演劇に注目しているが、ときどき目先を変えて、お笑いコント(小品)や漫才(相声)、 テレビドラマ(電視劇)なども見ている。演劇と違って、コントや漫才はウェブ上で舞台の録画がたくさん公開されていて 手軽に見ることができ、大変便利だ。
最近は漫才が気に入っている。漫才師(相声演員)を他によく知らない、というのもあるが、 有名な郭徳綱・于謙のコンビがやはりおもしろい。郭徳綱は貫録のある外見ながら、1973年生まれ(天津出身)である。 無名の下積み時代が長かったようだが、今では主宰する徳雲社という漫才社団の人気も高く、 多くの弟子や若手芸人を抱えて漫才活動を展開している。ホームページによると、 徳雲社は北京市内6か所の茶園式劇場を拠点にする他、南京、黒竜江、西安にも劇場がある。 若手が数多く出演する毎日の定期公演は、チケットが20〜120元程度と気軽に足を運べる価格だ。 ただ、大御所の郭徳綱となるとチケットは価格もさることながら、入手自体まず困難のようである。

郭徳綱は漫才(対口相声)と講談(単口相声、評書)どちらもやるが、于謙のツッコミが絶妙なので、 やはり掛合漫才がおもしろい。日本の漫才と同じように、中国もボケとツッコミの役割がはっきりとある。 ただ、中国はボケの方が圧倒的に発話量が多い。滔々と話すボケに対し、微妙な間合いをとらえて合いの手と切り返しを入れ、 ボケを引き立てるのがツッコミの役割のようだ。
つい話を引っ張っていくボケの方を熱心に聞いてしまうが、ツッコミの言葉をよく聞くと、こちらもなかなかおもしろい。 たとえば、「廃話!」「神経病!」「胡説八道!」「甚麼玩意儿!」などである。 こうした中国語の語気はかなり鋭く下町風だと思うのだが、一つずつ直訳すると、「くだらないことを!」「頭がおかしい!」 「でたらめを言っている!」「なんという奴だ!」というやや調子が狂う日本語になってしまう。意訳はまとめて、 「なんでやねん!」「何ぬかしとんねん!」「アホ言え!」「待たんかい!」「どないやねん!」 などといったお決まりのフレーズが相当するだろうか。
他にも、「甚麼乱七八糟的!」(何わけのわからないことを!)、「甚麼毛病!」(それおかしいでしょ!)、 「好好儿説話!」(ちゃんと言いなさい!)、「有完没完!」(いい加減にしろ!)等々、逐一拾っていけばまだまだある。 これらは日常生活の文脈に持ってくるとただの喧嘩になってしまうから、そう使う機会はなさそうだ。が、もちろん相手を見つつだが、 少し不満を表明したいときなどには使えるかもしれないな、とひそかに覚えておこうと考えている。
[2016.4.19 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語18……假如我們都不存在(仮に私たちが存在していないとしたら)
最近は、なかなか中国に行く機会がないことを言い訳に、作品鑑賞を専ら映像に頼ってしまってよくないなあ、と思っているが、 ウェブやDVDで作品が観られるのはやはりありがたい。YouTubeで検索したら、台湾では押しも押されもせぬ有名な演出家 ・頼声川率いる表演工作坊の作品がヒットしたので、今回、その中で比較的新しかった『影の如く』《如影随形》 (台北・国家戯劇院、2008)を観てみた。
頼声川の作風は、序盤、立ち上がりは遅いが、後半からじわじわと盛り上がって、最後には思いもかけず美しくまとまるという 印象がある。『影の如く』は、自分が死んだことに気付いていない幽霊たちと、彼らに調子を合わせてしまう人間たちを描いている。 前半、どうも噛み合わないシーンが長々と続いて退屈だ、と思っていたが、後半から幽霊たちがなぜ幽霊になったのかの経緯が明らかになり、 最後は(以下ネタバレだが)幽霊になった父親に対して自分が死んでしまったことに気付いてほしい、 と言った娘も実は同じ幽霊だと告げられ愕然とする、という結末で幕を閉じる。
何が真実か、何が実体かが明らかになっていくこの舞台を観た後は、思わず自分というものの実体や自分の見ている世界についても 点検したくなる。自分は誰か。相手は何者か。自分は他人の前でひたすら演技をしているかもしれないし、相手もそうかもしれない。 あるいは、自分の想像で都合のいい世界や、逆に居もしないモンスターを作り出したりしていないか。
登場人物たちは皆、架空の世界を生きている。少女は自分が幽霊だと気付かない。彼女が見えてしまう親友は、何も言わず、 生きているときと同じように振る舞う。親友は自分の両親にもぎこちない芝居を続けさせる。少女の母親は、 浮気する夫の気を引こうと自分にも架空の愛人を作り出し、その世界に没頭していた。夫は架空の男の存在を信じ込んで嫉妬に狂い、 自殺してしまった。そして、少女は不安定になった母親の運転する車で出かけ、交通事故に遭ったのだ。皆、 虚構を信じざるを得なかった人たちである。
この中に一人だけ架空の世界に喜々として入り込もうとする人物がいる。自殺を調べる女性警察官だ。 秘かに小説家志望の夢を抱くこの妙な警察官は、登場人物たちの心理に好奇の目を向けてやたらと首を突っ込みつつも、 ふと「假如我們都不存在」(仮に私たちが存在していないとしたら)と皆が戸惑うことを口にする。そのとおり。少女は死んでしまったし、 少女の親友は本当は一人きりだ。親たちはわけのわからない芝居をする必要はなく、少女の母親の愛人は存在せず、 少女の父親が嫉妬した相手もただの想像。
そして、物語が終われば、観客が観ていたこの2時間余りの舞台も、当然ながらまったくの虚構。最後は観客が劇場の外に出て、 現実の世界に戻る番である。でも、現実を見ることは大事だが、たまになら虚構にひたってみるもよしとしたい。
[2015.11.24 榊原真理子]
天津・北京行
2014年は例年になく中国に行く機会が多い年で、3月の訳学書学会(北京)、7月の「元白話と近代漢語」会議(武当山)、 8月の「元白話と西北方言」会議(西寧)と続いたのだが、その締めくくりとして、12月には天津と北京を訪れることになった。 天津の南開大学と北京の中国社会科学院語言研究所で学術報告をすることになったのだ。これは講演というほど大げさなものではなく、 研究者や大学院生を前に行う一回性の講座のようなものである。
中国西南の少数民族語の研究で名高い南開大学の曽暁渝先生は、遠藤光暁先生主宰の研究会などを通じて 昔からよく知っている方なのだが、2013年の夏に杭州・浙江大学であった「韓漢語言学」会議の時に、 今度南開大学の学術交流事業で呼びたいと言われた。聞くと、妻と一緒に来てほしいと言う。本当は古屋昭弘先生(早稲田大学) を呼びたかったが、体調の関係でお断りになられたので…という話。僕と妻がコミだと古屋先生と釣り合いが取れるというのが 何ともリアルで、光栄なことでもあるので謹んでお引き受けすることにした。
それで、その話を社会科学院の祖生利氏にしたところ、ついでにうちにも来てやってくれないかという話になり、 天津からの帰りに僕だけ北京に寄ることになった。社会科学院語言研究所といえば中国における言語研究の中心地、 そこの研究員は学界のスターみたいな人ばかりで、なりゆきで引き受けたはいいものの、とたんに気持ちがズーンと重くなる。 いつもそうなのだが、僕は後先考えずに引き受けてしまってから、事の重大さに気づいて真っ青になるというパターンが実に多い。
出発は冬休みに入った12月23日、今回は娘も同行する。曽先生は娘がごく幼い頃に会っていて、その時に、 うちの娘は姓名ともすべて入声の漢字になるように名前を付けたんですと言ったら、それでこそ中国語学者だと面白がってくれた。 娘はもちろん記憶にないそうだが、曽先生は久々の再会を楽しみにして下さっていた。 天津・南開大学を訪れるのは2003年末に行われたカム・タイ諸語講座に参加して以来で、 考えてみたらその時の模様を書いた「水文字で村おこし」が僕の「いろいろな話」デビューである。
天津での滞在中アテンドして下さったのは曽先生の娘さんである陳暁さん。遠藤先生の監修のもと太田辰夫「清代の北京語について」 (1950年)の中国語訳を詳細な訳注付きで発表し(『語言学論叢』第48輯、2013年)、 最近北京大学で博士号を取った気鋭の研究者である。日本に都合2年留学していたので日本語が非常に流暢で、 日本の研究事情にも詳しい。今回はIT企業に勤めているという旦那さんと一緒に、いろいろ世話を焼いて下さった。
学術報告会は25日の午前なので、前日はその最終準備に費やすつもりだったのだが、 神戸外大の協定校である天津外国語大学に留学中の学生たちと北京ダックを食べに行ったところ、 つい昼からビールなど飲んでしまう。午後からは眠くなってホテルに戻っても舟をこいでいて、 妻と娘は僕の緊張感のなさに呆れていたようだ。

報告は僕が清代満漢合璧資料の全般的な紹介、妻が19世紀の広東語文献に見られる文体差というようなテーマだった。 大体一人50分ぐらいの見当だったが、さすがに身内が隣にいると心強いもので、質疑応答もそれなりに切り抜けることができた。 娘は言葉もわからず退屈だったと思うが、隅の方でずっと冬休みの宿題をやっていた。 曽先生は、この人たちはとにかくいろんな言語ができる、と大げさに褒めて下さるが、当館の吉池・中村両氏や、 日頃付き合いのある遠藤先生・伊藤先生・更科氏などのポリグロットぶりに比べたら、我々なんかお粗末の極みである。 午後に開かれた大学院生との交流会では、ある院生から、自分は手にまつわる語彙の歴史的研究をしているのだが、 日本語の「お勝手」の語源は何か、と聞かれて答えに窮したりしたが、充実した時間を過ごすことができた。

南開大学のシンボル、周恩来像。
今回南開大学で交流した研究者の中では、古代語文法が専門の谷峰氏が印象に残っている。 彼はB. Heine, T. Kuteva著『World Lexicon of Grammaticalization』(2002年)の中国語訳(『語法化的世界詞庫』、 世界図書出版公司、2012年)を出した人で、献呈されたので見てみると、 訳だけではなくて中国語における文法化の例が注釈の形で大幅に追加されている。 原著は中国語の例が貧弱なのが非常に残念で、実は10年ほど前に何人かでその増補版の作成を計画したこともあるのだ。 いい本をもらったので、早速大学院の授業で使ってみようと思う。
翌26日は南開大学の中国語教育の模様を見学させてもらったり、天津市内の観光をしたりして過ごした。 南開大学では見学の後で体育館に連れて行ってもらい、陳さんの旦那さんと卓球の試合をした。 実は、僕は小・中と卓球をやっていたので腕前には少々自信があるのだが、旦那さんは代表チームにいたこともあるほどのレベルで、 そもそも勝負になるはずもなかった。
27日に天津から北京まで送ってもらい、妻と娘はそのまま帰国。僕だけ北京に残って社会科学院での報告に備える。 3月の訳学書学会では北京大学の構内から一歩も出ずにとんぼ返りだったので、今回の北京では、 懐かしさもあって25年ほど前に留学していた中央戯劇学院のそばにホテルを取った。 25年前はただの裏通りに過ぎなかった南鑼鼓巷は、今や北京一のおしゃれスポットということで大変な賑わいになっている。
29日朝、約束の時間に建国門にある社会科学院のビルに行ってみると、祖さんが迎えに来て6階へ。いきなり所長の劉丹青先生、 副所長の張伯江先生に挨拶されて慌ててしまう。旧近代漢語研究室は現在改組されて「歴史言語学二室」になったそうで、 今回はもったいなくも主任の呉福祥先生が司会をして下さるという。他にも、マレーシアで知り合った馮蒸先生(首都師範大学)や、 僕とほぼ同年輩で北京語の研究をしている陳前瑞さん(中国人民大学)も聞きに来られていて、何というか、 緊張を感じるほどの余裕もなかった。

中国社会科学院のビル。
報告は小さめの会議室で1時間ほど。南開大学の時と同じようなテーマではあるのだが、 こちらの方では専門家も多いのでやや突っ込んだ話をした。清代の合璧会話書はほとんどの場合満洲語・ 中国語が対訳の形で並んでいるので、満洲語の訳である中国語の部分は当時の話し言葉そのものというよりは 満洲語の語順に影響されている可能性が高い、同じ言語の接触でも「眼の干渉」と「口の干渉」は区別すべきではないか… というような趣旨だったのだが、祖さんを中心にいろいろ問題提起してもらい、とても勉強になった。 向こうとしても遠来の客ということで手加減してくれたのだろうが、ともかくも無事に終えることができてほっとした。
近くのレストランで昼食をご馳走してもらってお役御免となる。ふと、たぶん留学の時以来となる故宮に行ってみる気になった。 僕が大学に入った年に公開されたベルトリッチの映画『ラスト・エンペラー』は、西洋人から見た東洋趣味だとか、 とかく批判はあるようだが、僕にとってはやはり重要な映画で、これを渋谷の映画館で見ていなかったら 中国を専門とすることはなかっただろうし、北京に留学することもなかっただろう。ようやく緊張から解放されて後は帰るだけだし、 この機会に坂本龍一のサウンド・トラックでも聞きながら故宮を歩き、存分にその世界に浸るのも悪くない…

留学していた中央戯劇学院のある東棉花胡同。
と思ったら月曜日はお休みということで入れなかった。ははは、こんなこともある。気を取り直して故宮の外側を回り、 北にある景山に登る。留学の時には元日にご来光を拝みに来た場所だが、久々に登って上から故宮を眺めると どんな気分になるかと思いきや、口を突いて出たのが1年生の教科書『話す中国語』でおなじみの「整個故宮都能看到!」 というフレーズで、何とも…。

故宮の角楼。
翌30日、安いチケットだったので、朝北京を発った後、上海を経由して夜日本に帰る。とにかく大学と中国語学会の仕事が大変で、 この1年もあまり自分の研究は進まなかったが、最後にこんな満ち足りた気分を味わえたのは、 神様がくれたご褒美ではないかという気もする。よし、来年もがんばろう、うん。
[竹越孝 2015.9.15]
舞台で聞いた中国語17……崔民国,民就是国富民強的民,国就是山河錦繍……的祖国的国。 (崔民国です、民は国富民強の民、国は山河錦繍……の祖国の国。)
李伯男演出の『売れ残り』《剰女郎》(北京人芸小劇場、2008)のDVDを観た。李伯男は若者の生活や感情を素材にした 等身大の作品を作る演出家である。作風は、はっとするような斬新さや鋭さはないが、なんとなく、そうなんだよねえ、 とうなずかせられる共感性がある。今回観た『売れ残り』は「愛情三部曲」という連作の一作目で、ある男女の出会いを描いている。 二、三作目(『ほどよい男と結婚する』《嫁給経済適用男》2009、『隠れ婚男女』《隠婚男女》2010)では、彼らの結婚後が続く。 「連続ドラマ」ということで先が気になり、今回一気に観てしまった。
少々長いが、表題のセリフは、主人公・崔民国がお見合い相手の女性(続編では妻になる)にする自己紹介である。 こう聞くと民国さんもずいぶん立派な由来があるようだ。もちろん「祖国」を修飾する「山河錦繍」(山河が美しい) は明らかに不要で、ここは笑いを取るシーンなのだが、むしろ女性の前で自分をよく見せたくて気負ってしまうがちょっと空回り、 という主人公の素朴さが感じられるセリフである。
中国の人は自己紹介が流暢すぎて(自分の名前なのだから当然だ)、漢字の説明を聞いても、恥ずかしながら、 どんな説明だったのかわかったためしがない。テレビドラマなどを見ていると、字幕の助けで、なるほど、名前はこう説明するのか、 とようやくのみ込める。たいていは日本語と同じで「田んぼの田」のように「〇△的〇」となるようだが、 「さんずいの河」のようにへんやつくりを言う場合もある(たとえば、呉さんは「口天Wu」:Wuは簡体字の呉)。 ネイティブの友人にも説明の仕方を尋ねたことがあるが、響きがよく意味も好ましい単語を使って、「〇△的〇」 と言えばよいということだった。
中国語を話す日本の人も、中国語で自分の名前の漢字をどう説明するか、ふだんから考えて用意しているのだろうか。 自分の名前の発音は中国語の最初の授業で教わるものだが、初級を少し進んだら、 そのうち名前の漢字の説明の仕方も授業のどこかで教われたらいいと思う(そんなもの好きに考えろと言われそうだが)。
話を戻して、気になる崔民国のお見合いの結果はというと、彼はカフェでの支払いの際に所持金が足りなかったために心証を損ない、 二人ともそれぞれまた別のお見合いへと散っていった。だが、二人はその後偶然が重なって再会し、 偶然故障したエレベーターに一緒に閉じ込められ、互いに心を開くようになり、(わかっていたけど)めでたしめでたし、である。 テレビドラマ風の印象を免れ得ない作品だが、エレベーターという閉鎖空間を中から透明な壁やドアを叩く身振りだけで表していたのは、 やはり舞台ならではの演出でよかった。
李伯男の最近の作品はなかなか観る機会がないが、国内各都市だけでなく海外公演も行って好評であるらしい。「継続関注」である。
[2015.7.28 榊原真理子]
再び林兆華作品だが、今回は翻訳劇でなく国内のものをと思い、『説客』(ぜいかく)《説客》(北京人芸首都劇場、2010)を観た。 ストーリーは有名な『史記』仲尼弟子列伝第七、孔子の弟子・子貢(端木賜)の諸国遊説の話である。 脚本は徐瑛による(「春秋三部曲」の完結編だということだ)。いわゆる時代劇だから中国語はかなり難しかった。 そそくさと『史記』と『論語』を予復習した次第である。
孔子の弟子(孔門の十哲)の人物像については言うまでもないかもしれないが、子貢は口達者な商人、 劇中で子貢とともに旅する子路は、情に厚い豪傑だったとして知られている。 ふつう子貢と比較対照される弟子は清貧で称えられた顔回や原憲である。 だが、今回、子路を同行させた脚色がおもしろく(『史記』では子貢の外交に同行者はいない)、 その役を高亜麟が演じていたのも興味深かった。
高亜麟は1972年生まれ、テレビドラマ『家有児女』のフレンドリーな父親役で人気を博したことで、 「国民baba」、「萌ba」(可愛いパパ【ba=父+巴】)などと呼ばれている俳優である。 この数年ですっかりメタボなオッサンになってしまったものの、それがうまく転じた「霊活胖子」(きびきびした太っちょ) 路線がなかなか楽しい。今回も、孔子と対等にやり合うまっすぐで豪快な子路を好演し、 舞台のオアシスとなっていた(ミーハーな余談をもう少し言うと、最近はダイエットに成功し、 さらに役柄の幅を広げているようだ)。
他方、劇中の子貢は打って変わって苦悩する人である(俳優は濮存釬)。子貢は孔子に重用され、如才ない外交官のように 斉、呉、越、晋と交渉をまとめ、見事、攻め滅ぼされそうになっている魯を救う。しかし、 「乱世出英雄,乱世也出大混蛋。我就是個大混蛋」と自責の念に苛まれて、少しも心の安らぎを得られない。 子貢は弁舌やビジネスの才に秀で、懐も豊かだった。が、その多言と富裕さゆえに、孔子の信頼を今一つ得られなかった。 劇中で子貢が「先生が一番好きな弟子は子路、一番親しい弟子は顔回……」とつぶやくとおり、 子貢の長所は孔子の理想主義的な志向とあまり合わなかったと言われている。子貢は孔子の死後も慕い続けるが、 冒頭とラストシーンはどちらも苦悩の独白で、少しせつない。
このような子路の豪快さも子貢の胸の内の苦しみも、ユーモラスな二人の道中も緊迫した交渉の席も、 この作品では、俳優以上にすべて音楽と歌で表現される。音楽劇と呼んでもよいと思う。ふんだんに使われていた伝統的な楽器 (おそらく笙、笛、三弦、太鼓など。舞台の片隅では管楽器奏者の生演奏もあった)による音楽は、 伝統的な邦楽を思わせるような躍動的かつ簡潔な曲調で、劇空間を美しく形作っていた。
一つ苦言を呈すると、途中、呉王夫差の側室・西施役の女優が独唱するシーンは歌唱力が今一つで、ずっこけそうになった。 謎のシーンである。
[2015.6.30 榊原真理子]
青海再訪
次に彼らと会うのはいつになるだろうか…と思っていたら、3週間後にはまた会ってしまった。というのはウソで、 もちろんまた会うことは知っていたわけですが。

今回は8月14日から16日まで青海省・西寧の青海民族大学で開催された「元白話与西北漢語方言国際学術研討会」で、 中国社会科学院と青海民族大学の共催。西寧は2005年夏に海南チベット族自治州の共和県(チャプチャ)で方言調査をした時、 行き帰りに立ち寄った所である(その時の記事はこちら)
武当山での学会の直後と言っていい時期だったし、テーマも似通っているので、連絡をもらった時点では参加をためらっていたのだが、 「元白話」つまり「漢児言語」的な現象を主題とする国際学会が開かれること自体めったにないわけだし、 前々から関心のあった中国語西北方言にも触れられるということで、参加してみることにした。
出ると決めた以上は発表をしなければならない。中国語学会では事務局の他に大会運営委員会の仕事もしていて、 一年で最も忙しい時期に論文提出の締切が重なったため、本当にヘトヘトの状態だったが、前回の発表の一部を発展させる形で なんとか書き上げることができた。やれやれどうにか間に合った…と思って提出したら、折り返し開催日を一週間後に変更しますという通知が来る。 うむむ、もう飛行機のチケットを買っているのに、一体キャンセル料はどうしてくれるのだ。
まあこの業界ではよくあることなので、怒っていてもしょうがない。お盆ということで妻と娘が実家に帰省するのを見送ったあと、 うだるような暑さの日本から出られたことにホッとしつつ、北京経由で夜の西寧空港に降り立ってみると…
寒い!たかをくくって半袖しか持って行かなかったのは完璧に甘かった。聞けば、内陸部の夏は寒暖差が激しく、 昼は30度以上にもなるのに、朝晩は10度ぐらいまで冷え込むのだそうだ。2005年にも同じような経験をしていたはずなのに、 すっかり忘れていた。出迎えの人と落ち合って、空港から同乗するもう一人の先生が来るのを車の中で待っている間、 ずっとガタガタ震え通しだった。

西寧の市街地から。遠くにストゥーパ(仏塔)が見える。
翌朝も寒かった。9時には学会が始まるので、服を買いに出かけている余裕はない。 仕方なく会場に着くなり体を温めるためにお茶をガブガブ飲んでいると、僕があまりにミゼラブルな表情をしていたためか、 青海民族大学の大学院生がジャケットを貸してくれた。ありがたく拝借することにして、以後学会の期間中はずっと着ていることになった。 中国の学会ではお決まりの集合写真でも、僕はそのジャケット姿で写っている。

青海民族大学の正門。チベット語・中国語・モンゴル語の三体で記されている。
もっといっぱいいると思っていたのだが、参加した外国人は僕一人だったらしい。主催者の一人から、 あなたのおかげで「国際」会議になったと感謝され、何だかトホホな気分になる。全体として西北方言の専門家が多いようだったが、 武当山の学会に参加していた中では、社会科学院の祖生利、楊永龍両氏、復旦大学の梁銀峰氏、蘭州大学の敏春芳氏らが来ていた。 社会科学院からは方言研究室の李藍、沈明両氏も来られていて(今回の学会はむしろ方言研究室の企画だったようだ)、 君は確か『太田・古屋論集』の関係者だよねと言われ、お二人とも執筆者だったことを思いだした。
僕は元白話と西北方言を比較して云々するほどの蓄積がないので、『元朝秘史』関連の内容でお茶を濁したのだが、 議論自体は西北方言が中心だった。文法関係では、
阿哥是怕人的人不是是。(兄さんは人を恐れる人ではないのだ)
という、思わずのけぞりそうな「漢児言語」的例文がいくつも挙がっていて、とても興味深い。そうした発表を聞きながら、 むしろ朝鮮資料の性格を分析する上でヒントになりそうなアイディアが浮かんだのは収獲だった。
他にもへえーっと思うような発表は多かったのだが、特に社会科学院の人たちは、 個別的な事象のみを取り上げてすぐに類型論的(というよりは「言語類型地理論的」というべきか)な議論に持っていくのではなく、 まずその方言体系の中に位置づけて解釈すべきだ、というコメントを繰り返し述べていて、その点は大いに共感できた。 やはり研究がお国自慢のようになってはいけないのだ。

大学の前の通り。オアシス都市の雰囲気が感じられる。
二日間の充実した学会を終えると、せっかく来たのだから翌日は青海湖見学のツアーに行くという人もいたし、 これから方言調査に行くという人もいた。僕は翌々日に市民講座の予定が入っていて、早々に帰国しなければならなかったのは残念だ。 考えてみたら前回の方言調査からもう10年にもなるのだから、来年あたり共和県を再訪してみるのもいいかもしれない。 今度来る時は長袖を忘れないようにしなければ。
[竹越孝 2015.4.22]
舞台で聞いた中国語15……あしたになれば、万事うまくいくよ*(到明天一切都会好些的)
21作品を収録した林兆華演出作品集のDVDをなかなか観終わらないため、昨年からずっと林兆華とのお付き合いが続いている。 林兆華は現役とはいえ、1936年生まれで現在もう80近い高齢だ。だが、「最新消息」によると、 昨年末にイプセンの『人民の敵』を演出したとのこと。ちっとも年齢を感じさせない快走ぶりで、 百歳を超えても変わらず仕事をしているだろうという気がする。
今回観たのは『三人姉妹・ゴドーを待ちながら』《三姉妹・等待戈多》(北京人芸首都劇場、1998)という、あえて言ってしまえば、 ややとっちらかった作品である。その名のとおり、チェーホフ作『三人姉妹』とベケット作『ゴドーを待ちながら』を組み合わせて脚色したものだが、 その方法は2作品を細かいパーツに切り分け、取捨選択し、それらを交互に縫い合わせて1枚のパッチワークに仕上げるという力技である。 率直に言うと、ちぐはぐな印象でもう少しなんとかならなかったのかという感じではある。興行成績も著名な林兆華の作品にしては大失敗作だった。 林独自の不条理劇として、これはこれでおもしろい世界が広がっているのだが、やはり観客に打てば響くような反応はなかなか求め難かったようだ。
『ゴドーを待ちながら』は20世紀の演劇に大きな影響を与えた不条理劇である。不条理劇では、対話、時系列、 ストーリーの文脈などが非連続でつじつまが合わないままにある状況がただ描かれる。ただ、 それは「不条理」という日本語の語感から来るような哲学的で難解なものではない。不条理劇作家としてベケットと並んで有名なイヨネスコは、 そもそも英会話の教則本に出てくる「1週間は7日間です」「床は私達の下にあります」「田舎は都会よりも静かです」「そうですね。 でも都会は田舎よりも人口が多いし商店も多いです」といった自明の真理の対話のばかばかしさ(absurd, 不条理)に開眼し、 そのノリで戯曲を書いたらどうなるか、というこれまたナンセンスなチャレンジをとりあえずやり遂げてみたところから出発している。 別役実が、不条理劇ではなく「しっちゃかめっちゃか劇」**と呼べばわかりやすい、と提案しているのもうなずける話である。
『ゴドーを待ちながら』のあらすじも、神もどきのゴドーという謎の人物を虚しく待ち続ける二人の男、 という暗いイメージが知られていると思うが、脚本を改めて読んでみると、くすっと笑えるところも多い肩肘の張らない作品だ。
そのなかで何気なく口にされる「あしたになれば、万事うまくいくよ」(到明天一切都会好些的)とは、 自分の生活にも重なるものがある。『ゴドーを待ちながら』は1953年にパリで初演された。そして、21世紀に日本にいる私の生活にも、 なんとなく何かを待ってしまう時間が時々ある。「もう行こう」「だめだよ」「なぜさ?」「ゴドーを待つんだ」といったセリフが有名だが、 ほかの何気ないセリフにも含蓄がある。待っているものが必ず来るとはわからないし、万事うまくいくかどうかはもっとわからないが、 明日になれば、という仕切り直しの気持ちはきっと誰にもあるのではないだろうか。
* 『ゴドーを待ちながら』のセリフは、安堂信也・高橋康也訳『ゴドーを待ちながら』(ベスト・オブ・ベケット1、白水社、1990)に依った。
** 別役実『うらよみ演劇用語辞典』小学館、2003、52頁。
[2015.3.24 榊原真理子]
武当山での学会
昨年の7月22日から26日まで、中国・湖北省で開催された「元白話与近代漢語研究国際学術研討会」に参加してきた。 中国社会科学院語言研究所と湖北大学文学院共催の国際会議で、2010年6月の「“《老乞大》《朴通事》的語言”国際学術研討会」 を引き継ぐ催しである。日本からの参加者は、遠藤光暁先生(青山学院大学)、舩田善之さん(九州大学)と僕の三人。 前回出席されたペイローブ(A. Peyraube, 貝羅貝)先生や、最近中国語西北方言を手掛けているというジャムリ(R. Djamouri, 羅端) 先生も参加予定と聞いていたが、いずれも予定が合わずお会いできなかったのは残念だった。
今回の会議の開催については、1月後半に社会科学院の祖生利氏から主だった研究者に連絡があったそうで、 当初僕はそれを遠藤先生から聞いて、何だよ、僕には来ないのかよ…などと若干スネていたのだが、 単に誤って前の勤務先のアドレスに連絡が行っていたということらしかった。論文の提出は6月末とのことで、 参加と回答した時点ではまだ余裕があったのだが、その後4月から日本中国語学会の事務局を担当することになってものすごく忙しくなり、 加えて昨年から続いている『元明漢語文献目録』の編纂作業もいよいよ大詰めにかかっていたので、青息吐息の状態ではあったが、 なんとか1本でっち上げて行くことになった。
上海や北京経由の便が取れなかったので、7月22日の夜に香港経由で武漢に入る。さすがに中国三大カマドの一つ、 夜といっても暑さは半端なものではなく、クーラーなしではとても眠れなかった。 翌日は午前中に湖北大学のキャンパスで開幕式と遠藤先生らによる基調報告があり、昼食後に皆で武当山のホテルに移動して、 次の日ホテルの会議室を借りて残りの発表を行うということだった。武当山は河南省との境界にほど近く、武漢からバスで半日かかる。 標高が高いため、この季節でも快適に過ごすことができた。

前回と同じく、今回も会議の規模は小さかったが中身は濃かった。風光明媚な場所でテーマと人数を絞り集中的に討論するというのは いいアイディアだと思う。全体として勉強になる発表が多かったが、特に驚いたのは最近中国の学界でも結構な「満洲語熱」 があるということだった。祖生利氏の発表は清代の北京語に特徴的な「来着」の起源に関係するものだったし、 同じく社会科学院の若手陳丹丹氏も満漢資料を用いた発表をしていた。自分で出したことすら忘れかけていた 『清代満洲語文法書三種』(『KOTONOHA』単刊No.1, 2007年)が引かれたりしていて、舩田さんから、 竹越さんは先見の明がありますねえ…などと感心される。聞くところでは、北京語の歴史を扱った研究プロジェクトも すでにいくつか動き出しているらしい。
もちろん、アヘン戦争(1840年)以降を「現代」と称し、それ以後の中国語には基本的に変化がないものと長年捉えられてきた 中国の学界に比べて、1950年代から清代・民国期の中国語に関心を寄せてきた日本の学界の方にアドバンテージがあるのは当然で、 こういった場で日本の研究者である我々が多少とも丁重に扱われるのは、全くもって先達のおかげである。 遠藤先生と僕が主編となって出した『清代民国漢語文献目録』(ソウル:学古房、2011年)は出版直後に社会科学院に送ったので、 その影響もあるのかも知れない。ようやく日本の研究に光が当たるようになってきたのは喜ばしいことだが、 追いかけてくる中国の研究にも相当な勢いを感じる。
武当山の道観。この後山頂までロープウェイと徒歩で登った。


山頂付近から見た景色。


帰りに立ち寄った湖。武術映画のセットとして使われたらしい。


会議が終わった翌日はエクスカーションで、著名な道観(道教寺院)群を有し、中国武術の聖地でもある世界遺産・武当山の観光を皆で楽しんだ。 学会よりも観光がメインで、一体何しに来てるんだか…的な国際会議も多いと聞くが、 学問の方が充実していればエクスカーションも楽しめるものだし、何より良い情報交換の機会になる。 舩田さんは社会科学院(歴史研究所の方ということだが)に留学経験があるので、社会科学院出身の研究者達と旧知で、 その関係もあって人見知りの僕も今回は彼らとよく話した。彼らは例外なく議論好きでアグレッシブだから、こちらもへとへとに疲れる。 そこで、ちょっと喉渇いてない?などと舩田さんを誘い、改めてビールを飲みに出かけたりするわけである。
こうしたところで育んだ縁を大切にして、いつまでも国境を越えて互いに切磋琢磨していければと思う。 次に彼らと会うのはいつになるだろうか。
[竹越孝 2015.3.24]
舞台で聞いた中国語14……起来! 不願做奴隷的人們!(起て! 奴隷となることを望まぬ人びとよ!)*
ご存知、中国の国歌の冒頭である。日本の国歌「君が代」がスローテンポで神妙な雰囲気を漂わせているのに対し、 中国の国歌は「義勇軍進行曲」というだけあって、しゃきっと勇ましく生命力がみなぎっている。 中国にはこのような戦時下の人心を鼓舞する歌がごまんとあると思うが、そうした文脈から切り離して聴く分には、 単純明快な長調のものが多く、存外音楽として楽しめる。
私が初めて生の中国国歌斉唱を聴いたのは、小劇場の舞台の劇中においてだった。『もし、ぼくがぼくでなかったら』 (《如果,我不是我》周申・劉露演出、東方先鋒劇場、2012年)というコメディ作品である。ストーリーは、親の意向に組み敷かれつつも、 自分の選んだ仕事や恋愛を貫こうと試行錯誤する若者のドタバタで、残念ながら作品自体にそれほど新鮮味はない。 だが、シリアスな場面とコミカルな場面のメリハリがよかったのと、客席を舞台の延長として劇中に取り込む演出方法がうまかったのとで、 なぜか引き込まれる、後味も爽やかな上演だった。劇中、主人公のカップルが小学校時代を回想し、 学校行事での国旗掲揚を再現するというシーンがあったが、そこで小学生になりきった俳優が、 伴奏なしの独唱で声を張り上げ国歌を歌い上げていた。
客席でもどこからともなく手拍子や合唱する声が聞こえてきたりと、観客は観客でこの劇中の学校行事に子供時代の自分を 探し当てていたようだった。こういうとき、自分は明らかに異文化に属していると感じ、歓声や拍手にも乗り遅れて焦ってしまうのだが、 そうした客席の反応や雰囲気が直に見えるところも観劇の良さである。
中国の演劇やテレビドラマを見ていると、たいていはコメディ作品においてお笑い風にという演出ではあるが、このように折にふれて、 四字成語が口に上るかのごとく人口に膾炙した歌がふと歌われることが多いように思う。たとえば、「団結就是力量」(団結こそ力)。 やはり元来、戦時下での発揚の歌だったようだが、今日では、仲間で力を合わせ他社よりもいい仕事をしよう、 などというシチュエーションでよく歌われていて、場が盛り上がっておもしろい。こうした歌を注意深く聴いていくと、 革命歌や人気歌手の流行歌のほかに童謡も案外多い。童謡はアクセスしやすい異文化の入り口であるから、YouTubeで「儿歌」(童謡) をあれこれ検索してみるのも楽しい。「小星星」(きらきら星)や「大象」(ぞうさん)など日本でもお馴染みの歌も中国語で聴くと なかなか新鮮である。
さて、中国の国歌を歌う際に忘れてはならないのは、やはりなんといっても前奏部も「パ」で力強く歌うことだろう (もちろん伴奏なしのときに限るが)。前奏部はそもそもこの曲の主題であるし、あの高らかに響くトランペットの音色は、 やはり「なんちゃって」でも欠かすのは忍びないものである。
* 出典:ウィキペディア
[2014.10.29 榊原真理子]
蟹の鋏
今年の春休みに家族でアメリカの西海岸に行く機会があった。サンフランシスコとロサンゼルスをめぐる格安のツアーである。 娘もだんだん大きくなってきて、いつまでも3人で旅行ができるとは限らないから、ということで急遽決めた旅だった。

サンフランシスコの最終日に、フィッシャーマンズ・ワーフのレストランで名物の蟹を食べるというナイトツアーがあって、 3人とも特に蟹が好きだという訳でもないのだが参加してみることにした。ダンジネス・クラブという大ぶりのワタリガニのような蟹で、 一匹ずつ皿に乗ってうやうやしく運ばれてくる。テーブルにはクルミ割りのようなクラッシャーが置いてあって、 これで殻を割って食べるのだという。
蟹を食べるのは本当に久しぶりだった。一人一匹というのも嬉しく、僕は存分に堪能してきれいに食べてしまったが、 妻と娘はそもそも食べ慣れていないためか、食事の間ずっと悪戦苦闘している感じだった。特に蟹の鋏の部分は殻がだいぶ硬い上に、 他の脚に比べて身が取り出しにくいので、ほとんど食べずに残してしまっている。
何だもったいない、と言って鋏の部分を引き取り、あらかた身を取り出した後で、ふと蟹の鋏を動かしてみる気になった。 鋏の部分は身がすっかりなくなると透明な腱のようなものが残るのだが、それを押したり引いたりすると、蟹の鋏が閉じたり開いたりするのだ。
妻と娘はそんなことは全く知らなかったようで、すごい、さすが海育ち!などとしきりに感心している。 そんな驚くような大した芸当じゃない、と言いながらヒョコヒョコと蟹の鋏を動かしているうちに、不意に涙がこぼれ落ちそうになった。
僕は青森県の日本海側にある小さな漁師町で育った。父も漁師で、ずっと共同経営の小さなトロール船に乗っていた。 季節ごとに獲れる魚は違っていて、父はいつも出荷用にならなかった魚を家に持ち帰り、それが食卓に上ることになるのだが、 冬になるとたまに毛ガニを持ち帰る時があり、それは僕たちにとって何よりのご馳走だった。
我が家では毛ガニは夕飯のおかずではなく、食事が終わり風呂に入った後、寝る前に食べるものだった。 真っ赤に茹で上がった毛ガニが出てくると、居間に新聞紙を広げて皆で車座になり、真中に殻入れのボールを置く。 もちろん殻を割ったり身を取り出したりする道具はないから、取り分けてもらった脚を歯でバキバキと割りながら、 僕は一つ年上の次兄と争うようにして食べた。そんな時、自らは鋏の部分を取った父がやって見せてくれたのが、この芸当だった。
父は3年前の冬に亡くなった。その年の秋に入院先の秋田の病院を見舞った時、頑丈で大きかった父の体はすっかり痩せ細っていた。 病院は海に面していて、外では暗い日本海が荒々しい波を立てていたが、きつい消毒薬の匂いがする父の病室の窓からは、 海ではなく鉛色の空と隣の病棟が見えるだけだった。
父は上半身を起こして話をすることもできたが、リクライニング式のベッドなので体が自然とずり下がってしまい、 時折もとの位置に戻してやる必要がある。しかし、父の体は思いのほか重くて僕一人では引っ張り上げることができず、 結局後で来た長兄の手を借りなければならなかった。父は僕に、青森を離れて何年になる、と尋ね、大学の教師というのはずいぶん力がない、 とかすれた声で言った。後で母は、このところずっと点滴をしているのだが、すでに栄養分が吸収されずに 下半身にたまっているから重いのだと教えてくれた。
父が危篤の状態に陥ったという知らせを受けたのは12月のある夕方で、その日のうちに発つことはできず、 翌朝の飛行機で行くことになった。秋田の空港に降り立って携帯電話の電源をつけると、すでに着信が何件も入っていて、 飛行機に乗っている間に何があったのか想像がついた。父は慣れ親しんだ故郷の海を再び見ることなく、永遠の眠りについたそうだ。
サンフランシスコで過ごす最後の夜、指先にかすかに残る蟹の匂いを感じながら、僕はベッドの中で父のことを思った。 通夜でも葬式でも、僕はひたすら呆然とするばかりで、一滴の涙をも流すことはなかったし、 正直に言えば死者を弔うという気持ちさえ生じることがなかった。3年経ってようやく、 自分の中で父を失ったことが実感として受け止められるようになったのだろう。
[竹越孝 2014.9.23]
舞台で聞いた中国語13……為祖国健康工作五十年(祖国のため50年健康に働こう)
舞台を観る楽しみとはもちろん本編の上演にあるが、終演後の俳優や関係者たちのカーテンコール(謝幕)も、 実は見どころの一つとして欠かせない。私がこれまでに観たなかでもっとも見応えのあったものは、『老いる前に遠いところへ』 (《在変老之前遠去》邵沢輝演出、東方先鋒劇場、2012年)の終演後のミニコンサートである。
ふつう、もっともよくあるカーテンコールといえば、キャストが全員出て来てお辞儀をしてしめやかに終わるものだ。 次に多いのが、俳優に加え、演出家や脚本家などもいそいそと出て来て、キャスト紹介、解説、宣伝などを述べるタイプ。 もう少し本格的にアフタートーク(座談会)が催されることもある。そして、どうやら私の観てきたものは少々特殊だったようだが、 中国ではときおり歌を歌うものに出くわす。私が観た『老いる前に遠いところへ』のカーテンコールは、 その大サービス拡大版とでもいうべきものだった。
終演後、どういう意図なのか、「本番はこれからです」(我們的演出正式開始)と冗談交じりにギターの演奏が始まり、 俳優二人による歌と演奏で計5曲が30分かけて披露された。そのうち1曲は、なぜかさだまさしの「関白宣言」中国語版。 さだまさしの次に披露されたのはこれまたなぜか「清華大学校歌」だったが、それを歌う俳優、そして観客の反応がとても興味深く、 かつ清々しかった。
清華大学には「為祖国健康工作五十年」*というスローガンがあるらしいが、彼らはそれを完全にジョークにした替え歌を歌った挙句、 最後は「為祖国健康工作五百年」と締め括り、観客席を大いに沸かせた。皆、本編の上演より盛り上がっていた。笑いのツボは、 「祖国」とか「何年」とかいうところだろうか。これはやはり中国ならではのユーモアだ。日本では「祖国」よりも「会社」とか「年金」、 「メタボ解消」あたりならば、ピンとくるかもしれない。
といっても、実は私にとっては、異国の地で聴く中国語のさだまさしと、それに大爆笑していた中国の人々の方がずっと印象深かった。 「亭主関白」(男子漢主義)ということばは日本でもすでに死語になったと思うが、女性がパワフルな中国で聞くと、 まるで新鮮なお笑いのようで久しぶりに腹の皮がよじれた。歌い始める前に、「日本では結婚式でこの歌が必ず歌われるそうです」 と紹介されたのには、さすがに異論があったが。
蛇足を少し。『老いる前に遠いところへ』は、ある日突然都会から雲南へ赴き、しばらくそこで教師をした後に事故死した青年の ドキュメンタリー。映像を多用した静かな作品である。
* 1957年の当時の学長蒋南翔の演説に由来するが、清華大学にかぎらず、「健康工作五十年」という文句は一般的に言われているようである。 参照:http://www.edu.cn/html/e/tsinghua/sport
[2014.8.19 榊原真理子]
マレーシア行
昨年の6月、学会関係の会議で東京に行った折にある人から、マレーシアに行く気はありませんか?と言われた。 聞くと、10月にマレーシアで学会があり、経費は主催者持ちなのだが、自分は都合で行けないのだと言う。 せっかくただで招待してくれるのに日本から誰も行かないのは申し訳ないので…という話だった。
ただほど安いものはない。僕は根っからのお調子者で、うまい話があると後先考えずに飛びつく性質なのだが、 あまりにがっつくのも恥ずかしいので、いやいや僕なんかより○○先生とか△△さんの方が…などと一応言ってみると、 その辺は全部断られたのだそうだ。おそらく僕に回って来たのは15番目ぐらいだろう。それなら行きます! ということで関係のメールを転送してもらう運びとなった。
転送してもらったメールによると、10月の5日と6日に、マレーシア・クアラルンプールのマラヤ大学が中文系の設立50周年を記念して 「中国語言文字国際学術研討会」なる国際学会を開くのだそうで、確かに飛行機代と宿泊費は持つと書いてあったが、 それよりも目を引いたのがエクスカーションでマラッカに行けるということだった。マラッカといえば丙種本『華夷訳語』の 「満剌加国訳語」である。生涯の目標として「『華夷訳語』ゆかりの地全踏破!」を掲げる僕としては、この機会を逃すわけにはいかない。 発表論文は7月中に出すように、ということでスケジュール的にはものすごくきつかったが、何とかひねり出して行くことになった。
日本から約6時間のフライトでクアラルンプール国際空港に着くと、出口ではプラカードを持った学生さんが待ってくれていて、 タクシーでホテルに向かう(さすが招待)。学生さんはいずれも華人系で中国語が流暢だった。誰かが、マレーシアの四季は 「熱、更熱、湿、更湿」なのだと言っていたが、確かにそんな感じで、一歩外に出るとむっとした東南アジア的熱気に包まれる。

マラヤ大学の正門

学会会場の入口
マラヤ大学はマレーシアの最高学府で、50年の伝統を誇る中文系はマレーシアの華人社会で一貫して指導的な役割を担ってきた教育研究機関だという。 後で聞いたら、金文京先生(京都大学)が木魚書のコレクションを目にして研究を始めるきっかけになったのもこの大学だそうである。 学会は非常に盛大なもので、大物中の大物である唐作藩先生などは今回初めて実物を見ることができた。北京大学を退休後、 しばらくマラヤ大学で客員教授を勤められていた縁から招待されていたらしい。
僕自身の発表は二日目の最後のセッションに割り当てられていて、しかも戴浩一(国立中正大学)、 鞢伯慧(曁南大学)両教授に挟まれるという恐ろしいプログラムだった。マラヤ大学の学生も含め300人ほどいた聴衆は、 二人の大物の間になぜこんな小物が混じっているのかと終始「?」を頭に浮かべている感じだったが、まあ僕のせいではないので許してもらおう。 幸いにというか情けないことにというか、特に質問は出なかった。

マラッカで乗った水上バスから
学会が無事終わった翌日、チャーターしたバスに乗って約3時間の道のりでマラッカに行った。 中心部の小高い丘の上にあるセント・ポール教会跡にはフランシスコ・ザビエルの像が建っていて、 その日本への遥かな道のりを思うとやはり胸が熱くなる。この丘から眺める夕日は絶景中の絶景だそうで、 沢木耕太郎の『深夜特急』でも、マラッカ海峡に沈む夕日を眺めるためにわざわざマラッカに立ち寄ったことが記されているが、 今回は日帰りだからそれはかなわなかった。自由時間ではチャイナタウンを散策し、「世界ふれあい街歩き」的な気分を存分に味わった。

フランシスコ・ザビエル像
今回学会に参加した研究者の中では、馮蒸氏(首都師範大学)、李無未氏(厦門大学)、胡明光氏(ベトナム・人文社会科学大学) などとの交流が特に印象に残っている。馮氏は「華夷訳語文献目録」(『語学教育フォーラム』第13号、2007年)の共同編者なのだが、 今回初めてお目にかかることができた。李氏とはマラッカへの行き帰りのバスでずっと隣りに座って話していたが、 日本に1年滞在したことがあるとかで日本の研究状況にとても詳しく(著書に『日本漢語音韻学史』商務印書館、2011年がある)、 出しぬけに君は確か許衡(1209-1281)の専門家でしょう、言われて驚いたりした。
滞在最終日は深夜発の飛行機だったので、朝から中華街(唐人街)を歩いたり、かつて世界一高いビルとして知られていたツインタワーを 下から眺めたり、その近くにある水族館を覗いたりして過ごした。あたりまえだが、クアラルンプールはアジア有数の大都市で、 オフィス街の雰囲気や交通のインフラなどは東京にいるのとそう変わらない感じである。ただ、 そんな中でも中華街のエリアだけには濃厚な中国的猥雑さが横溢していて、そこに行くとなぜだかとてもほっとする。

クアラルンプールの中華街入口

中華街のそばにあるヒンドゥー教寺院
僕はアジアの中でも北方に興味が偏っていて、東南アジアにはこれまで積極的に足を向けることがなかったのだが、 今回のマレーシア行でまたしても食わず嫌いを反省した次第である。東南アジア方面からの招待お待ちしています。
[竹越孝 2014.7.13]
舞台で聞いた中国語12……gan ma ne?(何だよ?)
昨年、北京を訪れた際、人気の孟京輝演出の公演をタイミングよく観に行くことができた。 『南京虫』(《臭虫》、マヤコフスキー原作、蜂巣劇場)、2000年の作品を改編したリバイバルである。
この作品の印象的なセリフは何だろうと考えてみると、「毎個人都想上天堂」(誰もが皆天国に行きたい)とか 「雖然共産主義離我們很遠,但是它在」(共産主義はわれわれから遠く離れているが、でもあるのだ) とかいったものがなんとなく思い浮かぶが、孟が重視する「北方民族的人与人之間的速度和質感」 (北方民族の人と人との間にあるテンポと感触)を考えるならば、それよりも、gan ma? やzeme zhao!? (ここはあえて、zenme ではない) などをやはり挙げたくなる。
gan maはカジュアルな口語として、日常会話で使用頻度が断然多い表現の一つだろう。用途が広く、 このフレーズ一つで「どこ」や「何」や「なぜ」を問う表現になるところが何より便利である。ni zai gan ma ne? (何をしてるの)、 ni xiang gan ma?! (何するんだ――やや喧嘩腰の語気)などのほか、動詞を付けてni gan ma qu le? (どこに(何しに)行ってたの)、 ai gan ma gan ma. (したいことをする)というのもよく聞く。zao gan ma qu le? (何をやっていたんだか、もう手遅れだ)は、 好ましくない状況が起こったとき、言わんこっちゃない、とばかりによく第三者が冷たく言い放つ表現である。 gan ma はカジュアルな度合いが強いから目上の人に対しては使えないようだが、一旦、ni xiang zuo shenme? などと置き換えてみると、 語感やリズム感が替え難いものだとわかるように思う。
さて、2013年版『南京虫』は特筆すべき点が三つほどあった。一つ目は、途中で上演が中断され、 俳優と観客がストーリー展開について討論する時間が設けられていたこと。 二つ目は、その討論のなかで出た観客の意見がその場で即興で演じられたこと。 そして三つ目は、最高額の席(日本のSS席に当たる)の観客には、終演後、その舞台への支持と理解に感謝するとして、 チケット代金(380元)がサプライズで返金されたことである(ちなみに、ほかの席は200元、150元、100元、学生50元)。 討論と即興劇は、ライブであるという演劇の特長を大いに活用したものだと言えよう。私が鑑賞した日は、 多く挙手があったなかから選ばれた数人の観客が、百年の冷凍保存から目覚めた主人公の今後について、 「保険に入る」、「ポルノ男優になる」、「火星に行く」などと忌憚のない意見を述べていた。 そして、その意見ですぐに即興の劇中劇が作られたのは見物だった。意見に関わらず結局お笑いコントに堕してしまうこの即興劇には、 辛口のコメントをする劇評もあったが、俳優の技量を存分に味わいたいと思う私には、十分に見応えのある舞台だった。 チケット代金の返金も、初めて見る粋なサービスである。
それにしても、上演中、討論の時間になって観客に向けて挙手発言が求められたとき、 思わず身を固くした私はどう考えても修行が足りないようだ。小劇場はいわば客席も舞台の一部。 「観る」ではなく「参加」なのである。心して足を運ばなければならない。
[2014.6.24 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語11……我還没拉完ne(まだ出てないんだけど)[ne=口+尼]
あまりきれいでない話題で恐縮だが、トイレにまつわるセリフである。それも動詞は「拉」であるから、大の方。 作品は過士行作・林兆華演出の、その名も『トイレ』(《厠所》、北京人民芸術劇院、2002年)である。 今ではもう見られない一昔前の舞台だが、『林兆華戯劇作品集(21DVD)』(中国人民大学出版社、2012年)の録画を鑑賞することができる。
作品は、北京の公衆トイレとその管理人を軸に、そこを行き交う人々と時代の移り変わる様を描いた内容で、 同じトイレが1970年代の汲み取り式便所、80年代の有料水洗トイレ、90年代の高級ホテルの化粧室、と様変わりしていく。 老舎の『茶館』のように、固定した場に集い、また散りゆく人々が対話を繰り広げつつ、時代が3段階変遷するという手法から、 「しゃがむ"茶館"」(蹲着的"茶館")といううたい文句で宣伝された。 主演のトイレの管理人である史(「屎」と同じ発音)爺役は、趙亮。やや小太りの三枚目、という印象だが、 『トイレ』のようなコミカルな役も、凄みのある犯罪者などのシリアスな役もよく似合う実力派である。 活躍は舞台よりも映像の方が多いようだ。
「還没拉完」というセリフは、トイレに入ったあとすぐに邪魔が入ったりしたときに、しきりに発せられる。 そして、このセリフとセットとも言えるのが、「拉不出来」(出てこない)。日本語では「出ていない」と「出てこない」で、 意味の違いのわりに言葉の違いは少ししかないが、中国語では補語ががらりと変わるから、違いがはっきりとわかっておもしろい。
しかしこの作品、ほかにも「bie不住!」(もれそう)や「別bie壊了」(我慢すると体に悪いよ)など[=bieは「幣」の上半分に「心」]、 トイレにまつわる日常会話をマスターできる(非中国語話者に限定されるだろうが)以外にはこれといって印象的なシーンなどもなく、 観終わった後、どうも釈然としなかった。だが、そう思ったのは私だけではないようだ。過去の劇評を見てみると、 ありありとした実生活の描写が評価される一方で、マナーやプライバシーがなかった頃の生活の再現に不快感があるとか、 リアルなセットや背景の演出が過剰で煩わしいとかいったものも目に付いた(実際、舞台上にトイレがあり、俳優たちもズボンを下ろしたり、 便器に座ったりする)。リアルな生活感が良くも悪くも際立っていたということだろう。
さて、「還没拉完」という言い方、使うときには少々気を付けた方がいいというアドバイスをもらった。 劇中では、中年男性が「まだ出てねえよ!」というニュアンスで使っていたわけだが、ネイティブの友人によれば、 「拉」はかなり「不雅」であるから、「還没完事」とすると婉曲的でよろしい、ということである。 確かに、日本語でもいちいち出ただの出てないだのというよりは、「まだトイレが終わってない」とか「済んでない」という方が好ましいだろう。 そして、「拉不出来」は、端的には便秘という事態を指すということである。 要は、意に反して出てこない、ということだ。この言い方に限らず、動詞と方向補語(結果補語)に挟まれた「不」はいかにも苦しそうで、 にっちもさっちもいかない感じが伝わってくるものである。
[2014.5.27 榊原真理子]
杭州ふたたび
ヨーロッパから帰って1週間ほどたった8月末、慌ただしくも今度は中国・杭州に出かけることになった。2年に1度開催される「韓漢語言学国際学術研討会」と、3年前に韓国・牙山で開催された「清代民国時期漢語国際学術研討会」の続きとなる「元明漢語ワークショップ」に参加するためである。杭州は3年ほど前に『老乞大・朴通事』関係の学会で訪れたことがある。
今回はなかなかの強行軍である。韓漢会議は金曜と土曜、元明ワークショップは日曜だから、本来は木曜のうちに着いているのが望ましいのだが、その週は東京で仕事があって木曜の夕方まで拘束される。そこで、成田から木曜夜の飛行機に乗ってその日は上海に泊まり、翌日の朝一番に高鉄(中国版新幹線)に乗って杭州に行けば、遅れは最小限で済むだろうという算段になった。高鉄に乗るのは今回が初めてである。
しかしこれが結構大変だった。成田を夜の7時半に発って、上海の浦東空港に着いたのは現地時間の夜10時過ぎ。公共の交通機関はもう終わっているのでタクシーを待つほかなく、ホテルにチェックインしたのは12時近かった。そして、翌日5時には起きて高鉄の始発となる虹橋駅に向かい、方々を探し回ったあげく何とか有人の切符売り場を見つけ、杭州行き7時半発の高鉄に乗り込んだ。高鉄自体は非常に快適で、1時間ほどして杭州に着くと、駅前でタクシーを待つ長い行列に並び、ようやく9時過ぎに浙江大学の西渓校区に到着した。会議はもう始まっている頃合いだが、やれやれ、何とかさほど遅れずに済んだ。

上海・虹橋駅

浙江大学西渓校区の正門
…と思ったら甘かった。小規模な会合なので大学の構内には横断幕や看板が一切なく、学会プログラムにあった「中文系大会議室」を探して炎天下をさまよい歩くはめになった。いろんな人に尋ね、やっとのことで中文系の入っている建物を見つけ、3階に上がったところで、何やら人の集まっている気配がするので、これだっ!と勢いよくドアを開けると、全然違う関係の講座をやっていて大恥をかいた。結局、フラフラの状態で会場に飛び込んだのは10時に近い頃だった。
今回の主だった日本側参加者は、遠藤光暁先生をはじめ、東京外大の伊藤英人先生、関西大学の小嶋美由紀さん、中央大学の千葉謙悟さん、首都大学東京の荒木典子さんといったところだが、特筆すべきは当館の吉池さんが参加されたことだろう。吉池さんは1週間ほど前にギックリ腰をやったとかで、コルセットを装着した痛々しい姿だったが、元気に司会と発表をこなされ、特にハングルの創製にチベット文字の造字法が関与しているのではないかという説には深い感銘を受けた。

会議の様子
僕自身の発表はヨーロッパに行く前に慌てて書いた原稿に基づくもので、何ともひどい出来だったが、ひどいなりに勉強にはなった。会議を主催された浙江大学の汪維輝先生、方一新・王雲路ご夫妻とはとりわけ実り多い交流ができたものと思う。特に、元明ワークショップの中で、太田辰夫先生の『燕山叢録』に関する研究を紹介したら、初めて聞く書名だというので、単行本になっていない太田先生の論文というのはまだいっぱいあるんですよ、と話したら中国側の先生方がとたんに色めき立ち、そういうのはぜひ日本側の責任で単行本化して欲しい、と言われたのが印象に残っている。今回の二つの会議については浙江大学漢語史研究センターのサイトに報告が載っているので参照することができる。
例によって、会議が終わった日の夜には中国・韓国の先生方や浙江大学の院生たちとカラオケに行き大いに盛り上がったが、僕は歌わされる段になるといつも「岬めぐり」とか「青春時代」とかの懐メロでごまかすほかなく、情けない思いをしている。今回は吉池さんも来られていて、こういう場はさぞかし苦手だろうと思いきや、「昴」とかを熱唱していて(笑)驚いた。
次回の韓漢会議、あるいは「元明」に続く「隋唐宋遼西夏金漢語ワークショップ」は日本で開催することになったのだが、その開催校というのは…何と神戸外大である。うーむ、とりあえずカラオケのレパートリーを増やすことから準備を始めるか(笑)。
(竹越孝 2014.1.7)
ヨーロッパ訪書行(その4)〜パリ編〜
8月16日、いよいよ今日は海を越えてパリに渡る日である。ベッドから起き上がると少しフラリとする。どうやら風邪を引いてしまったようだ。大英図書館でゲホゲホ言っていたおばさんからうつされたものかもしれない。やれやれ、今日は長丁場なのに…といまいましく思いつつ、急いで朝食をかきこみ、チェックアウトを済ませると、国際列車ユーロスターの発着地であるセント・パンクラス駅に向かう。列車が出るのは8時半である。

セント・パンクラス駅
実は、今回のヨーロッパ滞在中最も緊張していたのがこの日だった。もともとパリでの訪問予定はフランス国立図書館(Bibliotheque nationale de France)だけで、7部閲覧するには1日もあれば充分と踏んでいたから、この日は移動だけですむ予定だったのだが、文献照会に対する返事によると、国立図書館は1日の閲覧部数が5部までと限られているため、7部申請した場合には2日に分ける必要があるという。訪問の予定は土曜日だったので、日曜日を挟んで月曜日も来ますかと問われたのだが、日曜日の夜には帰りの飛行機に乗らなければならない。それだったら本来移動日としていた金曜日の午後から行くしかない、ということになった。
ホテルは図書館に近いルーブル美術館のそばに予約している。ユーロスターの終点であるパリ北駅には正午ごろに着く予定だから、そこから地下鉄を乗り継いで最寄の駅まで行き、できればホテルに荷物を置いて、午後2時ぐらいには図書館までたどり着きたい。全く土地勘のない場所で、これくらい効率よく動けるものだろうか、ということで緊張していたのである。しかも、予約したホテルから送られてきた周辺地図はかなり大雑把で、頼りになるのは『地球の歩き方』だけという心細さ。
というわけで、列車の中では車窓の景色を楽しむ余裕など全くなく、とにかく『地球の歩き方』を熟読し、どうやってメトロの切符を買うか、どう乗り換えて最寄駅まで行くか、どう話してホテルに荷物を置かせてもらうか、そこからどう歩いて図書館まで行くか…等々、頭の中で綿密にシミュレーションを繰り返した。
パリ北駅につくと早速自動券売機でメトロの切符を買う。手元のローラーを転がして選択表示を変えるというシステムが最初よくわからなくて難儀したが、何とか買うことができた。4号線に乗ってシャトレで1号線に乗り換え、目的のパレ・ロワイヤル=ミュゼ・デュ・ルーブル駅に到着。ここまでは至極順調。しかし、一歩地上に出たとたんに方向感覚を失い、どっちがどっちやら全くわからなくなる。地図を見て想像していた景色とぜんぜん違うとパニックになってしまうのだ。これはヤバイ。
まあいいや、とりあえずこっちに行ってみるか、と大雑把な方向だけ決めて歩き始める。こういったヤケクソ的行動を取ると往々にしてドツボにはまるのだが…
ところが、いつものパターンと違って、歩き始めた矢先にホテルが目に入ったのでホッとする。チェックインの時間前だろうから、とりあえずフロントに荷物だけ預けようと思っていたのだが、チェックインできるということで早速部屋に案内され荷物を下ろす。そしてここからは『地球の歩き方』に頼り、コメディ・フランセーズの横を通ってリシュリュー通りを北に歩いていくと、1時半には目指す図書館に着いた。何だか信じられないほどの順調さで嬉しくなる。僕もやればできるではないか!

コメディ・フランセーズ

リシュリュー館の入口
閲覧はカードに文献名と図書番号を書いてカウンターに提出し、名前を呼ばれるまで待つというなじみの方式。 カードを受け取った目つきの鋭い女性から早口のフランス語でまくしたてられ、あわわ…と一気に緊張感が高まったが、 僕の書いた図書番号の一部が「5」か「S」かを確認したいということらしかった。そ、そんな怒ったように言わなくてもいいと思うんだけど。
ここのコレクションは『Catalogue du fonds mandchou』で目星を付けていたものを閲覧したのだが、さすがクラプロート(1783-1835) やアベル=レミュザ(1788-1832)が収集に関わっているだけに、満漢資料のヨーロッパにおける受容を物語る文献も数多く収蔵されていた。 例えば、『清文啓蒙』の巻二「兼漢満洲套話」はスタニスラス・ジュリアン(1799-1873)によってコレージュ・ド・フランスの中国語教科書 『日常口頭話』(1863年)として生まれ変わったわけで、その遥かな道のりを思うとやはり胸が熱くなる。
リシュリュー館には翌日も行き、残りの文献を見た。この日は見たことのない『清文指要』の版本を手に取ったのが収獲。二日とも、 夕食はホテルまでの帰り道にあった日本食のレストランで味噌ラーメンを食べた。麺がクタクタで味もイマイチだったが贅沢は言えない。 幸い、味噌ラーメンを食べているうちに風邪もどこかに行ったようだ。
翌日はヨーロッパ滞在の最終日である。日曜日なので完全オフとして、セーヌ川観光の船に乗って凱旋門に行ったり、 エッフェル塔に登ってみたりと、おのぼりさん的な一日を過ごした。ルーブル美術館は外から眺めただけだが、規模は大英博物館の数倍あり、 その大きさに呆然となる。それぞれの国を代表する収集物が、イギリスは考古遺物でフランスは美術品だというのも気質を表していて面白い。

ルーブル美術館

凱旋門

凱旋門から見たエッフェル塔

エッフェル塔から見たセーヌ川
夕方、バスに乗ってシャルル・ド・ゴール空港へ。無事チェックインを済ませ、家族用のお土産を買った後で、 手元に残ったユーロをはたいてビールを買うと、旅の完結を祝ってひとり乾杯する。
大変だったけど、とても充実した旅だった。おそらく、ただの観光旅行だったらこんな充実感は得られないだろう。さらばヨーロッパ、 予算が残っていたらまた会おう(笑)。
[竹越孝 2013.12.17]
舞台で聞いた中国語10……生存還是燬滅,是個値得考慮的問題(To be, or not to be: that is the question.)
林兆華・任鳴演出の『ハムレット』(《哈姆雷特》1990年、北京人民芸術劇院)の録画を観た。北京人芸は、老舎などのいわゆる 「北京もの」の話劇作品のほかにも、シェイクスピアやオニールなどのクラシックな翻訳作品も得意としている。最近では、 昨年、チェーホフの『たばこの害悪について』と『白鳥の歌』(ともに林兆華演出)、ミラーの『セールスマンの死』(李六乙演出)が 上演されたのが記憶に新しい。
"To be, or not to be: that is the question."というあまりに有名なハムレットのセリフは、なるほど、中国語ではこのように 訳されるのか、と感心しつつウェブを検索してみると、やはり日本語と同様に揺れがあるようだ。朱生豪訳では「生存還是燬滅, 這是一個値得考慮的問題」、卞之琳訳では「活下去還是不活,這是問題」、英若誠訳では「生,還是死,這是個問題」と、 似ているようで案外違う訳出になっている。英若誠は北京人芸の俳優・演出家でもあったから、林・任演出ではいわば 身内の英若誠訳が使われたのかと思いきや、古典的な朱生豪訳の方だったらしい(正確には、朱生豪訳を基にした李健鳴訳 ということである)。
ちなみにこのセリフの日訳はというと、こちらも同じく有名な三つの訳を挙げてみると、坪内逍遥訳では「世に在る、世に在らぬ、 それが疑問じゃ」、福田恆存訳では「生か、死か、それが疑問だ」、小田島雄志訳では「このままでいいのか、いけないのか、 それが問題だ」である。なるほど…ばかり連発してしまうが、こちらもそれぞれ趣が異なっていて興味深い。
今回観た林・任演出の『ハムレット』のキャスティングは、北京人芸や特別出演の「明星」揃いで豪勢だったが、ハムレット役の濮存釬と 王妃ガートルード役の徐帆がとくに好演していた。濮存釬はその爽やかな容貌の印象から、どうももの静かなインテリに見えてしまうが、 『ハムレット』では復讐心をたぎらせ、鬼気迫るハムレットとなって、実力を余すところなく発揮しているように見えた。
徐帆はかつて「錯愛」というテレビドラマで、略奪愛と継子いじめをした末、その継子がかつて手放した実子だったと判明すると いう悲劇というより「悲惨劇」の主人公を水を得た魚のように演じていたが、やはり狂気と紙一重のような陰と危うさを帯びた人物が ぴたりとはまっていた。
だが、この『ハムレット』、問題が一つ。一人二役、一役三人などとキャスティングが交錯しているのだ。基本的に人物は固定して いるようでだいたいのところはわかるのだが、よく聞くと、衣装などはそのままにクローディアスやポローニアスがハムレットの セリフをしゃべっていたりして、ときおり非常にややこしい。斬新な演出だが、視覚が頼りのガイジンには思っていたより ハードルの高い作品であった。
[2013.11.12 榊原真理子]
ヨーロッパ訪書行(その3)〜SOAS編〜
8月15日、この日はロンドン滞在の実質的最終日で、ロンドン大学のSOAS(東洋アフリカ研究学院、School of Oriental and African Studies)を訪問することになっている。ここはヨーロッパにおける東洋学研究の中心の一つで、古くは老舎が 1930年代に中国語講師として教鞭を取り、近年ではアウンサンスーチー氏が助手として勤めていたことでも知られる。
SOASはラッセル・スクエアに隣接しているので、ホテルからあっという間に着いてしまい、開館まで時間をつぶすのが 大変だった。メインの建物に入って図書館に用がある旨を告げると、数字を記したワッペンを胸に貼られてゲートを通過。 図書館入口の受付でメンバーシップカードの発行手続きをする。日本で記入してきた発行申請書と、顔写真入りの教職員証を 見せたら大丈夫だった。中国系らしき女の子が手続きをしてくれたのだが、いざ発行の段になって印刷がうまくいかないとかで 半ベソになっているのが微笑ましい。

SOASの図書館。

メインの入口。

建物の傍らにある謎の銅像。
ただ、失礼ながら本の管理・保存状態はあまり良いとは言えないようだ。『Manchu Books in London』には図書番号も 載っているのに検索では引っかからず、問い合わせても所在不明というケースがいくつかあったし、いま『KOTONOHA』に 翻字・翻訳を連載中の『新刊清文指要』の原本も下巻しか出てこなかった。現在のところ所蔵はここだけと思われる貴重な 会話書『満漢合璧集要』(1764年)は、綴じ糸がほつれていて裏打ちもしていないので、1枚めくるごとに紙がボロボロ崩れて くるありさま。大英図書館では漢籍も洋装本の体裁に改装されているものが多く、それはそれで不便なのだが、ここまで ほったらかしだとやはり心配になる。
結局この日も昼食は食べず、調査が全部終わったのは大体午後3時ぐらいだった。貴重書室を出て、帰りしなに全体を見て回る ことにする。SOASの図書館は基本的にすべて開架で、中央にある閲覧席を囲む巨大な吹き抜けの構造になっている。この重厚感は やはりさすがで、蔵書も非常に充実しているように見受けられた。
建物を出たところで雨が降り出して来たので、雨宿りがてらに大学生協のやっているパブのようなところに入った。中では 日本や中国の留学生がビールを飲みつつ談笑しているので、おっかなびっくりビールを1パイント頼んでみる。これが僕にとっての パブ初体験となった。
ちょっとホロッとしたところでうまい具合に雨が上がり、そういえば大英博物館もすぐ近くだったと気付いて行ってみることに した。本当は一日ぐらいかけてじっくり見て回らなければならないところだが、まあそれは次回まわしでいいだろう。とりあえず これだけは見なければと思っていたロゼッタストーンは、やはりすごい人だかりでよく見えなかった。エジプトの考古遺物は さすがの迫力で、よくこんな重たそうなものを運んできたものである。

大英博物館。

エジプト考古遺物のコーナー。

博物館向かいのパブで。
旅の恥はかき捨てとばかり、フィッシュアンドチップスにギネスという真正おのぼりさん的な組み合わせを注文すると、 歯に矯正具をつけた若い女性の店員さんがニッと笑いつつ、片言の日本語で「はい、サカナとイモね」などと言うのでちょっと脱力。 考えてみたらこれがイギリスでは最初で最後の外食となった。夕暮れの市街をぶらぶら歩いてホテルまで帰り、シャワーを浴びた後、 満ち足りた気持ちでベッドに入る。
さて、ロンドンは無事終わった。明日はいよいよドーバー海峡を越えてフランスに渡る日だ。
[2013.11.12 竹越孝]
ヨーロッパ訪書行(その2)〜大英図書館編〜
8月13日、いよいよ図書館めぐりのスタートである。ロンドンの滞在は実質3日間で、そのうち2日を大英図書館、 1日をSOAS図書館の訪問にあてている。ホテルはそのどちらにも歩いていける距離のところに取っていた。
やはり時差ボケなのか、夜中の変な時間に眼が覚めてしまったため少し眠いが、昼食は食べるかどうかわからないので、 朝はしっかり食べておきたい。宿泊についていた朝食はコンチネンタル・ブレックファストのビュッフェだったが、 やや高級なイングリッシュ・ブレックファストの会場も隣接していて、そちらでは5ポンドの追加料金を取られる。 最初知らずにイングリッシュの方に並んでいたら、シッシッという感じで追い払われた。
出発までやや時間があるので、朝食の後で少し散歩に出てみる。日本では真夏なのだが、ロンドンは驚くほどひんやりしていて、 ジャケットを着ていないと寒いぐらいだった。ラッセル・スクエアのあたりをブラブラ歩いてみるが、実に落ち着いた 雰囲気の公園で、やはり伝統の重みを感じる。

ラッセル・スクエア。

ホテル・ラッセル。

大英図書館。

「プロパガンダ」という展示が行われていた。
まず中2階の登録受付に行って来意を告げ、証明を要求されたのでパスポートと残高証明書を見せると、パーフェクト!と 言われニンマリ。横にあるコンピューターで登録するように促される。わからない単語を辞書で調べつつ、自分の情報を打ち込んで 申請ボタンをクリックすると、間もなく奥の方から声がかかり、担当の方と面談することになる。準備してきたメールの通信記録を 見せつつ説明すると、その場で写真を撮ってくれて、めでたく顔写真入りのリーダーズ・パス発行となった。いったん半地下に あるロッカールームでカバンなどの荷物を入れてから、3階にあるAsian & African Studiesのリーディングルームに向かう。
大英図書館で不安だったのは、閲覧を希望していた文献が外部のオンライン検索では引っかからないことだった。日本から メールでその点を問い合わせると、東洋語文献のオンライン検索はまだ不完全で、来館時に閲覧の仕方を説明するという返事を もらったのだが、文献自体はあるともないとも書いていなかったので、どうなるかわからなかった。
カウンターに行きメールの記録を見せて説明すると、風邪をひいているらしい係のおばさんがゲホゲホ言いながらも丁寧にやり方を 教えてくれた。手続きはすべてオンライン上で行い、申請ボタンをクリックすると閲覧まで何分かかるかが表示され、 準備ができるとそれも表示されるという仕組み。日本の図書館のように紙に記入してカウンターに出したりすることはなく、 ○○さーんと呼ばれることもない。ずいぶんオンライン化が進んでいるという印象だった。
幸い、見たかった文献は全部所蔵されているようで、図書番号も『Manchu Books in London』に記されているものと同じだった。 一度に閲覧できるのは6点までということだったので、まず大英図書館所蔵の『清文啓蒙』を6種類全部出してもらうことにする。 『清文啓蒙』は清代に最も流行した満洲語の教科書で、とりわけ版本の数が多いことで知られているのだが、6つものテキストを並べて 見たのは初めてで、じわーっと感動がこみ上げる。ああ、これだけでも来た甲斐があった。
結局その日は昼食も食べずに閉室の午後5時まで粘った。出してもらった文献を全部返却して帰ろうとすると、スキンヘッドで 眼光鋭い出納係のおじさんに呼び止められ、この本は帙入りだったはずだがと言われたので、思わず憤然としてノー!と 叫んでしまう。とにかく勢いだけは伝わったようで、それ以上追及されることはなかった。図書館を出るとふうっと大きな息が出る。 あまりの空腹と疲れでフラフラになりながらホテルに帰り、途中のスーパーで買ったサンドイッチをビールで流し込むと、 その日はすぐに寝てしまった。
翌14日も朝から大英図書館に行き、残りの文献を閲覧した。この日のメインは『問答語』という刊本で、池上先生の論文でも 紹介されていたので、今回ぜひ見たいと思っていた本の一つだった。道光7年(1827)刊の薄い本だが、対訳の中国語はかなり口語的 色彩が強く、いい資料になりそうだ。これはぜひとも複写を申請して帰らなければならない。しかし…
複写担当の人は昨日の出納係よりもさらに怖い感じだったのでビビりまくる。全部見終わってから1時間もの間逡巡し、頭の中で あれこれ英語の文章を組み立て、最後にありったけの勇気を振り絞って(たぶんここ10年ぐらいで一番緊張した瞬間だと思う)、 恐れ入りますがこの本の複写はどうやって申請したらいいのでしょうか、と聞いてみると、一言「オンラインでできる」と返され 一気に脱力。ただ、この方も親切に申請の方法を教えてくれた。
そんなこんなで二日目の調査はわりと早く終わり、少し気が楽になったので、夕方から地下鉄に乗ってソーホーの中華街に行き、 パオズ(包子)を食べながらブラブラした後、最終的にはテムズ川まで足を延ばした。この日は街中いたるところにサッカーの ユニホームを着た大男たちがたむろしていて、地下鉄の中でも「ウェンブリー!ウェンブリー!」と節をつけて大合唱しているので、 こ、これはもしやフーリガンというやつでは…と思っていたら、単にイングランド対スコットランドの代表戦ということで 街中が盛り上がっていたらしい(ウェンブリーは有名なサッカー場)。一人の時は豪勢な食事をしたいと思わないし、 パブに入る勇気もないので、この日も帰りにスーパーで買った食材をホテルの部屋でもそもそと食べ、早々にベッドに入る。

中華街のレストラン。

テムズ川から眺めたビッグ・ベン。
[2013.10.15竹越孝]
ヨーロッパ訪書行(その1)〜準備編〜
以前、いつか遠藤光暁先生の「北京からパリへ―ヨーロッパ中国語学の旅―」(『漢語方言論稿』所収,好文出版,2001年)の ような旅をしてみたいと書いたことがあったが、念ずれば通ずというのか、その機会は意外に早くやってきた。今年度、清代満漢合璧会話書の 研究というようなテーマで予算がついたのである。ここ数年、『KOTONOHA』誌上に連載してきた『清文啓蒙・兼漢満洲套話』や『清文指要』の 翻字・翻訳の実績がついに実を結んだ格好で、実に喜ばしい。いや、もちろん予算を目当てに連載していたわけではありませんが。
それで、前々から予算がもらえたら是非やりたいと思っていたのが、「ヨーロッパ満洲語学の旅」(笑)だった。お手本としたのは 池上二良先生の「ヨーロッパにある満洲語文献について」(『満洲語研究』所収,汲古書院,1999年)で、それぞれの文献に対する記述は 簡潔ながら、池上先生がヨーロッパ各地を巡って相当な量の調査をこなされていたことがわかる。遠藤先生によると、それこそ「ヨーロッパ 中国語学の旅」の最中に、フランス国立図書館(Bibliotheque nationale de France)で池上先生にお会いしたこともあったそうだ。
池上先生のように満洲語文献を網羅的に調査するだけの実力はないが、満漢合璧会話書についてはこの機会にできるだけ多くのテキストを 見て、きちんとした文献学的記述を残そうというのが今回の目的である。もちろん、時間は限られているので、いかに効率よく動いて目的と する文献の調査をこなすかがポイントになる。文献にせよ方言にせよ、調査の成否は事前の準備が決める、ということで今回は準備編。
学校行事の関係や家族の予定を勘案した結果、取れる日程は夏休みの1週間程度しかなかったので、行先はロンドンとパリに絞り、 ロンドンでは大英図書館とロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)図書館、パリではフランス国立図書館に行くことにした。ロンドンの 文献についてはHoward Nelson and Walter Simon編『Manchu books in London』(British Museum, 1977年)、パリの文献については Jeanne Marie Puyraimond, Walter Simon and Marie Rose Seguy編『Catalogue du fonds mandchou』(Bibliotheque nationale, 1979年)が あって、調査する文献の目星が付けやすかったからである。閲覧は目下最優先課題としている『清文啓蒙』と『清文指要』の関係書を中心に して、余力があればその他の満漢合璧会話書も見るという計画を立てた。
本格的に準備を始めたのは1ヵ月ぐらい前からである。上記二つの目録をもとに閲覧したい文献の一覧を作り、各図書館のウェブページで 片っ端から検索していき、ヒットしたものとしなかったものをリストアップした上で、各図書館に向けて、自分は日本の研究者だが、今度 これこれの文献を見に行きたいというメールを送った。そして、ヒットしなかったものについてはなぜヒットしないのか、また閲覧に 当たって事前申請は必要か、閲覧の際に必要な書類は何かなど、担当者を紹介してもらって事細かに尋ねた。
以上のメールはもちろん全部英語だから、送る前に妻にチェックしてもらったりしたのだが(妻は英語で学会発表できるぐらいの 達人である)、なぜこういうことをしたかというと、プリントアウトしたメールを持って行って当日係の人に見せると、いちいち 説明しなくてもすぐに事情が分かってもらえて便利だと聞いたからである。英語にからきし自信のない僕にとっては、そうするのが 一番手っ取り早く、また確実な方法に思えた。そもそも「行けば何とかなる」なんて到底考えられなかったのだ。そしてこの作戦は 見事的中し、各図書館からいずれも友好的で丁寧な返信をゲットするのである。
準備としては他にも、大英図書館では日本の住所を英文で証明する書類が必要だということで、銀行に英文の残高証明書を発行して もらいに行ったり、またいざという時のために勤務先の図書館にお願いして特別に英文の紹介状を作ってもらったりした。入念すぎるんじゃ ないのと妻には笑われたが、せっかく行ったのに入れなかったとか、見たい文献が見られなかったとか、そういう事態だけは避けたいと 思ったのである。とにかく僕は目的のない旅というのが苦手で、「世界ふれあい街歩き」みたいなことはとてもできそうにない。
準備のメドが立ったら、出発前に何としても仕事を片付けておかなければならない。今年の前期はいつもにも増して無節操に仕事を 引き受けすぎて、5月の連休あたりからずっと締切に追われて青息吐息の状態が続いていたのだが、ここが踏ん張りどころということで 脂汗を流しつつ書き進める。最後に残った中国語の論文は我ながらかなりひどい出来だったが、とにもかくにも8月11日の夕方には決着を つけて、その夜大阪に移動した。
翌12日の朝に関西空港を発って午後にソウル・インチョン空港で乗り換え、それから12時間もの長い長いフライトを経て、ロンドン・ ヒースロー空港に降り立ったのは現地時間で12日の夕方6時過ぎ。それから地下鉄ピカデリー・ラインに乗り、予約したホテルのある ラッセル・スクエア駅には8時頃に着いた。サマータイムを実施しているからか、それでもまだ明るい。朝日本を発って、合計14時間 あまりのフライトを挟んでまだ夕方だというのは信じられない感じがする。駅を出ると、いきなり風格のあるパブで赤ら顔の大男たちが ビールを酌み交わしている姿が目に入り、その「いかにも」な光景に笑ってしまう。街並みといい、歩いている人々といい、確かに これまで僕が馴染んできたアジアの風景とは何もかもが異なる。

夕暮れの街並み。二階建てのバスはさすがロンドン。

ホテルの窓から。目の前にある建物からしてこんな感じなので圧倒される。

さて、いよいよ明日からだ。
[2013.9.10 竹越孝]
展示「モンゴル帝国―パスパ文字と『東方見聞録』―」開催中
愛知県立大学(長久手キャンパス)の図書館にて展示が行われている。 モンゴル帝国・元朝のパスパ文字が書かれた文物(拓本、印鑑、錘、貨幣)と関連書籍(『東方見聞録』の5カ国語 バージョンなど)が展示されている。
主催:愛知県立大学図書館/高等言語教育研究所
協力:古代文字資料館
期間:7月18日〜8月13日
場所:図書館1階ロビー


正面拓本は玄中寺フビライ牛年聖旨碑(パスパ文字・モンゴル語)

左は銅錘(漢字、パスパ文字、ウイグル文字、アラビア文字が刻まれている)

各種銅銭(パスパ文字・漢語)

中央は官印。左右は私印(両者ともパスパ文字・漢語)

拓本は玄中寺フビライ牛年聖旨碑(漢字・漢語)
舞台で聞いた中国語9…我靠!(すごっ!)
この感嘆詞で最初に思い出すのは、「街中すべてピラミッド」(満城全是金字塔:2007年初演、戯逍堂)の冒頭のシーンで、 主人公の青年がピラミッドのなかで財宝を見つけたときに言っていたセリフである。最初、この言葉の意味がまったくわからず、 その後ずいぶん月日が経ってから、ああ、あれはただ驚いていただけで全然意味はなかったのか、とようやく理解した。教科書だけ 勉強していたのでは、なかなかお目にかかれない中国語である。
びっくりしたときの中国語といえば、やはり教科書でも習う「ai ya!」、「ai yo!」だろう。もしくは、もう一音節力を込めて 「ai yo wei!」とか。だが、若い世代の間ではタイトルに挙げた「wo kao!」、あるいは「wa sai!」が好まれて使われており、 こちらの方がずっと実感がこもっているようにも聞こえる。ただし、「wo kao!」はかなり粗野で「不文明」であるらしい。状況に よっては喧嘩腰にも聞こえかねない語感を伴うから、劇中の人物のような青年の使う男性語ということだろう。「wa sai!」の方は、 子供や女性も含めた若者世代に定着していて、(今ではやや古くさくなっているようだけれど)どちらかというとポジティブな文脈で 使われている。日本語でいうと、「すごい!」、あるいは、きゃあきゃあ喜びながら言うときの「ヤバい!」のようなニュアンスだろうか。
他にもう少し長いフレーズもある。「(wo de)ma ya!」、「(wo de)tian a!」、「hao jia huo!」など。日本語に置き換えると、 こちらはかえって「なんとまあ」とか「あらやだ」くらいに収まってしまって、「ai ya!」とあまり区別がなくなってしまうのだが。
さて、「街中すべてピラミッド」は「wo kao!」というセリフからも推察されるように、制作側、観客層ともに若者が中心の作品である。 ストーリーも恋愛がテーマで、親に別れさせられた恋人の再来をミイラになって待ち続けるヒロインと、生まれ変わってピラミッドの 発掘にやって来たその恋人が、ピラミッドのなかで再び出会い、記憶を呼び戻し、恋を成就させるというラブコメディだ。
この作品は、時代を超えて恋人たちが再会するという突飛な設定と、脇役4人の演技とキャラクターが際立っていたのが受けて、 2007年から2010年にかけて再演を重ねるロングランとなった。脇役というのは、主人公二人の再会に居合わせてしまう、盗掘をしていた コソ泥3人と、主人公二人の恋路を邪魔する宇宙人である。
特に宇宙人役の俳優は秀逸だったという記憶がある。だが、ひどい南方なまりを話すという設定だったため、具体的には彼が何を話して いたのだか結局よくわからなかった。流行語や若者言葉の知識のほかに、ある程度地域なまりにも対応できるようにしておかないと、 外国語の作品理解はやはりなかなか難しい。
[2013.7.16 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語8……聴見了(わかりました)
前々稿に続き、ディスクで北京人芸の『雷雨』(曹禺作、1934年初演)1997年版を観た。『茶館』と並ぶ名作話劇の双璧である。
『雷雨』は見るからに悲劇だ。最後には3人も人が死ぬ。それでなくとも、登場人物は腹に一物抱える人ばかりでハッピーな人は誰もいない。 だが、そのなかで異彩を放っている人物が一人いる。舞台となる周家の次男周沖。若くて溌剌とし、最初に登場するときなど、 テニスラケットを手に持っていたりする、それはまあ爽やかな御曹司である。役どころは、良く言えば天真爛漫な癒し系、 悪く言えばいい人で終わってしまうまぬけキャラ、というところ。何しろ最後には人を助けようとして、巻き添えになって 死んでしまうのだから。
だが、そんな愛らしい彼も弱冠17歳にして実は悩み多き人物だ。使用人の四鳳を好きになるがプロポーズを断られ、 不仲の両親の板挟みで苦しみ、父親の持つ鉱山の労働者(四鳳の兄)と父親の間のいさかいでも板挟みになって、血も涙もない 父親の代わりに良心を痛めている。そして、ダメ兄貴(異母)の結婚の心配までしている。その兄が自分の好きな四鳳と秘かに 付き合っているとは知らないのだから、滑稽なまでに健気だ。主役は四鳳だが、彼が主役でも十分脚本が書けそうである。
最後のシーンに至っては、四鳳が兄と付き合っていて妊娠3か月だとわかるのはまだ序の口で、兄と母 (兄にとっては継母)がかつて関係を持っていたこと、そして、実は兄と四鳳は異父兄妹でしたというまさかの血縁関係が発覚する。 韓流ドラマも顔負けのドロドロぶりに、彼のアイデンティティーはもはやズタズタである。衝撃の事実に四鳳は半狂乱に嵐の屋外に 飛び出して、落雷に遭いあえなく死亡。気の毒な周沖は四鳳を追いかけて自分も一緒に感電し、はかなくもドラマティックな生涯 を閉じるのだった。ほどなくして、兄の拳銃自殺ですべての悲劇の幕が下ろされる。
この周沖のセリフで、"聴見了"(わかりました)というのはシンプルにしてなかなか象徴的だろう。文脈にもよるが、 これはよく"聴見了[口+馬]?"(聞こえたか、わかったか)という語気の強い念押しを受けて言う。劇中の子供たち(兄、四鳳、四鳳の兄) が自我を通してどんどん大人たちと対立を深めていくのに対し、周沖だけは封建主義の父親の命令口調に従順に返事をする。
反対に、彼にも唯一"不"と潔く母親を制して心のたけを述べる一瞬があるのも、キャラクターの奇特さを引き立てている。 クライマックスで、妊娠がわかった直後、血縁事実発覚前のわずか数行のシーン、四鳳が望むのなら二人を応援する、と。
封建主義の父親が薬の服用を自分の妻に強要する例の有名なシーンも見どころだが、キャラクターの際立った脇役に注目するのも この作品の醍醐味である。
[2013.6.11 榊原真理子]
★上文において、『雷雨』のクライマックスで四鳳は「落雷に遭い」死んだ、と述べましたが、正しくは、送電線接触による感電死でした。 この場を借りてお詫びするとともに、訂正致します。また、ご指摘下さいました摂南大学瀬戸宏先生に御礼申し上げます。[2014.8.19補]
舞台で聞いた中国語7……両張比薩餅(ピザを二枚)
前稿に続き、『茶館』の話題をもう一つ。『茶館』(老舎作、1958年初演)は北京人民芸術劇院のロングラン作品だが、 最近地方公演が始まったとラジオで聞いた(ちなみに、ラジオはインターネットで聞ける北京人民広播電台の"文芸"チャンネル。 北京のローカル局だけあって、キャスターたちのアル化音がコロコロと耳に心地よい)。
巡演先は、深セン、武漢、重慶である。"文芸"チャンネルの毎正時の短いニュースでは、市内の公演情報と天気予報、 交通情報が流れる。北京人芸関係者が電話インタビューで、誇らしげに古き良きリアリズムの『茶館』をアピールしていた。
キャストは20世紀後半を華々しく担った于是之、鄭榕、藍天野らの代から入れ替わり、今は梁冠華、濮存釬、馮遠征らが演じている とのこと。第二世代(といっても、年齢は50〜60代だが)は映像での活躍が多く、テレビドラマやコマーシャルで見るような爽やか だったり知的だったりするイメージにとらわれてしまうが、そんな彼らがどう『茶館』の貫録ある旦那たちを演じるのかは、 実に興味深く楽しみである。
拙稿5で紹介した『アナーキストの事故死』が、実は『茶館』とリンクしている。『アナーキスト…』の一シーンに 『茶館』のパロディが盛り込まれているのだ。そのなかでは『アナーキスト…』の登場人物であるイタリアの刑事も囚人も、 皆"警察局"の主人や客になって、"大清国"ならぬイタリアのご時世を嘆いている。茶館に現れた貧しい母娘に常四爺が"李三, 要両個爛肉面,帯[女+也]們到門外吃去!"「李三、肉うどんを二杯、これたちに表で食わせてやってくれ」*と言うかの有名なセリフは、 「李三、ピザを二枚(両張比薩餅)、これたちに表で食わせてやってくれ」となって、高らかに、大真面目に叫ばれる (李三はなぜか李三)。
このパロディ、観客には大うけである。客席では拍手や"叫好"の歓声が一斉に起こる。『茶館』をよく知っていなければ このシーンの面白さはわからないから、観客の速やかで明快なリアクションに、『茶館』が国民的話劇なのだと痛感する。 少しおかしなたとえになるが、日本人が"マスオさん"と聞いたときに、すぐにどういう状況なのかが理解できるのと同じぐらいの 浸透度ではないだろうか。
マスオさんはさておき、この観客の拍手喝采にはパロディの妙の賞賛以外に、やはり不朽の名作への畏敬の念も込められている はずである。だから、今回の地方公演、よい席は1,000元を超えるという高額であるのは、高嶺の花すぎて少し残念に思う。
* 『茶館』老舎作、沢山晴三郎訳注、大学書林、1982年、pp. 56-57.
[2013.4.16 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語6…溜達溜達(ぶらぶらする)
最近、北京人民芸術劇院の話劇のディスク(公演録画)を観ている。そのうちの言わずと知れた名作「茶館」 (老舎作)は幾度となく観たが、改めて観るとやはりなかなか味わい深い。
北京に留学したことがあるせいか、個人的にかなりの北京びいきだ。だから「茶館」を観ると、 あのこてこての北京のセリフや情景(京味儿)だけで、もう文句ないのである。
しかし、北京語(北京方言)というもの、かなり好みがはっきりと分かれる。いくら標準語が北京語を基礎に 作られたといっても、やはり北京語は標準語や南部の発音から見れば癖が強い。誰もが知っている特徴的な語尾の アル化音、強い反り舌音を使うかどうか、好むかどうかは一種の争点だろう。私は適度にアル化しないとどうも もの足りないし、反り舌音と軽声もはっきり強調する話し方のほうが繊細で好きだ。アル化音によって出る滑らかさと、 軽声の作るリズム感は北京語の命であると思う。老舎の"茶館"に限っては、cha guan ではなくcha guanr だというのも、 断固譲れない。まあ、南部派の人にとってみれば、それがどうした、という特徴ではあるが。
文法や語彙の違いもある。"着"は会話の節々に隠し味的に隠れている。教科書でも習う用法だが、持続 にzhe、強調に zhe ne、結果補語にzhao とくると一味違う。
語彙は、聞いたことがある限りでは、"下館子"(到飯館去)、"没戯"(没希望)、"貧"(話多)、 "圧根儿"(根本)、"[心>戈]"あるいは"倍儿"(非常)などが北京風で小粋だ。そして、タイトルに挙げた"溜達"も ちょっとこなれた雰囲気のある、よく使われる動詞である。
「老爺子,nin na,外辺儿溜達溜達?」:「おじいさん、さ、表をぐるっとしてきてくだせえ」 (「茶館」第1幕、李三が茶館のなかに入ってきた物売りの老人に対して言うセリフ)
標準語に置き換えると、"散歩"とか"走一走"になるが、どうもこれでは味気ない。要は"歩く"と いうことなのだが、日本語でも"ちょいとそこまで"とか"ぶらり"とか言うとしっくりくるのと同じことだ。
このディスクは1992年、焦菊隠演出(1950年代)のリバイバルである。主演の王利発役はこちらも言わずと 知れた名優于是之。くしくも于是之はつい先日、1月20日に死去した。北京人芸公式ホームページによれば、享年86歳。 たまたま見始めただけだったのが、追悼鑑賞になってしまった。おそらく彼を偲んで、同じように多くの人々が映像を 観ていることと思う。
[2013.2.19 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語5……情況太複雑了!(状況複雑だし!)
このセリフには次のように二の句以下が続いて1セットとなる。
……現実太残酷了、理想都破滅了、我也不想活了!(……現実残酷だし、理想はズタボロだし、オレもう死にたいし!)
これは、本稿の3でも紹介した演出家・孟京輝の作品「アナーキストの事故死」(《一個無政府主義者的意外死亡》 ダリオ・フォ原作)の中で、主人公の囚人が言うセリフである。言葉の語呂合わせやリズムを生かした、テンポのいい セリフ回しがなんとも孟京輝らしい。なぜかこのセリフの繰り返しだけで、ポンポンとシーンも進行するのである。
状況は、というと、設定はイタリアの警察署内。取り調べ(というか拷問)中の被疑者の予期せぬ死亡を事故死に 偽装しようと画策する刑事たちと、それを無理やり手伝わされる囚人・瘋子との喜劇的やりとりの中、刑事たちによる強制的な 偽装工作への加担に、瘋子がうんざりして思わずつぶやき、それが叫びへと変わるところだ。
しかし、これが劇中の保身に走るイタリアの刑事たちに向けた嘆きであると同時に、中国の現実社会への憤懣でもあるのは、 すぐに聞き取れる。瘋子はその偽装工作に対するやる気のなさを刑事に咎められて、死亡した被疑者がそう言って窓から飛び降りて 自殺したのだ、という流れに切り替え、さらにその後、苛酷な現実社会に絶望した刑事たちもそう言いながら窓から飛び降りました、 と彼らを窓際まで誘導しようとする。もちろん、刑事たちはそうまんまと最後まで話に乗ってはくれないのだが。
このシーンの前後にも、瘋子が被疑者「自殺」のシナリオの番外編を創作する場面――「刑事たちが資産家の息子だったら どうだろう、犯罪行為をしても警察は親が有力者だと知ると謝罪して手錠を解いた上、家まで送り届けてくれます、紆余曲折を 経て最後に一家はアメリカへ行ったのでした」といったてんやわんやのやりとりなど、孟京輝の鋭さの映えるシーンが たくさんある。リズム感のあるセリフや挿入歌、ドタバタのパロディだけでも楽しめるが、状況設定やセリフの行間も よくよく汲み取ってこそのおもしろさだろう。
孟京輝は1964年生まれ。改革開放政策以降に隆盛してきた「実験演劇」(前衛的な小劇場演劇)のトップランナーで、 すでに話劇史にその名が刻まれている。
ところで、冒頭に挙げたセリフの訳、もっと適した妙訳があれば、ぜひご教示いただきたいと思う。
[2013.1.15 榊原真理子]
三田渡碑を見に行く
今年の7月28-29日に徳成女子大学で行われた第4回訳学書学会のあと、奎章閣に行って文献調査をするつもりで 1日空けておいたのだが、夏季の蔵書整理期間中ということで閲覧がかなわなくなった。午前中は本屋回りをすることに して、午後で行って帰ってこれるくらいの観光場所はないものだろうかと思っていたところ、ある方から、三田渡碑に 行ってみるといいですよと言われ、おお、それそれ!ということで行ってみることにした。今回も相棒は東京外大大学院の イケメン杉山豊氏。勝手に相棒呼ばわりして申し訳ありませんが。

午前中に行った司訳院跡。ソウルの中心部、世宗文化会館の裏手にある。
三田渡碑は、1636年に起こった清の太祖ホンタイジの朝鮮出兵、いわゆる「丙子胡乱」の講和条約である「三田渡の盟約」 を記念して建てられたもので、中国語名は「大清皇帝功徳碑」。仁祖がホンタイジに対して「三跪九叩頭の礼」を行うなど、 盟約は朝鮮王朝側にとって屈辱的な内容であったため、建碑後様々な流転の歴史があって、現在の場所に落ち着いたのは 2008年のことであるという。


蚕室駅の地上に出て交差点を渡ったすぐのところにある。
この碑が貴重な理由は、その内容もさることながら、満洲語・モンゴル語・中国語(文言)の三言語対照で記されて いるためである(ただし、それぞれの内容は完全に同一ではない)。言ってみれば司訳院における清学・蒙学の原点とも いうべき存在なのだから、訳学書に関心を寄せる身としては行くのが遅すぎたぐらいである。
三田渡碑の最寄駅は蚕室(チャムシル)、言わずと知れたロッテワールドの拠点であり、地下鉄を降りた瞬間から 華やいだ空気が伝わってくる。地上出口のところで杉山さんと待ち合わせ、交差点を渡ったらすぐに碑があった。 碑の向こう側はロッテワールドの敷地で、こちら側は普通の道路で車がビュンビュン行き交っている。こういう雰囲気の ところに第一級の歴史資料が実在しているのは、何とも珍なる光景というか…。

満洲語とモンゴル語が刻された面。

漢文面。題名はわりとはっきり見える。
碑の高さは5.7mというからなかなか巨大である。表には右側に満洲語、左側にモンゴル語が刻され、裏には漢文が刻されている。 もちろん周りは柵で覆われており、中に入って触ったりすることはできない。漢文面の方は何とかところどころ読めるものの、 満洲語・モンゴル語の面は磨滅が激しく、題名が漢字でないとわかるぐらいで、本文の方はほとんど何が書いてあるかわからなかった。

碑身のない方の亀の台座。碑身のサイズに合わなかったため遺棄されたという。
むしろ注意を引いたのは二つあった亀の台座(亀趺)で、むかし授業で太田辰夫先生の『中国歴代口語文』を読んでいた時、 『紅楼夢』の第23回に、
要有心欺負ni,明兒我掉在池子里,叫個癩頭鼈吃了,去變個大忘八,等ni明兒作了一品夫人病老歸西的時候兒,我在ni墳上替ni駝一輩子碑去。 (もしも君を馬鹿にする気があったというなら、明日僕は池の中に落ちて、化け物スッポンに食べられ、大スッポンに生まれ変わって、 将来君が一品夫人になって死んだら、墓で一生君のために石碑を担ぐよ)
という台詞があって、「石碑をスッポンが担ぐ」という光景を学生に何度説明してもわかってもらえなかったのだが、この写真を 見せれば一発だったのになあ、とか変なことを思い出したりした。

碑の向こうに見えるロッテワールド。
暑い夏の昼下がり、碑の向こうにはロッテワールドの浮世離れした建物群が見え、フリーフォールのような遊具から時折 ワーッという歓声が上がる。三言語対照碑文なんてものはもちろん日本にはないし、ここは確かに大陸と地続きなのだなあ という感慨を覚える。この碑が生まれた背景とそこで使用された言語、そして碑がその後にたどった歴史を思うとき、これは これでなかなか味のある風景だった。
[2012.12.17 竹越孝]
舞台で聞いた中国語4…愛情跟婚姻没有必然的聯系(愛と結婚に必然のつながりはない)
テレビドラマや映画と同じで、演劇でも恋愛や結婚は時代を通して大きなモチーフとなる。愛情と金銭の比較とか、 両人の文化の違いが生み出す悲喜劇とか、嫁姑問題とか普遍性があり、何よりもとても身近で皆の関心事だ。
「いい加減にできる愛がどれほどあると」(《有多少愛可以胡来》李伯男演出)では、愛と結婚の比較がテーマ。 その中で、今を生きる女性・真真は一白のプロポーズを断る際、「愛と結婚に必然のつながりはないわ」と何度も繰り返す。 そして、去り際のとどめのセリフはこれ。「まだ遊び足りないの。私は木1本のために森全部を捨てたりしない」 真真が登場して有無を言わせずこう言い切る前には、平凡な結婚生活を望みながらも一白に待たされ続け、ついに彼の もとを去ってしまう暁丹が観客の同情を誘っていた。
平凡な幸せを望む女性と、望まない女性。家庭生活に幸せを見出す女性と、見出さない女性。一見、正反対のタイプの 人物を対照させているかのようだが、どちらも自分なりの幸せを求めるために恋人と別れて、再出発する行動力がある、 という点では共通性がある。自分の幸福を見定めている女性は態度がはっきりしている。
今日の中国で、それぞれの世代、性別、あるいは地域で、結婚や恋愛がどうとらえられているかというのはなかなかおもしろい。 「白馬王子」、「二人世界」とこちらで聞いたかと思えば、あちらでは「婚姻是愛情的墳墓」と言ってたりして。
李伯男は現代の若い世代の心のひだを掘り下げることをテーマとしているから、この作品ではおよそ20〜30代の女性の、結婚に まつわる二つの声を代弁していることになる。
でも、やはり興味深いのは主人公・一白の不甲斐なさ。結婚を決意するタイミングがかみ合わなくて、暁丹、真真、 そしてもう一人と、結局3人の女性に去って行かれる。最後には、彼女たちが踏み出していった向こう側に行けない自分に 気づき、しんみりとするのがなんとも哀愁的。それも、今日の中国男性の一つの姿ということか。
[2012.12.11 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語3…一只牙刷多少銭?(歯ブラシ1本いくら?)
青年・馬路が「恋愛訓練課」のクラスメイトとポーカーをしていると、歯ブラシのセールスマンがやって来た。
「ダイヤモンドブランドのダイヤモンド歯ブラシです。只今、お客様感謝キャンペーン中につき、1本のお買い上げでもれなくもう2本差し上げます(買一只免費贈送両只)。1本のお値段16元で3本があなたのものに!」
馬路は彼に尋ねた。「歯ブラシ1本、一体いくらだ?」
セールスマンはにこやかに答える。「16元です。今ならキャンペーンでさらに2本おつけします」馬路は再び尋ねる。「3本なら?」「16元です。2本はキャンペーンの無料プレゼントです」
馬路は訝しんだ。「ちょっと待て。1本いくらだって?」「16元です」「3本なら?」「16元です」「1本だと?」「16元です。でも只今キャンペーン中ですので、もう2本無料でおつけしております」
馬路は不機嫌になった。「何の冗談だ! 1は3じゃない! 1本いくらだ!?」「16元ですけど、キャンペーンでもう2本…」「歯ブラシ1本いくら!!」「……」
だんだんと激高する馬路に、セールスマンはしまいに泣き出して言った。「大哥、我錯了…」
このエピソードは「恋するサイ」(《恋愛的犀牛》廖一梅作、孟京輝演出)のメインストーリーに唐突に挿入される1シーンである。 作品の主題は叶わぬ恋に偏執する馬路の苦悩で、雰囲気はとてもシリアスだ。そして、こうした馬路の参加する「訓練課」の レッスンやクラスメイトの破天荒なエピソードの挿入が、このストーリーのもう一面を支える。賛否両論あるが、重々しいシーンと カラッと明るいシーンの対比がユニークな作品である。
その二側面を孟京輝の現代社会への痛烈でストレートな批判精神が貫いて、全体がまとめられる。このシーンは大量消費社会への 懐疑ということか。
他愛もない言葉遊びにすぎないようだが、3本で1本分の値段。さて、本当の値段はいくらなのか。確かに、馬路ほど激高 しなくてもよいが、“免費贈送”を見かけたら一考してみてもいいかもしれない。ふと、我に返る1シーンだ。
[2012.10.30 榊原真理子]
契丹学国際会議(赤峰市)
2012年8月20日より23日まで内蒙古自治区赤峰市において契丹学の国際会議が開催された。主催は 赤峰市人民政府、内蒙古博物院、中国社会科学院民族学与人類学研究所、赤峰学院。協力は巴林左 旗人民政府、巴林右旗人民政府。正式な会議名は「内蒙古契丹遼文化研究会成立大会曁契丹学国際 学術研討会」。20日と21日(午前)に会議が行われ、21日(午後)から23日にかけて遺跡や博物 館の視察。会議の内容については論文集『契丹学国際学術研討会会議論文集』(412頁)がある。 (目録PDFはこちら) ここでは写真を何枚か紹介する。

赤峰賓館からみた赤峰市の様子。

これは会議冒頭の雛壇の様子。会議は赤峰賓館でおこなわれた。

主題報告の後、歴史組と考古組と文字組に分かれて報告がなされた。これは文字組の様子。

これより視察の写真を紹介する。上は巴林左旗の遼上京博物館。館の右上に契丹大字貨幣を模した
飾りが見えるであろうか。契丹文字の文物を含むさまざまな資料を写真に収めることができた。

宿泊施設の京都酒店より車で十分程の距離にある遼上京遺跡。写真左に“遼上京考古隊”の赤い旗が。

遼上京遺跡の様子。

同じく遼上京遺跡。蓮華の台座。

遼上京遺跡より1時間ほど車に揺られて遼祖陵祖州遺跡に着く。長い石段を上る。

石段の上の石窟。

同遺跡ふもとの文物管理所。ここには契丹大字の碑文破片が幾つかあり写真に収めることができた。
次に、車で巴林右旗に向かう。

1時間半ほどで巴林右旗にある有名な白塔に到着。白塔の見学を終え、いよいよ待ちかねた慶陵に向かう。

30分ほど車に揺られたであろうか。諸陵墓を望む峠で車はストップ。近くまで行けるのは数年後であるという。

峠にあるオボーに旗を立てて引き返す。

翌朝8時半、右旗をたって赤峰市への帰路につく。11時には赤峰市博物館に着。
館所蔵の契丹大・小字の拓本をはじめ、さまざまな文物を写真に収めることができた。
これで全ての行程が無事終了。実りの多い国際会議であった。
運営にあたられた方々のご苦労を思えば感謝するしかない。

翌日の午後は有志3名で赤峰市中の骨董店をみて歩く。
ケースのなかに契丹文字が書かれたモノが3点、みえるであろうか。
『象院題語研究』出版始末
『象院題語』という書物のことについてはこれまで幾度か書いたことがあるが、昨年この書物に関する研究書を 韓国で出版することになり、さらには今年その本が韓国で優秀学術図書に選ばれるという幸運に恵まれたので、 今回はそのことを書いておきたい。自慢話のように聞こるかも知れないが、まあ一生に一度のことですんで。
きっかけは昨年のゴールデンウィークに台湾の高雄で開催された第4回韓漢語言学国際会議の時だった。 参加されていた朴在淵先生(韓国・鮮文大学校)から、『奎章閣資料叢書・語学編』の1冊として出た『象院題語・華夷訳語』 (ソウル大学校奎章閣、2010年)を示され、この本の『象院題語』の解題は私が書いたのだが、参考文献が 付けられないというので君の論文を挙げることができなかった、これでは申し訳ないので、君の論文をまとめたものを 韓国で出版しないか、というお話があった。論文は日本語のままでよい、付録として我々の論文と訳注をつけるから、とのこと。
韓国で自著を出版!?もちろん飛び上がらんばかりに嬉しかったけれど、その時点では半信半疑な部分もあった。 だが、朴先生からは帰国後矢継ぎ早にメールが来て、請われるままに原稿を送り、序文を送り、著者紹介の略歴を送り、 カバーに使う画像を送る、という具合で、あれよあれよという間に出版の手筈が整っていった。それから約2ヵ月後の7月に 京都大学で開催された第3回訳学書学会の時に、朴先生からハードカバーの立派な装丁の本をポンと手渡された時には、 嬉しいというよりもあまりの展開の早さに唖然とするばかりだった。

その後、出版社から送られてきた20冊ほどを師友に配ったりして、この件は幕を閉じたと思っていたのだが、幸運は続く。 今年の6月30日に、朴在淵先生が来日されたので会いに行ってみると、先生がニコニコ顔で仰るには、『象院題語研究』が このたび韓国の優秀学術図書に選定されたという。その時は、何ですかそれ?という感じでよくわからなかったのだが、 帰ってから調べてみると、日本の文科省にあたる文化体育観光部が選定する2012年優秀学術図書の言語部門に『象院題語研究』が 入っていたのである。
聞くところでは、この優秀学術図書というものに選ばれると、政府が出版社から一定部数を買い上げて全国の図書館や 研究機関に配布してくれるので、とにかく出版社が大喜びなのだという。言ってみれば韓国は国家として学術出版社の モチベーションを上げ、出版を支援する体制が整っているわけで、学術書の出版にやたら冷たい日本とは大違いである。
さらに、この7月28日と29日にはソウルの徳成女子大学で開催された第4回の訳学書学会に参加したのだが、僕の発表の番になると、 朴先生が今回の件を皆の前で紹介し、その場で出版社が作ってくれたという記念品まで贈呈して下さった。僕なんかの ツマラン本のためにこんなサプライズまで用意して下さるとは…ということでちょっとウルウルきてしまい、発表の方はだいぶ しどろもどろになってしまった。その夜の飲み会では、金文京先生(京都大学)から、よし日本でも今度お祝いをやろう、 竹越君のおごりで、という声もあがる始末。そ、それはちょっと困るんですけど。
さて、学会が無事終わった7月30日、いつものように本屋めぐりをしていて、ソウルでは随一の規模を誇る書店である 教保文庫に行った。いつもそうするように、「言語学」「国語学」などの棚を端から見て回っていると、あった。 『象院題語研究』が1冊、きちんと書棚に収まっていた。海外で自分の本に出逢うというのは、何とも恥ずかしいような、 誇らしいような気分である。でもやっぱり嬉しい。実は、この本に収められた自分の論文の出来には全く満足していないので、 今度出すならもっといい本にしたい。もちろん、オファーがあればの話ですが。

フフホト開催の契丹に係る研究会に参加して
2012年7月17日より20日まで、内蒙古大学の蒙古学学院にて「契丹文字及相関領域検討会」が開催された。 27の研究発表がなされ、いずれも興味深い内容であったが、日本の新進気鋭の研究者二人の発表が特に印象に残るものであった。 武内康則氏"Linguistic Characteristics of Kitan Language"、大竹昌巳氏"On Some Phonological Features of Kitan Language"の 二つである。三日目と四日目には遺跡などの視察がおこなわれた。何枚か写真を撮ったので紹介する。

蒙古学学院前。モンゴル学という文字が彫られた石の上に一羽の鳥の姿がみえるであろうか。


学院のフロアー。貴重な石碑資料がある。

会議開始前。垂れ幕には第二回とある。第一回は5年前に開催されたという。

ここからは視察の一部。フフホト郊外にある万部華厳経塔。

内部には仏龕(逗子)がある。

その石作りの四面には契丹文字が墨書されている。それとともに、現代の落書きも見える。人名であろうか。 簡体字で「劉永?」か。『契丹小字研究』(1985年刊)に掲載された写真にも同様の落書きがあるから、 この落書きは27年以上前のものである。

ここには漢字で「大元至元十九?仲夏末」とある。至元十九は1282年。 ここにも無数の落書きがある。上に「四人登塔」とあり、大元という墨書の右横には「1977」年とある。
舞台で聞いた中国語2…相当(副詞:相当、かなり、とても)
“かなり”古い、と思われるかもしれないが、もう何年も前に宋丹丹が「小品」(コント)の台詞で多用して流行った「相当」という 副詞がユーモラスで好きである。インターネットで過去の舞台の録画を視聴できるので、検索すればすぐに参照可能だが、太いだみ声で強調しつつ言うのが笑いを誘うコツである。
宋丹丹は国内最高峰の話劇団・北京人民芸術劇院の俳優である。古いところでは、1992年上演の『茶館』の小丁宝 という少女役がバイオグラフィーの一つで、彼女の本業はやはり舞台であると思うのだが、昨今では専らテレビでの知名度が高い。 その中でも、好評な「小品」が証明しているとおり、シリアスなドラマよりもアットホームなコメディが得意のようだ。映像の代表作は 『我愛我家』や『家有儿女』だろう。
今でも流行語としての「相当」は巷でぼちぼち使われているようである。「相当」(副詞用法)という語自体は何ということも ないただの程度副詞だが、「すごく」や「とても」の替わりに用いると、途端に宋丹丹扮する自慢好きの東北出身老婆のようなおかしみがにじみ出てくる。
私が思うその応用の好例は、小劇場のあるコメディ作品で聞いた、女:「你愛我嗎?」男:「…相当愛你。」という台詞である (典型的ないわゆるバカップルの会話)。といってもこれは上級だろうから、初級としては、ともかく「好」と一緒に用いるのがよい。 基本形は「相当地好!!」である。宋丹丹のオリジナルの台詞には「相当地隆重」、「相当有銭」等々があるが、前者はともかく、 後者は残念なことになかなか真似ができない。
力強い「相当」は舞台の上で披露するにふさわしい。一度、宋丹丹の肉声を聞いてみたいと思っている。
[2012.6.26 榊原真理子]
舞台で聞いた中国語1…「普通話」(標準語)
非母語話者の中国語の習得度を測るテストに、HSK(「漢語水平考試」)があるのはよく知られているが、 中国語の母語話者にも、中国語のレベルを測る「普通話水平測試」というテストがあるのは、あまり知られて いないのではないだろうか。
「普通話水平測試」で測られるのは「普通話」を話す能力で、試験内容は単語や文章の朗読などである。 レベルは上から1級甲、1級乙、2級甲…と並び、中国では、職業によってこの試験の一定のレベルに達している必要がある。 たとえば、教師は2級以上。中国人の友人も、教員免許の取得のため大学在学中にこの試験を受験していた。
1級必須の職業はというと、アナウンサー、番組の司会、俳優である。前置きが長くなったが、中国の俳優は、 身体や容貌、声や運動能力などの諸条件、さらに演技力がいくら優れていても、標準語がきちんと発音できなければ 論外ということになる。
個人的な印象では、洗練されているが立て板に水のアナウンサーよりも、腹の底から発声し、抑揚もはっきりした 舞台俳優の話し方の方が耳に心地よい。舞台特有の誇張した話し方は、俳優の舌の動きや発音の構造がよくわかって 発音の悩みの原因に突然ピンときたりすることがあり、非母語話者には興味深いことも多い。
この「普通話水平測試」は非母語話者も受験可能である。留学生が受験して、高得点を取ったと聞くこともある。 HSKをほぼ攻略したら、次の目標に、ぜひ。
この度、「いろいろな話」で連載させていただくことになりました。演劇を通じて感じた中国語の面白さについて 短い話題をご紹介します。どうぞよろしくお願いします。
[2012.5.29 榊原真理子]
石垣島の唐人墓碑
我が家では毎年1回、年末に家族で旅行することにしていて、昨年は沖縄県の石垣島に行った。 新しい職場に赴任したてで緊張続きの1年だったし、ちょうど『長田夏樹先生追悼集』(好文出版, 2011) の仕事も一段落したところだったので、ゆったりと南国で疲れを癒すはずだった。
ところが、好事魔多し。到着した日の深夜から猛烈な吐き気と高熱に襲われ、それから2晩はひたすらベッドで 震えながら毛布をかぶっている羽目になった。石垣島から船が出ている竹富島も西表島も行けず、楽しみにしていた カヌー体験もおじゃんになった。僕は体育会ボート部の出身なので舟の扱いには慣れており、たまには家族の前で いいところを見せようと張り切っていたのに…。
結局、ただ寝ていただけで何もしないまま帰る日を迎えたが、空港に行くまで少し時間があるということだったので、 妻と娘は陶芸体験とかでシーサーを作りに行き、陶芸にもシーサーにも関心のない僕は一人でその辺をぶらぶらすることにした。
市街地をあてずっぽうに歩いて行き、フラリと立ち寄ってみたのが石垣市立八重山博物館である。ややつつましい 感じのする館内には石垣島の民具や美術品・工芸品がいくつか展示されていたが、その中で目を引いたのが唐人墓碑だった。

ガラスケースには全部で3体の小ぶりの碑が展示されていたが、その文面を移録するとこうなる(原文はそれぞれ3行):
1)咸豐二年壬子十月二十日死/福建省泉州府同安縣/的人姓林名本歳二十四
2)咸豐二年壬子八月二十三日死/福建省泉州府同安縣/的人姓郭名有歳二十八
3)咸豐二年壬子十月二日死/福建省泉州府同安縣/的人姓王名所歳二十一
読んでみて、誰しも「ん?」と思うのが“的”の存在ではなかろうか。見た目は文言そのものだが、少なくとも 正格の文言で“的”を用いることはありえない。そして、文言にしてはやや格調が低い感じもする。
そこで思ったのは、これはいわゆる「文白混淆体」ではないかということだった。金文京氏・山崎直樹氏らに よって提唱された「文言」と「白話」の中間に位置する文体、「文白混淆体」という概念が、ドミニコ会宣教師 フランシスコ・ヴァロの『官話文典』(Arte de la lengua Mandarina, 1703)に言う「官話」の3つのスタイル、 即ち高雅な第1モード、中間的な第2モード、粗野な第3モードと符合するという考えは、古屋昭弘 「明代知識人の言語生活―万暦年間を中心に―」(『現代中国語学への視座』東方書店, 1998)で示されている。 石垣島は木津祐子氏の一連の研究で知られる「琉球官話」の中心地の一つであり、かつては中国語の通事も多く 居住していたはずであるから、この碑文に見られる「文言風かつ白話風」という奇妙な文体も、そういった時代背景の 中で理解すべきではないかと思ったわけである。
以上は単なる空想のようなもので、何の確証もないのだが、ともかくこの唐人墓碑を通じて、石垣島が中国語圏に 極めて近い存在であることを改めて意識させられた次第である。僕にとっては散々な旅行だったが、最後の最後に いいお土産ができた。
そう言えば、ごく最近知ったことだが、「文白混淆体」という言葉こそ用いていないものの、早くからそうした概念の 重要性を強調されていたのは長田夏樹先生だという。とすれば、『追悼集』の刊行直前に唐人墓碑に出逢ってこんな ことを考えたのも、長田先生の導きによるものだったのだろうか。いろんな物事がいろんな所で繋がっているものである。
[2011.12.20 竹越孝]
はじめての台湾
ゴールデンウィークの4月30日と5月1日に、台湾・高雄の国立中山大学で開催された 「第四届韓漢語言学国際学術研討会」に参加してきた。遠藤光暁・厳翼相両先生の尽力で、 これまで3回行われてきた「日韓(韓日)中国語学会議」が、今回からこの名称でリスタートする ことになったわけである。もともとこの会議は、単に日韓の研究者が中国語学を論じる場と いうわけではなくて、朝鮮資料を用いた中国語研究に関心を持つ者が集う場なので、より ふさわしいこの名称になったのだという。
日本からは、遠藤先生、更科慎一さんに僕といった第1回からのメンバーに加え、今回は 三木夏華さん(鹿児島大学)や小島美由紀さん(関西大学)、梁淑鏜さん(新潟大学)といった、 必ずしも朝鮮資料を専門とはしておられない方も参加・発表されていて、この分野もだいぶ裾野が広がってきた感じがする。

→他の写真へ
台北から高雄までは新幹線で1時間40分の距離だが、北回帰線を越えたあたりからぐっと暑くなり、 亜熱帯に入ったという実感があった。前回は山東省の威海で開かれた「リゾート学会」だったので、 この会議は風光明媚なところでやるというのが恒例となった感があるが、今回も前回に負けず劣らず 景色の良いところだった。海沿いにキャンパスがあって、会議室を出た廊下からは広大な海が 望める。コーヒー・ブレイクには山盛りのフルーツが出たりして、南国ムード満点の学会だった。
学会が無事終わってから、飛行機の関係で台北に1泊しなければならなかったので、いつもなら眼を 血走らせて本屋めぐりをするところだが、なんだか面倒くさくなって、故宮博物院を訪れたり、 地下鉄で行ける温泉地・北投に行ったり、夜市を歩いてみたり、翌日は海を望む淡水まで足を伸ばして みたりして、のんびり休日を過ごした。
はじめて行った台湾は本当に良いところだった。交通と情報のインフラが整備されているのは当然だが、食べ物は何でもおいしいし、人々も穏やかでよそ者に優しい。食わず嫌いを反省して、これからの人生は大いに軟弱になろうと決意した次第である。台湾だったら、北京にいた時のようなストレスを感じずに暮らすことができそうだ。…でも、あのストレスがたまらなく懐かしかったりもするんだよな。
[2011.10.18 竹越孝]
冬の奎章閣
夏の「『象院題語』の旅」ですっかり味を占めてというか、ソウル大学校の奎章閣で実際に古籍調査ができることを知ったので、今度は冬の補講期間に入った直後の12月15日から18日までソウルに行ってきた。これがあるから後期は1回も休講にしなかったのである。今回のターゲットは奎章閣蔵の『老乞大諺解』銅活字本4種で、影印本には写らない「紙による訂正」を調査してくるのが目的だった。
この「紙による訂正」というのは何かというと、書物が印刷された後に誤字が見つかった場合、その部分を切除して紙を貼り正しい字に直すことである。朝鮮王朝時代の活字本というのはせいぜい100部程度しか印刷されず、終るとすぐに活字はばらされてしまう。印刷された本の大部分は王から臣下や役所への下賜品(内賜本という)で、地方の役所ではそれを覆刻し木版本を作ることによってその書物を広く流通させる。内賜本は王の権威の象徴であり、また覆刻本の版下にもなる以上、誤字があってはまずいので、紙を貼ってでも訂正するわけである。この訂正という現象については、藤本幸夫先生の論文「朝鮮本の訂正に就いて―『重修政和経史証類備用本草』を中心にして―」(『朝鮮文化研究』1号,1994年)に詳しい。
なぜ『老乞大諺解』で訂正が問題になるのかというと、同書の巻下には訂正が行われたバージョンと未訂正のバージョンがあり、奎章閣にはその両方が収められているのだが、現在流通している『老乞大諺解』の影印本はすべて未訂正本の「奎2044」を底本としているからである。奎章閣に訂正本と未訂正本の両方が存在することは、1944年に奎章閣叢書の1冊として『老乞大諺解』が影印刊行された直後から知られるようになり、1946年には方鍾鉉先生が両者を比較した論文を書いている(「老乞大諺解の廂庫本と訂正本との比較」『ハングル』第96号)。僕は以前天理図書館蔵の内賜本『老乞大諺解』を対象として訂正を調査したことがあり(「天理図書館蔵の内賜本『老乞大諺解』について―印出後の訂正状況を中心に―」『愛知県立大学外国語学部紀要』第41号,2009年)、その際奎章閣蔵本の訂正状況については方先生の論文を参照したのだが、60年以上前の論文ゆえわからないことも多く、今回実際に原本を手に取ってより詳細な記述をなそうと思い立ったわけである。
ソウルには15日の夕方に到着したのだが、18日の朝に離れるまで、今回はとにかく猛烈に寒かった。この冬一番の冷え込み、といっても気温がマイナス10度以下に下がるのだから名古屋や神戸あたりとはわけが違う。僕は青森の出身なので、寒さには強いだろうとよく言われるのだが、実際にはそんなことは全くない。北国の人はそもそも冬あまり外に出ないし、出る時はブクブクに厚着するから、生身(?)ではかえって寒がりなのである。

→他の写真へ
さて、奎章閣には『老乞大諺解』の活字本が全部で4種類所蔵されていて、うち昌徳宮の倉庫だった「廂庫」の印を持つものが3種(奎2044、奎2304、奎2347)、そうでないものが1種(奎1528)ある。前者は未訂正本、後者は訂正本で、調査は方鍾鉉先生の論文を手引きとして、訂正本である天理図書館蔵内賜本と上記4種の訂正状況を突き合わせるという形で行った。そもそも、なぜ未訂正である廂庫本が影印の底本となってしまったのかということについて、安秉禧先生は、一般に「廂庫」の印を持つテキストは紙質が良く善本が多いことから、底本の選定が書物の外見と先入観によって行われたのだろうと推測しているのだが(「『老乞大』とその諺解書の異本」『人文論叢』第35号,1996年)、確かに廂庫本3種はいずれも造本や紙質等がとても立派で、その点奎1528は明らかに見劣りがするので、前者が底本に選ばれたのもむべなるかなという気がする。ただ、もちろん未訂正の廂庫本に基づいて(特に漢字音の)研究をするのは非常に危険であるという認識を新たにした。
それにしても、この紙による訂正というのはさすがに王の権威に関わるものだけあって非常に精巧に行われる。ぱっと見にはぜんぜんわからないし、袋とじに少し隙間を作ったり光にかざして見たりしてやっと判別できることもしばしばだったので、まるまる2日かけて何とか所期の目的は果たしたものの、見逃してしまった部分も多いことだろう。杉山さんと共に4つの原本をためつすがめつしながら、無名の訂正者のプロ意識に感嘆することしきりだった。いつもながら朝鮮半島の印刷文化には畏敬の念を覚える。
なお、ちょうど韓国の国語学会がソウル大で開かれている時期だったということで、2日目の調査が終わってから少しだけ参加してきた。その日は夜のプログラムもあって、韓国の学会では簡単な夕飯を食べた後に集中講座みたいな形で講演を行うこともあるのだという。講演を聞きたい気持ちもあったのだが、それよりも調査完了の祝杯を挙げたい気持ちが強かったので、我々は早々に失礼して行き当たりばったりの店に入り、おいしいサムギョプサル(豚の三枚肉の焼肉)をつつきながらしこたま酒を飲んだ(こればっかりですが)。
というわけで、今回もとても楽しく、充実した4日間を過ごすことができた。これもすべて杉山さんのおかげなのだけれど、僕自身としてもなんだか韓国とは本格的にウマが合いそうな気がする。さあて、今度の春休みは何を見に行こうかな…などともう考え始めている自分がコワイ。
[2011.1.18 竹越孝]
『象院題語』の旅(その2)
今回の訳学書学会では、2日目の午後に高麗大所蔵古籍の見学というプログラムが予定されていて、閲覧希望の文献がある場合には1週間前までに申し出るようにとのことだった。それはそれで楽しみなのだが、僕にとって高麗大学校といえば、鄭光・尹世英『司訳院訳学書冊板研究』(高麗大学校出版部,1998年)によって知る人ぞ知る司訳院旧蔵の版木(冊板)の所蔵機関である。しかも、そこには『象院題語』の版木もあるのだ。
そこで、前もって鄭丞惠先生に、この機会に高麗大所蔵の版木を見せていただくことはできませんか、できれば『象院題語』を見たいのですけど…というメールを出しておいたのである。鄭丞惠先生からは折り返し、学会長である鄭光先生に話しておきます、という返事をいただいたのだが、その後奎章閣での調査に気を取られてこの件についてはすっかり忘れていた。

学会の風景
『象院題語』の版木があると知ったら、急いで確認しなければならないことがある。前回記した句点のことはもちろんだが、それ以上に気になっていたのは、最後の2葉に相当する部分の版木の状態である。僕はかつて『KOTONOHA』第37号(2005年12月)に 「『象院題語』の版本と冊板」という小文を書いたことがあり、そこで、ごくわずかな違いではあるが、この2葉に関して『象院題語』のテキストは二つの系統に分かれることを述べるとともに、その違いが生じたのは版木の一部が割れて補板したことによるのであろう、という予想を記していたのだ。
前々日に奎章閣で見たテキストのイメージが湯気を立てそうなくらいホットな状態だったので、どれが目当ての版木かはすぐにわかった。句点については思った通り最初の2葉分だけ版木に刻されており、これでダメ押しになった。そして次に、最後の2葉に相当する版木を見てみると…あっ、やっぱり補板した跡がある!杉山さんには奎章閣での調査の時にこの予想について話してあったので、「ホラ!言った通りでしょ!」「すごい、ホントですね!」と二人で手を取り合って(笑)大騒ぎになった。
その後はなんだかフワフワした感じになり、まるで夢の中にいるみたいだった。学会のプログラムがすべて終了したあと、何人かで連れだって東大門にタッカンマリ(鶏の丸ごと一羽鍋)を食べに行き、大汗をかきつつしこたまお酒を飲んだことは覚えているが、その後どうやってホテルに帰ったのかは全く記憶にない。

タッカンマリのお店で
[2010.12.28 竹越孝]
『象院題語』の旅(その1)
8月12日と13日の2日間、ソウル・高麗大学校で開催された「訳学書学会第2回国際学術会議」に参加してきた。昨年の9月に発足した訳学書学会の2回目の会合である。この学会は、朝鮮司訳院の四学(漢学、蒙学、倭学、清学)を対象としたものなので、中国語学の関係者だけでなく、日本語や韓国語の専門家も多く参加している。僕は「漢学」のセクションだったが、それにしても海外で発表するのは今年の前期だけでもう3回目で、さすがに自らの粗製濫造ぶりに嫌気がさしてきた。
コリョデ(高麗大)を訪れるのは鹿児島大学に勤めていた1998年の夏に短期留学して以来のことで、変わらぬ威厳に満ちた白亜の校舎が懐かしかった。研究上の交流もとても実り多く、特に鄭丞惠先生(水原女子大学)が行った新発見の刪改本『老乞大』に関する発表などは、思わず身を乗り出してしまうほどに興奮するものだった。ただ、僕の中で今回はそうしたこと以上に「『象院題語』の旅」として記憶されることになった。
この『象院題語』という書物を初めて目にしたのは2005年春のことである。満洲語の資料を見るために東京・駒込の東洋文庫に行き、時間が余ったので何の気なしにこの本を出してもらったら、中身が白話だったので飛び上がらんばかりに驚いた。慌てて複写を申請し、帰ってから調べてみると、本書に関する先行研究がほとんどないことがわかったので、これは自分が学界に紹介しなければ、という気になった。その後、ある方の好意でソウル大学校奎章閣に所蔵される同書の複写も入手することができ、その年から翌年にかけていくつかの論文を書いた。
研究が一段落したところで、その後はずっとほったらかしにしていたのだが、今年の6月にあった『老朴』関係の学会で(前項参照)、ネタに困って本書を取り上げたことから新たな展開が生まれることになった。奎章閣蔵本に見られる句点(。)の位置が中国語的でないということを話題にしたら、その句点はもともと版木に彫られたものなのか、誰かが筆で書き入れたものなのか、それとも竹筒を使ってハンコのように捺したものなのか、という質問を受け、複写しか見ていない僕は答えに窮してしまった。その様子を見ていた遠藤光暁先生(青山学院大学)から、これは現物を見て確認するしかない、これで見に行かないのは学者魂にもとる、とさんざんハッパをかけられ、よおし!と決意したわけである。
帰国してからすぐにソウル大学校に留学中の杉山豊さん(東京外国語大学大学院)に連絡して閲覧申請書を取り寄せてもらい、今回の学会の前日をその調査に当てることにした。大学院入試があった日の夕方に飛行機に乗って、夜遅くソウル市内の安ホテルにチェックインし、翌日の昼に「ソウル大入口」駅で杉山さんと待ち合わせた。タクシーに乗って奎章閣に着くと、杉山さんがあらかじめ申請書を提出し話を通しておいてくれたので、手続きは非常にスムーズに行き、すぐにご対面となった。

奎章閣の入口付近

横から見た奎章閣

『象院題語』の奎章閣蔵本「奎7493」を手に取ってみると、真実はあっけなく分かった。句点は最初の2葉分だけ版木に刻されたもので、あとの葉はハンコの要領で捺したものだった。墨の色が違うので一目瞭然なのである。声点とか角筆研究の世界では当たり前のことだろうし、前に天理図書館で『老乞大諺解』の紙訂正を調査した時にも感じたことだが、やはり現物をじかに見ることでしか得られない情報というのはあるものだ。その後、杉山さんに手伝ってもらいつつ、複写ではよく見えなかったハングル注音の部分についてメモを取ったり、マイクロリーダーで改めて複写を取ったりしているうちに、時間はまたたく間に過ぎていった。充実感たっぷりに奎章閣を出て、杉山さんと大学内のカフェで飲んだコーヒーのおいしかったこと。まあ、ビールならもっとよかったのだが…。
僕は遠藤先生の「北京からパリへ―ヨーロッパ中国語学の旅」(『漢語方言論稿』所収、好文出版、2001年)が好きで、あの血沸き肉踊るような文献探索の旅を自分もいつか体験したいと思っていたのだが、今回そうした雰囲気の一端を味わうことができたのは幸いだった。これまで日本の図書館にはかなり行ってきたが、遅まきながら海外の図書館でも同様の古籍調査ができることを知って、ますます自分の世界が広がりそうな気がする。もちろん、今回は杉山さんがいたからこそ苦労せずに済んだので、言葉の問題が大きいとは思うけれど。
さて、「『象院題語』の旅」はこれだけでは終わらず、その翌々日にもっとすごい僥倖に恵まれることになるのだが…それは次回。
[2010.10.19 竹越孝]
リゾート地での学会・再び
6月の12日と13日、中国・浙江省の桐廬県というところで開催された「“《老乞大》、《朴通事》的語言”国際学術研討会」に出席してきた。中国社会科学院語言研究所と浙江大学漢語史研究所の共催ということで、全体としては20人程度の少人数ながら、アラン・ペローブ、曹広順、方一新・王雲路ご夫妻といった「大物」も何人か参加されていた。日本からは、遠藤光暁(青山学院大学)、沈力(同志社大学)、舩田善之(九州大学)に僕といったところ。金文京先生(京都大学)は直前になって都合がつかなくなったそうで、ペーパーだけの参加となった。
中国で行われる最近の学会といえば、観光地のホテルで行われ、エクスカーション付きというものが圧倒的に多く、中には観光のために発表時間を大幅に圧縮したりして、いったい何をしに来ているのかわからないものもあるという。今回も杭州からバスで2時間ほど行った富春江の川沿いにあるリゾートホテル風の施設で行われるということだったので、正直ちょっと警戒していた。
到着した日は暗くてよく分からなかったのだが、次の日早起きして散歩に行ってみると、果たしてホテルの前にはまるで山水画のような風景が広がっている。うーむ、やっぱりこれは「リゾート学会」になるかも。

→他の写真へ
しかし、そうした心配は見事に裏切られ、会議は非常に実りの多いものとなった。それは、テーマが比較的狭い範囲に限定されているため議論がよく噛み合い、また中身のある討論をするのにちょうどよい人数だったことがあると思う。そのテーマというのが、日本の研究者にはおなじみの「蒙文直訳体」と「漢児言語」をめぐる諸問題に直結するので、僕もできるだけ臆せず発言し、ワールドカップよろしく「日本代表」の一人として頑張ったつもりである。お前が日本を代表すんな、というツッコミが聞こえてきそうですけど…。
プログラム最後の総合討論の時間には方々からコメントが行き交い、しまいには「俺にもしゃべらせろ」状態になるほどだった(恥ずかしながら僕もマイク争いに加わった一人)。『朝鮮時代漢語教科書叢刊』の編者である汪維輝先生(浙江大学)が「問題がこんなに複雑なものだとは思わなかった」と洩らされていたように、全体としては『旧本老乞大』をめぐる問題の奥深さを改めて認識したといった感じである。
その他にも、今までメールでしかやりとりのなかった祖生利さん(社会科学院語言研究所)と初めて会ったり、僕が入力した『老乞大四種対照テキスト』が中国でも使われていることを知って驚いたりと、様々な面で収獲の多い会合だった。2日間の充実した会議を終えて、エクスカーションで行ったダム湖では、遊覧船の上で今回知り合った人達と記念撮影をしたり、ディープな話題で盛り上がったりと、楽しい時間を過ごすことができた。
こうしてみると、リゾート学会も悪くない、うん。
[2010.8.17 竹越孝]
清代民国時期漢語国際学術研討会
ゴールデンウィークの5月2日から5日まで、韓国・牙山の鮮文大学校で開催された「清代民国時期漢語国際学術研討会」に参加してきた。この国際会議は遠藤光暁先生の企画立案になるもので、清代及び民国時期の中国語に関わるすべての領域、つまり中国本土の資料はもとより、満漢、唐話、西洋などの域外資料から、呉語、広東語などの方言資料までを一望のもとに収め、この時期の中国語に対する360度の俯瞰を得ようとする壮大な試みである。これまで、それぞれの領域ごとに一定の研究成果が挙がっており、分野によっては日本がその先頭を走っているものもあるのだが、それら全部を同じ俎上に乗せて総合的に検討しようとする発想はなかったわけで、いつもながら遠藤先生の構想力と企画力には驚かされる。
今回はうかつにもカメラを持って行くのを忘れてしまったので、自分で撮った写真というのがまるでない。画像中央の白髪男は僕である。ややうっとうしいがご勘弁を。

→他の写真へ
さて、今回の学会もその日を迎えるまでがとにかく大変だった。というのも、この学会に合わせて『清代民国時期漢語研究文献目録(稿)』を出すことになっていたからである。僕は満漢資料の部分の作成とともに、全体の体裁面でのチェックを担当することになっていたので、入力マニュアルを作ったり、他の人が作った目録を見直して手を入れたりする必要があった。
それに加えて、僕はこの4月から勤務先を変わることになっていたので(古代文字資料館の館員は続けていますのでご安心を)、忙しさは倍加した。3月は引越しの準備や各種送別会の合間を縫って、各担当者から送られてくる目録に対応し、新しい勤務先で辞令をもらった4月1日にも、とりあえず事務室のパソコンを使わせてもらってメールをチェックするというありさまだった。そうして作ったこの目録は、結局400ページを超える巨冊となって学会の参加者に配られた。今後必要な増補修正を加えて「(稿)」の字を外し、正式出版することになっている。
目録は大変だったが、学会自体はとても実り多く、また楽しいものだった。今回は妻も発表するので家族旅行を兼ねることにし、9歳になるうちの娘も連れて行った。ホテルでは家族用のオンドル部屋に泊まり、チムジルバン(低温サウナ)も初体験した。学会のプログラムがすべて終了してから全員でハイキングに行き、夕刻になると酒を酌み交わし焼肉をつつきながら、一人ずつ歌を唄ったりしたのは忘れ難い思い出である。
参加者の中には、またこういった会合を持ちたい、次回はいつやるのか、と尋ねる人も多かったが、遠藤先生は即座に、この集まりは一回性のもので、次回やるとしたらそれは「明代漢語国際学術研討会」だと答えていた。これからどんどん中国語史をさかのぼっていくのだそうである。うーむ、あと何回目録を作ることになるだろうか。
[2010.7.13竹越孝]
読んではいけない!?
先日NHKテレビで「ためしてガッテン」という番組を見た。この番組、私はめったに見ないのだが、たまたま見る時にはなぜか、言語や文字に関連する内容をやっている。今回は速読についてだった。一般の人でも10日ほど訓練すれば2倍程度の早さで文章が読めるようになるという。キャッチフレーズは「読んではいけない」だそうだ。音読はもちろんのこと、黙読でも頭の中で音声を思い描くような読み方だと速読はできない。訓練方法としては、新聞の見出しから内容を読みとったり、一行の文字数が少ない新聞のコラムを数行ずつのかたまりとして読んでいく方法が有効らしい。
話は変わるが、マンガ『ドラゴン桜』の中で、英語の先生がリスニングのコツについて、「音を聞き取ろうとしてはいけない」というようなことを言っていた。英語の発話を聞き取るのに、個々の音声を追いかけても聞き取れるようにはならないということらしい。確かにそれはだれもが実感していることだ。発話全体からボンヤリと意味が浮かび上がってくるのが自然なリスニングと言えるのかも知れない。
文章は一字一字を読むと早くは読めないし、音声は一つ一つの音を追いかけると聞き取れないというのはどういうことなのだろう。言語学習では、普通は小さな単位から徐々に大きな単位へと向かう。ロシア語であれば、まずキリル文字を覚え、基礎単語の綴りと発音を覚え、文法を少しずつ覚えながら文を解釈してゆく。少なくとも初習外国語である限り、これ以外の方法はあるまい。ところが、ある段階に至って、長い発話を聞き取ったり、長い文章を読むためには、個々の音声や文字を気にしてはいけないという。始まりは意識的に、しかしある段階からは無意識的に意味を捉えてゆく必要があるということだろうか。
一体、意味の認識のメカニズムはどうなっているのだろう。私はもちろんこの方面には無知だが、言語以外のことも含めた種々の経験から、「無意識」ということの重要性(あるいは必要性)は承知している。字を書く時に、普段は自然に書ける字も、いったん「こんな字だっけ?」などと意識し出すと、途端に上手く書けなくなってしまう。ひらがなでさえ、そうなのだ。音声にしても、「ありがとうございました」と言っているはずの店員さんの言葉を、本当にその音声だけを聞き取ろうとすると、何と発音しているか分からないことが多い。「あーたんしたー」とか「あーざーした」としか聞こえないこともある。それでも習慣的に「ありがとうございました」と認識しているのだ。もしも外国人が音声だけを頼りに聞き取ろうとしたら、何と言っているのか理解できまい。おそらく脳というのは無駄な労力を省くようにできていて、習慣的な行為には解析や分析を行わないようになっているのだろう。
言語研究という立場から言えば、しかしながら、無意識の域に達することだけを求めてはいけないのではないか。常に意識的に文字や音声や文法を気に掛けながら進むしかない。たとえ速読ができなくとも、外国語のリスニングが十分にできなくとも、やはり個々の音声、個々の文字、細かな文法にこだわりたいのだ。それが言語や文字にたずさわる者の癖(あるいは資質)なのだから。 [2010.4.14 中村雅之]
リゾート地での学会
9月12〜13日に韓国・全州で行われた訳学書学会のことは前回記したが、その翌週の9月19〜20日には中国の山東省威海で学会があった。今度は「第3届中韓日中国語言学国際学術研討会」で、これまで厳翼相・遠藤光暁両先生の尽力のもと、ソウル・東京で開催された日韓中国語学国際会議が、今回初の中国開催となったわけである。
僕は全州の養士斎で良い「気」をもらった翌日の夜、日本に帰り、その2日後にはまた中国に向けて発つことになった。なぜそんな面倒なことをしたのかというと、…要するにその2日間には会議があったわけですね。教師稼業もなかなか楽ではないのだ。
名古屋−威海は直行便がないので、まず韓国・仁川の空港近くで一泊し、翌日午前の便で威海に着いた。今回の学会は山東大学威海分校の主催だったが、大学のキャンパスではなく近くのホテルで行うということで、早速そのホテルにチェックインをした。学会は明日からだし、とりあえずのんびり散歩でも…と思って外に出たら驚いた。だって、目の前にこんな景色が広がっているのだ。

→他の写真へ
思わず「え、地中海?」と言いたくなるような光景である(もちろん地中海に行ったことはないが)。威海は日清戦争の激戦地だったことで知られるが、近年は主に韓国資本で大規模な観光開発が行われているそうで、空港では韓国からゴルフに訪れる人の姿が目立っていた。
これでは学会というよりはリゾートに来たようなものではないか、気持ちが浮ついて学問に集中できないのでは…と思ったが、さすがに僕も大人だからそんなことは全くなく、始まってしまえばいつもと同じだった(と言っておこう)。
1日目を終えた夕方、歓迎会の会場まで海岸を歩いて向かったのだが、夕闇迫るその水平線の美しかったこと。宴会が終わった後も、主催者側はホテルまでのバスを用意してくれていたのだが、誰もバスに乗ろうとする人はなく、皆で来た道をぶらぶら歩いて戻った。
学会が終わった後も、本当はもう1日ぐらいのんびりしたかったのだが、早々に日本に戻らなければならなかったのは残念だ。なぜかというと、…やっぱり会議のためです(泣)。
[2010.1.12 竹越孝]
2009年以前の記事はこちら。